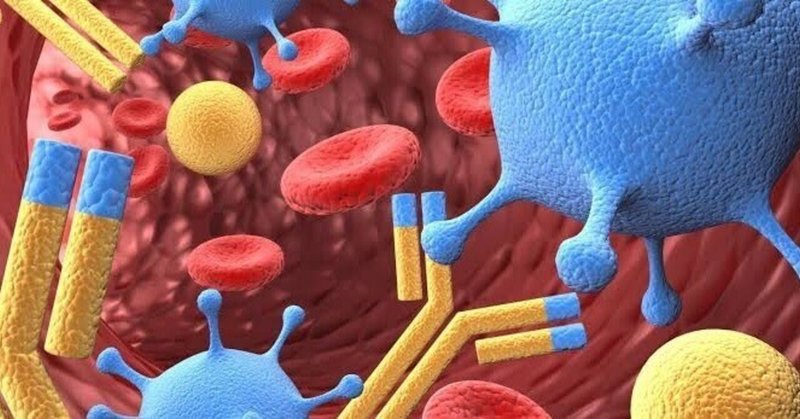
糞食らえコンテクスト なんかでかくて強いやつ
内部と外部
電話
「もしもし、今電話大丈夫ですか?」机の上の携帯は瞬時に遠方とつながる、否、つながった状態で待機中なのだ。技術の発展は都市でのスケール感をマヒさせる。スマートフォン、新幹線、エレベーター、ランニングマシーンetc これらは空間と空間をつなぎ内部環境を人工化する。生活は段々範囲がひろがるテクノロジーがもたらすプロフェッショナルとの接触と電気信号の伝達を基にできあがり、家庭生活だけでなくメディア、政治活動、国家、国際的に接触を要求されている。内向きには安全性に向かって、専門家たちは日に山ほどかかってくる電話にノイローゼ気味に修理に出かけ、外向きには快適性のために家や職場の不自由さを相談するためにパラノイア的にコールセンターへ電話をかける。品質のためにマニュアル化したサービスは均質空間をさらに均質に持続させるように働く。町に平等に高いコーヒーを提供するスタバとその看板から、部屋のエアコンディショナー、一杯のフラペチーノと接客術これらの無限のコピーアンドペーストによりサービスを受ける客もコピー可能な匿名性を得た客となる。電話越しだと顔は見えないというが、見えた所でスマイルはゼロ円の一律価格の商品である。
ピアス
マニュアル化した都市は改変不可能性を増殖する。大手の強大さはインパクトのみを読み手に与え、かつて地縁によって存在した改変可能性を諦めさせる。このインパクトは都市、建築、家具、衣服まで及び、この中にアイデンティティを担保できるものはない。モール、ハウスメーカー、ニトリ、ユニクロ。改変可能なのは皮膚一枚、ピアスやワンポイントタトゥー、アクセや整形のみ。それでも均質空間はキワモノの人間にならないよう見張っている。いくらユニコーンカラーに髪を染めても、舌にピアスをつけてもファストフード店は平等にスマイルをサービスする。中心と外皮が乖離しており内と外の活動は連動しないために着飾っても都市の外皮には無力なのだ。作者不在のチェーンの集積、田舎のロードサイドとモール、都市のショッピング街(そこに形態はもはや問題でなく、増殖のみがある)は常にユニークなのに強烈に見慣れた景色となっている。古くなったら、飽きがきたらリニューアルを繰り返せばいい。商いは町で何かをしようとすれば必ず消費を促す。こうして私たちの内部空間は皮膚一枚まで裸にされ外部空間はお手軽にニーズが増えれば広がる世界となった。
建築家
内部と外部の関係は無くなり、それに伴って都市的コンテクストも無くなり、主体性も匿名性の消費活動として失われた。本来建築家が対応すべきこれらの諸問題は建物の規模故にもはや統御できなくなった。ファンタジアのミッキーのように、フランケンシュタイン博士のように。建築家が頭を抱えているのはアトリウムやラウンジの採光と天井を高くするために天井内のグロテスクな機械と配管、ダクトとケーブルをいかに収めるかだ。
ビッグネス
レムコールハースの唱えたビッグネスはもはや巨大建築に止まらず社会全体へと巨大化を続ける。テレビ局やオフィスを収納しながらその核に商業施設が入り込んだ六本木ヒルズや駅直結の巨大ショッピングモール、ラゾーナ川崎、アリオ倉敷etc さらには農村(生産)(流通はインフラにより短くなりつつある)都市(消費)といったふうに国土全体が大きなスーパーマーケットのようなモデルを採用中だ。都市-周辺領域は等方性を持った複数のビッグなスーパーとして我々を労働と消費へ順応させる。ゾーニングは均質性により必要ない。ランドスケープは生産と消費の合理性により必要ない。
挑発される農村と観光
スマート農業
タワマンや大型ショッピング施設、駅、公園それらを整頓する再開発によって都会はますますランダム性が無くなりデカルト的グリッドが広がると思われるが、この傾向が最も強いのは意外にも農村である。
衛星通信により自動化したトラクター、ボイラーとエアコンにより恒温恒湿化も可能にし、照明により日照時間も操作できる。徹底した品質管理により均質な野菜が食卓に並ぶ。他方休耕地や放置された山林は㎡あたり200Wと捉え太陽光パネルが設置される。僻地のメガソーラーは圧巻で泥田坊もぐうの音もでないだろう。生産状況もコンピューターで管理され、最大効率を獲得するにはどのタイミングで肥料や殺虫剤を散布すればよいか計算され、パネルも日々の発電量をデータとして送信する。畜産小屋は単位面積当たりの頭数、健康状態、出荷時期、生物に対してもデジタルな対応でグリッド化する。
太陽光発電
ところで何が休耕地をも太陽光発電に駆り立てるのか。もちろん土地を手放したい経済的要因もあるが、昔から雑草が生い茂った耕作地は忌み嫌われたのである。一度手を入れた田畑や山林は放置したら元の自然に帰るわけでなく、ケガレとして認識される。だから放置林や休耕地は荒らしたままでおくよりは発電していた方がましなのである。しかし出た芽を忍耐強く世話していた時代と違い、土地を㎡の生産性で刈りたてている。これはハイデッガーのいう挑発である。田園の特権である詩的な世界は都市の特権に変わるかもしれない。
ケガレ
さてケガレの話が出たが、かつて都市では地理的・感覚的要請により配置によって外部が規定されていた。日本は内部と外部の間に何層もの入れ子がある。内の内には仏壇や神棚、大黒柱など崇める対象があり、その外側、家へは靴を脱いで内側と外側を規定する。家の外は生垣や格子で隔て、町は河川などで区切られている。河川や街外れには刑場や遊郭が置かれ、さらにその外には里地里山のクッションを置き、山、海、森などが異界として存在した。技術と呼ばれるもの、焼き物やたたら製鉄など特殊技術も神聖視ひるがえって蔑視された。いっぽんだたらや器物の妖怪はそれらを表す。現在は技術や自然は使いこなせるものとして認知されている。恐るるに足らないわけだ。
観光
交通の発展により自然も赤線も皆、内外の区別なく広がっていき、歴史的差別の文脈を無視して観光に出かける。この物見遊山は本来地元民のみに認識されていた彼岸を、観光客も自分の外側というインスタントな彼岸として、ボーダレスな世界でのカジュアルな差別を助長する。自然にせよ歴史美観地区にせよ、こういった場所を観光地化することは余暇産業に徴用することであり、匿名性に堕ちた日本人は自分の外部に日本の原風景を規定する自分探しの旅に出る。
都市-周辺領域
家具
ビッグネスにおいてはスケール、構成、伝統、透明性、倫理性から離脱する建築はこれらを内包しているため克服されねばならない。都市組織の中間カテゴリーとして建築が克服されると、大都市は家具オブジェクトと直接的につながり運用される。モールはキオスク、パーテーション、ベンチで区切られる。椅子と食器棚、ストリートファーニチャーは完全に同質のものと変わり、量で応答する。都市の強力な都市化、農村への流出は高速鉄道の付置によって加速した。今後も無限に広がるこのプロセスは、質よりも量が優先されるという消費社会の増大する特性を説明するのに役立つだろう。
インフラストラクチャー
鉄道、自動車をはじめインフラストラクチャー、エレベーター、エスカレーターの搬送設備そして奥まで生命を保つ空調・換気・照明設備により可能となった。新技術の発見と産業の効率性と絶え間ない資本主義の進歩の扉が開かれていることを信じている限り続く。いや一人歩きして止められず都市-周辺領域として巨大化するのだ。
スーパーマーケット
単に大きいというだけで良し悪しも超えた段階にすでに入っている。計画という計画はオフィスで一応練られるものの内部と外部を結びつける素直さは存在しない。外皮は看板や駐車場、巨大になれば壁面や屋上面にパネルを敷き詰めて発電可能だ。このモデルは強いて言えば工場、スーパーマーケットからインスピレーションを受けている。生産構造として工場は都市組織を予見する。自分の工場の労働環境を合理化する試みはオフィスを休暇村のように見立てる。リフレッシュスペース、コワーキングスペース、オフィス内のサウナやジム。スーパーマーケットは合理的な消費組織システム内での商品の絶対的な循環を表す。この2つのモデルに基づいた反復を基本とする都市に自分の家具だけを購入して居住者は居つくことができる。最小限の入力に対する最大限の成果。繰り返すとすべての現実内のデータを均質に混合したために、土壌文化を超えたサジを投げた実験場となりゾーニングは必要ない。あらゆる形の財の倉庫となるため形態は自由となりランドスケープも必要ない。まさにコンテクストから自立しているために白紙状態でも耐えられる。歴史や場所性から搾り取られたものを触媒としない。インフラ設備さえ整い始めたらフジツボのように気づいたら根を張っているのだ。作家性は必要なく、構造計算や熱負荷計算、換気計算等技術チームにより設計され、施工される。個性の入り込む余地はない。個として確立しない一般的な街となる。個性というものは小さすぎてすぐ飽和状態に達しやがて使い果たすだろう。中心は弱まり周辺が広がる。
推し活
日常
現代は地縁も社縁も成り立たない。というより耐えられない。巨大な街では事件は起こらない。起こっても街の巨大さゆえに雀の涙のようなもので、改変可能性は先に述べたように皮膚一枚まで切り詰められているためにやりきれなさ、あきらめ、不吉、不潔、理不尽が点滅する。永遠に日常が続く。それらを鈍感にやりすごしてきたおっさんたちは事件を努力によって解決できると考えている。改変不可能なものを解決できると信じているおっさんたちはわけ知り顔で一線を越えてくる。人生に対する諦めを自分の外部に規定するとおっさんたちは外部を行き来し、皮一枚の内面に肉薄する。「今日、夕飯に行かないか?」と残業後に誘う上司、「おかえり、車来ているから危ないで」と地域を見守るボランティアの近所のおじさん。これらの縁に耐えられないのだ。ありがたいことに縁はサービスがとって代わっているから危険はsecomに頼めばいい。世話焼きの何でも屋的な電気屋さん(最近いないが)よりもその場限りのサービスマンのほうがいいに決まっている。人と人との間の縁よりも電話でのサービスのほうが楽ちんだ。外部と繋がり続けているから向かい合う必要もない。コミュニケーションがデジタル(そもそも言葉はデジタルだと思うが)になれば面倒くさくない。たまに冷たく感じるが応答はいいねやスタンプでかまわない。乗り越えてくるおっさんは統一価格ではないスマイルや怒り顔を添えているから厄介なのだ。
免疫学
これほど匿名利用が増えた今、主観はあれど主体はあるか疑わしい。均質空間はどこにでもある特性から、場所性を記憶しない。私は自身の決定には記憶と自分の特異性、非自己の認識、外部への多様な反応性、外部への反応のパターンの増大が必要であると考えている。免疫学からアプローチすると個性は記憶なしには形成されず記憶も個性が見せる瞬間から保存される。出来事と出来事を示す場としての記憶が個性を育み、個性が出来事を脚色して記憶する。しかし匿名性により特異性は失われ、均質空間により出来事の場は薄められる。コミュニケーションの単純化記号化により反応性も極端に減る。都市的創生物の生成不可により自分の出力もわずかに消費行動に残るくらいである。
推し活
このあたりで推し活を説明できるのではないだろうか。「推し」という自分に強い反応性を示すものを外部に策定して、反応として大きな消費行動をとる。オタクの活動はdigる地面が存在しアンダーグラウンドな性質を持っていたが、推し活時代はニーズが多く地下街として掘り尽くされ整備された。ライブ、限定グッズ、配信、イベントへの参加は推し活につきものだ。消費者はジャストインタイムに移動する。一方でグッズにあぶれた人はフリマサイトなど二次的市場で「担降り・推し変」に伴う物品を特定のキーワードで取引する。街の巨大さ故にアウトサイドがインサイドに包摂され、予め推し活は流通システムが整備されていることが、「掘り出し物」を探し当てていたゼロ年代のオタクとの違いだ。自分の行動の特異性を担保するために消費行動に自己寛容でありながら自分とは違う同族に「同担拒否」として反発反応を示す。推し活は孤独との関係がよく指摘されるが、孤独は一人が成立しないとならない。考えるに孤独以前に自分がなく推し活の結果孤独を感じるのである。このようにして自己抗原としての偶像を策定、アイデンティティとしてのファンを演じ続けることで自分の同一性を担保しようと試みる。別に推し活を否定したいわけではない。愛をもって自分を算出する行為は素晴らしいだろう。だが内部と外部の連関を持たないただただビッグな都市においてカジュアルなアウトサイドを作り出す試みはますます無力感を強くするのではないか。インフラによりネットワーク化するといえば聞こえはいいが、実際は経路づけられているという暴力性が隠れている。秋葉原、日本橋、下北沢、アメリカ村、といったオタクやサブカルの町はあり得るが推しの町はあり得ない。推しの子は渋谷スクランブル交差点をジャックしたが、カルチャー自体が都市的創成物を作ることなく消費都市の看板を借りることしかできなかった。全国のフリースペースに拡散する推しのコーナーはパーテーションという薄い膜で仕切られている。
地面に聞けば良かったんだ
場所
場ないし場処locusを通じて都市のモニュメントの、自然の重合を見出せる。類型は建築的歴史性、意味が収斂した核となる。幾重にも沈殿し成層化している都市の要素は都市的知の本質的基礎である。記憶が事実や場所に結びつけられているならば都市は集団記憶の場所である。都市と住民との縁こそが建築あるいは風景に成ることができる。神社に来る人は験かつぎかもしれないし、悲しみをお祓いするためかもしれない、謝辞の場合もある。理由は様々あれど由緒を求めて来ており、個々の印象の総和で成り立っている。場所に質を見出した古代人の魔力である。
方法
いかにして大きいことに対抗し、場を回復するか?方法としては場に居つき、場の歴史や性質を調べることである。ドカンと強い外部を設定するのではなく、階梯をつくり丁寧に入れ子構造を作るのである。なにもスマホを今すぐ売っぱらって仙人みたいな生活をしろというのではない。むしろ脱サラして農家にあこがれることは自然を強い抗原として置きすぎている。農業従事者が減る中でそれ自体は素晴らしいことではあるが。いわば内部と外部の間に関連するトーンを置き、共生の方法を模索するのだ。この方法として湿地帯ビオトープと木登りを挙げる。
ビオトープ
湿地帯ビオトープには動植物を呼び込みその往来が庭とその外側を曖昧にする。ビオトープそれ自体にもエコトーンと呼ばれる水と陸の中間がある。湿地帯に暮らす多様な生物を守ることにつながる。湿地帯ビオトープは氾濫原湿地や二次的自然である水田や溜池を睡蓮鉢などに再現し生物の居場所を復活させる試みである。「わざとならぬ庭の草も心あるように」徒然草のような日本的情緒を含まんとする新しい造園は自然史を模倣する。氾濫原から田、池の歴史のミニチュアは都市的知を内包する創成物なりうるだろう。生物がたくさん暮らせるようになり水生生物などがやってくる。こうして睡蓮鉢は出来事と出来事を示す印となる。個別性の始まりと終わりを示す境界線はソリッドな物と場所との関係であり芸術の場である。
アマチュア木登研究所
アマチュア木登研究所は1000年代に日本文化として木登りが大成しているというパラレルカルチャーである。木に登るという原初的な行動は木の不動性から場所に密接に関わる。木に登るものは中空と実体を同時に感じることになるだろう。樹皮と木々同士の間隙、あるいは木々を登る所作と所作の間は中空であり、体を中空と幹の間に置く。内心の緊張を持続し、心に充実緊張がある状態、それが外面に見えてしまうと意図的なものになってしまう。アマチュア木登研究所では、背景として植えられたであろう木を登る対象にするという脱規範として実践している方もいる。物質としての木に触り、好奇心や恐怖心を感じることは場所の本質である。これら場の観念は都市の文脈となり一つの創成物となる。ランドスケープとしての植栽は背景としての意図が透けて見える。一般に環境という観点から考えており、ある一様で整然とした連続的な環境を作り上げる。この種のデザインはイメージやイメージを洗練させる趣味に還元され、都市の理解に及ばない。容易に機能を覆し得ることを忘れているのである。木登りをする際、場は環境と区別される。
モニュメント
環境と対置されるのがモニュメントである。古代人は木にしめ縄をつけて神木とした。歴史的に規定された存在以上にリアリティを持っている。軍事都市、学術都市といった計画学の実践的なものに木登りは反対する。場所の分類に誘発される個別性により抵抗可能である。1000年代に木登りが大成していれば植樹はランドスケープと対極に位置し、執拗な直感というべき形で自然への接近を試みるだろう。素朴な外部としての木につかまり自分の身を置く場所を探す、脱規範となる出来事は木に記録され登った経験は場所と共に記憶される。新しい技術と共に消費されてしまう新奇なスタイルとイメージを使う代わりに厳格に木1本、虫1匹から出来事を始めよう。象徴的、地理的特異性として都市内部の例外状態としての場に関心を向け大きい事に異議を唱えよう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
