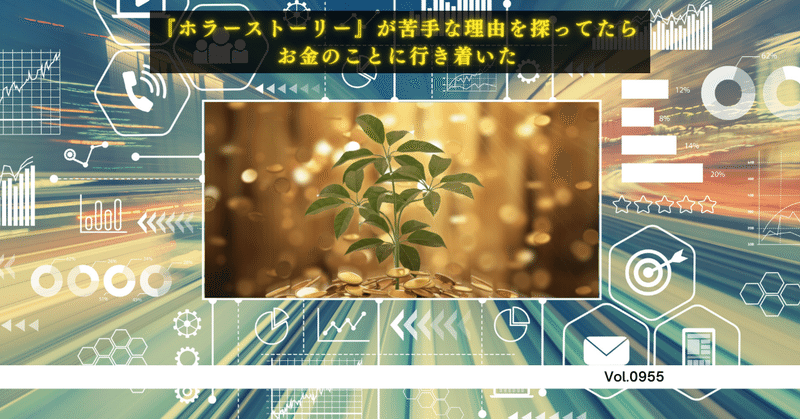
『ホラーストーリー』が苦手な理由を探ってたらお金のことに行き着いた
『ホラーストーリー』これは映画や小説、ゲームのことではありません。
プロモーションの1つで、お客さんの不安や失敗を想起させてそれを解消・解決できる商品を私たちなら提供できると伝える手法です。
私はこのアプローチが嫌いです。
それを強く感じたのは、マーケティング部に在籍していた時です。
元々マーケティングに興味を持ち、社内公募による異動の機会を得て念願のマーケティング部に入りました。
私が扱っていた商品は、パソコンソフトの保守サービスでした。それは保険的な内容であり、「加入していないと困りますよ」というメッセージを前面に出していました。その効果は出ていて売上も伸びていました。
でも、私は疲弊していきました。
“きれいごと”かもしれないけれど、「加入するとハッピーになりますよ」というハッピーストーリーで届けたかった。これは言うが易しでなかなか難しいことです。
もっと言うと・・・。
会社に勤めている私たちのほとんどがそのソフトを必要とせず、日常的に使うことはほぼありませんでした。なので、ユーザーの気持ちを理解するどころか汲み取ることすら私には難しかったです。ユーザーアンケートもほぼ意味ないと感じてました。
そんな私たちが提供するサービスでどれほどお役に立てるのだろうか?
という問いがいつもありました。
私は、自社の社員が100%勧められないサービスをお客さまに勧めることに罪悪感がありました。
昨対○○%という数字にもヘドが出そう・・・。
私自身、お客さまに電話をかけ、サポート加入を勧める部署出身でした。
私は100%の加入を目指した結果が20%であり、20%を目指しての結果でなない!と、上司に食ってかかったことがあります。
この辺りの話は置いておいて元に戻します。
私は不安を煽って売ることが嫌いなんです。
清廉潔白な人間ではありませんが、自分が提案する内容には誠実でありたい。
これは私のお金に対する解釈がとても影響しているように感じています。
お金を稼ぐことは大変なことで、そのお金をいただくことは大変なことだ。
以前の会社の評判が悪かったのかと言えば、それは違います。
保守サービスによって問題が解決されたお客さまも多くおられました。その結果、安心や快適性を得た方もいます。
要は私の潜在的なお金に対する嫌悪感が炙り出されただけです。
ハッピーストーリーで届けたとしても、すべての人がそう捉えてくれるわけではありません。
これまたホラーとハッピーという二元論です。
ホラーだけ、ハッピーだけ、そんなのは無いですよね。
ハッピーだけも胡散臭い(笑)
現在のお金に対する解釈がどんな体験によって形成されてきているのか。
まずは自分自身のことを紐解いていきます。
自己探究の旅はつづく・・・
Insight Journey continues・・・
Vol.0955/2023年4月20日に配信したメルマガを加筆・修正したものです。
本号では他に「世間で使われるフレーズを再考する」「自分の中にある自然法則に気づけた」についても書いてます。メルマガにご登録いただければバックナンバーをお読みいただけます。
< 編 集 後 記 >
仕事やプライベートの場面で、イライラしたり心がざわざわするようなことに出くわす。
私には日常茶飯事です。勢い余ってイライラを相手にぶつけようものなら、決まって後味が悪い思いをするもので、そんなことも幾度となく経験しています。
最近、自分の解釈や思い込みが作り出す現実について学ぶ機会がありました。
今起こっている自分にとっての不本意な現実は、自分の解釈や思い込みによって作り出されるものであり、その解釈や思い込みを作り出す根っこには、過去の体験からくる痛みや恐れ、不安がある。そしてそれを避けるための行動が、また不本意な現実を引き起こす。
自分の中に感じる不快を避けるため、防衛本能として起こす自分の言動が、起こる現実を作っている、というわけです。
冒頭に書いたイライラ、ざわざわする出来事が、自分自身が無意識に駆動させている反応が引き寄せる現実だとすると…?
ちょっと頭を冷やして相手の言動を思い出してみると、確かに私の解釈や思い込みが入っていそうだぞ、誰も私を狙い撃ちしてきてるわけではないよね~、と苦笑。
そして、周りの人にも恐らくそれぞれ何かしらの痛みや恐れがあり、それを避けるために行動することがあるのだとすれば、相互作用によってさまざまなことが起こるのは何ら不思議なことではないし、そうやって人と人は関わりながら生きているのだとすると、お互いが引き寄せ合って作る現実も、味わい深く思えてきたりもします…。
にしても、これまで私の勢い余った反応に遭遇してしまったひとたち、ごめんねぇ。
お気持ち ありがとうございます。 あなたからいただいたサポートは、また誰かのサポートへと循環していきます。
