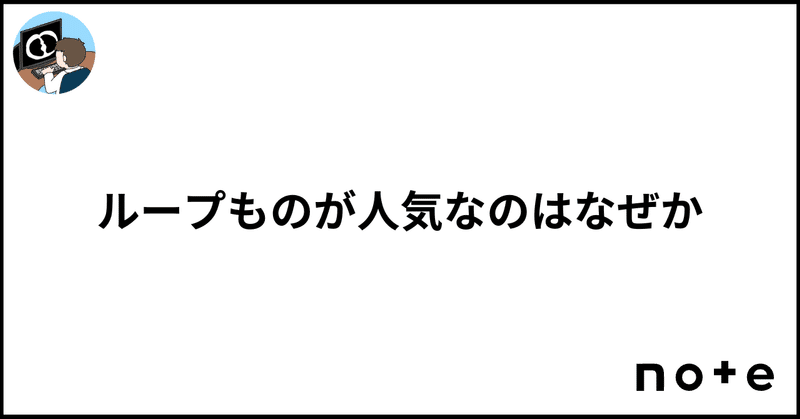
ループものが人気なのはなぜか
昨日の『8番出口』もそうですが、ループものは最近人気ですよね。江草の激推しのゲーム『Outer Wilids』もそういえばループものでした。
ループものとは、同じ日(なんなら人生全体)をひたすら繰り返して、自分の死だったり、大事件が起きたりするのを未然に防ぐために、やり直すたびに試行錯誤するアレです。
江草の家のリビングも夜にきっちり片付けたはずなのに朝起きると既におもちゃが無惨にも散らかっているという現象が繰り返されているので知らず知らずのうちに無限ループにハマってるのかもしれません。(違う)
もちろん、昔からジャンルとしてループものはあったと思うのですが、ここのところドラマに漫画に映画にと珍しくもない一大ジャンルとして普及した感があります。
ループものが人気の理由は科学的思考の普及かも
これだけループものが人気を博している、支持を集めている理由は何か、つい気になりますよね。
江草の仮説は、科学的思考のエッセンスが人々に広まったことが理由の一つというものです。世のループもののやってることは科学的思考(帰納的推論)ととても感覚が似ているからです。
理科の実験をイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。試薬なり、温度なり、分量なり、色々と少しずつ条件を変えてみて、結果がどう変わるかを観測して自然法則を解明したり、実用面重視のアプローチであれば何度も試行することで求める理想の結果に迫ろうとします。同じ状況から始めてやることを少しずつ変えることで試行錯誤するループものとそっくりですよね。
プログラミングもちょっと似たようなところがあるかもですね。同じコードであれば実行すれば(インプットが変わらない限り)基本的には同じ結果になることを前提としています。その実行環境が周囲の影響から免れていることを前提として、繰り返し試行錯誤をして求めるコードを開発するわけです。
科学の営みには「自然の斉一性」の前提あり
こうしたやり方は「自然の斉一性」が前提とされていることが特徴です。
「自然の斉一性」とは「同じ条件下で同じことを行えば同じ結果が得られる」というものです。「自然法則は常にいつでもどこでも同一に保たれている」という形の表現もされます。
もっとざっくりカジュアルに言うと「これまで太陽は毎日東から昇って西に沈んでるんだから明日も当然同じように東から昇って西に沈むだろう」という考え方です。だからこそ、今目の前で行った実験結果は、明日同じ条件であれば同じように再現可能だし、この実験結果を応用した製品開発も可能と信じられるわけです。
全く同じ状況で同じことをしても違う結果になり得るのだとすれば、明日全く同じ実験をしても違う現象が起きちゃうかもしれないし、製品化した途端全く思いもよらない動きを見せちゃうかもしれないので、そこに何の法則も見出せないし、実用化の目処も立たなくなってしまいます。
だから、あくまで、基本的に「普遍かつ不変的に成り立っている法則があるはずだ」という前提で、繰り返し実験をし、それが明日も将来もずっと成り立つのだと信じて営まれているのが科学的手法なんですね。
もちろん、同じ実験をしたのに同じ結果が得られないなんてことはラボではしょっちゅう起きます。ただ、そういう時でも科学者は「何か見えない条件が変わったせいで誤差が生じたに違いない」と考えるのであって「自然法則自体が昨日と変わったのだ」とは考えないはずです。
違う結果が得られた理由を「同じ条件や試行ではなかったからだ」といきなり断定する点で、やっぱりこれは「自然の斉一性」を前提としていることには変わりはないのです。
もっとカジュアルな例で言うと、体重計に乗って自分の体重が増えたのを見て「今日来てる服は重いから」とか「さっき水分取ったばかりだから」とか「体重計が壊れてるからに違いない」と言い訳する人はいても「この部屋の重力定数が変わったからに違いない」と言う人はまずいませんよね。これも「自然の斉一性」の前提が守られている一例です。
「自然の斉一性」は正当化不能
この「自然の斉一性」。何となれば、とても常識的で当然のことに思われます。しかし、実のところ正しいという確実な根拠はありません。というよりどうしても正当化が不可能なんですね。
たとえば、これまで「自然の斉一性」を前提としていた科学の歩みや、科学的根拠に基づいた様々な製品が現に実用化され上手く世の中で機能していることからすれば、当然これは正しいに決まってるだろと思われるかもしれません。
ですが、この発想自体「これまでうまくいってたんだから明日以降も同じようにうまくいくはず」と「自然の斉一性」を前提とした主張となっています。「自然の斉一性」の正当化に「自然の斉一性」を持ち出している循環論法の誤謬に陥っています。
困ったことに、「自然の斉一性」を正当化しようとしても、この循環論法からどうしても抜け出せないんですね。
つまり斉一性原理の正当化は循環論法に陥り、うまくいかない。
だが、自然の斉一性を仮定することは科学の基礎でもある。現行の自然科学は、基本的にひとまずはこの原理を仮定することによって成り立っている。
だから、絶対論理的に正しいとは言えないけれど「ひとまずそうしている」。そうであると信じて歩んでいる、それが科学の営みの実態であるわけです。
「自然の斉一性」の理想系がループもの
もっとも、ここで語りたいのは「自然の斉一性」の前提はダメだとか、科学は事実無根だとかいう謎の極論ではありません。江草ももちろんごく普通に「自然の斉一性」に基づいて生きてますし仕事もしてます。そして何より科学大好きっ子です。
ただ、このようにあくまで仮の前提、いわば思想に過ぎない「自然の斉一性」が、人々に広く信じられるまでに普及したことの象徴が「ループもの」ではないかという仮説の説明のために、「自然の斉一性」の紹介をしたまでです。
「自然の斉一性」の考え方を、最も理想的に実践できるとすれば、それは全く完全に同じ状況が用意されてる場です。そういう場であれば、得られた結果が違っても「何か見えない条件が違ったからかもしれない」などと悩む必要がなくなります。
結果が異なってしまった理由がただ一つ「自身の行動」すなわち試行内容そのものだけに限られるから、非常にスッキリするんですね。ただ、自分が何をすべきかという変数だけに集中できる。(ここでもちろん「自然法則が変わったせいだ」としないのが「自然の斉一性」です)
実際、科学者なら誰しもそのように全く同一の条件が保たれていて外部からの影響も全く受けない実験室を夢想するでしょう。そんな環境があればどれだけ楽か。
そうした科学者の夢を、作品として描き出したのが、まさしくループものというわけです。「自然の斉一性」の究極の理想系がループものだからです。だって、ループしてやり直すのだから、全条件は全く同じことが保証されています。試行錯誤し放題です。ヒャッホー。
そして、そうしたまさに科学者の夢みたいな話が、多くの作品に取り込まれ、人々に愛されるようになってきたことは、それ自体が「自然の斉一性」を人々が受け入れていること、すなわち科学的思考の発想が人々にインストールされたことの象徴であるのではないかというのが江草の仮説と言うわけです。
エビデンス主義と自助努力主義の「科学実験室」感
実際、「ループもの」に限らず、その他の場面でもその兆候は見られます。
「エビデンスはあるんですか?」という言葉が巷でも普通に用いられるようになったり、「周りに文句を言っても仕方がない、自分がどうするかで道を切り開くしかない」という自助努力的な言説がよく聞かれるようになったのも、同様にこうした「守られた科学実験室」的な発想が背景にあるように思われます。
エビデンスの存在にこだわるエビデンス主義というのは言わずもがな「過去の知見が未来にも成り立つ」というのを前提としています。
自助努力主義も、所与の条件であり不可侵な外部環境ではなく自分自身に選択権がある試行内容にのみ策を集中すべきという発想です。
これらは、「自然の斉一性」や「外部条件」に疑いの目を持ってはならない、という規範的前提が見られる点で、科学的思考の前提に類似しているんですね。
だから、こうしたエビデンス主義や自助努力主義的な言説が人々に広まっていることは、ループものが人気を博していることと合わせて、広く人々に科学的思考が普及したことの証左であると言えましょう。
広く普及したからこそ科学的思考の死角にご注意を
先ほども述べた通り、別にこれは科学的思考がダメだよとかそういう話ではありません。
むしろ、「科学離れ」が懸念されていたにも関わらず、いつの間にかこれだけ科学的思考のエッセンスが広く普及していたことは、驚異的なことと言えます。これが、果たして科学教育や科学コミュニケーションの成果かどうかは不明ですが、これはこれでなかなか素晴らしいことだと思います。
ただ、思った以上に普及したからこそ「過ぎたるは及ばざるが如し」ということで、その死角にも注意を払った方がいいだろうとは思います。
科学的思考の背景にある「自然の斉一性」の前提も必ずしも正当性が保証されてるわけではないですし、エビデンス主義や自助努力主義も「理想的な科学実験室」を夢想し過ぎているきらいがあります。
だから、あんまり素朴に科学的思考(帰納的推論)を絶対視すると、当然ながら視野が狭くなり、死角を作ることになるわけです。これがもし世の人々全員でやっていたらやっぱり危険なんじゃないかとは懸念します。
人々が複雑怪奇に絡み合う社会現象や政治経済なんかはカオスすぎて斉一性のある法則を見出すことは困難と言えますから、昨日のエビデンスもどこまで明日の事象に適用できるかは不確実性が高いです。(エビデンスがないよりもある方がマシという比較優位的な考え方でさえも確実な正当性が保証されないのが「不確実性」の恐ろしいところです)
また、自助努力主義が想定するほど、個人は外部環境から隔離されていないですし、そもそも外部条件を変えようとすることも個人の試行努力の選択肢の一つという可能性を勝手に独善的に除外しています。
科学的根拠(エビデンス)を声高に掲げる人や、自助努力の必然性を説く方々は、どうも「自分たちこそが現実を見ているリアリストだ」と現実主義を自認している雰囲気がありますが、江草個人的にはむしろ逆に「自然の斉一性」や「科学実験室の夢」みたいな理想的な仮定を勝手に信じ込んでいる点で、彼らこそが理想に溺れた夢想家に見えるというのが正直なところです。
残念ながら、世の中はそんな夢の「ループもの」ではなく、法則も外部条件もコロコロ変わりうる不確実な世界で私たちは生きているという現実を忘れないでいたいですね。
フィクションはフィクションとして、現実とごっちゃにしないように楽しみましょう。
あとがき
今回語った、帰納的推論の死角や、不確実性と付き合うことの悩ましさについては過去noteでもちょいちょい触れてますので、本稿のトピックが面白いと思われた方は、もしよければこれらの記事もご参考にしてください。
……って、昨日のnoteで書いたように、『8番出口』を息抜きのためと思ってプレイしたはずなのに、結局なぜかこんな固い話につなげちゃってるじゃないですか。
なんてこったい。
江草の発信を応援してくださる方、よろしければサポートをお願いします。なんなら江草以外の人に対してでもいいです。今後の社会は直接的な見返り抜きに個々の活動を支援するパトロン型投資が重要になる時代になると思っています。皆で活動をサポートし合う文化を築いていきましょう。
