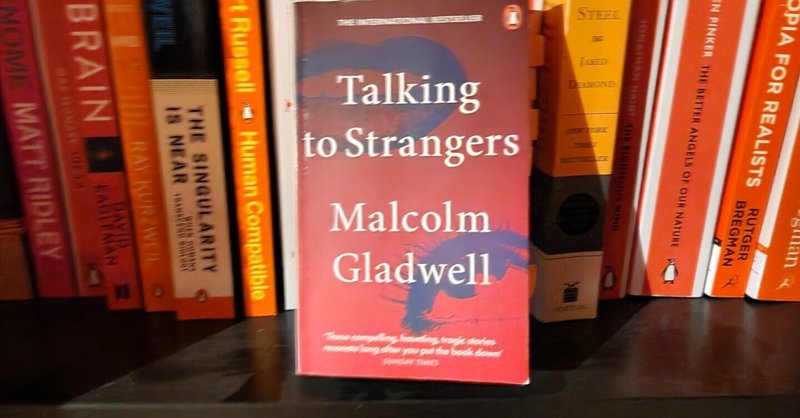
【読書】他人とのコミュニケーション/「Talking to Strangers」から
人は、見知らぬ人を判断するのが苦手。その理由として、人は他人の言動や仕草、あるいは人種や宗教といった情報に基づき人を判断してしまいがち、そこから悲劇が生まれるとするマルコム・グラッドウェルの一冊。
記事要約
本書のテーマは見知らぬ人に対するコミュニケーション。人は、見知らぬ他人の言動や行動を評価・判断する事が不得意、そこから悲劇が生まれる。
性善説的に他人が真実を言っていると思ってしまうDefault to truth的傾向がある。
豊富なストーリが散りばめられた読みやすいポップな本、テーマやストーリーは面白かったが、メッセージ性に欠ける気がした。
1.本の紹介
本のタイトルは「Talking to Strangers What We Should Know about the People We Don't Know」(2019年刊行)で、邦訳は、「トーキング・トゥ・ストレンジャーズ 「よく知らない人」について私たちが知っておくべきこと 」。
イギリス生まれカナダ人のジャーナリスト兼米国コラムニストであるマルコム・グラッドウェル/Malcolm Gladwell(1963-)著。

彼がhow to academy mindsetというプログラムで、本書を説明している動画は以下。
2.本の概要
物語は、些細な交通違反をした黒人女性(@テキサス)と彼女を取り締まる白人警官の会話から始まる。会話がエスカレートし、指示を出す警官に苛立ちを見せる女性、その反抗的な態度にたいし黒人女性を拘束する警官。結局彼女は逮捕され拘置所に送られ、そこで自殺してしまうというストーリーから始まる。
本書のテーマは見知らぬ人とどうコミュニケーションを取るか。人は、見知らぬ他人の言動や行動を評価・判断する事が不得意で、そこから悲劇が生まれると著者はいう。
その例としてアメリカのCIA奥深くまで潜入したキューバの2重スパイ、アナ・モンテス/Ana Montesやジェリー・サンダスキー/Jerry Sanduskyによる児童性的虐待の疑いを巡る国民的議論が紹介される。一見、これらの悪名高い2重スパイの卓越した隠蔽能力や児童虐待者の異常性に注目が行きがち。しかし彼らはむしろ、超一流のスパイでもなければ、自分の異常な性的嗜好を隠蔽することに長けた犯罪者というわけではないという。
むしろ彼らを取り巻く人間達側が、2重スパイの疑いや異常行動の片鱗を垣間見ながらも、それを問題として認識できなかったことにある。まさかあの人がスパイなわけないし、児童虐待者なはずはない。目の錯覚や自分の勘違いと思い込んでしまう。そういった性善説的に他人が真実を言っていると思ってしまうDefault to truth的傾向が人間にあるという。
そして興味深いのが、人が嘘をついているかほんとうのことをいってるか、裁判官とコンピューターの判断能力を比較した研究の紹介。結論としては、コンピューターの方がプロの裁判官よりも正しく判断できる。その背景には、裁判官の判断には物事の事実関係だけでなくそれ以外のextraの情報(例: 表情や感情表現、仕草、目付き)も加味して判断する、それが謝った判断に繋がりやすいとしている。
結果、プロの裁判官でさえ、有罪の人を無罪、無罪を有罪と判断してしまう。特にプロは、容疑者らの言動や行動を観察、無罪なら無罪者、有罪なら有罪者らしい振る舞いや言動をすると想定しており、そこにミスマッチが起こると謝った判断をしてしまう。つまり、無罪なのにも関わらず緊張のあまり変な行動や言動をしてしまう人は有罪と見られたり、有罪にも関わらず嘘がうまい人は無罪と判断されがち。
イタリアで発生した殺人事件で、殺害された若い女性の同居人女性とその彼氏が本当の犯人と共に逮捕、刑務所に送られた事件があったが、それは同居人と彼氏が、人々が考える"通常の行動"(例: 悲しい顔をする、お悔やみをいう等)から逸脱した行動(例: 翌日に下着の買い物に行く)を取ったから。
他にも、アメリカのスタンフォード大学の大学生による女子学生のレイプ事件なども取り上げられている。がここでは割愛。
3.感想
いつも通り、豊富なストーリが散りばめられた読みやすいポップな本。ノンネイティブでもサクッと読める優しい英語。
今回のテーマは知らない人に対する人のコミュニケーション。テーマやストーリーは面白かったが、メッセージ性に欠ける気がした。結局著者は、人は赤の他人を判断しコミュニケーションすることが苦手ということは分かったが、なにかそれいじょうのことをいおうとしているのか疑問だった。
なお、彼の他の書籍概要は以下
最後に一言
なお本記事は、あくまで私がポイントだなと思った部分のみ書き出しまとめているだけです。この概要記事がきっかけとなり、この本に興味を持っていただけたら幸いに思います。
あわせて他の記事もご覧いただけたら幸いに思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
