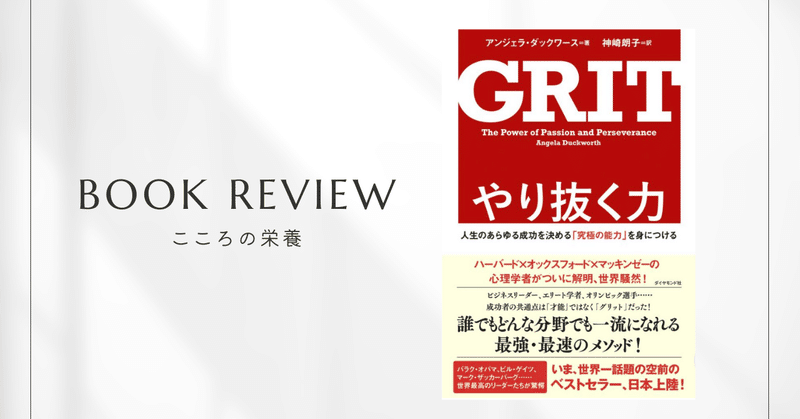
「やり抜く」という基準
こころが動かされた本との出会いを、琴線に触れたところにフォーカスしながら綴っていくBOOKレビューです。
要約
長期的な目標達成における「GRIT -やり抜く力-」という概念を探求する。
GRITとは、熱意と持続力を持って努力し続ける能力のことを指し、成功にはそのような特性が重要である。
才能×努力=スキル
スキル×努力=達成
このように、達成を得るには、努力は2回影響している。
目標に向かって困難や失敗を乗り越える力が、単なる運や才能よりも重要である。
GRITを高める方法として、4ステップがある。
1.興味:情熱を抱き、没頭する技術
2.練習:やっただけ成果の出る方法
3.目的:鉄人は必ず「他者」を目的にする
4.希望:「もう一度立ち上がれる考え方」をつくる
やり抜く力が高いほど、幸福感も高いというデータが出ている。
そして、この力があれば、誰でも努力で「天才」になれるのだ。
「やり抜く」の定義
日本人は、誠実・努力・勤勉といった美徳を育みやすい文化が形成されています。だからと言って、GRIT -やり抜く力- が強いとは限りません。
この本でいう「やり抜く」は、二つの要素から成り立っています。
ひとつのことに専念する「情熱」
動機が保てている「粘り強さ」
やめないことでもなく、ものすごく頑張るということでもない。
これだ!という興味に従って、本当に好きなことに打ち込み、愛し続けることができれば、それは情熱といえるでしょう。
この「ひとつのこと」という粒度は、人生哲学を織り交ぜた抽象度が「最上位」の概念を、さしています。
著者の職業人としての最上位目標は、「心理化学を利用して、子どもたちのしなやかな成長を助けること」。
この最上位目標の設定がとても大切。
これはパーパス/志と呼ばれるものに近く、パーパス経営が流行している理由が垣間見えます。
これに沿ってみると、私の場合はこんな感じです。
最上位目標
「自立と共生の場を通じて、争いのない世界を創ること」
中位目標
感性をひらくサービスで「間=自分に還る瞬間」を生み出し広げる
自立と共生のコミュニティを育む
下位目標
ブランドの仲間の輪を広げる
共感を生み出す
・・・など
この最上位目標を掲げるためには、これまで35年の人生体験、そして言葉として結晶化するために3年間を要しました。
しっくりくる目標にすることは、容易いことではありません。
固定概念や、格好つける他者目線の動機、そういったものを手放して、心の奥の奥にある願いに耳を傾ける日々。
一気に目指すことなく、仮留めしながら、言葉を紡いでいくプロセスです。現時点で掲げている、この目標もニュアンスは変わっていくかもしれません。体験が伴うほどに、磨かれて、ピカピカになっていくものです。
ニュアンスを味わう
興味の種は、どこに転がっているか分からないものです。
自分の好き嫌いを知り、外の刺激と交流する中で、「いつの間にか興味を持っていた」と気づく、そんな記述がありました。
ひとつ興味の軸が定まると、何を体験しても、その興味に結び付けられる感覚に入ります。
私は「人間」に興味を持っていると認識してから、どんなことでも人間に紐づけて考えるようになったからです。
「やり抜く」鉄人たちが、ひとつのことにずっと興味を持ち続けるのは、どう説明がつくのだろうか。
じつは、私と同様にシルヴィアも、エキスパートほどお「知れば知るほど、分からないことが出てくる」ということが多いのを実感していた。
-中略-
すなわち、初心者にとっての「目新しさ」とベテランにとっての「目新しさ」は、別物だということだ。
初心者は初めて経験することばかりで何でも目新しく感じるが、ベテランが目新しいと感じるのは微妙な差異ーニュアンスーなのだ。
人が意識を向けたところから、物事が始まっていきます。
いつもそれに対して考え続けていると、観察力が磨かれて、解像度がどんどん上がっていくのです。
意識をどこに置くか、「興味」に重心を置くことで、好きなことだから楽しんで取り組むことができます。そうすると勝手に努力ができ、どんどん熟達して「やり抜く」鉄人へと成長する流れが生まれていきます。
ニュアンスに気づき、味わっていくことで、好きから偏愛に、そして、こだわりへとステップアップしていくことを、楽しんでいきたいものです。
脳は鍛えられる
次のステップとしては、ありたい姿を定めて、そこに向かうためにやるべきことを細分化して「意図的な練習」を重ねていくこと。
さらに、鍛錬を重ねたことが、自分のためだけでなく、他者のために役立ちたいという目的が拡大していくことで大きな力を生んでいきます。
それでも逆境に立たされた時、どうしていくのか?
そのヒントが「希望」を持つことであると述べています。
才能は伸ばせると成長思考を持っていると、楽観的に考えられるようになり、無力感を乗り越えられる。
だから、逆境でも粘り強く考えられる、と説明があります。
それは、今からそうしよう!と決めて行動していくことで、脳もトレーニングしていけるのです。
そのときに必要なのは、乗り越えた体験。
脳の神経回路の再配線が起こるには、下位の抑制領域と同時に、制御回路が活性化する必要がある。
それは実際に逆境を経験して、それを乗り越えた時に起こる
これは、逆境を乗り越える能力に限らず、どんなことでも脳は可塑性という性質があるからこそ、いつまでも変容をしていけるのです。
成長思考の反対は、固定思考。
変わると決めたら、変わる。
変わらないと決めたら、変わらない。
年齢や、環境に甘んじて「変わらない」と思うとそのままです。でも「変わりたい」と強く願い、言葉を変えて行動を起こしていけば、脳も味方してくれるのです。
どちらを選ぶかで、その後の人生大きく変わりそうですよね。
常に脳をアップデートし続けていくコツをセッションでも伝授しています。
人生における研究テーマは「大人になった脳でも柔軟に可塑性を起こす」こと。
私自身も変容しながら、皆さんをサポートしていきたいと思っています。
興味ある方は、こちらからどうぞ!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
