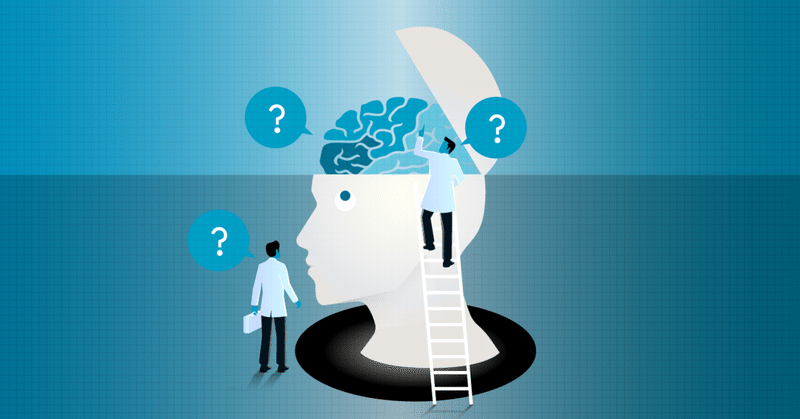
生涯の研究テーマ「脳と心」
私は、大学・大学院で生命科学と神経科学、医学を学んでいました。
神経科学を志すようになったきっかけや、博士課程に進まなかった理由も踏まえて、最近また別の角度から「脳と心」をテーマに学びを再開し、これは生涯の研究テーマだなと確信したので、私の頭の中を記しておこうと思います!
1.なぜ脳に惹かれるようになったのか?
私は中学校の時からパティシエになることを志しており、大学栄養学を学んでからパリで修業を積むという人生計画を立てていました。
しかし人生の転機が早速高校時代に訪れます。
校区内にあった公立進学校に進学したのですが、たまたま高校2年生になるときに、所属校が文科省が認定するスーパーサイエンスハイスクールに指定され、サイエンス特化型クラスが出来るということで話題に。
文理どちらに進むかも決めあぐねていたので、どうせ選ぶなら面白い方にと興味本位でそのクラスへの進学を決断しました。
そのクラスで、初めて「脳」というものに触れる体験を持ちました。
生物担当の恩師が阪大で神経科学を学んでいたという繋がりもあり、高校2年生の時の阪大の小田先生ラボでの実習をさせていただく機会がありました。(現在は、名古屋大学の小田洋一教授
今でも鮮明に覚えていますが、ガラス電極を作成し、その電極を魚の逃避運動をつかさどるマウスナー細胞に刺して、音刺激を与えたときの活動電位を見るというもの。
2日間という短い実習期間でしたが、当時の私のハートは鷲掴みにされ、神経科学を学んでみたいという想いが強くなります。
それまで志していた、パティシエという道を残すのか?諦めるのか?別の形を探すのか?当時は葛藤も多かったのですが、今の自分が興味を持つものを極めてから考えてみようという想いで、脳科学を学べる世界を探し始めました。
「脳」というのはフロンティアで90%以上が解明されていないということで研究も盛んにおこなわれていたのですが、まだスマートフォンもなく、研究室がHPを持っていることも稀な時代背景だったので、どこで何を学ぶのかは手さぐり。
そんな中、恩師から紹介いただいた一人の女性研究者と出会い、進みたい道が決まっていきます。
無事に希望する大学が合格し、大学4年生の時は高校の時から希望していたラボに所属することが叶って念願の研究者生活がスタートします。
2.研究者の道を諦めた理由
研究者は、非常に頭がいい人たちが、ものすごくストイックに突き詰めた先に見えてくる一筋の光を頼りに粘り強く、信念を貫いて、真理を探究していきます。
大学4年生からは、仮説を立て検証してみては上手くいかない原因を探る、一度上手くいっても再現性がとれなければ条件を見直す。科学者の基礎の基礎の部分、忍耐的なマインドも含めて鍛錬した生活を繰り返していました。
解明しようとしていることは脳科学の中でもほんの一部。
よほどの信念がない限り、地道な研究を続けることが難しいということ。
アントレプレナーシップに非常に近い感覚でもあります。
特に私が着手していた研究は、in vivoの研究がマストなので、なかなか仮説検証のスピードを上げることもできない、たくさんの論文を読み漁って、自分のやっていることが筋があるのかないのか突き詰めていく。全く進んでいない感覚。
焦燥感と挫折感を味わいながら過ごす毎日だったと記憶しています。
博士課程を見据えたときに、「本当に私はこれをしたいのか?」迷子状態の中で、真の志が見えておらず、周囲と比べたときに研究者的センスの欠如しているという感覚もあり、研究者という道を選ぶことが出来ませんでした。
私の最初の挫折です。
振り返るともっと別のアプローチを考えたり、ディスカッションしたり、交流の幅を広げていたら見いだせたものもあったのでは?と思いますが、視野狭窄。
目の前のことしか出来ていなかったなと思います。
脳を学んでいくと切っても切れない関係なのが心。性格や感情を創り出している脳への神経科学的アプローチは一旦中断するものの、興味は変わらないので別の方向から解明をしていこうと、こちらには一度心に蓋をして現実的に考えます。
高校まではパティシエになりたいという夢を持っていたという背景もあり、食を通じて心と身体の健康に寄与する食品メーカーでの就職を目指し、就職活動を始めます。
そこで最初に訪れる関門が、自己分析。
私が本当に何をしたいのか、そんなやりたいこと探しの旅。
過去にさかのぼって私がパティシエになりたかった理由を探します。
初めて自分が創り出したもので、人が感動してくれた原体験があったからです。
褒められると嬉しい、喜んでもらえるともっと極めたくなる、小学生の時は毎週お菓子作りに励んでいました。
特に好評だったのは、マーマレードクッキー。
大人たちから「売り物になるよ!また作ってね!」と言われたことをハッキリと覚えています。
人の生活に密接にかかわる食で、自分も大好きな食べ物で人の心を豊かにすることが出来ないか…そんなことを漠然とイメージしていました。
基礎研究では世の中への還元イメージがつかないということも味わったので、私が目指したのは直接商品を開発する商品開発部門。
ご縁があって、味の素グループに入社します。
会社に入ると様々な洗礼があり、脳と心の関係はすっかり忘れてしまった6年間でしたが、複数で部署が変わり、マーケティングに携わるようになり、基礎から学びを初めて、また思い出します。
「マーケティングって脳科学じゃないの?」と。
3.マーケティングと脳科学
マーケティング部門に配属になったものの、経営学やマーケティングについては一切の素人。本当に何も知らない状態からのスタートで日々勉強でした。
配属先部署は、マーケティングのみならず、商品開発、ソリューション営業、事業戦略立案及びPL管理、かなり手広く担当しなければならない刺激的な場所でした。
つまり、マーケティングだけではなくアカウンティングや、経営戦略など複合的知識が必要…何も分からないまっさらな状態の私はただただ危機感を感じました。
理系で学んでいたころもあり、基本を忠実に学びたくなる性質なので、マーケティングと経営それぞれの基礎を叩き込まないと、ということでMBAを教えているグロービス経営大学院大学の門を叩きます。
そこで、経営のヒト・モノ・カネ全般を学んでいくのですが、マーケティング系科目を取り進めていけばいくほど、心を動かす職種であるという理解が進みます。
既に廃止された科目ですが、「顧客インサイトとブランディング」は最も刺激的で最高のクラスでした。本人も気付いていない本音に触れていく、それを探る洞察力を養っていく授業なのですが、セオリーではない、人との対話、コーチングによって相手の深層心理を探っていくというもの。
そもそも、人はモノを買うとき、いいと思ったとき、必ず説明可能な論理的理由があるとは限りません。その要因を探ったり、仮説を立ててみたり、実際にインタビューを重ねながら体得していきます。
行動経済学に分類されるかなと思います。ザックリいうと、経営学に心理学を取り入れた学問です。人の行動をつかさどるのは脳であるといわれる中で、建前(思考)と本音(本能)を探っていくというのは、脳を神経科学ではないアプローチで分解していくような感覚で、知的好奇心爆発!
この科目を通じて分かったことは、私自身の脳と心への興味が失われていなかったということ。そして、神経科学ではない方法でも脳を科学することができるということ。
研究欲求が加速していく中…本業のマーケティングは妊娠によってお休みということに。でも、そんなことで諦めません。産育休中も何かしらの方法で、脳を科学できないか、色々模索をしていくのです。
4.多面的な脳へのアプローチ
MBAでの学びを通じて、再び脳と心に興味が集中していきます。
そして、妊娠出産を経て、さらに色々な書籍と出会い、多面的にアプローチしていきます。
恥ずかしながら、私は出産前後まで「内省」という言葉をほとんど使わずに生きてきました。MBAの授業の中でも志を探すために内省する、とか出産後に所属したMIRAISでコーチングというものに触れます。
自分とは何か?
何に興味があるのか?
何を成し遂げたいのか?
本当にやりたいことは何か?
様々な角度から自問自答を繰り返し、自分の心に向き合っていく。
「これも…脳科学じゃないの?」と思い始めます。
実際に、NLPというものはカウンセリングや神経科学と密接にかかわっているし、そもそも臨床心理学は脳科学の別の側面からのアプローチだし…面白い。内省・コーチングについては、詳しい方がたくさんいらっしゃるので専門的な話はお任せするとして、私の知的好奇心はかなりくすぐられます…
しかし、脳科学なんだと繋がったことに満足したので、コーチングを本格的に学ぶ、ということはしませんでした、限られた人生の時間をなんでもかんでも探求し続けると本当にやりたいことに割く時間が減ってしまう…ということで、この側面を知っておくだけでも非常に有益ということで、触れておくレベルで留まりました。これまでの通り、色々な視点から脳を分解しようと試みます。
次に手を出したのが、哲学と宗教。出口先生のこの本は、一家に一冊常備したい、辞書的な役割の本です。歴史から順番に、哲学と宗教を解説してくださります。
哲学と宗教が、なぜ脳科学に繋がるのか?ですが、これもズバリ、出口先生が冒頭に記載してくださっています。
人間が抱き続けてきた、2つの素朴な問い。「世界はどうしてできたのか、また世界は何で出来ているのか?」、「人間はどこからきてどこへ行くのか、何のために生きているのか?」この問いに対して答えてきたのが、宗教であり哲学であり、さらに哲学から派生した自然科学でした。
順番としては最初に宗教があり、次に哲学があり、最後に自然科学が回答してきました。そしてとくに自然科学の中の宇宙物理学や脳科学などが、2つの問いに対して、大枠ではほぼ最終的な回答を導き出しています。
ー中略ー
人間の意志決定や行動のほとんどは、脳の無意識の部分がコントロールしている。宇宙の構成要素におけるダークエネルギーやダークマターのような存在が、無意識の領域、といえるかもしれません。
そうなんです、神経科学でも解明できているのは10%にも満たないといわれており、私が探求したい道を神経科学のアプローチだけでは限界があると感じたゆえんです。
だからこそ、神経科学だけではなく、哲学、宗教、心理学、行動経済学、スピリチュアル、量子力学、様々な角度から脳を理解するために、書籍に触れ、自分のリソースを使って実証実験をしていく必要があると、強く感じています。
まだ考えはまとまってはいませんが、自分なりの仮説を、またnoteでも紹介出来たらと思っています!
最後に本の紹介
脳の視点から色々な本に触れ、良書にも出会いました。
上記で紹介していないものも、こちらに紹介しておきたいと思います。
まだまだ探求の旅が続くので、推薦書あれば教えていただきたい…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
