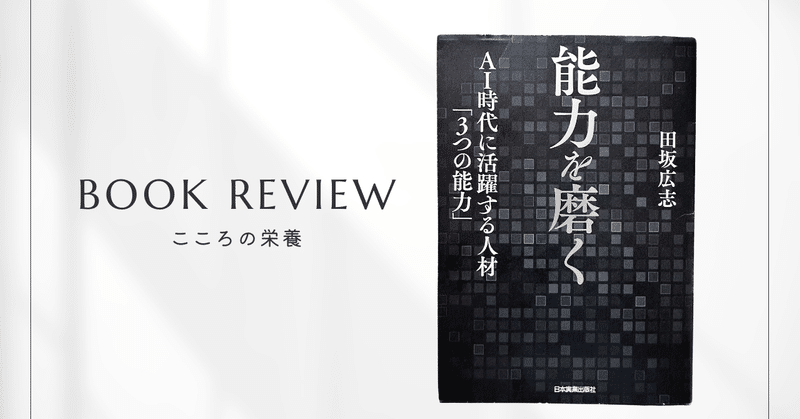
「能力を磨く」を読んで
こころが動かされた本との出会いを、琴線に触れたところにフォーカスしながら綴っていくBOOKレビューです。
要約
AI時代が到来しても、誰もが「AI失業を語る」、しかし誰も「対処法」を教えてくれない。この危機は、これから必要な能力を磨く絶好の機会である。
危機(crisis)とは、危険(risk)と機械(opportunity)の二つの意味を含むのだ。
これからの時代は、機械では代替できない人間の能力をさらに大きく開花させる革命だ。
では、AI時代活躍する人材に必要な能力とは何か?
知的労働に求められる能力は5つある。
基礎的学力:知的集中力と知的持続力
学歴的能力:論理思考力と知識の習得力
職業的能力:直感的判断力と智恵の体得力
対人的能力:コミュニケーション力とホスピタリティ力
組織的能力:マネジメント力とリーダーシップ力
このうち、職業的能力・対人的能力・組織的能力の3つだ。
AIに置き換え難く、淘汰されずに生き残る。
それぞれどのように磨くかを簡潔に述べると、以下の通り。
職業的能力:「知識の修得力」よりも「智恵の体得力と伝承力」
対人的能力:「言葉のコミュニケーション力」よりも「言葉を使わないコミュニケーション力」と「体験的共感力」
組織的能力:「管理マネジメント力」ではなく「心のマネジメント力」と「成長のリーダーシップ力」
この6つの力を磨いていくことで、これから活躍できる人材へと成長することができる。
知識を智恵に
これから個人セッションの門戸をひらこうと、「私らしさ」の棚卸をしています。ひとつのシンボルが胃的好奇心。
“食”や”食べる”をあらゆる角度から深掘りする事で
好奇心を膨らませ食べるを通じて人生を、ココロ豊かにしていこう!
食は五感をフル活用するもので、転じて、身体性や体験など頭ではなく身体で感じることもテーマに配信しています。
好奇心ドリブンで生きてきた私は、頭で理解することも大好き。
積極的に学びの場に身を置くのですが、たくさん知識を詰め込むほど、情報の波に溺れ、身体が悲鳴をあげます。
思考が先に走ってしまって、身体が追いつかないという現象です。
対処方法は、学んだら実践すること。
または、自分の引き出しにある、過去の体験と紐づけること。
知的好奇心も大切だけど、胃的好奇心も満たしてあげることで、心身が一致してバランスが取れてきます。
これを本書では、「文献的知識」と「体験的智恵」という対比で紹介しています。そして「経験」は「体験」まで深めていくことで、智恵となると語っています。
漠然と仕事の経験を積んでいるだけでは、そこから掴むべき智恵(体得した感覚)がこぼれ落ちて、体験にまで深められていかない。
体験まで深めるために必要なことが、反省=振り返り。
経験したことを何度も咀嚼して、意味づけをしていくということだと捉えています。
コンテンツが溢れる時代、動画配信で気軽に学ぶことができるのですが、ただ見て終わりだと消費で終わってしまいます。
そこから、一歩踏み込んで、これまでの自分を振り返って、次の行動を決めて実行する。
ここまでセットにすることで、初めて「体験的智恵」を掴むことができるようになります。
今、私たちに必要なのは、経験をもとに自らに「問い」を立てて深く思考していく力を育むことなのではないでしょうか。
体得したものを、伝承していく側に回っていくことで、さらに能力が磨かれていくと続いています。
ここで必要なのは、具体と抽象を行き来して解像度を上げていくということ。
個人的経験を体験として咀嚼して、それをメタ認知して捉えた時、どう表現ができるのか?個人のものから集合のものへと昇華させていくステップを踏んでいく。
ここで壁を感じます。暗黙知の伝承の難しさは、経験しないと体得できないからこそ。
心構えと、経験までのサポートをしながら、相手が振り返りをするところまで伴走していく。これは、もしかすると「組織的能力」にも繋がることかもしれません。
Comma Labで提供している、コーヒーの焙煎によって五感でプロセスを味わっていく体験の美しさも、言語では表現がしきれない。
まずはやってみる、そこから丁寧に対話をしていくことで、胃的好奇心が育まれていくのですが・・・最初の一歩を踏み出すための魅力が伝わらない。
精進します。
真の共感力
本書では、「共感力」について、このように説明があります。
相手に深く共感する力のこと。
同情や憐憫と混合されることがあるが、
「相手の姿が、自分の姿のように見えること」である。
-中略-
その本当の「共感力」を身につけるために何が必要か?
誤解を恐れずに述べよう。
それは、苦労の経験である。
この文を読んで、救われました。
ああ、あの苦しみや辛さは、人に共感をするために意図して体験したことだったのだろうと、過去の痛みを癒すことができたのです。
周りの方から「えすみんなら、分かってくれると思った。」と、言われることも多いのは、過去の私があったからなんだと。
今、確実に役立っているんです。
こういった共感力のことを「体験的共感力」と呼んでいます。
痛みを伴っただけ、強くなり、そして周りに優しくできる。
この言葉は嘘ではなかった、それを私はしっかりと「体験」してきました。私らしさの一つが、また見つかりました。
リーダーに求められるものは、究極「逆境観」である。
人生や仕事における、苦労や困難、失敗や敗北、挫折や喪失といった「逆境」を、どう受け止めるか。どう解釈するか。
その「逆境観」である。
そして、その「逆境観」の根本にあるべきものは、一つの覚悟である。
「人生において与えられる、すべての逆境には、深い意味がある」
その覚悟である。
全てのことは、最高最善に起きている。
私は、そう信じています。
願った未来に向かう中で、ぶつかる困難があっても、時に失敗をしても、自分を成長させてくれるスパイスだと。
スパイスすら、自らが望んで振りかけているのであって、それは必要な感情を体感していくため。それが、私なりの逆境観です。
人間力を分解しよう
この3つの能力を育むことは、ビジネスだけではなく、子育てにも、パートナーシップにも、さまざまな側面で活用できます。
これまで、人間力というビッグワードでまとめられていた言葉を、分解して、要素を抽出した時に、AIでは代替不能な「能力」として浮き彫りになってきました。
田坂さんの、真実として聞き届けた上で、私自身の考えも最後に述べておきます。
これからの時代は、この3つの能力を磨いていくことが必要です。
観察力:非言語も含めた全ての事象を注意して観て、察していくこと。
洞察力:観察したものに、意味づけをして、本質的な要素を見出すこと。
行動力:本質的なことを実行し、今の行動で未来を作っていくこと。
その第一歩として、自分の身体で実験することをお勧めします。
声なき声を汲み取るために、ボディスキャンをして観察していくこと。
不調や、好調なところを見出して、それがなぜ起こっているのか洞察をしていきます。
そこから、身体が本当に求めることが何かをキャッチして、行動に変えていきます。
今すぐに出来ることですよね。
東洋医学では「未病」という言葉があります。
これは、発病には至らないものの軽い症状がある状態を指しています。なんとなく調子が悪い、気だるい、眠気が取れない、これらも含まれます。
現代人は、未病が多い。
心的ストレスや、環境による外的ストレスにさらされ、病名のつかない不調が蔓延しています。
医師を頼ることはもちろん大切です。でも、任せっきりになるのは危険です。自分の身体のことは、自分が一番よく知っています。
今こそ、身体と対話をし、声なき声に耳を傾けるとき。
これを内受容感覚といい、脳の島皮質で情報が統合され、ここが育まれると共感力が高まるいう研究があります。
マインドフルネスも、内受容感覚を研ぎ澄ますのに効果的だと言われています。今に集中する、その一つの対象として、自分の身体を観察して、洞察して、行動に移していくことをお勧めします。
これを習慣化をすることで、感度が高まって、直感と思われていたことをも、体感覚的に説明ができるようになると思うのです。
田坂さんがおっしゃっている3つの能力を磨くことにも繋がるのではないでしょうか。
心、身体、思考、全ては繋がっています。
このズレが、いわゆる不調を生み出します。
ズレに気づき、調律していく個人セッションを提供しています。
ご興味を持っていただきましたら、こちらからお申し込みください。
お目にかかれるのを楽しみにしております。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
