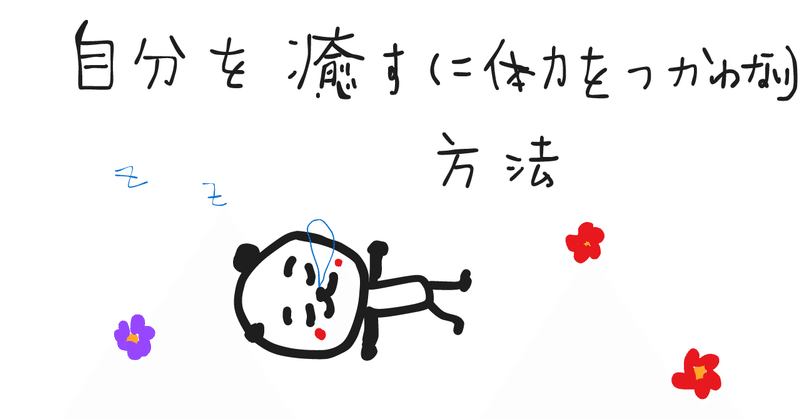
自分を癒す(=体力をつかわない)方法
1 自分が「うつ」になった時の周りの反応
うつは本来の自分とは違う感性や思考になり、
少しの刺激に過剰に反応し、
様々なつらい身体症状が現れ、
生きていく気力さえなくなってしまうこともある状態である。
現代人の場合、ほとんどが感情疲労による蓄積疲労が原因でうつになりやすいようだ。
大変つらい状態だが疲労し切っているだけだから、しっかり休みさえすれば回復する。
しかし、これがまた難しい。
なぜなら、休むといっても数日の休みでは足りない。
疲れ切ってしまっていると骨折から治るのと同じぐらい、数か月から数年の時間がかかるからだ。
この間、周囲や家族がサポートすることも多くなる。
当然のことならが、家族は大切な家族や仲間を「必死に」支えようとしてくる。
例えば、死にたいなどと本人が考える場合は、その考えを変えさせようとする。
また、乱れている生活リズムを整えさせようとする。
さらに、過剰に自信がなく不安な思考になっている本人に「もっと違うポジティブな考え方」のヒントを教えてくる。
悩んでばかりでなく、行動して問題解決することを勧めてくる。
悩まない体質になるように、運動や自己啓発を勧めてくる。
また、周囲の人も「もし自分だったらこうサポートしてもらうと救われる」と考え、援助してくるのだ。
しかしこれらは、元気な時の悩みを解決する方法だ。
実は、うつの時は、「考え方を変えろ、行動しろ」と言われるのが大変つらいのだ。
うつの時に頑張れは禁句というのは昔から言われるが、どうしても家族や周囲の人が必死になりすぎるのも理解しておくこと、自分を癒す(体力をつかわない)方法が変わってくるのだ。
2 心の立て直し方
自分を癒す(体力をつかわない)為には、
まずは「認める」、
次は「離れる」、
そして「休む」の順番が大切だ。
つまり自分を癒す(体力をつかわない)ということは、
弱い自分を認め、
そしてストレス源から上手に距離を取り、
最後に疲れた心と身体を癒し、
そしてまた戦うということだ。
逆に、自分を癒していない(体力をつかう)時は、直面する問題解決には関係しない方法から、逃げている、成長しないと感じる
心の葛藤の天秤の揺らし方として、人は二者択一で悩むことがあるが、特にプチうつになると不安を中心に考えてしまうのだ。
どちらを選んでも悪いところやイメージされ、どちらも選びにくくなるのだ。さらに、そのまま抱え続けるのも辛くなる。
自分を癒す(体力をつかわない)ためには、そういう時はとにかく、軽く行動してみることがポイントになる。
例えば、同じぐらいの重さの物を掌に乗せて、ただじっと比べていても、なかなか差を感じにくい。しかし揺らしてみると比べやすくなるのだ。
これは重さが、加速度として拡大されることから、感じやすくなるのかもしれない。
実は、心も同じなのだ。ずっと頭の中で悩んでいては、決められない。
とにかく行動して、不快感の加速度を感じてみるのだ。すると、決めやすくなるのだ。

原因を自分に求めるか外界に求めるか
何かあった時に原因を外界に求めるか、自分自身の内部に求めるかの2方向の対応がある。
1 外界に求める他罰傾向である。
他者に何かを改善してもらうための行動で非難、要求をとることだ。
この時発生しやすいのが怒りの感情である。怒りによる攻撃、相手を撃破する時に、一瞬の自信や高揚感を感じるが、結果は相手次第で決まるので主体性がなく、深い自信は感じにくい。
2 自分自身に求める自罰傾向である。
反省し自らの行動を改善することだ。この時は、自責の感情が起こる。
自責は改善を自分に強いるので負担が大きいが、逆に言うと、自分で事態をコントロールできる部分があるので、自信に通じるので無力感を小さくできる。
自責は一見、自信がないように思えるが、逆に根柢の自信がある人が感じる感情なのだ。
自分を癒す(体力をつかわない)時は、この2つの視点を自動的にシフトしながら、上手に使っていくとうまく癒される。
まず敵が近いときは、1の外に原因があるという視点にする。
これは、相手がいるので相手に改善してもらうことが先決だ。
この状態では怒りが沸くが、怒りは原因が自分ではなく、相手にあるという前提で情報を集め、その視点で思考を進めていくのだ。
次に敵から距離が取れ時間が経つと、次第に2を発動し始めさせる。
自責は自分が悪いという前提の思考である。
しかし実際は、相手が悪い部分と自分が悪い部分もどちらもある。
自分を癒す(体力をつかわない)感情機能が、緊急性という現実に応じて、自然に「怒りから自責」と認知をシフトしてくれることで、人の対応を幅広いものにしてくれるのだ。
自責で受け止めるか無力感で受け止めるか
辛いことがあると、自責を中心に受け止める人と、無力感を中心に受け止める人の二つのパターンに分かれるようだ。
1 自責を中心に受け止め傾向では、自分が何か悪かったのではないか、自分がやるべきことをしなかったからこうなったのではないかと、現在の不幸の原因を自分に紐付けて考えるのだ。
これは自分のあら捜しをすることなので、とても辛いことで我慢もたくさんする。
また、他者から非難されるかもという不安や対人恐怖を感じ、他者に影響を与えようとしてもそれがうまくいかないでイライラを感じやすくなる。
この自責スタイルで受け止める人は案外多く、その思考の背景には「この事態は自分でなんとか対処できるところが大きい」という認識が隠れているからだ。言い換えれば、ある種の「自信」が潜んでいる。
2 無力感を主体に感じる傾向で、「自分は何もできない」という認識がベースになる。
翻弄される感じで辛いが、自分にやれることがないのなら諦めるしかない、つまり自助努力をする必要がないので、楽な面もあるのだ。
自分を癒す(体力をつかわない)ために、どちらの認識が正しいかどうかではなく、「今の自分」にとってどちらのスタンスの方が今回のストレスを受け流しやすいかが大切だ。
さらに自分をしっかり癒す(体力をつかわない)為に、この辛さが大きい時は、この自責と無力感バランスを意識的に調整してみるのだ。
例えば、震災ついての事態の発生や社会・周囲の人動きは、自分にはどうにもならない場合は無力感で対応して諦めるのだ。
しかしそれに対して、どう生きるかは自責と認識し、自分でエネルギーを使って改善できる範囲だと考える。
このバランスだと、社会に過剰に不安がり絶望やイライラすることもなく、むしろこの変化をなんとかうまく活用して、より充実した生活を送ろうという意欲が湧いてきてくるのだ。
無力感は自信がない極端のバージョン
無力感は人のメンタルヘルスケアの中核部分である。
自信のなさは、不安の強さに通じる。
無力感は「何をやってもダメだ」という途方に暮れる感じで、自信がない極端なバージョンである。
無力感には3つのバージョンがある。
1 「あることができない」という部分的な無力感である。
これは生きてる限り誰でもおこる。
落ち込むが、それをバネにして成長する原動力にもなる。
2 うつ状態の人が感じている無力感である。
まず「できない」に、
「いつもやっていたこと」ができない、
「他の人は簡単にできているのに自分だけできない」、
という要素が加わり、
「自分がダメになってしまった」という感覚になるのだ。
自分の人間としての機能に関する信頼の低下である。
こうなると「こんな無能な自分は周りから、切り捨てられる、見捨てられる」ような恐怖を伴い、苦しさのレベルが一気に上がるのだ。
3 そんなダメな自分でも守って、受け入れてくれる仲間・組織がある、という認識が崩れてしまった時である。
「居場所がない」
「誰にも必要とされない」となってしまう。
うつ状態になると、いつもは感じることの少ない2と3の無力感が急に強くなる。
現代人のうつ状態は、蓄積疲労が主因なので社会生活を休むことによって回復するのだが、一方で「会社を休む」となると、この2と3の無力感が強く刺激される。
だから辛いのに休めないというジレンマに落ちいっていく。
自分を癒す(体力を使わない)為には、まず3の無力感をケアする。
自分の苦しい話を否定せずに聞いてもらうことで、自分の苦しみを分かってもらう人が1人はいるという感覚を持つのだ。
3の無力感がある程度満たされると、すこし理性的に戻れ、休むという決断に進みやすくなる。
うつについてあまり知識のない周囲の人々が、本人に自信をつけさせようとして、何か課題を与えて克服させようとしがちだが、
それは1の無力感対策であり、うつ状態の時はむしろ負担感の方が強く、つらくなることの方が圧倒的に多いのだ。
考えないようにする、忘れてしまう対処
人は嫌な出来事があると、それを考えないようにして乗り切ろうとする。 この考えないようにするという対処法は、現実的な刺激から離れるためには大変有効な手段である。
もちろん、物理的に離れられれば一番いい。
それができなければ、時間的に離れる、イメージ的に離れることを試みる。考えない、というのはイメージ的に離れる手段である。
考えないと同じような技術に「忘れる」「他のことに集中する」「終わったこと、考えても無駄、答えは決まっている、などと言い聞かせる」「アルコールなどの快でごまかす」などがある。
この対処法は大変な優れモノであるので、小さい時から、このスキルだけを鍛えてきた人が多いかもしれない。そして、それでだいたい乗り切ってきた。
しかし、現実の刺激から距離をとるには適切だが、思い返しに対して使うと防衛記憶を育てやすい。嫌なことを忘れてしまうのは、それはそれでOKだ。しかし、当然その人のことを思い出しては嫌な気分がするので、また必死に忘れてしまう。何とかやり過ごし日常に戻るが、しかしまた思い出す。 結局、何度もその人の嫌なイメージを思い出すことになり、その人の邪悪、危険な部分が増幅された防衛記憶が出来上がりやすくなる。
自分を癒す(体力をつかわない)ために思い返し記憶には、触れていく。
自分で押し殺して、無かったことにされている感情や言い聞かされて委縮している感情に、「触れて」それの声を聞く。
しかし、触れ過ぎると感情に飲み込まれて苦しくなる。
一方できちんと触れないと、いつもの言い聞かせの答えのままになるのだ。
触れるには、距離感がとても大切なである。呼吸で緩んだ身体と自己愛で問題を考えることで、問題との良い距離を保つことができる。
防衛記憶を防ぐのに、その時は感情に巻き込まれないように触れながら、自己愛(体力)を作り記憶とのちょうどよい距離をとりながら、慣れていく。
すると、記憶にうまくアクセスできて慣れが生じ、新しい見方が生まれる。そうすることで防衛記憶とならず、過去のファイルに収まってくれるのだ。
例えば、我慢強い人が恨みを育てあるとき暴発するのは、この触れるという感情のケアのスキルを知らないからだ。

つらい出来事の後の成長
辛い出来事の後、それを引きずるのがPTSDだ。
しかしつらい出来事の後に、それを糧にして成長できることもあるのだ。それをPTG(Post Traumatic Growth)といい、その力をレジリエンスと呼ばれている。
何がPTSDとPTGを分けるかというと、経験したことが自信になればPTGになる。
ところが成功しても「たまたま」と感じれば、それは自信にならず、今回はたまたま生き残ったけれど、つぎは避けなければならないと強く警戒するのでPTSDになる。
たまたまと感じないために、
「自分にはこれができる」、
「自分の能力や生き方はこれでいい」、
「自分には仲間や愛する人がいて居場所がある」という自信が満たされないといけないのだ。
悲惨な出来事の後は自分は何もできなかったので「自分にはこれができる」の自信が低下し、
フラッシュバックや悪夢などで自分は壊れてしまったと「自分の能力や生き方はこれでいい」の自信も低下していく。
このときPTSDを避けるには、そのつらさを本当にわかってくれ、自分を責めず、しかも頼りがいのある仲間が必要になる。
例えば、死にたい人には仲間が寄り添えばいいだけだ。
その人の人生の苦境を代わってあげることはできないし、下手にその人の人生にアドバイスもしない。
しかし、比較的近くにいて、身の回りの世話を焼き、必要なら話し相手にはなれる。
普通の、日常的気づかいをするだけなのだ。
なぜなら死にたい気持ちを抱えている人は、内面の問題を抱えながら、日常生活を送るのさえ難しくなっている。
その日常生活を支え、孤独でない環境を作るだけでも大きな支援になる。

幸せを感じる方法
自分を癒す(体力をつかわない)為に、幸せを感じられる、感じやすい状態にすることは可能だ。
つまり長期的な不幸を呼ばないで、一時的で些細な幸せを感じやすいように自分を整えておくことが、現実的な幸せを感じる方法になる。
自分を癒す(体力をつわない)ことから考えると、
嫌な刺激から離れること、
疲労をためないことが、一番現実的で幸せを感じやすい状態だ。
その後に、
自分の身体を鍛えたり、
成長を感じることで得られる自信、
仲間や組織との絆を感じられる自信なら、
自分でコントロールして補強できまる。
そのほかにも、記憶のケアもある。
自分が幸せかどうか、
これから幸せに過ごせそうかどうかは、
実は記憶によるところが大きいのだ。
そこで、過去記憶が重要になる。
人は危険を回避するために、ネガティブなことを記憶しがちになる。
客観的に普通の日でも、否定的な視点で認識しそれを記憶しがちなる。
そんな昨日が連続した過去は、どうしても幸せとは感じにくくなるのだ。
自分を癒す(体力をつかわない)為に、昨日のまだ記憶が鮮明なうち、良いことを意識的に復習して「昨日はまあまあ良いことがあった、良くできた」と認識しておくのだ。
一日分のプラスは小さくても、塵も積もれば山となるのだ。
その視点が癖になるころには、うっすらと自分の人生もまずまずだと感じやすくなっている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

