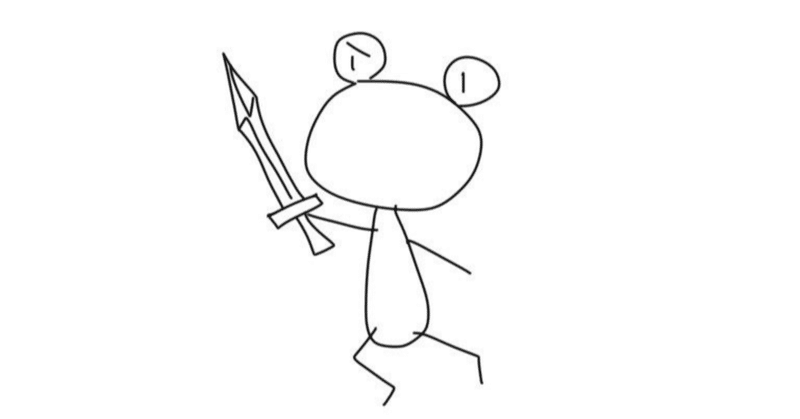
僕はもう一人で闘わない、闘えない
こんにちは。安田です。いかがお過ごしでしょうか。今回は個人的に試験があったので、その話を。その名もCandidacy examと言います。その試験に合格することは北米では博士課程を卒業するために必要な条件となっています。話を聞く限り、日本の博士課程ではこのような試験を導入している大学は稀であり、最後に自分の研究を発表し、教授からの質問に答えて卒業するようです。なので、あまりイメージしにくいかもしれません。
ですのでこの試験の説明から。この試験ですが、大学、学部、学部内のグループによってフォーマットが違うようです。私の場合ですが、事前に3つのトピックについて(私の場合、モチベーションの文化差について3つの理論を用いて70ページほど執筆)ペーパーを書いて、コミティメンバーと呼ばれる、そのトピックに詳しい教授グループに提出。そのペーパーが受理されると、次に口頭試験。この試験では、そのコミティメンバーと呼ばれる教授で構成されるグループの前に立ち、最初の10分で自分の書いたペーパーについてのプレゼンを行い、その後、3時間にわたって、教授からの質問を受け続けます。
例えば
試験官「文化を定義してくだい」
私「文化とは…」
試験官「あなたの定義からするとカップルに文化は存在しますか?」
私「私の定義からすると…」
や
試験官「防止焦点はスポーツではあがりと正の関連があるらしいのですが、防止焦点優位の日本人は促進焦点優位のカナダに来たらあがりは減ると思いますか?」
私「考えうるシナリオ、結果を左右する要因は最低でも二つあるでしょう。一つは…」
そうやって、一人ひとりの試験官が納得するまで私に質問をし続けます。そして、3時間後、全員の質問が終わると、私は部屋から出て、試験官が私が試験に受かったかどうかを議論して、結果を伝えて終わる、という試験です。要は、私が博士号を取るに値するほど、幅広く、且つ、深い知識があり、論理的思考ができる人間なのかを試す試験ということです。難しさとしては個人的に大学院で一番難しいと思います。自分の研究についての発表であれば質問は常にその研究についてだけですが、今回は、より広範囲のトピックを扱い、教授も基本的に何でも聞いていいからです。だから、私のトピックと教授自身のトピックを混ぜ合わせた質問をしたりするわけです。そして個人的に大学のレベルを上げて(どうやら最近世界の大学ランキングトップ100に入ったぐらいのレベル)且つ、応用心理学ではなく基礎心理学というゼロからイチを生み出す人たちの世界に飛び込んだわけで、かなり難しい試験になるだろうと思っていました。
ここで私のストーリーを一つ。話は少し変わって、博士課程の前の修士課程の話。修士課程の卒業するための試験として研究発表があるのですが、基本的には同じフォーマットで行われます。自分の研究について10分ほど話して、研究について複数の教授から質問を2時間ほど受け続けるというものです。私ももれなく修士課程を卒業する際にそういう試験をしたのですが、一つの質問にうまく答えることができませんでした。おそらくそれが原因だと思うのですが、私が卒業するに値するかどうかを試験後に教授グループが話し合った時、一人の教授が安田は卒業するに値しないという意見で、私の卒業が危ぶまれたんです。結局、無事卒業はできたのですが、それから今の今まで3年間、研究者として、劣等感を抱きながら生きてきました。そして、その劣等感をモチベーションに、その劣等感を払拭するために、どういう思考をすれば有能な研究者になれるのか。そのためにはどういうトレーニングをすればいいのかを考え、それを実践しながらここ3年を生きてきました。だから、今回、同じようなフォーマットであるCandidacy examには”勝たなくちゃいけないんだ”と思っていました。この試験に受かってこそ、研究者としてあの時から成長したと言えるんだ。今まで積み重ねた思考やトレーニングが正当化されるんだ。これに受かってからが研究者としてのスタートラインなんだと思っていました。そういった意味で私の中ではリベンジだったわけです。
ただ、それと同時に一人で闘うということに疲れ切っていた自分もいたんです。今まで、正直、自分の身、一つで闘ってきたんだと思って生きてきました。
この記事にもあるのですが、
https://note.com/enjoyfootball28/n/n406a895dd6b9
例としては、イギリスの大学院に進学する前。私の周りの人間は海外の大学院に進学する人間はおらず、ふとネガティブになる自分と向き合うことで、自分を前に進もうとしてきました。そうやって一人で闘ってきた理由は探せば色々あるのでしょうが、その一つとして、根底に「自分の人生の経験は誰も経験していない。自分の経験はあまりにユニークすぎる。だからきっとだれにも分かってもらえないだろう。」という一種の犠牲者精神だったように思います(今となっては「ちゃうねん。お前がちゃんと説明しない限り他人は知らないし、分らんねん。」っと突っ込みたい)。だから、特段一人で闘うなんてかっこいいように聞こえそうで、ただの強がりだったんです。そうやって、ブルドーザーのように自分の人生を前に推し進めているように見えて、実は操縦士は耳を塞いでいる状態だったんです。とはいえそういった考えから、今まではふとネガティブになる自分とは、もう一人の自分がその自分と会話させることでしか自分を前に進めることができなかったんです。
ただ、そうやって一人で闘うことはだんだんとできなくなっていました。その一つの理由として、「誰も知らないのに僕は何でこんなに頑張らなくてはいけないんだ?誰もこんなに頑張っていないのに何で自分だけこんな思いしなくちゃいけないんだ?この努力の先には一体何が待っているんだ?」と疑い始めたことが原因だと思います。だから、自分を守るために、そんなネガティブな自分と闘えるように、自分の挑戦には意味があるのだと思えるように、意識的に色々な人とつながろうと思ったんです。特に、パンデミック下でできた少数の大学院の友達。スポーツ系でつながった友達。オンラインでつながった友達。そして、圧倒的信頼を置くお世話になっている大家さん。時としてバーに誘って友達と話をしたり、メッセージを送って、どういう対策をすべきかのアドバイスをもらったりしていました。そして、試験当日、朝起きたら、そういった人たちから応援メッセージが届いてたんです。本当に僕の周りにいる人はみんないい人(こんな形容しかできない自分を恥じる)。そして、この応援メッセージは確実に自分の力になった。プレゼンの直前、大家さんからのメッセージを見て、「大丈夫、自分の力を出せば問題ない」と思えることができました。それぞれの方のそれぞれの言葉が、確実に自分の力になり、試験に臨むパワーになっていました。
結果、試験に受かることができました。それ以上に「あなたの結果を決めるのに時間がかかりませんでした。」という言葉が嬉しかった。その言葉で、ようやく修士課程から続いた劣等感をぬぐい、しっかりと3年前から成長し、研究者としてスタートラインに立てた気がしました。そしてなにより、そうやって応援してくれた方々に本当に感謝したい。実際、テスト練習を前日に行ったのですが、試験が終わった後「あの時は受かるか心配だった」という教授からの言葉がありました。前日から当日にかけて、自分のパワーを最大発揮できたのは、確実に応援のメッセージがあったからであり、それが無ければふとネガティブになる自分のセルフトークに負けて、結局、自分のパフォーマンスも変わっていたと思います。だから、これからは、一人で頑張ることはせずに、自分の弱さを認めながら成長していきたい。そして、頑張っている人を見つけたら、今度は自分もその人を応援できる人間でいたい。30代。まだまだプレッシャーと闘ってる。まだまだ成長してる。これからも頑張る。
よろしければサポートをしていただけると嬉しいです。博士課程の学生らしく、貧乏な暮らしをしております。
