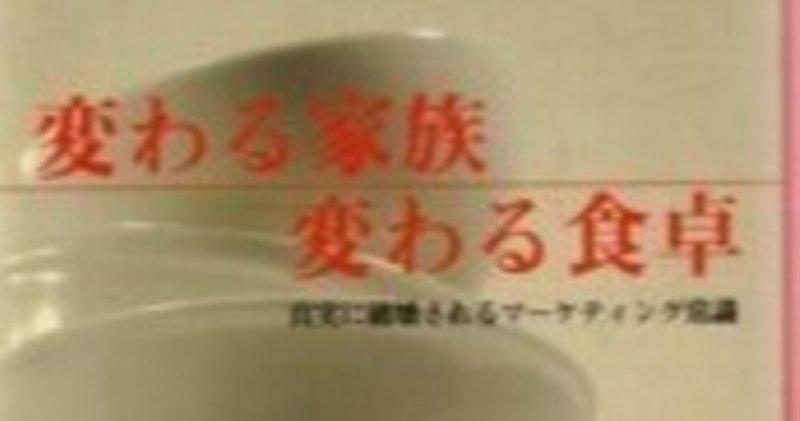
岩村暢子『変わる家族変わる食卓 真実に破壊されるマーケティング常識』(毎日読書メモ(514))
岩村暢子『変わる家族変わる食卓 真実に破壊されるマーケティング常識』(勁草書房、現在は中公文庫)を読んだ。『普通の家族がいちばん怖い 崩壊するお正月、暴走するクリスマス』(新潮文庫)を読んで衝撃を受け、その前段にあたる、通常の食事(『普通の家族がいちばん怖い』は、クリスマス、正月等行事食を中心にまとめた本だった)のリサーチ結果をまとめた本を手に取ってみた。2003年の刊行で、1998年から2002年にかけて、年に1回ずつ行われてきた調査から見えてきた事項について述べられている。
今から20年近く前のリサーチだが、現代家庭の食生活というものが、作者がイメージする家族生活とその基盤となる食、というものとは激しく乖離していることが、どのページからも読み取れる。読者であるわたしも、たぶん気持ちは作者に近く、えっ、これが日常の食事なんですか、と驚くような事例多数。一方で、リサーチに対してデータを提供している側は、自分は自分なりに食について考え、実践しているつもりだが、その「つもり」が、「諸事情により」イメージ通りになっていないことが、「きわめて頻繁に」起こっていることを、必ずしも自覚していないらしい、ということが読み取れる。1960年以降生まれの主婦に対する調査が中心となっているが、その世代で既に、家庭で家事の手伝いを殆どしていないらしいこと、そして、並行調査で調べた家庭科の教科書を見て、家庭科の教科書において、調理への記載が大きく簡略化されたところを境目に、家庭での調理も一気に、手間をかけた「きちんとした」料理が衰退していっていることが読み取れる、という結論に達している。
本を読みながら、印象的だったフレーズを幾つかメモしていたので以下引用する。ページ数は単行本(勁草書房)に準拠。
したくないということを簡単に言うようになった背景には、「こんな食卓じゃ不満だ」「それでも食べたい」という欲求自体が低くなってきていることも関係しているに違いない。
私たちはそれを「自分母尺度の平等感」(個々が自分尺度で「満足の平等性」を求める感覚)とも呼んで、現代家族の平等感の特徴と捉えている。
簡便食品や、でき合い品は、女性の高学歴化や社会進出で、近年売れているわけではない。我慢しない、譲り合わない、個の尊重の加速化と家族間の葛藤回避志向、そしてそのような要望に対応し切れない主婦に、絶好の商品として選ばれていることは見逃せない。
大変でも「しなければならないから」「すべきことだから」とちょっと無理をしたり頑張ったりすることを夫婦ともあまりしなくなり、子どもにもさせなくなっている。外側からの働きかけは「強制」「無理強い」と言われ、自ら頑張ったり無理したりすることは「良くない」と考えられているから、この共感的で寛容な家族関係が毎日の食卓を楽な方へ楽な方へと変化させていることは否定できない。
年齢が若くてまだ経験が浅いから判断できないのではなく、「自分の感覚や考えに拠って行動する」ことは「いい加減なこと」「危険なこと」、それよりは「書いてあることに従うべきだ」とする考え方が共通して認められることに注意したい。彼女たちは「書いてあるんだから、そうするべきでしょう」と言うのだ。
その時々、自分に都合のいい使える情報だけを集めて当てはめていくことを、私は「自己愛型情報収集」と呼んでいる。
「配合飼料型メニュー」が、以前からある「五目入り」と異なるのは、素材自体の特性やミックスしたときの味のハーモニーなどは度外視して、食材を栄養・機能で記号化して捉え、その種類や量を優先しているところにある。ワンメニューで効率よく多種の「記号」を網羅しようとする指向とも見ることができる。
このように舌や腹で食べるのではなく、「頭」で食べる食になってきていることも、今日の食卓の崩れに拍車をかけているのではないだろうか。
「栄養・健康」の名のもとに食卓によく出現するものは、ゴマ、シラス、バナナ、納豆、ヨーグルト、魚肉ソーセージ、ブルーベリージャム、冷奴、冷凍枝豆などで、どれも主婦の手を一切わずらわせずに「出すだけ」の食品ばかりである。そして、それさえ出せばバランスのよくない食事でもすべてが相殺されるとでも言わんばかりに、アリバイや気休めのように出される。従って、それら「健康に良い」と言われているものが出されているときには、一層粗末な食事内容になっていることが多い。私たちはこれを「免罪フード」と呼んでいる(後略)
引用が長くなってしまった。
わたし自身が、この「食卓の崩壊」を驚きを持って伝えるリサーチを読み進めて思ったのは、実のところ、食べることが好きな人って意外に少ないのではないか、ということだった。
美味しいものが嫌いな人はいないし、贅沢な外食をすれば写真に撮ってSNSに上げたくなるのは人情だ(逆に美味しいものをこっそり食べて、誰にも言わないのも人情だろうね)。
でも、それはハレであって、ケにおいては別に食なんてどうでもいいよ、と思っている人が増えているんだと思う。
すごくすらっとして、格好よく見える人がいるけれど、たぶんそういう人はわたしの半分もカロリー取ってないんじゃないかな、と思う。
その人の優先度が美容とかダイエットにあるのであれば、たまに会食とかで美味しいものを食べても、あとは霞を食べていればいいのよ、と思っているのではないかと。
わたしは食いしん坊で、出来るだけいつでも美味しいものが食べたいと思う。それは毎日贅沢な外食がしたいということではなく、口にして安心で、納得できるものを食べていたいな、ということである。
でも、そうしなくても毎日生きていけるのが現代社会だ。
例えば100年くらい前みたいに家電製品が殆どなくて、家事全般に大きな労力と時間を費やさずにはいられなかった時代には、余暇とか余計なことを考える時間とかはあまりなく、だからこそ、時間をかけて作らざるを得なかった食事は、簡素でもバラエティに富んでいなくても、貴重であり、少しでも美味しいものであってほしい、という願いが込められたものだったのではないかと想像する。
時間も労力もかけなくても、食べるものはすぐ手に入る時代に、食に興味なんてなくても、そんなに困らない。栄養バランスは考えたほうが健康のためにはいいだろうけれど、どこかで帳尻が合えばいいや、と思ってしまう人もそれなりにいるのではないかと思う。
それよりも仕事をばりばりこなす、子どもの教育に力を入れる、インテリアに凝る、ガーデニングに力を入れる、趣味に没頭する、社交する、旅行に行く、スポーツとか音楽を極めたい、限られた時間の中で、食の優先度が下がっていることは明らかで、それがリサーチ結果に反映されているのは不思議でもなんでもない。
伝統芸能の承継のように、各家庭の食生活が継承されるということはあまり考えられない。
定点観測的に、類似のリサーチを続けていれば、たぶんもっと食の崩壊は進んでいるだろうと想像できるし、リサーチに協力する、「余力のある」家庭とは別に「食の貧困」という問題が別方面からも突き上げてくるだろう。
自分自身は、いつも、美味しいな、と思えるものをお腹いっぱい食べられれば幸せだと思うし、そういう状態を誰もが求めて得られる社会であればいいと思うけれど、胃袋から世界を眺めていない人も沢山いるであろうこともわかる。さみしい、と思うのもわたしのエゴかな、と思いつつ、人の食卓を覗き見したような読書であった。
#読書 #読書感想文 #岩村暢子 #変わる家族変わる食卓 #真実に破壊されるマーケティング常識 #中公文庫 #勁草書房 #アサツーディ・ケイ #食DRIVE #普通の家族がいちばん怖い
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
