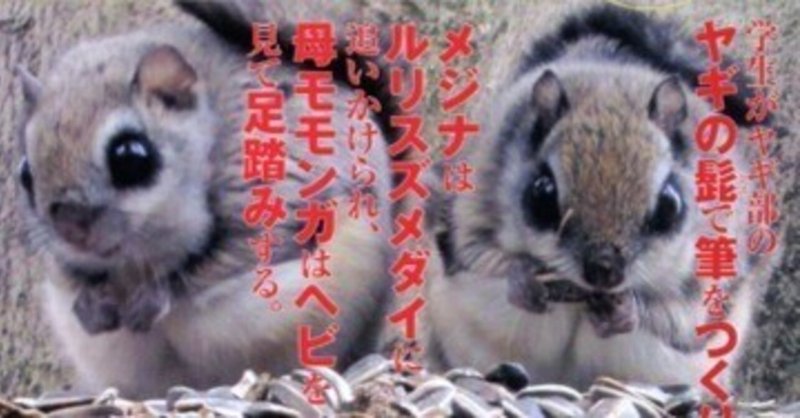
鳥取環境大学の森の人間動物行動学「先生!」シリーズ(毎日読書メモ(507))
小林朋道さんは、公立鳥取環境大学の教授。専門は動物行動学、人間比較行動学。
コロナ禍になって、在宅勤務主体の生活になって、それまで十数年、新聞を端から端まで読む習慣が絶えていたのが復活した、という話はこれまでも何回か書いてきたが(こことか)、それは、新聞に掲載されている書籍の広告にもよく目を通すようになったということでもあった。
新聞の一面の一番下(朝日新聞でいえば「天声人語」の下)は、毎日、出版社の広告が出ているが(サンヤツと呼ばれ、三段分の枠を8つに分けて、8社分の広告が出ていることが多い)、その中に、小林朋道『先生、大蛇が図書館をうろついています!鳥取環境大学の森の人間動物行動学』(築地書館)の広告があった。文字だけの広告だがこのタイトルに心惹かれ、調べてみたら、「鳥取環境大学の森の人間動物行動学」シリーズは、既に10冊以上刊行されていると知り、1冊目の『先生、巨大コウモリが廊下を飛んでいます!鳥取環境大学の森の人間動物行動学』から、ほぼ時系列に読み進めてきた。それぞれの本で、何種類かの動物を取り上げて、それぞれの観察や実験によって得られた知見を味わい深く記しているので、発表順に読まなくても面白く読める。よく出てくるのは、大学で先生が設立したヤギ部の話、フィールドワークに行って観察するコウモリやモモンガの話、ヘビと他の動物との遭遇のエピソード、などなど。
1年に1冊くらい新刊が出ているので、このシリーズの存在を知った後も、新刊が出る都度、サンヤツに広告が出て、小林先生は相変わらず元気に動物たちと触れ合っているのだな、と心温まる思いで広告を見つめ、他の本を読む合間の口直しのように少しずつ先生シリーズを読み進めている。
昨日今日で(『三体』読み終わってリラックス気分で)、『先生、イソギンチャクが腹痛を起こしています! 鳥取環境大学の森の人間動物行動学』を読んでいたのだが、その中でドキドキした記述が出てきたので、そこをちょっと引用。まー(「まー」というのは小林先生の口癖、本の中で多用されている)ここをクローズアップされるのは小林先生の本意ではないだろうが、コロナがきっかけでこのシリーズを知ったということもあり、なんだかすごく暗示的な気持ちに(この本の刊行は2016年5月)。
「コウモリは結構ニオイに敏感だ!」という章で、先生と学生は実験のためにフィールドワークに行った洞窟から何匹かのキクガシラコウモリを連れ帰り、行動学の実験をして、また、洞窟に連れ帰って放す、という行為をしているのだが、
…個体の性別や体調を調べるためにそのコウモリを天井から引き離すのだが、その時の感覚は、まさに実った果実をもぎとるときの感触とよく似ている(中国のある地域に生息するキクガシラコウモリは数種の病気の原因になるウイルスを保有していることがわかっており、コウモリにさわるときは手袋が必要だ。慎重を期して学生たちにはこの作業はさせない)。
と書いてあり、更に、この洞窟の中でハクビシンと遭遇したシーンで
中国では、ハクビシンがキクガシラコウモリが保有するウイルスをヒトに媒介させる可能性も指摘されており、日本でもハクビシンがなにかひどい害獣のように思われている空気がある。(中略)でも、率直な気持ちだ。私は宮殿の中のハクビシンを「神々しい」と感じたのだ。同時に、野生の威厳と悲哀を帯びた動物と感じたのだ。
とも書いている。発表時点では、読者は特に何も感じずに読み進めていたと思うが、2020年以降の読者は、この辺を読むとかなりドキッとしてしまう。
いやいや、こんな危機警鐘をクローズアップするような本じゃないんです。真摯に動物と触れ合い、行動学のヒントを見つけては実験により実証しようとする過程と、対象となる動物への愛情に溢れ、また、フィールドワークの様子とか、地方で大学教育を行うとはどういうことか、という片鱗も伺わせる、色々なアプローチの出来るシリーズなのです。
機会があれば是非手に取っていただきたい、愉しい本です。
これが最新刊。来年1月にはまた新刊が出るらしい。
#読書 #読書鑑賞文 #読書の秋 #小林朋道 #先生シリーズ #公立鳥取環境大学 #動物行動学 #人間比較行動学 #キクガシラコウモリ #先生巨大コウモリが廊下を飛んでいます #先生イソギンチャクが腹痛を起こしています #先生ヒキガエルが目移りしてダンゴムシを食べられません #先生大蛇が図書館をうろついています #築地書館 #サンヤツ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
