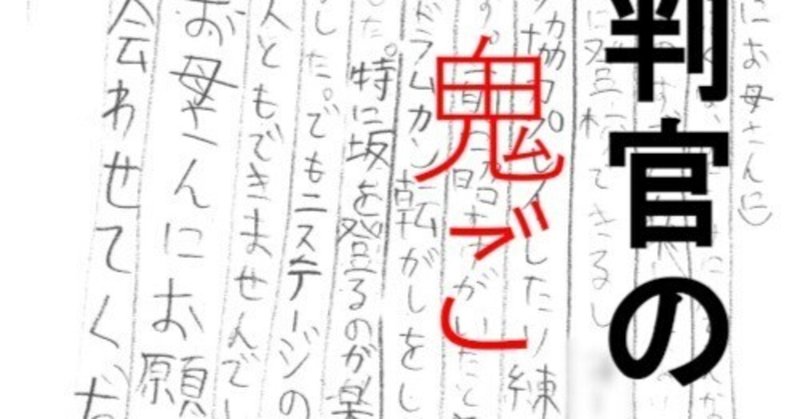
裁判官の鬼ごっこ: 熊本家庭裁判所令和4年9月16日審判裁判官:若林慶浩の検討について
はじめに
「権力は腐敗する、絶対的権力は絶対に腐敗する」。
これはイギリスのケンブリッジ大学教授であったジョン=アクトンによる格言である。これが使われたのは1887年だが、この言葉が現代にまで残っていることに、この言葉が持つ普遍性が表れているといえるだろう。それだけ、権力者の腐敗が歴史で繰り返される普遍的事実だということだ。
さて、では裁判官はどうであろうか。裁判官に課せられている理由提示義務や、その義務を誤魔化す手口がされていないか、また、そこから裁判官の腐敗が見えないかについて検討する。
なお、裁判官を評したものとしては以下のもの等がある。
井上薫「狂った裁判官」幻冬舎新書、2007。
森炎「司法権力の内幕」ちくま新書、2013。
岡口基一「裁判官は劣化しているのか」羽鳥書店、2019。
瀬木比呂志「檻の中の裁判官 なぜ正義を全うできないのか」角川新書、2021。
一般に、裁判官には客観性や公正性があるイメージを持ちやすいが、必ずしもそれが的確なものでないことは、これらの著書で元裁判官や現役裁判官自身が述べている。
もし裁判官に幻想をいだいているのなら、本書を読む前にこれらの著書に目を通すことで、裁判官に対する幻想を捨てて先入観を取り除いてほしい。
2021年に放送された裁判官が主人公であるドラマ「イチケイのカラス」には、「信じることは知ることの放棄」とのセリフがあった。もし裁判官への幻想を抱き続け、無条件に裁判官を盲信することでその実態を知ることを放棄したいというのなら、裁判官は絶対に誤ることがないと思考停止をすれば良い。ただし裁判官が間違いを侵さないとすることは、三審制の否定でもあるし、上訴で結論が変わる場合もあることと矛盾するが。裁判官だからといって思考停止することは、根拠なく信じる盲信や狂信というべきものだろう。
あるいは、もし人が完全ではなく、それは裁判官も同様であり、また、現状の制度が完全ではなく、より良い社会制度を目指していくことが人類の進歩だと思えるのなら、本書に目を通すことに意味を感じるかもしれない。
ちなみに、ドラマ「イチケイのカラス」では、裁判官が熊本に異動になるシーンがある。ストーリー的に左遷で、問題があると判断された裁判官のいわゆる都落ちだと思った視聴者も多いだろう。「イチケイのカラス」はフィクションとはいえ、問題のある裁判官の左遷先が熊本で、本書がテーマとしているのは熊本での裁判官のまともさである。その関連性をあれこれ考えてみるのも興味深いかもしれない。
幻想を抱きやすいということでは、いわゆる宗教の聖職者もそうであろうが、その聖職者による児童性虐待は歴史上稀なことではない。むしろ、聖職者という立場を利用しているという点で悪質である。たとえば、フランスのカトリック教会内での児童性的虐待の加害者は、1950年以降、“最も少なく見積もっても”2900~3200人に及ぶとの調査結果がある(2021年10月、フランスのカトリック教会内での児童性的虐待問題を調査する独立委員会による発表)。
裁判官も幻想を抱かれやすい職業であるが、聖職者と同様、その立場を利用しての汚職も容易であるとともに隠蔽されやすい。だからこそ、裁判官には知識のみならず、高い倫理観や道徳心が求められるのだが、そのような道義的努力が期待できないのなら、裁判官の暴走や悪い意味での独裁に対して、法的な抑止力を設けていくことも必要だろう。
また、2021年10月12日、イギリス下院は政府の新型コロナウイルス対策の検証報告書を公開している。その中では「英国の経験の中で、最も重大な公衆衛生上の失敗の一つ」との批判もあり、対応の討議を迅速に公開し、「外部の異論にさらすこと」が必要だと強調している。イギリスのこの時点での累計死者数は1414に迫り、欧州最悪となっている。
さて、これも裁判官の問題点と類似性がある。外部の異論に晒されないようでは、裁判官の暴走の抑止力にならないし、外部の異論に晒すことができない理由不記を裁判官が繰り返しているかぎり、その判断の正当性や合理性も検証できない。そもそも、判例集等の判決文は裁判官が取捨選択したものしか記載されていないため、結果に重大な影響を与えるが恣意的判断をしたい裁判官にとって都合が悪い主張や証拠は、その存在自体が黙殺されている可能性がある。
原審は熊本家庭裁判所だが、熊本県は水俣病が起きた地であり、それを引き起こした企業であるチッソは、1966年までメチル水銀を海に流し続けている。しかし、チッソはネコに工場の廃液を混ぜたえさを食べさせる実験をしており、チッソの付属病院長だった細川一氏らは1959年には廃液と水俣病発症の因果関係を解明していた。それにもかかわらず、チッソは結果を公表せずに廃液を流し続けて被害を拡大させており、水俣病の裁判では、このようなチッソの態度を裁判所は厳しく批判している。
さて、このようなチッソの態度、つまり都合が悪い事実を無視して被害を長期化させるという態度は、人道的な罪というべきである。同様に、裁判官が恣意的判断のために都合が悪い事実を無視した場合も、もはや裁判官としての適格性に欠落した態度であり、そこに公正な裁判は存在しない。このことは裁判制度に対する国民の信頼を根本的に喪失させるものであり、また、公正が欠落した裁判は国民にとっての不利益でもある。
熊本県は後の最高裁が謝罪することになる、ハンセン病特別法廷(いわゆる「菊池事件)」があった地でもある。これは裁判官による差別の歴史であり、裁判官が判断を誤る事実を示すものでもある。「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」とはドイツ宰相であったビスマルクの言葉であるが、裁判官を絶対視することは歴史から学ぶことができない愚者ということになるだろう。
世の中に裁判官という生まれつきの人種がいるわけではない。裁判官の役割を担っている人がいるだけであり、その中にはまともな者もいれば、腐敗している者もいるのは、どのような職業であっても同様である。つまり、裁判官無謬説とでも言いたくなるような態度には何ら合理性はない。
では、裁判官の実態を見ていこう。
第1 裁判官を検証するための基礎知識
1 裁判官の理由提示義務
裁判官は裁判当事者に対して、その判断の理由や結果を書面に記すことで知らせる(刑事事件では被告人の前で結論を述べたり、理由を述べたりするが、原審は家事審判である)。その書くべき内容は法律で定められており、「主文、理由の要旨、当事者及び法定代理人、裁判所」(家事審判手続法第76条2項)となっている。主文は結論で、当事者や裁判所は事実を書くだけなので、問題は「理由の要旨」である。
ちょっと想像してみよう。もし審判書に主文しか書かれていないならば、裁判官の判断理由や、当事者の主張や証拠をどのように採用、あるいは不採用にしたのかが分からない。裁判官の判断に誤りがあったとしても隠蔽され、上訴をしたくても具体的主張をすることが不可能になる。
法律が規定している理由提示義務について、最高裁判所第三小法廷判決昭和60年1月22日(民集第39巻1号1頁)の判示がある。この判例では旅行法第14条について、単に根拠規定を示すだけで、基礎となった事実関係が具体的に示されていない場合、理由付記に不備があるため違法であるとしている。更に補足意見では理由付記の不備が違法である理由として、理由付記が拒否事由の有無について慎重さと公正さを担保してその恣意を抑制するとともに、拒否理由を申請者に告知することによつて、不服申立てに便宜を与えるためとしている。
より近年で右判例を踏襲したものとしては最高裁判所第三小法廷判決平成23年6月7日(民集第65巻4号2081頁)がある。この判例でも、行政手続法第14条1項の規定は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名あて人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという点にあり、同項本文の定める理由提示の要件を欠いた違法な処分は取消しを免れないというべきであるとしている。
さて、既に述べたように、家事審判手続法76条2項の二にも理由付記が規定されている。そのため、家事審判手続法76条2項の二が規定する理由付記についても、裁判官の慎重さと公正さを担保してその恣意を抑制し、不服申立てに便宜を与えるものでなければならず、そうでなければ裁判の公正性は担保されないし、裁判官の恣意的判断は抑制されず、判断理由に即した有効な上訴も不可能になる。むしろ、行政の決定に対しては審査請求や行政訴訟においてその正当性を問う機会があるが、裁判では終局的な判断がされるのだから、旅行法や行政手続法で規定されている理由付記以上に、裁判での判決書や決定書には、裁判官らの判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、判断理由を当事者に知らせて不服の申立てに便宜を与えるものでなければならないというべきである。当然、上訴できるからと1審であれば適当でかまわないといったことにはならない。
つまり本件事件では、原審の裁判官である若林慶浩がこの理由提示義務に対してどのような態度であったか、それがまともなものであったかが争点の1つである。
2 裁判官の理由付記に関する能力
裁判官の理由付記については、以下の指摘もある。
「採用するに足りないとか、これを認めるには足りないとか、国語力だけでつぶす人もいるんですけど、それでは説得力がないし、『こんな理由ではねたの?』とみんなに思われてしまうと、その裁判官のプライドにかかわるんですよね。それはすごく嫌なんです。当事者、代理人に見られるのも嫌だし、もちろん高裁の裁判官に見られるのも嫌だしね。だから、『確かにこういう証拠はあります。しかし、こう考えると、これはダメです。』と、反対証拠を説得力をもってつぶすのが裁判官の能力だとみんな思っているので、そこにものすごい時間がかかるんですよ。」(岡口基一「裁判官は劣化しているのか」羽鳥書店、2012)。
さて、上記の指摘が当てはまらない裁判官もいることに本書面を読み進めることで気づくかもしれない。つまり、説得力のない審判書を書いても気にしないし、そこにプライドを持つ矜持もない裁判官である。
むしろ、反対証拠を説得力をもって潰すのが裁判官の能力のバロメーターというのなら、反対証拠を説得力をもって潰すことができない裁判官は、低能ということになろう。それどころか、反対証拠を採用しない合理的理由を提示できていないのならば、民事訴訟法253条3項や家事審判手続法76条2項の二が規定する理由付記に反する違法裁判官ということにもなる。
そもそも単純に考えて、反対証拠を説得力をもって潰せないのなら、その証拠は正しいと判断すべきなのではないか。少なくとも、その証拠の矛盾や、より説得力のある証拠の存在を示す等で、その証拠を採用しない合理的理由を明らかにすべきである。
また、裁判官に対する幻想を捨て去れば、裁判官がその地位を利用して恣意的判断をするため、説得力をもって潰すことができなかった反対証拠は無視することで恣意的判断を強行したのではないかとの疑義が生じるのは、当然の帰結である。
3 一括不採用の検証不可能性(魔女っ子裁判官)
裁判官が理由付記ならぬ理由不記をする手段として、以下のものがある。
「あまりにも多くの意味のない主張がされた場合、それらをまとめて排斥する例がないわけではない。その場合、判決には『控訴人は、るる主張するが、いずれも採用するに足りない』などと記載される」(岡口基一「最高裁に告ぐ」132頁、岩波書店、2019)。
岡口基一はこのように述べているが、「るる」が意味のない主張の排斥のみに使われているのと断言できる根拠はあるのだろうか。むしろ、この「るる」は容易に悪用可能である。つまり、裁判官が恣意的判断をするのに都合が悪い主張や証拠を一括で排斥するのに悪用している可能性である。そしてこの可能性が否定されないかぎり、その裁判官の結論が合理的理由によって導かれたものであるとは言えない。
たとえて言えば、「私、魔法少女ルル。合理性判断なんてバカみたいよね。私が『るる(縷縷)~』と唱えたら、どんな都合が悪い主張でも全部誤魔化せちゃうの。矛盾する主張や証拠は触れなければOK! 書きやすい理由だけ書いて、あとは『るる(縷縷)~』って誤魔化したら一応それっぽい文章になるしね。これでどんな恣意的判断も好き勝手に自由自在よ♪」という裁判官の態度だと言えるだろう。
上記した岡口基一の指摘についても、もはや国民は裁判官に対して、「意味のない主張にしか“るる~”を唱えない」との根拠がない信頼感を向けておらず、むしろ、恣意的判断をするため、都合が悪い主張は「るる~」と唱えて誤魔化していると考えるのが、合理的と言える。そのため、裁判官が「るる~」を唱えた場合、それが意味のない主張にしか使っていないのか、それとも、恣意的判断をするために合理的理由をもって排斥できない主張に答えていないことを誤魔化す手段として「るる~」と唱えていないかを検証しなければならず、その検証可能性のために裁判官は判断理由を具体的に記載しなければならないが、それは結局、全ての主張について、それを採用する理由、あるいは、排斥する理由を具体的に記載する必要があるということなのだから、結局のところ、裁判官が「るる~」と囀ることは国民にとって、裁判所に対する不信感を深めるだけで、何のメリットもない。むしろ、裁判官の魔法少女ルル化という意味では有害である。
これは法の支配にとって非常に恐ろしいことであり、裁判官の魔法少女ルル化は、当事者がどんなに合理的に主張し、十分な証拠を示したとしても、裁判官の資質次第でそれらを一括で排斥しての恣意的判断が可能ということである。
最初に述べたように、権力は腐敗する。裁判官に悪意(ヒラメ根性も含む)があれば、どんな主張立証も無視して恣意的判断が可能という法制度は、法の支配の前提である公正な裁判に対する重大な危機である。
そのため、裁判官の独立は保障されるとしても、その判断の根拠が適切であるかの合理性は検証されなければならず、その検証が不可能である理由提示が不十分な判示は、それ自体が家事審判手続法第76条2項が定める理由提示義務に反していると言わざるをえない。
4 独自の見解裁判官
裁判官の知性に疑義が生じる態度として、「独自の見解裁判官」がある。これは「独自の見解」とのレッテルさえ貼れば,主張を排斥する理由になると思い込んでいる裁判官の一形態である。しかし「独自の見解は採用できない」を換言すれば、「少数派の見解は間違っているに違いない」、「主流派の見解は常に正しい」と言っているのと同義の、何の合理性もない判断であり、そこに少数派に対する弱者救済や、合理的思考といったものは全く存在しない。当然、検証可能性も皆無である。歴史を振り返っても、当時の社会では受け入れられなかった「独自の見解」が、後世で正しいことが証明された事例は枚挙に暇がない。小学生でも分かるたとえを挙げれば、ガリレオ・ガリレイの地動説もこれに該当するだろう。「独自の見解」であることを理由に当事者の主張を排斥することは、事実上、新しい考え(独自の見解)は無条件に間違っているとするのと同様の、老害の典型的な見本というべき醜悪な態度である。
5 ただちでなかったら無問題裁判官
「(ただちに)~ない裁判官」の知性にも疑義が生じる。これは「(ただちに)~ない」とさえ言えば,どんな不合理でも誤魔化せると思い込んでいる裁判官の一形態である。そもそも、“ただち”でなかったら問題ないのか、結局、長期的に見れば影響があることを否定できないということではないのか。そのような疑問からすれば、「(ただちに)~ない」だけで排斥している裁判官の態度がまともな合理的理由を提示できていないことは明らかである。
6 不意打ち裁判官
裁判所が当事者間で争点になっていない新たな法的見解を採用するつもりならば,その争点について当事者に主張立証の機会を与えなければならず,それをしていない釈明権の行使を怠った判断は違法である(最高裁判所平成22年10月14日判時2098号55頁)。このような違法を犯す裁判官が「不意打ち裁判官」である。
7 ようするに裁判官
これも合理性に欠いた裁判官の一形態で、当事者の主張を「ようするに」との言葉に続けて言い換えることで、都合が悪いが合理的理由をもって排斥できない当事者の主張を無視したことを誤魔化す手口である可能性が疑われる。
裁判官盲信教や裁判官狂信教の信者でなければ、裁判官であっても判断を誤る場合があることを否定する者はいないだろう。だからこそ、裁判官はその判断の理由を明らかにすることで、当事者に不服申立ての便宜を与えるものでなければならない。
そうすると、当然、この「ようするに裁判官」はまともな判断理由の提示をしていないのだから、その判断に誤りがあったとしても、適切な理由を記載しての上訴をすることが困難になる。むしろ、裁判官は適切な上訴をさせないために故意にこのような「ようするに裁判官」になっているのかもしれないが、それが不適切であるのは言うまでもない。
8 裁判官の科学的態度について
心理学者で元新潟大学教授であった鈴木光太郎は、科学とは絶対的真実を認めず、常に誤りを修正し続ける活動であると述べるとともに、以下のようにも述べている。
「教科書には正しいことだけが書かれていなければならないとは思っていない。むしろ、誤った記述があっても許されると思う(誤りは直せばよい)。科学は誤ることがあたりまえであって、そもそも科学とは、そうした誤りをたえず書き改めてゆく営みだからだ。私が許されないと思うのは、だれかが誤って書いたものをなにも考えずに受け売りしたり、それを孫引きやひ孫引きしたり、果ては先祖がたどれない引き方をしている場合である。」(鈴木光太郎「オオカミ少女はいなかった 心理学の神話をめぐる冒険」2008年、新曜社)
さて、裁判官の理由の記載が根拠をたどれない場合、科学的態度に反しているのは明らかである。理由の記載が科学的でないということは、判断自体が合理的でないということでもあり、具体性のない理由付記だと上訴をしたくても具体的主張をすることが不可能という意味においても、裁判官に課せられている理由付記の義務(家事審判手続法76条2項の二等)の履行は、具体的で検証可能性があるものでなければならない。
9 採証法則
我が国の裁判は自由心証主義となっていて、たとえば民事だと以下のような条文がある。なお、家事事件においてもこの条文が準用されている(家事事件手続法第79条)。
「民事訴訟法第247条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を採用すべきか否かを判断する。」
この自由心証主義とは、事実認定や証拠の評価などを裁判官に委ねることである。しかし、これは裁判官の恣意的判断を合法とするものではなく、自由心証主義であっても裁判官の判断は論理法則や経験則に基づく合理的なものでなければならない。これは当然であり、証拠を無視したり曲解したりする権限までもが裁判官に付与されているのかと言えば、これを肯定する者などいないだろう。事実、仮に裁判官の判断が合理性に欠けている場合、最高裁は違法との判断をしている(たとえば、最高裁判所昭和47年4月21日第二小法廷民集26巻3号567頁、最高裁判所平成18年11月14日第三小法廷判決集民第222号167頁、最高裁判所令和3年5月17日第一小法廷判決民集第75巻6号2303頁等)。
つまり、証拠を適切に判断できていない裁判官は、違法を犯しているということである。
10 裁判官の鬼ごっこ
2020年、アニメ「鬼滅の刃」の劇場版が国内上映映画の興行収入歴代1位になったことで話題になった。このアニメには鬼が出てくるのだが、その鬼のボスのセリフに、「私は何も間違えない」や「私の言うことは絶対である」といったものがある(なお、これらのセリフはアニメだと1期26話にあり、上記した2020年劇場版には出てこない)。
さて、鈴木光太郎が許されないとしている、先祖をたどれない非科学的な態度は、根拠や原典をたどれないとも換言できる。裁判官の具体的理由が示されていない「その他申立人が主張することは、いずれも採用することができない。」等の記載が正にこれであり、裁判官が採用しなかったことの中に誤りがあったとしても、それを検証することができない右記載は、検証可能性が無いという意味においても非科学的であり、非合理である。そして、なぜ裁判官がこのような記載をするかといえば、その精神性の本質が上記セリフに示されている鬼のボスと同じところにあるからとの結論に至る。つまり、このような裁判官は「黙れ、私は何も間違えない。私の言うことは絶対である。だから判断理由の具体的説明なんかしない。とにかく私が"正しい"と言ったことが"正しい"のだ。」との態度だと言えるだろう。
なお、一見、傲慢に見える上記セリフであるが、むしろ鬼のボスの精神性は“小物”との評価もされている。なるほど,自らが正しいと思うのならそれを正面から論理展開すれば良いのだから、非論理的な一方的な決めつけでしか語れない姿は、確かに小物なのだろう。
また、上記セリフはパワハラ発言とも指摘されている。他者の話を聞かず、だから他者の主張の合理性を検証することもなく、自分が過ちを犯す可能性の一切を否定した上記セリフがパワハラに該当するのは当然であるし、裁判官が同様の態度をとる場合も、裁判官の裁判当事者に対するリーガルハラスメント(司法的立場を利用したいじめ)と言えるだろう。
また、裁判官が判断の合理的理由を示さず、事実上、「黙れ、私は何も間違えない。私の言うことは絶対である。だから判断理由の具体的説明なんかしない。とにかく私が"正しい"と言ったことが"正しい"のだ。」との態度の場合、鬼のボスと類似の精神性であると言えるのだから、裁判官のこのような態度は「裁判官の鬼ごっこ」とでも呼称すべきだろう。
このような精神性を基礎とした裁判官の判示は、裁判官の慎重さと公正さを担保してその恣意を抑制し、不服申立てに便宜を与えるものになっていないことから、最高裁判所第三小法廷判決昭和60年1月22日(民集第39巻1号1頁)、及び、民事訴訟法253条3項ないしは家事審判手続法76条2項の二に違背していると言わざるを得ない。とはいえ、裁判所が組織的腐敗をしている場合、上記最高裁判例での理由付記の要件を無視して、裁判官には甘々な理由提示義務でかまわないとするのだろうが。しかし厳格性が求められる裁判において、裁判官に対する理由提示義務が甘々で、裁判当事者が十分な理解に至ることができず、そのため適切な上訴も困難となるようなものでもかまわないするという態度を最高裁がとるのであれば、それは最高裁の裁判官らの良心の欠如を示すものと言えるだろう。
なお、判例集等では裁判官が判示したものでしか当事者の主張が記載されていないため、裁判官に都合が悪いことは触れていない、つまみ食いした当事者の主張を対象にしか考察がされていないおそれがある。このことは、裁判官の理由不記は隠蔽されやすい構造となっているということである。このような裁判官による隠蔽や理由不記を見える化することも、裁判官の汚職を抑止するために必要である。
11 「不満」等へのすり替え裁判官
悪質な裁判官の手口の1つに、主張のすり替えがある。当事者が主張していることを無視しまくるのは対面が悪いが、だからといって恣意的判断のためにその主張を合理的理由をもって排斥することもできないとき、論点をずらすことで恣意的判断を強行するという手口である。
たとえば、当事者が「違法」として主張していることでも、それを「不満」や「不服」といった表現にすり替えるという手口である。なるほど、不満であれば、「原告は不満を主張しているにすぎない」で終わらせることができると思っているということだろう。しかしこれが違法であれば、「原告は違法を主張しているにすぎない」としても、「だったらその違法の主張が正当かどうか公正に検討するのが裁判官の役目だろ」となる。つまり、判断から逃げられないことになる。
さて、裁判官のどの手口にもいえることだが、岡口基一が指摘した「反対証拠を説得力をもってつぶすのが裁判官の能力だとみんな思っている」からすれば、原則的に裁判官は説得力をもった判示をしたがっていることになる。しかしそれを裁判官がしていない場合、そこに悪質や姑息な裁判官の心理が働いたと解するのが妥当だろう。要するに、「恣意的判断をするのに都合が悪いが、合理的理由をもって排斥できない当事者の主張であるため、無視やすり替えなどの悪質で姑息な手段によって恣意的判断を強行することを選択した」という裁判官の心理である。
ちなみに、裁判所のウェブサイトにあった控訴状の書式には、以下のような記載があった。
【上記当事者間の〇〇地方裁判所平成 年(ワ)第 号売買代金等請求事件について平成 年 月 日に言い渡された下記判決は,不服であるから控訴する。】
ここでは「不服」との表現が使われているが、「不服」だからということを根拠に、どのような控訴の理由を書いたとしても棄却されるのだろうか? 当然そのようなことはなく、「不服」だからと上訴したとしても、その後の判断は原審に違法性があったかで判断されなければならない。
そうすると、そもそも「不服」や「不満」といった表現に裁判官がすり替えたとしても、それによって当事者が主張した内容を検証することを怠る理由にはならず、それは裁判官としての職務怠慢や職務放棄というべきものだろう。
第2 事件の概要
1 親子交流
本書でまな板に上げるのは、いわゆる面会交流事件の審判で、別居している親と子の適切な交流について裁判官が判断するものである。これは別居をしている親と子どもとの交流に関して、同居親の義務を定めるものであるが、たとえ父母が別居、離婚をしたとしても、親子の交流の重要性が変わるものではなく、よほど児童虐待といった特別な事情がないかぎり、子どもと両親との交流は保証されなければならない。
このような審判は本来、両親が共に子の利益を理解し、子の利益のための行動ができていれば必要のないものである。別居、離婚をしたからといって、審判や調停を経なければ、同居親が子どもを別居親に会わせてはいけないという法律はないし、審判を経なければ、別居親が子どもにあってはいけないという法律もない。ではなぜ、このような審判が必要になってくるのだろうか。
それには同居親に問題がある場合と、別居親に問題がある場合があるだろう。同居親に問題がある場合、子を独占支配したいとか、子を会わせることを駆け引きの材料として利用したいといった、身勝手な思考によるものが多いように思わえる。一般的に子は両親が共に好きである。「両親のどっちが好きか」と聞かれた子どもが饅頭を2つに割り、「どっちが美味しい?」と聞き返したという逸話もある。つまりどっちも好き(美味しい)から比べられないという意味だ。そのような子の思いを蔑ろにして、自らの身勝手さから子どもともう一方の親との関係性を阻害することは、児童虐待行為の一種と言えるだろう。
次に別居親に問題がある場合であるが、別居親との関わりが子に悪影響を及ぼすことを防止するため、面会交流の制限や禁止をする必要がある。たとえば、子への不適切だったり、連れ去りの具体的危惧が高い場合、面会交流に誰かの付添(事実上の監視)を条件にしたり、交流場所の制限といったものも必要となるだろう。しかし逆に言えば、別居親の関わりが子に悪影響を及ぼすことを危惧しなければならない具体的理由がない場合、審判で面会交流を制限するする必要はないことになる。さすがに毎日面会交流をしたいなれば、子の生活リズムに悪影響があるだろうが、後述するように、別居親と子の関わりは、少なくとも35%以上が好ましいという学術的な調査結果もある。そのため、子の生活リズムは尊重しながらも、別居親が子と35%以上の時間を過ごせるようにし、仮に明らかに子の利益に反して別居親が同居親以上に子と一緒に過ごそうとするのでなければ、別居親の子に対する愛情は、子の利益に適ったものとして尊重すべきだろう。
2 請求の理由
詳細は後述する申立書や主張書面を参照してもらうとして、親子交流が必要な理由の要点を挙げる。つまり、これらが若林慶浩が判断を示さなければならない事項ということになる。これらに若林慶浩がどのような判断をしたのか、それは合理的なものなのか、必要な理由提示をしていない若林慶浩の鬼ごっこぶりを示すものであるのかが、本書での検証内容である。
主な主張
○ 児童の権利に関する条約9条において,「子供がその父母から,その父母の意思に反し,切り離されてはならない。」と規定されていること。
○ 子と別居親との交流は、子がどちらかの親と関わる時間の35%以上が好ましいとの学術的な結果が出ていること。
○ 母親には精神疾患があり、親の精神疾患は子に降りかかる恐れのある危険要因のあらゆる可能性のなかで,もっとも強い精神的な影響を及ぼすもののひとつであること。
○ 二男は母親に連れ去られた監護環境において,多動性行為障害,うつ病の疑い,発達障害の診断をされる状況になり、小学校の入学式で参列できず,その後も一学期の運動会に途中からしか参加できなかったり,2学期の学習発表会でも体育館に入れなかったり,3学期の持久走大会でも参加できなかったりしていること。
○ 面会交流は、父子の交流のみならず、父親が監護している長男と二男との兄弟の交流や、二男と父親方祖父母との交流の機会でもあること。
○ 母親方祖父母は二男に対して、父親のことを「きちがい」呼ばわりしており、二男はそれを嫌に思っていること。
○ そもそも、母親が父子交流や兄弟交流に配慮できていれば、面会交流の審判を申し立てる必要がないこと。
○ 仮に柔軟な面会交流では紛争が生じるというのであれば、子の利益に適った面会交流の実施方法を厳密に定めれば良いこと。
○ 相手方が申し立てたDV等支援措置によって申立人が二男の居住地を知ることができなくなっていることは、DV等支援措置の必要性の要件を満たしていない違法なものであること。
ところで、若林慶浩の判断を検証をしていくにあたって、無条件の裁判官信仰はしない。つまり、「裁判官は何も述べていないが慎重な審理をしたはずだ」「裁判官は公正な判断をしたはずだ」「裁判官はこんなふうに考えたはずだ」といった、根拠のなく裁判官を擁護することはしない。裁判官には理由提示義務が課せられている(民事訴訟法253条3項や家事審判手続法76条2項の二)。このことからすれば、そもそも理由をまともに書いていないこと自体が違法というべきであるのは、すでに述べたとおりである。そもそも、裁判官には判断理由を具体的に書くことが禁止されていないのだから、裁判官が任意の選択として、理由を具体的に書いていない部分があった場合、そこには裁判官が具体的な判断理由を“書くことができない”事情があったのではないかと疑うのが合理的であるし、それが恣意的判断を誤魔化す手口である可能性も疑うべきだろう。
第3 若林慶浩による判示への疑義
1 別件損害賠償請求訴訟の本人尋問について
若林慶浩は以下の事実認定をしている。
【申立人は、令和4年1月6日、別件損害賠償請求訴訟の本人尋問において、未成年者との従前の面会交流につき、①警察の臨場について、「向こうがそいう不適切に、お父さんが来たのに、お父さんが会いにきてくれただけのことで警察を呼ぶということは、いずれ向こうが子供から見下されることになるだろうなというのは感じていたので、正直すごく残念な態度には思いましたね。」と供述し、②面会交流の審判が確定した場合にその内容に拘束されるかについて、「そこ(審判の内容以上の面会交流)に応じるかどうかで向こうの人間性というか、親としての責任が出るかなとは思います。審判で決まっていないからしないか、審判にかかわらず子供のことを優先に考えるか、決まっていないからこそ選択肢があるからこそ、そこに人間性が出ると思うんですね。子供のことで強制されなきゃできないって、それは親じゃないでしょう。』と供述したほか、③相手方の居住地が分からないことについて、「それ自体ちょっと不当かなというふうに思っているんですね。・・・とにかく複合的に子供の利益を守るために、やれることはこれからもやっていかないといけないんだろうなというふうには思っています。」と供述した。】
(1) 親子交流や兄弟交流を制限する必要がないこと
さて、申立人や相手方は若林慶浩が判示した上記の事実認定以外にも様々な主張をしており、たとえば上記の別件損害賠償請求訴訟の尋問でも、申立人は他のことも多く述べている。その中で若林慶浩が上記を取捨選択して引用したのだから、そこには何か意味があるのかと思えば、その後の若林慶浩の検討には全く出てこないのだから、ここにも若林慶浩の合理性に欠けたまともではない判断が表れていると言えるだろう。
申立人が長男と共に二男に会いに行ったことについて、申立人は原審で以下の主張をしている。
【 そもそも、子と別居親との面会交流は同居親がまともであれば円滑に実施できるものであり、その実施に必ずしも審判決定を必要とするものではない。つまり、面会交流で紛争が生じるのは、同居親が面会交流を駆け引きに利用しようとしたり、子と別居親との交流を不必要に制限しようとするからである。
ちなみに、別居親が原因で面会交流に関する紛争が生じる場合もあるだろうが、それは別居親の子に対する関わりが明らかに不適切で子に悪影響を及ぼしていたり、別居親が面会交流以外の目的のために面会交流を利用している場合(たとえば、同居親に接触すること目的にしている場合等)等が考えられるが、本件事件にそのような事情はない。
また、仮に相手方が原告が監護する長男と交流したいならば、審判などを持ち出すまでもなく、原告は柔軟に対応するつもりであり、同様の態度を相手方もすることが子らの利益に反するといった特段の事情は認められない。そうすると、仮に相手方が柔軟な父子交流や兄弟交流に配慮をできていたとしたら、二男から相手方に対するの印象は、「お母さんは僕とお父さんのことや、僕とお兄ちゃんのことも大事にしてくれた。だから僕はお父さんやお兄ちゃんともいっぱい良い思い出ができたし、お兄ちゃんみたいにスポーツや勉強も上手になりたいと思えた。」といったものだったろう。しかしながら、相手方の態度は二男に適切な監護をするチャンスを自ら潰したものであった。そして、二男が相手方の行為の実態を知れば、「お父さんやお兄ちゃんが僕のために会いに来てくれても、お母さんはそれを邪魔したし、お父さんやお兄ちゃんが僕のために会いに来てくれたことを逆に利用して、僕からお父さんやお兄ちゃんを引き離した。お兄ちゃんはお父さんと一緒に暮らしていろんな経験をしたり、いろんなことに頑張ったりしていたのに、お母さんのせいで僕はお父さんに可愛がってもらえなくて、僕の人生からお兄ちゃんも消えてしまった」ということになる。このような相手方の態度が二男の利益に反していることは明らかである。なお、相手方は警察を呼ぶといった挙にも及んでいるが、警察が原告を逮捕していないことからも、申立人が法令に抵触する行為をしていなかったことが分かる。
その意味において、そもそも二男の利益に適った父子交流や兄弟交流に配慮する資質に欠けた相手方が二男を監護していること自体が二男の利益に反しており、そのことが紛争の根本的な原因だと言えるし、このような相手方を二男の親権者に指定した裁判所の判断も、紛争の発生に加担したと言える。子と別居親との交流に寛容な親と親権者(監護権者)として優先することを、フレンドリー・ペアレント・ルールと言うが、本件事件はそれに反する裁判所の判断がいかに紛争を生じさせるかと実証したものと言えるだろう。
さて、このことに若林慶浩が「あーあー聞こえない」といった態度を取るかにも、若林慶浩の判事としての資質が表れることになるだろう。
とりあえず、本件事件は子の引き渡しではなく面会交流であるが、上記の理由から申立人を紛争を生じさせた加害者扱いするのは誤りであるし、父子交流や兄弟交流を断絶されている二男の利益に鑑みても、速やかに父子や兄弟の定期的な人的な関係及び直接の接触が回復されなければならない。】
問題はこのように指摘したにもかかわらず、若林慶浩が「あーあー聞こえない」といった態度を取ったかであるが、残念ながら若林慶浩はその判示において申立人の上記主張について何ら言及していない。子に適切な配慮ができる同居親であれば、審判をすることなく子と別居親との交流にも配慮ができるのだから、相手方にその資質が欠けていることから子に不利益が生じている以上、審判によって親子交流や兄弟交流ができるようにすべきところ、若林慶浩はそれを怠っているのだから、若林慶浩の判断が子の利益を考慮し、かつ、合理的理由を示せたまともなものであったとは言い難い。
(2) 親子交流や兄弟交流が子にもたらす悪影響
次に、相手方によって父子交流や兄弟交流を断絶された未成年者や、兄弟交流を断絶された長男がどのような認識になる可能性が高いかであるが、1つには既に甲8で示しており、以下を原審でも引用している。
【小学生時代に母に連れ去れ家を出て,父と別居し,不登校や心的外傷後ストレス障害(PTSD)になった-。面会交流訴訟で弟(16)とともにこの立場で原告に加わった千葉県の男性(20)は十一日,東京地裁への提訴後に記者会見。「面会交流がより多く実施されていれば,ここまで苦しむことはなかったのでは」と,家族と自由に会えなかった過去を振り返り苦渋の表情を浮かべた。(中略)男性は「自由に面会できれば素直に本音がさらけ出せたかもしれない。離れていても,家族に気持ちを伝えたい瞬間はあるはずだ」と訴えた。】
さて、相手方が父子交流や兄弟交流を断絶させていることは、上記のような不登校やPTSDのリスクを高めていることであるし、若林慶浩が父子交流や兄弟交流を断絶させる判断をしたことも同様である。我が子にこのようなリスクを高めている相手方や、二男にこのようなリスクを高めている若林慶浩の判断が子の利益を考慮し、かつ、合理的理由を示せたまともであるとは言い難いし、相手方のこのような態度を子らが理解するようになったとき、子らが相手方に否定的感情を増大させることになっても何ら不思議はない。
(3) 親子交流に関する学術的知見
親子交流の断絶が子の与える不利益については、原審で以下のようにも既に述べている。
【40もの研究結果を包括的に整理したメタ分析の結果,それぞれの両親と少なくとも35%の時間を過ごす子は,父親や母親とより良い関係を持ち,学問的,社会的,心理的により良く,喫煙,飲酒,薬物使用の可能性が低く,不安,うつ病,ストレス関連の病気の影響を受けにくいことが分かっている(甲1~3)。そうすると、子と別居親との交流を断絶することは統計的に明ら、上記に関するリスクを高め、子の利益に反することになり、このことも当然に申立人は熊本家裁や福岡高裁で主張立証している。ちなみに、両親が高葛藤状態であっても子は両親との交流を維持したほうが子の利益に適うことも明らかになっている。
さて、これらに福岡高裁等の裁判官ら(注:以前に確定した審判)はどんな態度だったか。なんと、裁判官らは無視という挙に出ているんですねぇ。「都合が悪いが合理的理由をもって排斥できない当事者の主張は無視する」との裁判官らの態度が、まともなものなのか、そこに裁判官らの理性や良心があるといえるのかが、本件事件でも確認すべきことの1つである。むしろ、「子が学問的,社会的,心理的により悪く,喫煙,飲酒,薬物使用の可能性が高く,不安,うつ病,ストレス関連の病気の影響を受けやすくなっても父子交流や兄弟交流の断絶を優先する」と、裁判官らがそう明記するくらいの潔さがあればあればともかく、単に無視だからねぇ。「裁判官は正しいはずだ」「裁判官は主張や立証を慎重に検討したはずだ」との、裁判官盲信教の信者になることを期待しないでね。裁判官には判断についての理由提示義務(民事訴訟法253条3項や家事審判手続法第76条2項)があるのだから、正しい判断というのならそれを検証できる理由提示をちゃんとしようね。そして、親子交流や兄弟交流を断絶することのデメリットを無視している福岡高裁等の決定は、子の利益に適っていたといえる理由提示もしていない単なる無視でしかないのだから、子の利益の観点からも理由提示義務の観点からも不適切なものであった。
ちなみに、なぜこのような統計データが存在するのか、それは当然、両親の別離後もそれぞれの両親と少なくとも35%の時間を過ごしている子が存在するから、データを集めることができているのである。つまりこのような親子交流は実施可能なものであり、アメリカ・アリゾナ州だと6歳以降では平日1日夕方3-4時間+隔週3泊を裁判所自身が例示している(甲3)。そして、申立人が求めていたのもこのような客観的に子の利益に適った親子交流であり、このような客観的な基準を蔑ろにしている相手方や福岡高裁の裁判官等が、子の利益を害し、紛争を生じさせ続けていると言えるだろう。
で、このような客観的に子の利益に適った親子交流を定めていれば、申立人がそれ以上の父子交流や兄弟交流を求める必要性も動機もないのだが、このことも「またか」という感じで福岡高裁等は無視しているのだから、福岡高裁等の判断は誤っているばかりか、裁判官らの恣意的判断に都合が悪いことは無視するという公正性に欠如した態度を世に自己紹介するものであった。
相手方は審判で定めた父子交流や兄弟交流以外は頑なに拒否する態度に固執することで、自らが子の利益に配慮する資質に欠けていることを示しているが、だったら審判の内容を変更して上記したように客観的に子の利益に適った父子交流を相手方が阻害しないようにすれば、それ以上の紛争が生じることはなくなり、父子交流や兄弟交流もでき、そのことは二男が 父親や兄や父方祖父母とより良い関係を持ち,学問的,社会的,心理的により良く,喫煙,飲酒,薬物使用の可能性が低く,不安,うつ病,ストレス関連の病気の影響を受けにくくなることなのだから、二男や長男にとっては良いこと尽くめだよね。
だから本件事件で福岡高裁等の決定に言及するなら、上記の申立人が福岡高裁等でも主張した父子交流や兄弟交流の実施方法に、メリット以上のデメリットがあるといえるのかや、それについて福岡高裁等は理由提示義務を果たしているのかや、福岡高裁等が加害者という属性を理由に申立人の主張を審理拒否したことが公正で正しい裁判だったといえるのかが、本件事件でも問われるわけですよ。本件事件で誤った判断(以前に確定した審判)を基礎にしたら、結論も誤ったものになるのは当然でしょ。】
さて、この申立人の主張について若林慶浩がどのような態度だったか、「あーあー聞こえない」といった態度を取っていないかであるが、残念ながら若林慶浩は上記の子の利益に関する重要な学術的知見について、何ら判示せず、事実上の無視との態度であった。そうすると、若林慶浩の判断の審理不尽は明らかであるし、上記の学術的知見を提示した甲1~3に対する採証法則違反があることも明らかである。
ところで、裁判官は親子交流や兄弟交流の断絶によって生じる子の不利益について言及したら死ぬ病気にでも集団感染しているのだろうか? 「裁判官は親子交流や兄弟交流の断絶によって生じる子の不利益について言及してはならない」といった法文上の根拠はなく、むしろ親子交流や兄弟交流の断絶によって生じる子の不利益を無視することは、民法766条1項で面会交流等を「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と規定している法文上の根拠に対する、重大な違反である。
(4) 親子交流や兄弟交流が子にもたらす心情
統計ではなくまた個別事例に戻るが、心理の専門家である臨床心理士であり、元神戸親和女子大学教授でもある棚瀬一代は、以下のように述べている。
【片親から疎外され子どもへの影響は、10年後、20年後になって現れることもある。
「子どもが物心ついて、自分がどういうことをされたのかを理解した時、母親に対する愛を失ってしまう場合があるんですね。この前は「20歳になるのを指折り数えて待っているんだ」と言うお子さんがいました。「20歳になったら家を出て、父親と失った絆を築き直す。お母さんは捨てるんだ」って。ですので、短期的な視点で片親を遠ざけることができたとしても、長期的に見れば、子どもから見離されてしまうことも起きてしまうんです。それは親にとっても不幸なことですし、そのあたりを皆さん、本当にわかってほしいと思うんですよね」】
申立人は別件損害賠償請求訴訟の本人尋問において、「お父さんが会いにきてくれただけのことで警察を呼ぶということは、いずれ向こうが子供から見下されることになるだろうなというのは感じていたので、正直すごく残念な態度には思いましたね。」と述べているが、それは棚瀬一代による上記のような事例を知っていたからである。この事例自体は原審で提示していなかったが、学術的知見に基づく親子交流の断絶が子に及ぼす悪影響は主張立証していたし、そのような悪影響を生じさせている相手方が、いずれ子らから否定的感情を向けられるようになるリスクは決して低くはないと言わざるをえない。それにもかかわらず若林慶浩は親子交流の断絶が子に及ぼす悪影響や、その結果としての子らの心情を尽く無視しているのだから、それがまともな判断であるということはできない。
また、棚瀬一代は、以下のようにも述べている。
【「そういう子どもたちの生の声って、何年経っても非常に強烈なものとして残るんですね。たとえば、あるお子さんには小さい頃の記憶が残っていて、父親に肩車をしてもらいながら涼しい風がさわっと吹いてきた、そういうのどかな光景が今も残っていると言うんです。そして「会えなくなった父親に会いたいって気持ちがガァーって出てくるけれど、そういう思いが出てくるとあまりにつらいから、ぐーっ埋葬しておくんだ」って言うんです。「それで時々、自分が耐えられる程度に思い出すんだ」と」
「あるいは、もう何年も会っていない父親を一目見ようとして、今も家の前に1時間ぐらい車を停めながら、じーっと待っている大学生がいました。「遠くからでも父親の姿が見れないかな」って。私はそういう子どもたちの状況を、何とか代弁したいと思ったんです。】
子にこのような思いを抱かせるリスクとなる親子断絶が、親としてまともな態度とは到底言い難く、裁判官の判断としても子の利益を最優先に考慮したもの(民法766条1項)と到底言えない。つまり、統計的な学術的知見からも、そのような学術的知見を裏付ける個別事例的な観点からも、親子断絶を容認している若林慶浩の判断が子ら(申立人が養育している長男と、相手方が養育している二男の双方:二男のほうがこの事件の対象者となる未成年者)の利益に反したものであったのは明らかである。
若林慶浩の判断がまともでないとの判断から申立人は即時抗告をしているが、それによって福岡高裁の裁判官らが、親子交流の断絶が子に及ぼす悪影響や、その結果としての子らの心情に関する申立人の主張立証に対してどのような態度をとるか、それは合理的か、審理不尽や採証法則違反がないか、鬼ごっこをしていないかについて、国民が注視していく必要がある点であろう。
(5) 親子交流や兄弟交流が子にもたらすひきこもり
更にたたみ掛けると、令和4年10月21日、産経新聞のウェブサイトに掲載された日本大学名誉教授国士舘大学客員教授である百地章の記事に、以下のように述べられていた(甲16)。
【最近相談を受けた大手企業勤務のN氏の場合、平成23年10月、左翼弁護士に洗脳された妻が女の子を連れて突然家出をしてしまい、その後11年間、子供とは会っていない。娘さんは現在21歳になるが、漸(ようや)く得られた情報では9年間引きこもったままだという。精神科医の話では「お父さんと会わせないことで、心理的虐待を受けた可能性が高い」とのことだ。】
さて、これまでに述べてきた、親子断絶によって生じる悪影響の学術的知見、親子断絶を原因とする不登校や心的外傷後ストレス障害(PTSD)、親子断絶された子の心情に鑑みれば、この産経新聞の記事のように親子断絶の悪影響が長期化し、成人しても引きこもったままとの状態を生じさせているとしても、何ら不自然なことではない。
つまり、相手方や若林慶浩が親子断絶をしていることは、子が学問的,社会的,心理的により悪く,喫煙,飲酒,薬物使用の可能性が高く,不安,うつ病,ストレス関連の病気の影響を受けやすくし、不登校やPTSD、長期にわたる引きこもりを生じさせるリスクを高めていることになる。その判断が親としても裁判官としてもまともであるとは到底言えないことは明らかであろう。
(6) 支援措置の適用要件
論点の流れが変わるが、若林慶浩は別件損害賠償請求訴訟の本人尋問における申立人の以下の発言を引用している。
【相手方の居住地が分からないことについて、「それ自体ちょっと不当かなというふうに思っているんですね。】
これについて申立人は原審で以下のように述べている。
【相手方は申立人をDV等の加害者として、「ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者保護のための住民基本台帳事務における支援措置」(以下「支援措置」という。)の申出をすることで、申立人が二男の戸籍謄本等を取得できないようにしている。
しかしながら、名古屋高等裁判所令和3年4月22日判決は支援措置適用要件に該当しない支援措置の申出を違法なものとして損害賠償請求を認めており、本件事件も同様、申立人に支援措置適用要件に該当する行為はない。
右裁判例は支援措置適用要件として以下を判示している。
(ア) 申出者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者であること
(イ) 申出者が、加害者からの更なる暴力により生命又は身体に危害を受けるおそれがあること
(ウ) 加害者が、被害者の住所を探索する目的で、住民基本台帳の閲覧等を行うおそれがあること
当然、申立人は上記の支援措置適用要件に該当する行為をしていないのだから、申立人は二男の戸籍謄本等にアクセスする権利を、相手方から違法に阻害されていることになる。
なお、右裁判例は以下のようにも判示している。
「支援措置が実施されることにより、被控訴人は、市町村において、支援措置上のDVの加害者であって、その更なる暴力により被害者が生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものとして扱われ、そのことを被控訴人自身の行為によっては容易に是正することができない状態に置かれていることになり、被控訴人は、自己に関する誤った情報を是正することができないことにより人格的利益を害されたものと認められる。」。
「支援措置が加害者と扱われる者に一定の不利益を与えるものであることが否定できない以上、DV被害者が主観的に恐怖心を有するからといって、客観的に支援の必要性の存在が認められるものと解することはできない。」。
つまり、相手方が申立人を支援措置における加害者としたことは、申立人の人格的利益を害する行為であった。また、相手方が申立人に対して気に入らないことがあったり、被害妄想を増大させることで主観的な恐怖心を有したりしたとしても、支援措置適用要件に該当していない以上、相手方が申立人を支援措置における加害者としたことは違法なものであった。】
このように、名古屋高等裁判所令和3年4月22日判決からすれば、支援措置適用要件を満たしていない支援措置決定は、損害賠償に値する人格的利益の侵害ということになり、そのような人格的利益の侵害を申立人は「不当」と表現したにすぎない。
なお、本来、申立人が公正な行政による住民サービスによって二男の居住地を知ることができるのだから、申立人が二男の居住地を知らないことを前提にした以前の面会交流の確定した審判は、前提条件を誤った違法なものであった。
しかしながら、若林慶浩は本件の支援措置決定が支援措置適用要件を満たしているものであったのかについて、何ら判断を示さず、漫然と以前の面会交流の確定した審判を維持する判断をしているのだから、この若林慶浩の判断がまともであったとは到底言えない。
若林慶浩は、相手方による支援措置の申し立てが支援措置適用要件を満たしていたものであったか(換言すれば、申立人が二男の戸籍附票を取得するという住民サービスを受ける権利が侵害されていることに違法がないか)について、相手方に釈明を求めて確認することができる立場にあった。そして、相手方による支援措置の申し立てが支援措置適用要件を満たしていなければ、本来、申立人は二男の居住地を知る権利があるのだから、申立人が二男の居住地を知らないことを前提とした以前に確定した審判は誤りであったことになる。つまり、相手方による支援措置の申し立てが支援措置適用要件を満たしていたものであったかは、審判の結果を左右する重要な争点であった。それにもかかわらず、若林慶浩はこの争点について何ら判示していない。このような若林慶浩の態度は、親子断絶に都合が悪いが合理的理由をもって排斥できない申立人の主張立証を無視したものと言わざるをえないのだから、このような若林慶浩の態度がまともであるとは到底言い難い。
2 以前に確定した審判への忖度よりも子の利益が優先されることについて
若林慶浩は以下の判示している。
【家事審判は、国家の紛争解決機関に持ち込まれた紛争に対する一定の解決内容を提示するものであって、同種の申立てが繰り返された場合に全面的な審判のやり直しをせざるを得ないと解するのは、不合理であり、確定した審判についての再審の手続が整備されていること(家事手続法103条)とも整合しないから、面会交流の審判が確定した場合には、後の審判等における判断を一定程度拘束する効果があると解するのが相当であって、後の審判等において確定した審判と異なる判断をするためには、確定した審判において判断の基礎とされた事情が変更したこと等の特段の事情が認められることが必要と解するのが相当である。】
(1) 裁判所の紛争もみ消し機関化、紛争増幅機関化
まず、以前に確定した審判にしろ若林慶浩にしろ、裁判所を紛争解決機関ではなく、紛争もみ消し機関や紛争増幅機関とでも認識しているのではないかとの疑義が強く生じる。以前に確定した審判は申立人の主張立証の多くを無視し、その採用しない合理的説明ができていない点も多々あり、そのような全く説得力がない判示は「黙れ、私は何も間違えない。私の言うことは絶対である。だから判断理由の具体的説明なんかしない。とにかく私が"正しい"と言ったことが"正しい"のだ。」とする裁判官らの基本的態度が読み取れる。このような傲慢な鬼ごっこ的態度がまともでないのは明らかである。
また、ここでも岡口基一が指摘した「反対証拠を説得力をもってつぶすのが裁判官の能力だとみんな思っている」を思い出そう。裁判官が説得力をもった判示をしたがっていることを前提にすれば、それを裁判官がしていない場合、その理由は裁判官らが悪質で姑息な誤魔化によって恣意的判断に及んだためと解するのが妥当である。
つまり、裁判官のまともさをチェックするには、何を判示したかではなく、何を無視して判示していないかがより重要であり、合理性に欠けた裁判官の態度は、裁判所が紛争もみ消し機関や紛争増幅機関となっていることを立証することになる。
(2) 面会交流審判などでの再審手続き
若林慶浩は、同種の申立てが繰り返された場合に全面的な審判のやり直しをせざるを得ないと解するのは、不合理であり、確定した審判についての再審の手続が整備されていること(家事手続法103条)とも整合しないとしている。
しかしながら、再度の審判の申し立てが再審の手続きでなければならないといった法文上の根拠はなく、裁判実務においてもそのようにはなっていない。たとえば、子の引き渡し、面会交流、養育費といった、複数回の申し立てが稀ではない申し立てについて、これまでの裁判実務がこれら全てが再審の手続きでなければならないと、再審ではない新たな申し立て自体を全て却下してきているのであろうか。当然、そうはなっていない。そもそも、若林慶浩自身、本件を再審の手続きではないとして却下していないことも矛盾している。つまりこのような矛盾を晒していること自体が、若林慶浩の浅はかさな判断の矛盾を晒していると言えるだろう。そのような意味において、若林慶浩の判断こそが不合理である。
また、以前に確定した審判は、その時点での状況に対しての判断であり、そこから時間経過して申し立てられた審判は、もはや以前の状況に対しての判断のやり直しを求めているものとはいえない。その意味においても若林慶浩の判断は合理性に欠ける。
(3) 子の利益の優先性
若林慶浩は事手続法103条との整合について判示しているが、では民法766条1項との整合についてはどうであろうか。ここは若林慶浩がいかに家事審判の本質を理解していないかが顕著に表れているところであり、民法766条1項は面会交流等について「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と規定されており、これが本件事件の本質であり、明文化もされている最優先に考慮しなければならない事項である。
言うまでもないことだが、事手続法103条との整合性と、民法766条1項との整合性、どちらを優先すべきか。つまり、以下のどちらを優先すべきかということである。
●以前に確定した審判は子の利益に反していても、子の利益よりも以前に確定した審判への忖度を優先すべきである。
●以前に確定した審判が子の利益に反していれば、以前に確定した審判に忖度することなく子の利益を最優先に考慮した判断を優先すべきである。
これについて、事実上、若林慶浩は前者を優先する選択をしている。つまり、若林慶浩は子の利益よりも以前に確定した審判を優先している。だから若林慶浩は民法766条1項との整合性について何ら言及していない。申立人は父子交流や兄弟交流の実施が子の利益に適うとの主張を繰り返してきたのだから、若林慶浩の態度はまさに、「恣意的判断をするのに都合が悪いが、合理的理由をもって排斥できない当事者の主張であるため、無視やすり替えなどの悪質で姑息な手段によって恣意的判断を強行することを選択した」疑いが強いものであると言わざるを得ない。
そもそも、民法766条1項は「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」との規定であり、これは条件付きにはなっていない。仮に、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。ただし、以前に確定した審判があれば、その審判に対して子の利益に反していた等の主張がされたとしても、以前に確定した審判を優先し、子の利益を最も優先して考慮する必要はない」といった規定であれば、若林慶浩の判断にも妥当性があったことになるが、繰り返すが民法766条1項はこのような条件付きでの条文になっていない以上、若林慶浩は子の利益を最も優先した判断をしなければならなかったが、若林慶浩がそれを怠っているのは明らかなのだから、原審の違法性も明らかである。
(4) 審判の合目的性
そもそも、面会交流に関する審判の目的は何であろうか。これについて最高裁判所第三小法廷判決昭和59年12月20日(集民第143号481頁)は以下のように判示している。
【子の監護に関する処分にかかる審判は、家庭裁判所が子の福祉のため後見的立場から合目的的かつ迅速に裁量権を行使する形成的処分であつて、その性質は非訟事件の裁判である】
ここで重要なのは前半の部分、つまり、家庭裁判所は子の福祉のため後見的立場から合目的的に裁量権を行使しなければならないという点である。そうであれば当然、以前に確定した審判が子の福祉に反したものであるとの主張があれば、その内容も含めて慎重に検討し、子の福祉を最優先に考慮した判断をするように務めるのが裁判官の義務である。
それにもかかわらず、若林慶浩は数々の無視などによってこれを怠ったと言わざるをえないのだから、若林慶浩の判断が子の利益を考慮し、かつ、合理的理由を示せたまともなものであったとは言い難い。
3 若林慶浩が申立人が自己の主張に強く固執しているとの判示について
(1) 申立人が自らの主張に固執していたとする若林慶浩の判断の漠然性
若林慶浩は、申立人が自己の主張に強く固執していることで申立人と未成年者との面会交流の実施が困難となっているとしている。
まずここでの若林慶浩の問題点は、固執の内容や、それによってなぜ面会交流の実施の実施が困難であるかの具体的説明が全く無いことである。具体性がないから検証可能性もない。検証可能性がないから、科学的ではなく合理性もない。若林慶浩が自らの判断に自信があるのであれば、「申立人は~との方法の面会交流に強く固執し、そのような方法は~という理由で子の利益に反しているのだから実施は困難である」ということを具体的に判示すれば良かったことである。若林慶浩がそれをできずに具体性のない抽象的表現しかできていないことも、若林慶浩が恣意的判断を抽象的に誤魔化そうとしたのではないかとの姑息さを疑わざるをえない。
(2) 仮に申立人が自らの主張に固執していても面会交流不実施に理由になり得ないこと
そもそも、仮に申立人がある特定の面会交流の方法に強く固執していることを前提にしても、それは父子交流や兄弟交流を断絶する正当な理由になりえない。若林慶浩の判断は要するに、「申立人は子の利益に適った面会交流の方法に強く固執しており、それは海外での親子交流において実施可能な頻度や内容であることが立証されており、親子交流に関する学術的知見においても申立人が強く固執している面会交流の方法は子の利益に適ったものであるが、とにかく申立人がある特定の面会交流の方法に固執しているから親子関係や兄弟関係は断絶する」というものになっている。
もっと要約すれば、「申立人は子の利益に適った実施可能な面会交流を求めているが、子の利益に適った実施可能な面会交流に固執しているから親子関係や兄弟関係は断絶する」と若林慶浩は判断していることになる。子の利益を最優先に考慮すれば、このような若林慶浩の判断がまともでないのは言うまでもない。
(3) そもそも申立人は特定の面会交流の方法に固執していないこと
次に、そもそも申立人が特定の面会交流の方法に固執しているかについて見ていく。申立人は原審で以下のように主張している。
【まず、父子交流や兄弟交流が断絶されることのデメリットや、二男が精神疾患がある相手方に独占支配されていることのデメリットに鑑みれば、速やかに父子交流や兄弟交流が再開されなければならない。
また、申立人が求めているのは発達心理学の研究成果に基づいた子の利益に適った面会交流(甲1~3)の実施であるが,それに対して相手方が審判決定以上の面会交流に応じない態度に固執したことで,紛争が生じている。
そうすると,相手方に対して申立人と二男との交流を妨害してはならないと定めることで、紛争は生じなくなり、二男は父子交流や兄弟交流によるメリットを享受でき、精神疾患がある相手方による独占支配を余儀なくされる状況も軽減され、父親から養育を受けるという人格的利益も回復されることになる。ちなみに、申立人もそれほど暇ではなく、仕事や長男の監護等があるのだから、それほど面会交流に時間を割くわけにもいかず、そもそも申立人が求めているのは発達心理学の研究成果に基づいた子の利益に適った面会交流だとしても長期休暇以外で35%に近づけるのは困難なのだから、申立人が子の利益に反した過度な父子交流や兄弟交流を要求することはありえないし、そのような要求をする動機もないし、そのような要求をするおそれがあるとする具体的根拠もない。それでも上限を決めるべきというのであれば、発達心理学の研究成果に基づいた子の利益に適った面会交流を基準として、それ以上の面会交流を禁止すればよいだけである。
また,当事者間での面会交流の協議が困難というのであれば,相手方が親族なり友達なり弁護士なりに代理人を頼めば良いことであるが、むしろ二男が直接申立人や長男とやりとりすることも良いだろう。ここで「できるための工夫」ではなく「できないための言い訳」に思考の指向性がある場合、「子に葛藤が巻き込まれる」とか言い出すことも想定されるが、子が友達と遊びたくて親に許可を求めることが子の利益に反する状況だとはいえないのと同様、二男にとってその対象が友達ではなく父や兄だった場合に子らの利益に反する状況になるといえる具体的根拠はない。少なくとも、親子や兄弟の生き別れのほうがましなほど強い葛藤状態に陥ると言える具体的根拠はないし、そもそも、以前から父子交流や兄弟交流は良好であった。
それでもまだ文句をつけるのなら、面会交流の日時や頻度,時間の長さ,二男の引渡しの場所や方法等,面会交流の実施方法を発達心理学の研究成果に基づいた子の利益に適った方法で細かく定め、それ以外の父子交流を禁止すればよいだけである。
二男の受け渡しで相手方が申立人に会いたくないなら、相手方以外の者が受け渡しをすればよいことであり、というよりこれは以前から相手方はそうしている。
まあ「できるための工夫」ではなく「できないための言い訳」を相手にしているとキリがないが、そもそも相手方が父子交流や兄弟交流に寛容であれば紛争は生じなかったのだし、相手方が寛容になることができないとしても裁判所が相手方に面会交流を妨げてはならないとしても同じ効果になる。次善の策にはなるが、その他のいちゃもんも面会交流の方法を細かく定めたり、相手方が誰かに代理人を依頼すれば解決できることばかりである。】
さて、まともな読解力があれば、申立人が複数の案を提示していることが読み取れるだろう。つまり、そもそも申立人が自己の主張に強く固執しているとしたこと自体、若林慶浩の誤りであるし、仮に複数の案であっても全てを含んで申立人が自己の主張に強く固執しているとの評価をするとしても、これらの案は子の利益に適った実施可能なものであるのだから、その意味においても親子交流や兄弟交流を断絶している若林慶浩の判断に合理性はない。むしろ、申立人の複数の案の個々の問題点について具体的に説明できていない時点で、若林慶浩は自らの誤りに気づき、子の利益を最優先に考慮した判断へと正すべきであった。原審から述べていることであるが、合理的理由を持って排斥できない当事者の主張立証があれば、それを排斥しようとした判断のほうが誤っていると気づく知性くらい裁判官は持つべきであるし、そうでなければ公正な裁判が期待できない。
なお、原審で明記していた申立人の上記主張について、若林慶浩が気づかなかった可能性は低い(仮に気づかなかったとしても、それはそれでまともに主張を読み込んでいないのだから若林慶浩に注意義務違反があることになるが)。それよりも、故意に無視したと解するほうが妥当だろう。やはり裁判官は、合理的理由を持って排斥できない当事者の主張立証があれば、それを排斥しようとした判断のほうが誤っていると認める理性や良心を持つべきだろう。
4 相手方に転居の必要性はなかったことについて
若林慶浩は、面会交流を求めて一方的に相手方の居住地を訪問するなどしてきた申立人の従前の行為に照らせば、仮に申立人が相手方の居住地を認識した可能性が生じた場合には、相手方と未成年者は転居を余儀なくされることになるとしてる。
(1) 二男にとって父親や兄が会いに来てくれるのは好ましい出来事であること
上記の若林慶浩の判示は、申立人の原審での以下を無視したものとなっている。
【 申立人は申立人と同居する長男が二男に会いたがっていたこともあり、兄弟関係への配慮から長男を連れて二男の居住地に行った。そうすると相手方を二男を巻き込み転居したわけだが、相手方の言動はつまるところ、「申立人が長男と一緒に兄弟を会わせようと二男の居住地に行ったら、相手方は死にたくなって転居した」というものである。
しかしながら、兄弟の交流が子らの利益に反するとは言えないし、そのときに申立人が二男に会ったとしてもそれが二男の利益に反することでもないし、申立人が兄弟を会わせたいと二男の居住地に行ったことが相手方に対する何らかの法令に反する違法行為に該当していたわけでもない。むしろ、申立人や長男が二男の居住地に行ったことがあるからこそ、申立人が二男の居住地に行ったとしても申立人が相手方に何らかの加害行為に及ぶおそれがないことは立証されている。
さて、相手方に転居の必要性がなかったことは福岡高裁等でも主張しているが、この主張はどのように判断されているかな? なんと、裁判官らは無視という挙に出ているんですねぇ。「都合が悪いが合理的理由をもって排斥できない当事者の主張は無視する」との裁判官らの態度が、まともなものなのか、そこに裁判官らの理性や良心があるといえるのか、理的理由をもって排斥できない当事者の主張があれば排斥しようとしている判断のほうが誤っていると気づくべきではないのか、それに気づいても恣意的判断を強行しているおそれに鑑みて裁判官をより拘束して裁判官の恣意的判断を抑止する法改正が必要ではないのかといったことも、本件事件で問われていることの1つである。】
【「父や兄が会いに来てくれた ⇒ だから会わせた」がまともな親の態度というもので、申立人や長男が二男に会うことが二男の利益に反していたと言える具体手根拠は存在しないし、申立人や長男が二男に会いに行ったことで相手方が申立人から何らかの具体的危害を加えられたとする事実もない。しかし相手方は、「父や兄が会いに来てくれた ⇒ だから転居して父子交流や兄弟交流を断絶した」との態度に出ている。ここで大事なのは二男の心情ですよ。「父や兄が会いに来てくれた ⇒ だから転居して父子交流や兄弟交流を断絶した」に対して、二男が「なるほど」と納得するとても? 「父や兄が会いに来てくれた」を原因、「転居して父子交流や兄弟交流を断絶した」をその結果とすることには、論理の飛躍があるよね。まあ相手方は「父や兄が会いに来てくれた」ことを精神的負担に感じたようだが、ではなぜこれが精神的負担になったのかというと、そもそも相手方が父子交流や兄弟交流を断絶したいとの子らの利益に反した不適切な歪んだ認識を持っていたことに他ならない。ここ、大事だから若林慶浩が別の見解だというのなら、それを具体的に明確にするように。で、相手方が元々が子らの利益に反した不適切な歪んだ認識だから、それに基づく言動も子らの利益に反した不適切な歪んだものとなるのは当然であり、それが父子交流や兄弟交流の断絶や、二男を巻き込んでの一方的な転居だったというわけである。だから、何度も言うようにフレンドリー・ペアレント・ルールが大事なんですよ。
で、子の利益を最優先に二男の心情を考慮すれば、「父や兄が会いに来てくれたから転居して父子交流や兄弟交流を断絶した」という状況に納得できるはずがないでしょ? ここでもう一度、父子交流や兄弟交流の具体的内容(甲12の1ないし7)を振り返ろう。このような好ましい父子交流や兄弟交流を二男がする機会を奪ったのが相手方というわけなんですね。それに二男が反発したり精神的負担を感じるのは当然でしょ? そしてそれが二男の学校での不適応として表出していると解するのが当然でしょ? 二男の主観で言えば「お父さんやお兄ちゃんが僕のために会いに来てくれても、お母さんはそれを邪魔したし、お父さんやお兄ちゃんが僕のために会いに来てくれたことを逆に利用して、僕からお父さんやお兄ちゃんを引き離した。お兄ちゃんはお父さんと一緒に暮らしていろんな経験をしたり、いろんなことに頑張ったりしていたのに、お母さんのせいで僕はお父さんに可愛がってもらえなくて、僕の人生からお兄ちゃんも消えてしまった」となるわけである。相手方や裁判官らがどのように屁理屈を述べようとも、重要なのは父子交流や兄弟交流は好ましいものだったということであり、それを相手方が断絶させたということであり、相手方が二男を巻き込み転居をしたということであり、長期にわたって父子交流や兄弟交流が断絶された現状において二男が不適応を長期にわたって生じさせているという現実である。現実と、「申立人を加害者扱いしたい」との主義主張が矛盾した場合に、主義主張を優先することが愚かであることくらい、若林慶浩は理解できるよね?】
さて、若林慶浩はこれらの申立人の主張に対する検討を怠っており、このような鬼ごっこ的態度は、若林慶浩が裁判所を紛争もみ消し機関と認識しているのではないかとの疑義を強く生じさせる。
また、このような若林慶浩の鬼ごっこ的態度は、裁判所が紛争増幅機関となる結果を生じさせている。実際、本件のような即時抗告の必要性を生じさせ、若林慶浩の鬼ごっこ的態度について世に問う必要性も生じささせ、このような故意というほかない鬼ごっこ的態度が違法であるかを提訴する必要性も生じさせている。
若林慶浩は原審で申立人が釘を差していたことであっても、何ら説得力や矜持を持つことなく、無視という不適切な態度を繰り返している。このように、都合が悪い主張を無視しまくるのであれば、裁判官はどのような恣意的判断も可能であろうが、本来、それを抑制するために裁判官の判断には理由提示義務が課せられているはずであるにもかかわらず、それが機能せず、裁判官がその判断の合理性を何ら判示することなく、説得力のない恣意的判断をしていることを、若林慶浩は立証したといえるだろう。
(2) 相手方の脅迫的態度
前記でも引用したように、申立人や長男が二男の居住地に行ったことがあるからこそ、申立人が二男の居住地に行ったとしても申立人が相手方に何らかの加害行為に及ぶおそれがないことは立証されている。そのため、相手方が
「申立人に居住地を知られたら転居する」
との脅迫的態度を取っているとしても、それは父子交流や兄弟交流を断絶する合理的理由にならず、むしろ、相手方の同居親としての適格性の欠如を顕著に示していることになる。
仮に相手方による脅迫的態度が故意によるものではないにしても、相手方の主観的恐怖感は父子交流や兄弟交流を断絶させる合理的理由にならない。このことは名古屋高等裁判所令和3年4月22日判決において、「支援措置が加害者と扱われる者に一定の不利益を与えるものであることが否定できない以上、DV被害者が主観的に恐怖心を有するからといって、客観的に支援の必要性の存在が認められるものと解することはできない。」と同じ法理である。本件事件においても、相手方が申し立てた支援措置が支援措置適用要件を満たしていなければ、申立人が二男の居住地を知ることができる二男の戸籍附票の取得ができない現状は、違法なものとなる。
そのため、若林慶浩がまともな判断をする意志があったならば、申立人のどのような具体的行為が、支援措置適用要件のいずれに該当していたとして支援措置を申し立てたのか、若林慶浩に釈明を求めることもできた。そして、申立人に支援措置適用要件を満たす具体的加害行為が認められなければ、申立人は二男の居住地を知ることができることを前提にした判断にしなければならなかった。
それにもかかわらず、若林慶浩それをせず、申立人が二男の居住地を認識した場合に申立人が二男や相手方に具体的危害を加えるおそれがあるのかについてもなんら検討せず、漫然と申立人が二男の居住地を知れば相手方が転居を余儀なくされるとの判断をしているのだから、そこに合理性がないのは明らかである。
(3) 面会交流自体を禁止することに合理性がないこと
若林慶浩は申立人が相手方の居住地に行くことを避けなければならないことを前提にしている。そもそもその前提自体が必要なのかとの疑義はあるが、この疑義をとりあえず措くとしても、ならば申立人が相手方の居住地に行くことを禁止すれば良いだけのことであり、面会交流自体を禁止することは合理性に欠ける。
あるいは、相手方が申し立てている支援措置と、保護命令は要件が類似しているのだから、申立人が二男の居住地に行くことを避けないのなら、相手方が保護命令を申し立てて接近禁止命令等を求めればよいことである。
また、申立人は原審から以下のように主張している。
【当事者間での面会交流の協議が困難というのであれば,相手方が親族なり友達なり弁護士なりに代理人を頼めば良いことであるが、むしろ二男が直接申立人や長男とやりとりすることも良いだろう。ここで「できるための工夫」ではなく「できないための言い訳」に思考の指向性がある場合、「子に葛藤が巻き込まれる」とか言い出すことも想定されるが、子が友達と遊びたくて親に許可を求めることが子の利益に反する状況だとはいえないのと同様、二男にとってその対象が友達ではなく父や兄だった場合に子らの利益に反する状況になるといえる具体的根拠はない。少なくとも、親子や兄弟の生き別れのほうがましなほど強い葛藤状態に陥ると言える具体的根拠はないし、そもそも、以前から父子交流や兄弟交流は良好であった。
それでもまだ文句をつけるのなら、面会交流の日時や頻度,時間の長さ,二男の引渡しの場所や方法等,面会交流の実施方法を発達心理学の研究成果に基づいた子の利益に適った方法で細かく定め、それ以外の父子交流を禁止すればよいだけである。】
つまり、申立人と二男とで交流方法を話すようにすれば良く、それは申立人が二男の居住地に行かなくても電話やインターネットを利用して可能である。あるいはそれにもまだ文句をつけるのなら、細かく面会交流方法を決め、それ以外の父子交流を禁止するなり、申立人の相手方やその居住地への接近を禁止するなりすれば済むことなのだから、やはり父子交流や兄弟交流自体を断絶させている若林慶浩の判断は合理性に欠ける。そして若林慶浩が上記の申立人の主張を無視しているという事実が、若林慶浩が恣意的判断をするのに都合が悪いが合理的根拠をもって排斥できなかった主張立証の無視に及んだとの疑義を強く抱かせる。
5 面会交流実施に申立人と相手方の協力関係は必要条件ではないことについて
若林慶浩は、面会交流実施に当たって申立人と相手方とが協力関係を築くことを期待することは困難であるから、面会交流の実施は子の福祉に反するとしている。
(1) 若林慶浩の判示に検証可能性がないこと
さて、この若林慶浩の判示の検証可能性であるが、相変わらず皆無である。若林慶浩がどのような合理的根拠をもって、父母が協力関係を築いていない状態での面会交流の実施は子の福祉に反するとしているのか、その裏付けが完全に欠落している。
ここでまた、岡口基一が指摘した「反対証拠を説得力をもってつぶすのが裁判官の能力だとみんな思っている」を思い出そう。仮に若林慶浩が前提としている「父母が協力関係を築いていない状態での面会交流の実施は子の福祉に反する」ことに合理的根拠があるならば、それを敢えて若林慶浩が示さないことに意味があるだろうか。その根拠を示していれば、より若林慶浩の判示に説得力が出るし、申立人が今書いているように、若林慶浩の判示には合理的根拠が欠落しているとの欠点を指摘されることもなくなる。そうすると、若林慶浩が合理的根拠を敢えて示さないことの有意義性は見いだせないのだから、若林慶浩が上記について合理的根拠を示さないのは、示すことができない、つまり、そもそも合理的根拠が存在しないからだと解するのが妥当である。
つまり、ここでも若林慶浩の鬼ごっこ的態度が発揮されていると言えるだろう。「黙れ、私は何も間違えない。私の言うことは絶対である。だから判断理由の具体的説明なんかしない。とにかく私が"正しい"と言ったことが"正しい"のだ。」というのが若林慶浩の本質的な人格特性であることを疑わざるをえない。もっと分かりやすく表現すれば、若林慶浩の態度は「~に決まってるもん」と根拠なく決めつける幼児と同レベルものもでしかない。つまり若林慶浩の態度は、「父母が協力しなかったら面会交流できないに決まってるもん」と、根拠を示すことなく一方的に決めつけているものなのだから、若林慶浩の判断が子の利益を考慮し、かつ、合理的理由を示せたまともなものであったとは言い難い。
(2) 父母が協力関係を築けていない場合の面会交流に関する学術的知見
では、逆に「父母が協力関係を築いていない状態での面会交流の実施であっても子の福祉に適う」といえる合理的根拠はあるのだろうか。これについては東京国際大学教授である小田切紀子が、60件の研究のメタ分析論文から、「両親間の葛藤が高いと評価される場合でも、共同養育は単独養育より子どもにとって好ましい結果」であることを紹介している(甲3)。また、「親が物理的な親権を共有している子供は、1人の親が最初に取り決めを反対したときや、親同士の対立が激しいときでさえ、より良い結果をもたらすことを発見しました。」(甲2)との研究知見も既に存在している。
更に、このことを申立人は既に原審から以下のように主張していた。
【 これは根拠に基づく判断には重要なことであり、60件の研究のメタ分析論文により、両親間の葛藤が高いと評価される場合でも、共同養育は単独養育より子どもにとって好ましいとの結果が出ている(甲3)。
メタ分析って分かるかな? たとえば医学の分野では「EBM」の重要性がよく言われている。EBMとは「Evidence-Based Medicine」の略であり、「根拠に基づく医療」と訳されている。これは当然のことであり、医療機関が効果のない治療法で患者の健康を損ねることがあってはならないのだから、医療機関の治療法はきちんとした根拠に基づいた治療法である必要がある。そのためには信頼性が高い研究法で根拠が示されることが望ましいが、このEBMではレベルが低い(根拠として弱い)ものから、大まかに以下のように整理できる。
・データに基づかない専門家の意見
・個別の事例研究
・比較研究(非介入と介入の場合等があるが、ここでは深入りしない)
・データ統合型研究(系統的レビュー)
さて、上記で挙げたメタ分析は、研究法の質でいえばデータ統合型研究(系統的レビュー)に該当する。これも当然であり、たとえば上記した結果は60もの研究論文を集め、それを更に研究することで導き出された知見なのだから、その根拠としての質が高いのは言うまでもない。
いま、裁判官に求められているのは「EBJ」である。「Evidence-Based Judge」ね。「根拠に基づく裁判」とでも訳せば良いだろうか。あるいは、「根拠に基づく裁判をする能力がある裁判官」、「根拠の重要性を理解する能力がある裁判官」でも良いかもれない。これも当然で、裁判官が根拠がなくそのためにまともに説明ができない自らの思い込みを優先して、合理的根拠がある主張を蔑ろにしたら、根拠に基づく判断になるわけないし、子の利益を最優先に考慮した判断にもなるわけないでしょ。
そうそう、データに基づかない専門家の意見も、根拠の質としては高くないが、だからといって全く根拠にならないとまで否定されているわけではない。ただし、では裁判官は? 上記の60件の研究のメタ分析論文で言えば、医学や児童心理学、あるいは社会学なんかも関係する分野に入る余地があるかもしれないが、一般に裁判官はこれらの専門家であるといえる根拠があるだろうか? まあ、ないね。そうすると、上記研究に関しての裁判官のデータに基づかない見解は、そもそも根拠といえるレベルにない、ごみでしかない。なぜごみかといえば、根拠に基づく適切な子の利益を考慮するときに、より質の高い根拠を蔑ろにした根拠のない裁判官の意見は邪魔でしかないからである。ここは、裁判官が「無知の知」を自覚しているかという知性が試され、確認できるところでもある。裁判官が「無知の知」を自覚せず、質の高い根拠に基づいた主張や書証より、自らのデータに基づかないその分野の専門的バックグラウンドもない個人意見や、根拠が不明だが裁判所で運用されている判断を優先させるなら、歪んだ判断になるのは当然でしょ? だからこそ、根拠は大事なんですよ? 】
さて、このような申立人の主張立証について、若林慶浩はどのような態度であったか。判示の全てを見ても、若林慶浩は上記の子の利益に関する学術的知見について、何ら言及せず、事実上の無視をしている。なるほど、若林慶浩が恣意的判断をするためには、よほどこの研究結果は都合が悪かったのだろう。しかし本来、公正な判断をしようとすれば、このような研究結果を考慮した判断をするか、考慮しないのならこの研究結果が信用できないとする合理的理由を示さなければならない。そうでなければ、公正に判断した上での合理的理由から証拠を採用しなかったのか、あるいは、恣意的判断をするのに都合が悪いが合理的根拠をもって排斥できなかった主張立証を無視することで故意に採証法則違反に及んだのか、それを判別する判断材料が示されていないことになる。ただし、何度も引用している岡口基一が指摘した「反対証拠を説得力をもってつぶすのが裁判官の能力だとみんな思っている」からすれば、原則的に裁判官は説得力をもった判示をしたがっているのだから、裁判官が敢えて合理的理由を示さないことに合理性はなく、そうすると、若林慶浩は恣意的判断をするのに都合が悪いが合理的根拠をもって排斥できなかった主張立証を無視することで故意に採証法則違反に及んだと解するのが妥当であろう。
そうすると、提示された子の利益に関する証拠(甲1~3)に基づき公正に判断すれば、「両親間の葛藤が高いと評価される場合でも、共同養育は単独養育より子どもにとって好ましい」のだから、それに反する若林慶浩の判断を子の利益を蔑ろにしたものであったというほかない。
なお、申立人としても自らの主張が絶対だとするつもりはないが、若林慶浩がまともな判断をしているとする場合、提示された子の利益に関する論文などの書証について若林慶浩がどのような判断をしているかや、その判断は合理的なものであったかの検証を経なければならない。しかしながら申立人が読むかぎり、若林慶浩は提示された子の利益に関する書証について何ら言及していないのだから、若林慶浩の判断が子の利益を考慮し、かつ、合理的理由を示せたまともなものであったとことを裏付ける根拠は見当たらない。
(3) 父母に協力関係がない場合の具体的な面会交流の実施方法
申立人は原審において以下の主張もしていた(再度の引用となる)。
【当事者間での面会交流の協議が困難というのであれば,相手方が親族なり友達なり弁護士なりに代理人を頼めば良いことであるが、むしろ二男が直接申立人や長男とやりとりすることも良いだろう。ここで「できるための工夫」ではなく「できないための言い訳」に思考の指向性がある場合、「子に葛藤が巻き込まれる」とか言い出すことも想定されるが、子が友達と遊びたくて親に許可を求めることが子の利益に反する状況だとはいえないのと同様、二男にとってその対象が友達ではなく父や兄だった場合に子らの利益に反する状況になるといえる具体的根拠はない。少なくとも、親子や兄弟の生き別れのほうがましなほど強い葛藤状態に陥ると言える具体的根拠はないし、そもそも、以前から父子交流や兄弟交流は良好であった。
それでもまだ文句をつけるのなら、面会交流の日時や頻度,時間の長さ,二男の引渡しの場所や方法等,面会交流の実施方法を発達心理学の研究成果に基づいた子の利益に適った方法で細かく定め、それ以外の父子交流を禁止すればよいだけである。】
つまり、申立人と相手方に協力関係がなくても、協力する必要がないように相手方が申立人と二男との交流を妨げることを禁止したり、交流方法を細かく定めることで申立人と相手方が協力して協議しなければならない必要性をなくせば、子の福祉に反する状況になることはありえない。
そして、もう何度目の指摘になるのかとうんざりするが、これについても若林慶浩は無視で、このような方法であっても具体的にどのような問題が生じるリスクがあるかについて何ら合理的理由を判示していないのだから、理由提示義務を含め、このような若林慶浩の判断が子の利益を考慮し、かつ、合理的理由を示せたまともなものであったとは言い難い。
(4) 親子交流や兄弟交流の断絶が子にもたらす不利益についての若林慶浩の無視
既に述べたように、申立人は原審から親子断絶による子への悪影響や、親子断絶が不登校やPTSDを生じさせるほどの精神的負担を被らせるものであることを主張立証していた。
さて、これらについても、もう何度目の指摘になるのかとうんざりするが若林慶浩は無視であった。これらも若林慶浩にとっては都合が悪い主張だったということだろう。しかしながら、このような親子断絶によって子が被る甚大な悪影響に鑑みれば、親子断絶を望んでいる相手方や、親子断絶の判断をした若林慶浩が、子の利益を考慮し、かつ、合理的理由を示せたまともなものであったとは言い難い。
更に、親子断絶は子が同居親を見離すようになるリスクや、引きこもりを生じさせるリスクもある。そうすると、仮に申立人と相手方に協力体制がないことで二男に何らかの負担が生じたとしても(たとえば、申立人や長男との交流を楽しんでいる二男に対して、相手方が否定的態度を取るなど)、親子断絶のほうがより子らにとって悪影響なのだから、速やかに父子交流や兄弟交流を再開することが、二男や長男といった子らの利益に適っていることは明らかである。
6 申立人と相手方が複数の訴訟を係属していることについて
若林慶浩は、申立人と相手方との間に複数の訴訟等が係属しており、その対立関係が継続していることからすれば、面会交流実施に当って申立人と相手方とが協力関係を築くことを期待することは困難としている。
(1) 複数の裁判が係属中で実施された面会交流
さて、既に述べたように、そもそも協力関係がなくても父子交流や兄弟交流は実施可能なのだから、この時点で若林慶浩の判断の誤りは明らかである。
これについて本件事件の個別具体性を見ていくと、申立人は2019年の2月から11月までの面会交流の様子を撮った動画を原審から提出していた(甲12の1から7)。この期間に申立人と相手方は、離婚訴訟や損害賠償請求訴訟をといった複数の訴訟が継続していたが、動画を見て分かるように、父子交流や兄弟交流は好ましく実施されていた。そして、これについて若林慶浩がどのように判断しているかと言えば、またもや無視である。ここまでくると、若林慶浩がまともに書面を読む能力があるかについても強い疑義が生じてしまうが、この無視が能力の問題であっても、あるいは、理性や良心の問題であっても、不適切であることは言うまでもない。要するに、複数の訴訟が係属中であっても好ましい父子交流や兄弟交流ができていたことを立証する動画は、若林慶浩にとっては不都合だったということだろう。
つまるところ、学術的観点からも、「両親間の葛藤が高いと評価される場合でも、共同養育は単独養育より子どもにとって好ましい結果」であるし、本件事件の個別具体的な事情においても、複数の訴訟が係属中であることが、父子交流や兄弟交流を困難にしていたとは認められない。
ところで、若林慶浩の「父母に協力関係がなければ面会交流は困難である」との前提は、そもそも根拠がなく、学術的知見にも反し、1事例とはいえ本件事件で複数の訴訟が係属中でも好ましい父子交流や兄弟交流ができていた事情とも矛盾している。更に、このような若林慶浩の前提は、同居親が一方的に協力する気がなければ面会交流が実施不可能にすることができるということであり、これは、同居親が子を独占支配したければ、子と別居親との交流に非寛容になって紛争を生じさせれば良いということである。本件事件がまさにこれなのだが、若林慶浩の判示を見ても、このようなことをきちんと検討していることを伺わせる言及はないので、若林慶浩は審理不尽な判断しかできていない可能性が高い。本来、父親が我が子に、兄が弟に会いに来てくれたことは二男にとって好ましい出来事であり、その好ましいはずの出来事を紛争にと変えた相手方の態度こそが、子の利益に反したものであった。
(2) 裁判手続きは親子交流や兄弟交流を断絶する合理的理由になりえないこと
既に引用したように、若林慶浩自身、家事審判を「国家の紛争解決機関」と表現している。これは他の民事訴訟等の裁判手続でも同様なのだから、申立人と相手方が複数の裁判等を係属していたとしても、申立人が「国家の紛争解決機関」を通して問題解決を図ろうとしていることに何ら違法性はない。
そもそも、裁判等で当事者がどの程度の負担を感じるか、それが父母の協力関係にどのような影響を与えるかは、個人差が大きい事項である。裁判などが1つなら良くて複数なら駄目というということにも根拠がない。かえって、60件の研究のメタ分析論文から、「両親間の葛藤が高いと評価される場合でも、共同養育は単独養育より子どもにとって好ましい結果」でることが、客観的な学術的知見である。
若林慶浩の判示は、「父母が裁判などをしていると協力できないから面会交流は無理に決まってるもん」というものだが、これを極論すれば、「父母が面会交流審判で争っていると協力できないから面会交流は無理」ということにもなる。つまり、若林慶浩の態度は裁判所における面会交流審判の必要性自体を否定したものと捉えることもできる。若林慶浩の判示の全てを見ても、このことに気づいてないようなので若林慶浩の思考の浅はかさが疑われるが、そもそも、申立人と相手方が協力できる関係であれば面会交流の審判自体が必要になっていない。
では、申立人と相手方に協力関係がなくても実施可能な面会交流の方法があるかといえば、既に述べたように、申立人が提案したどの案であっても実施可能である。
7 その他の若林慶浩による無視について
既に述べたように、裁判官のまともさをチェックするには、何を判示したかではなく、何を無視して判示していないかがより重要である。ここではまだ言及していない若林慶浩の無視についてまとめる。
(1) 親子交流に関する学術的知見
申立人は海外の文献を元にした見解を示すことで、親子交流の重要性を主張立証している。これについて証拠説明書の立証趣旨では以下のように記載した。
甲1:40もの学術論文に対するメタ分析により,別居親と少なくとも35%の時間を過ごす子どもは,感情的,行動的,心理的,幸福の尺度においてより良い結果となること。
甲2:それぞれの両親と少なくとも35%の時間を過ごす子どもは,父親や母親とより良い関係を持ち,学問的,社会的,心理的により良く,喫煙,飲酒,薬物使用の可能性が低く,不安,うつ病,ストレス関連の病気の影響を受けにくいこと。
甲3:①定期的に面会交流を継続したグループの子どもがもっとも心理的に健康であること。
②面会交流をしなかった子どもは,自己肯定感の低下,社会的不適応,抑うつなどで苦しむ傾向があること。
③情緒的安定,対人関係,自己肯定感,学業成績などの多数の側面で,共同養育のほうが単独養育よりも子どもの社会的適応が良好であること。
④両親間の葛藤が高いと評価される場合でも,共同養育は単独養育よりも子どもにとって好ましいこと。
⑤6歳以上だと平日1回夕方3-4時間プラス隔週3泊が,発達心理学の研究成果に基づく好ましい面会交流であること。
⑥子どもの親との愛着関係の発達、心身の発達ついては、外国と日本の子どもに相違はないこと。
さて、過去の裁判例を見ていくと、面会交流に関する平成25年12月13日東京高等裁判所決定において、海外の文献について言及している。少し長いが、その海外の文献に言及した部分を以下に引用する。
【抗告人は、LBP(子を連れ去られた親)の立場にあり、原審が定める面会交流の頻度や態様では父子の構築は進まず、米国等で実施された研究によれば子どもに悪影響を及ぼすとし、未成年者にはPAS(片親阻害症候群)の兆候が見られると主張している。
なるほど、平成12年ないし平成13年頃に発表されたロバート・ハウザーマンの「共同監護と単独監護における子供の適法性の比較メタ分析報告」によれば、実質上(子供がかなりの時間あるいはほぼ同等の時間をそれぞれの親と過ごす場合)・法律上(片親が主に同居監護する場合で、他方の親も子供の教育への関わりを維持し、子供に関する事項決定は双方の親で行う場合)の共同監護下にある子供の適応状況を単独監護下にある子供のそれと比較する諸研究メタ分析を行った結果、実質上あるいは法律上の共同監護を受ける子供は、単独監護下の子供よりも適応性があったが、両親のある子供との間には差異はみられなかった、総合的適応、家族関係、自尊心、心理、行動、離婚等の各項目を比較すると、共同監護下の子供の方がよりよい適応性を示したとしている。その一方で、同報告では、合衆国ではほとんどの州で1990年(平成2年)初期までに共同監護がオプションとされる制度が採用されていること、上記研究報告の前提として研究対象の選出に偏向がある可能性を否定できないこと、共同監護方式を選んだ両親は、離婚前あるいは離婚当時から良好な関係を維持できていた元夫婦であるところ、共同監護家庭の両親の対立度が単独監護家庭のそれよりも低いことから、両親の離婚前、離婚時の対立度をコントロールすることが今後の研究の課題であろうとされている。
これに対して、わが国では、離婚時の子供の親権者については単独親権制度が採用されており、欧米諸国とはそもそも法制度が異なること、また、欧米諸国では、子供に対する一般的な養育方針ないし親子関係として、早い場合には乳幼児の頃から両親とは寝室を別にするなど、幼少時から子供が親から離れ、親も子供から離れて、子供が早期に自己を確立することを前提として養育がなされるのであって、現在のわが国における子供に対する一般的な養育方針ないし親子関係とは異なっているのが実情であり、上記報告によっても、共同監護方式を採用している元夫婦は、離婚前ないし離婚時から、夫婦間での対立の度合いが低かったとされているのであって、そのような前提を抜きに論じることは相当ではない。
そして、これまで述べてきた本件における個別事情を考慮すると、上記の外国文献等による研究報告の結果を直ちに当てはめて考えることは相当ではないというべきであるから、これを採用することはできない。】
まず、少なくとも提出された証拠にどのような判断をしたかを理由ととも示している点で、この裁判例は若林慶浩よりはよほどましである。そして、このような裁判例があるということは、裁判官が提出された証拠(この場合は親子交流に関する学術的知見)に対して判断を示すことができるということなのだから、この意味においても若林慶浩の判断の杜撰さや、そこから推測できる若林慶浩の人格的問題も顕著というほかない。
なお、この裁判例が親子交流に関する学術的知見に言及していることは評価するとしても、その内容は以下の理由からまともとは言い難い。
この裁判例の裁判官らは須藤典明、尾立美子、島村典男であるが、まず、須藤典明、尾立美子、島村典男は、わが国が離婚後単独親権制度で、欧米諸国と法制度が違うとしている。
「で?」としか言いようがないが、須藤典明、尾立美子、島村典男は法制度が異なれば子に必要な親子交流も異なるとする根拠について、何ら言及していない。つまり、法制度が異なることは、上記の文献での知見が日本においても子の最善の利益に適う方法であることを否定する合理的理由になっていない。ここで思考を放棄した裁判官盲信教信者だと、
「須藤典明様、尾立美子様、島村典男様の3柱の裁判官様方は、誤りを犯すことはありえない絶対不可侵の人間を超越したパーフェクト超人であり現人神でもあるが、日本と欧米諸国で法制度が違うから必要な親子交流も違うといった神勅は下々の民に下賜されておられない」
といったいちゃもんをつけるかもしれないが、仮に須藤典明、尾立美子、島村典男が子に必要な親子交流と法制度が無関係だと考えているとしたら、この文脈で法制度について言及したことと矛盾する。須藤典明、尾立美子、島村典男は海外の文献に関連して法制度について述べているのだから、須藤典明、尾立美子、島村典男が日本と欧米諸国の法制度が違うことを根拠にこの文献が日本では当てはまらないと判断したことは明らかである。しかし、その根拠が合理的根拠になりえていないことは、既に述べたとおりである。
また、須藤典明、尾立美子、島村典男は、欧米諸国では一般的に早い場合には乳幼児の頃から両親とは寝室を別にするなど、幼少時から子供が親から離れ、親も子供から離れて、子供が早期に自己を確立することを前提として養育がなされるのであって、現在のわが国における子供に対する一般的な養育方針ないし親子関係とは異なっているのが実情としている。
これも「で?」としか言いようがないが、須藤典明、尾立美子、島村典男は上記のような日本と欧米諸国の養育方針や親子関係の違いによって、子に必要な親子交流にも違いが生じているとする根拠について、何ら言及していない。つまり、養育方針や親子関係が異なることは、上記の文献での知見が日本においても子の最善の利益に適う方法であることを否定する合理的理由になっていない。
また、須藤典明、尾立美子、島村典男は、上記文献では共同監護方式を採用している元夫婦は、離婚前ないし離婚時から、夫婦間での対立の度合いが低かったとされているのであって、そのような前提を抜きに論じることは相当ではないとしている。
なるほど、曲解によってどのような誤った結論を導くことができるかという見本にもなりそうな文章だが、上記文献を素直に読めば、共同監護だと離婚前や離婚時に父母の対立の度合いは低くなるということである。そうであれば、この裁判例では文献で子の利益に適っているとされている子と別居親との交流が実施されていなかったのだから、上記文献を前提に論じれば、子と別居親との交流を拡充することが父母の対立の度合いを低くするとの結論に至る。
それにもかかわらず、須藤典明、尾立美子、島村典男は、父母が対立しているからこの文献を当てはめて考えることはできないとしているのだから、見当違いも甚だしい。この文献は、子供がかなりの時間あるいはほぼ同等の時間をそれぞれの親と過ごす等で、父母の対立の度合いが低くなるとの内容なのだから、これを換言すれば、子供がかなりの時間あるいはほぼ同等の時間をそれぞれの親と過ごす等をしなければ、父母の対立の度合いが高くなるということである。そして、このような親子交流ができていなかったこの裁判例において、父母の対立の度合いが高くなっていることは、文献どおりの結果ということになる。そのことが理解できていない須藤典明、尾立美子、島村典男の判断が子の利益に適ったものであったとは言い難い。繰り返すが、上記文献を前提にすれば、子供がかなりの時間あるいはほぼ同等の時間をそれぞれの親と過ごすようにすることで、父母の対立の度合いを低くすることができるのである。
さて、本件事件に戻るが、上記の文献と申立人が提出した文献は別のものだが、結論は類似していると言える。更に、申立人が提出した文献では、
【両親間の葛藤が高いと評価される場合でも,共同養育は単独養育よりも子どもにとって好ましいこと】、
【子どもの親との愛着関係の発達、心身の発達ついては、外国と日本の子どもに相違はないこと】
も述べられているため、これらを立証趣旨であることを証拠説明書に明記していた。そして、このような申立人が提出した文献についてなんら言及していない、事実上、「恣意的判断をするのに都合が悪いが、合理的理由をもって排斥できない当事者の主張であるため、無視やすり替えなどの悪質で姑息な手段によって恣意的判断を強行することを選択した」ことを強く疑わせる若林慶浩の判断が子の利益を考慮し、かつ、合理的理由を示せたまともなものであったとは言い難い。
(2) 相手方の精神疾患
相手方には以前から精神疾患があるが,親の精神疾患は子に降りかかる恐れのある危険要因のあらゆる可能性のなかで,もっとも強い精神的な影響を及ぼすもののひとつである(H.ルドルフシャファー「子どもの養育に心理学がいえること」新曜社、2001)。事実,二男の発達障害や学校での不適応等も,相手方の精神疾患に二男が強い影響を受けた結果であることは否定できない。そもそも親子交流の断絶自体が子の甚大な悪影響を及ぼすところ、相手方に精神疾患があることは、更に二男の健全な成長に重大なリスクを生じさせている。これも親子断絶の恣意的判断をしたい若林慶浩にとっては都合が悪く主張立証だったのだろうが、このようなリスクを無視して子の利益を最優先に考慮した判断をすることができないのは言うまでもない。そして、このようなリスクを軽減する意味においても、精神疾患等はない申立人との交流が二男の利益に適うのは明らかである。
(3) 二男の発達障害の疑いや学校不適応
上記でも触れたことであるが、二男は発達障害の疑いや、学校での不適応を生じさせている。それに対して、申立人が育てている長男は、そのような問題を一切生じさせていない。発達障害の疑いは、不適切な養育によって後天的に発達障害と類似した症状を生じさせることもあることから、相手方の不適切な養育が二男に悪影響を及ぼしている可能性も否定できない。このことは、相手方が父子交流や兄弟交流を断絶する態度であることや、相手方に精神疾患があることからも、よりリスクが高くなっている。このことも親子断絶の恣意的判断をしたい若林慶浩にとっては都合が悪く主張立証だったのだろうが、このようなリスクを無視して子の利益を最優先に考慮した判断をすることができないのは言うまでもない。そして、このようなリスクを軽減する意味においても、精神疾患等がない申立人との交流が二男の利益に適うのは明らかである。
(4) 兄弟交流が子らにもたらす利益
相手方の父子交流や兄弟交流の断絶により、申立人が育てている長男も二男と交流できない日々が続いている。しかしきょうだい関係は,パーソナリティ,社会性と認知的スキル,自己概念,価値観,外の世界から保護されている感覚,といったものに影響を与える。また,きょうだいは,価値観のモデリング,スキルを教えること,傷つきからの保護,そしてしばしばきょうだいの最初の友達として振る舞うことなど,家族の中でさまざまな機能を担っている(甲7)。そうすると、ただでさえ二男は発達障害の疑いや学校不適応を生じさせているのだから、このような二男に対して、発達障害の疑いや学校不適応等が一切ない長男が関わることは、二男に肯定的な影響が期待できる。このことも親子断絶の恣意的判断をしたい若林慶浩にとっては都合が悪く主張立証だったのだろうが、このような兄弟関係の効果を無視して子の利益を最優先に考慮した判断をすることができないのは言うまでもない。そして、このような効果を期待する意味においても、面会交流を認めることで兄弟交流を可能とすることが二男の利益に適うのは明らかである。
(5) 調査官調査の必要性
若林慶浩は、申立人が必要性を主張したにもかかわらず二男の現在の確認するための調査官調査を実施せず、「前件基礎事情に事情変更が認められない以上、未成年者に対する調査等を行う必要性もない。」と判示している。しかしながら我が国も締結している児童の権利に関する条約では以下のように定められている。
【第12条
1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。】
このように、子に意見を表明する機会を設けることは、法によって要請されている事項である。更に、そもそも父子交流や兄弟交流の断絶自体が子らにとっては著しい悪影響であり、相手方に精神疾患があること、二男に発達障害の疑いや学校不適応があったことからすれば、二男の現在の様子を慎重に確認した上で父子交流や兄弟交流を判断すべきであった。少なくとも調査官調査を実施していない状況において、二男が父親や兄との交流を望んでいるかの是非や、二男にとって父親や兄との交流が二男の利益を増進するかの是非を判断する材料となる情報が不足していると言わざるを得ない。
また、2018年には5歳女児が虐待死する目黒女児虐待事件が起こっている。この事件ではいろいろな経緯があるが少なくとも2017年8月に本児のあざを医療機関が見つけて児童相談所に通報しているが、一時保護などはされておらず、2018年2月に児童相談所職員が家庭訪問するが本児に会えず、そして2018年3月に本児は虐待の末に亡くなっている。
何が言いたいかといえば、仮にある時点で緊急性がないと判断されたとしても、それが絶対に間違っていないとは言えないし、その後に状況が変わることもあるということである。
二男についても、ただでさえ相手方の監護状況において二男は発達障害の疑いや学校不適応を生じさせており、相手方に精神疾患があることも二男の健全な成長にとっては懸念材料であり、相手方が二男と申立人との父子交流を断絶させていることは二男に対する心理的虐待でもある。
そうすると、二男の“現時点”での様子や心情は本件事件で考慮すべきものなのだから、若林慶浩が調査官調査を実施しなかったことは子の利益を最優先に考慮したものであるとは到底言えないし、よってそのような調査官調査の不実施がまともな判断であったとも到底言い難い。
8 福岡高裁等の判断の違法性
以前に確定した審判は、二男が成人して相手方の二男に対する親権や監護権が消失した後にも効力が及ぶ内容になっている。しかしながら、二男が成人した後も申立人が二男と交流するのに相手方との協議や裁判所の許可を必要としなければならないとする法的根拠は存在しない。そうすると、以前に確定した審判が条件成就までの間ではあっても、事実上、その条件成就までは無期限に効力を持つ決定により、相手方の二男に対する親権や監護権が消失する二男が成人した後にも、申立人が二男と交流するのに相手方との協議成立か裁判所の許可が必要だとした判断は、法的根拠なく父子交流を不当に制限する違法なものであった。
そもそも、面会交流の法的根拠である民法766条各項にしても、「子(未成年者)」を対象にしたものである。仮に民法766条の「子」が未成年者ではなく血縁上の関係を意味するものだとしたら、子が成人した後も父母が離婚するときには親権者を決めなければならないといった矛盾が生じることになるのだから、民法766条の「子」が未成年者を意味していることは明らかである。そのため、二男が成人して未成年者が存在しなくなっても効力が継続する決定をした以前に確定した審判は、民法766条各項が面会交流について定めた法律効果の範囲を明らかに逸脱した違法なものであった。
当然、このような違法な判断は速やかに変更されなければならない。
第3 まともな司法に必要なこと
裁判官らが国民からの信頼を得るためには、以下のことが必要だろう。
(1) 一次資料としての当事者の主張立証を踏まえての検討
司法が公正でまともな制度であるためには、個々の裁判官がまともな判示をしているかの検討を絶えずしていく必要があるだろう。
ここで大事なのは、裁判官が恣意的に取捨選択した情報のみを対象としないことだ。ここまで本書を見てきたなら分かるように、裁判官が当事者の主張立証を適切に判示に含めているとは限らない。都合が悪い裁判当事者の主張立証を無視して、存在しなかったかのような判示をしている可能性があるのだ。裁判官の判示だけを資料として判例研究することは、その時点で裁判官の姑息な手口に乗っかかっていることになる。そのため、裁判官が取捨選択していない一次資料としての当事者の主張立証と裁判官の判断を比較し、そのまともさを検討していく必要があるだろう。
(2) 裁判官による取捨選択の有無の検討
では具体的なチェック方法であるが、まずは裁判官が当事者の主張立証に対して、何に触れ、何を無視したかである。触れている場合はその内容を検証する必要があるが、それ以上に無視したもののほうに注意が必要である。なぜなら無視の場合、「裁判官が恣意的判断をするため、説得力をもって潰すことができなかった反対証拠を無視することで恣意的判断を強行した」との疑義が強く生じるからである。
(3) 理由の有無の検討
裁判官が当事者の主張立証に言及していたとしても、ただ当事者の主張として触れただけで、その後は無視し、その主張立証を採用しなかった理由が何ら述べられていないこともある。当然、そのような裁判官の判示は姑息な誤魔化しであり、そこに検証可能性や合理性は皆無で、まともな理由提示がされているとは言い難い。
(4) 理由の合理性の検討
当事者の主張立証が、無視されていないか、言及されていても採用不採用の理由は示されているかをクリアしたら、理由の合理性が検討されなければならない。それが屁理屈なものだったり、論理に飛躍があったりする場合は、当然、そのような決定は理由と結果が矛盾したものとして取り消されなければならない。
(5) 差し戻し
裁判官が当事者の主張立証を無視していたり、判断の合理性などの理由提示に欠如があったりした場合、それらを理由にしての上訴は自判ではなく差し戻しにしなければならない。これは上級審での不意打ちにより当事者が不利益を被ることを回避するためだ。もし一審で審理不尽や合理的理由の欠如があり、二審でもちょっと論点をずらしながらも新たな審理不尽や合理的理由の欠如があった場合、法律審である最高裁での救済が困難になるからである。
(6) 教育
裁判官の判示が、当事者に上訴の便宜を与える、無視や誤魔化しがないものになっているかについて、裁判官教育を徹底する必要があるだろう。
(7) 対比表
現在の判示は文章でつらつらを書かれていることで、どれほど当事者の主張立証を無視してもても、それなりに見える文体にすることが可能となっている。そのような裁判官の姑息さを防ぐには、「当事者の主張立証」を一つ一つ分けて書き、それとするに比較できるように「その主張立証に対する裁判官の判断」と「その判断理由」を記載することで、裁判官の誤魔化しを軽減できることができる。仮に裁判官の故意による誤魔化しでなくても、見落としの防止にもなるのだから、不当な恣意的判断をしたい裁判官以外にとっては、反対する理由はないはずである。
(8) まともでない裁判官の再任禁止
裁判官は10年ごとに再任する制度になっているが、当事者の主張を無視したり、判断のまともな合理的理由を説明できていない裁判官は、判断の慎重さと公正さを担保してその恣意を抑制し、不服申立てに便宜を与える基本的能力が欠如している。そのような裁判官は再任すべきではないし、能力の欠如が明らかになった裁判官は、その時点で速やかに事件を担当することからはずすべきである。
(9) 家事事件での裁判員制度
家事事件にも市民参加型の裁判員制度にすれば、主張立証の無視といったことは起こりにくいだろうし、裁判官の鬼ごっこなどといった異常な態度の抑止力にもなるだろう。
第4 おわりに
2022年10月、神戸市連続児童殺傷事件や佐世保小6女児同級生殺害事件などの重大少年事件で、裁判所が事件記録を廃棄していたことが報道された。これについて熊本大学法学部の岡田行雄教授は、「一連の記録廃棄は、裁判所がいかに検証を嫌がる組織かということを白日の下にさらした」と批判している(熊本日日新聞2022年11月1日)。
このような裁判官らの甘えを放置してきたことが、裁判官らの鬼ごっこや魔女っ子化などにつながっていると思わずにはいられない。それによって不利益を被ることになるのは国民なのだから、裁判官らのやり逃げを許さないように、裁判官らのまともさを検証していくことが、公正な裁判を担保していくためには必要だろう。
なお、本書は裁判官の判断に対する検証を試みたものであるが、本書に対して批判を試みる者も出てくるかもしれない。しかしその場合、本書のように根拠を明らかにしたものでなければ、単なる中傷にすぎないものとなる。たとえば、若林慶浩が判示していないことを持ち出しても、若林慶浩が本当にそう思って判断したかの検証は不可能である。つまり、そのような批判は後付けで考え出されたもので、若林慶浩がそう考えてはいなかった可能性を否定する根拠がない以上、根拠のない妄想による批判は論ずるに値しない。そもそも、若林慶浩が判示していないことを持ち出さないと批判できないということ自体が、若林慶浩の理由提示が不十分なものであったことを証明することになるだろう。
付録1 若林慶浩の判示











付録2 申立人の主張
家事審判申立書
(面会交流)
令和4年5月10日
熊本家庭裁判所 御中
申立人 〒861-8035
************************(送達場所)
電 話 **************
*******
相手方 住所不明 *******
未成年者(二男) *******(相手方と同居)
平成**年**月**日生(10歳)
申し立ての趣旨
相手方は,申立人と未成年者に,月2回の宿泊,4日以上の長期休暇中のうち半分の宿泊をさせよと。またそれ以外にも,相手方は申立人と未成年者との面会を妨害してはならない。
との審判を求める。
申し立ての理由
1 二男と申立人との交流が絶たれていること
申立人と相手方は,平成19年3月15日に婚姻し,同居生活を送っていたが,平成24年10月29日に,相手方は一方的に二男である未成年者を連れ去って不同意別居を開始し,その後に離婚している。
相手方は2020年2月を最後に、申立人と二男との交流を拒絶しており、これは申立人が監護する長男が二男との交流を絶たれていることでもあり、また、二男が申立人方祖父母からの愛情を受ける機会を喪失していることでもある。このような状況は二男の利益に反しており、また、兄弟交流の断絶は長男の利益にも反している。
そのため、本件申し立ての趣旨を速やかに認めることで、早期に二男と申立人、長男、申立人方祖父母との交流が再開されなければならない。
2 相手方は子の利益を考慮する能力や資質に欠けていること
相手方が二男に対して、父親や兄や父方祖父母との交流を断絶させている挙に及んでいることは、相手方が子の利益を考慮する能力や資質に欠けていることを示している。
そのため、相手方が任意に二男と申立人の交流に配慮することは期待できないのだから、本件申し立ての趣旨を速やかに認めることで、早期に二男と申立人、長男、申立人方祖父母との交流が再開されなければならない。
3 児童の権利に関する条約について
そもそも、児童の権利に関する条約9条において,「子供がその父母から,その父母の意思に反し,切り離されてはならない。」と規定されている。そして,申立人と二男との交流が二男の利益に反していると言える的確な根拠はない。かえって,二男が申立人や長男との交流を楽しんだり,小学校の入学式に参列できなかった二男が申立人の関わりで体育館に入れるようになったりしていることから,申立人との交流は二男の利益を増進させており,今後も父子交流による二男の利益の増進が期待できる。
4 支援措置について
相手方は申立人をDV等の加害者として、「ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者保護のための住民基本台帳事務における支援措置」(以下「支援措置」という。)の申出をすることで、申立人が二男の戸籍謄本等を取得できないようにしている。
しかしながら、名古屋高等裁判所令和3年4月22日判決は支援措置適用要件に該当しない支援措置の申出を違法なものとして損害賠償請求を認めており、本件事件も同様、申立人に支援措置適用要件に該当する行為はない。
右裁判例は支援措置適用要件として以下を判示している。
(ア) 申出者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者であること
(イ) 申出者が、加害者からの更なる暴力により生命又は身体に危害を受けるおそれがあること
(ウ) 加害者が、被害者の住所を探索する目的で、住民基本台帳の閲覧等を行うおそれがあること
当然、申立人は上記の支援措置適用要件に該当する行為をしていないのだから、申立人は二男の戸籍謄本等にアクセスする権利を、相手方から違法に阻害されていることになる。
なお、右裁判例は以下のようにも判示している。
「支援措置が実施されることにより、被控訴人は、市町村において、支援措置上のDVの加害者であって、その更なる暴力により被害者が生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものとして扱われ、そのことを被控訴人自身の行為によっては容易に是正することができない状態に置かれていることになり、被控訴人は、自己に関する誤った情報を是正することができないことにより人格的利益を害されたものと認められる。」。
「支援措置が加害者と扱われる者に一定の不利益を与えるものであることが否定できない以上、DV被害者が主観的に恐怖心を有するからといって、客観的に支援の必要性の存在が認められるものと解することはできない。」。
つまり、相手方が申立人を支援措置における加害者としたことは、申立人の人格的利益を害する行為であった。また、相手方が申立人に対して気に入らないことがあったり、被害妄想を増大させることで主観的な恐怖心を有したりしたとしても、支援措置適用要件に該当していない以上、相手方が申立人を支援措置における加害者としたことは違法なものであった。
そうすると、相手方は支援措置を悪用することでも申立人と二男との交流を絶っており、このことは当然に父親からの愛情を受ける機会を奪われた二男の利益を損ねる行為である。このことからも、相手方が子の利益に対して配慮する能力や資質に欠けていることが分かる。
5 二男の心情について
相手方は以前,二男が申立人との面会交流を嫌がっていると述べていたが,申立人と交流していた二男の様子からは,面会交流を嫌がっているとは認められない。そうすると,二男は相手方の不適切な言動のために,相手方に忖度して申立人との面会交流を嫌がる態度を余儀なくされていることになる。このような状況は精神的虐待であり,二男が相手方からこのような虐待を受け続けることが,二男の利益に反するのは明らかなのだから,二男は速やかに申立人に監護されるべきであるが,本件事件の申立ての趣旨は面会交流であるので、これを再開、拡充し,二男が被っている相手方からの虐待を最小限にし,申立人からの心理ケアを十分に受けられるようにするべきである。
よって,申立ての趣旨どおりの審判を求める。
6 その他
申立人は熊本東区役所(〒862-0902 熊本県熊本市東区東本町16−30)において,未成年者の戸籍謄本の交付請求をしても拒否されたことから,相手方及び未成年者の住所が不明である。そのため,裁判所から熊本市東区役所に対して,家事事件手続法第62条に基づく相手方及び未成年者の住所に関する調査嘱託を求める。
以 上
事件番号 令和4年(家)237号
申立人 *******
相手方 *******
未成年者(二男) *******
主張書面
令和4年8月11日
熊本家庭裁判所 御中
申立人 *******
第1 申立人の主張
1 調査官調査について
本件事件で担当裁判官である若林慶浩は、申立人の申立書と相手方の答弁書が提出された後、審理集結日(令和4年8月19日)と審判日(令和4年9月16日)を定めている。このことは、若林慶浩が期日を入れて家裁に申立人や相手方を呼ぶことことなく(これがあっても代理人だけが参加することもあるだろうが)、調査官調査をするつもりがないことを表している。申立人は念のため、令和4年8月10日に電話して中原誠書記官に確認しても、この日程での予定なので調査官調査はないと明言された。
さて、この若林慶浩の判断がまともかということであるが、我が国も締結している児童の権利に関する条約では以下のように定められている。
第12条
1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
この規定では児童の年齢や成熟度を考慮するとあるが、二男は以前にも調査官調査をされたことがあるため、より年齢が上がっている二男に対して、「自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与え」ることを若林慶浩が否定していることは、合理性に欠けるというほかない。
そもそも、なぜ本件事件で調査官調査が必要か。まずは上記したように裁判官が法に則った適正手続による裁判をするためである。上記した児童の権利に関する条約12条は司法や行政を対象にしていることから、裁判官の不当な審判指揮によって児童の権利が不当に蔑ろにされることがないように、裁判官による審判指揮に拘束を課したものと言える。
次に、適正な情報がなければ適正な判断をすることも不可能だからである。そのため、この程度のことも若林慶浩は知らないで判事をしているのかと、我が国の判事の選抜制度や教育制度には暗然たる思いになるが、例えば二男が相手方から虐待を受けていた場合はどうであろうか。これが可能性の1つにすぎないとしても、その可能性を否定する確認自体を若林慶浩は否定しているのだから、それが不適切であるのは言うまでもない。自動車保険が例えとして分かりやすいだろうが、調査官調査をしないというのは、事故る可能性が高いとはいえないから自動車保険に入るのは無駄というのと同じ発想で、それが社会通念に反したものだということを若林慶浩は理解できないのかな?
また、二男は以前から学校での授業や行事に参加しないといった不適応を起こしており、それが継続している場合はどうであろうか。というか、案の定、相手方の不適切な対応のために二男の不適応が長期化しているようだが。二男にはこのような学校不適応があるのだから、本来、面会交流よりむしろ速やかな子の引き渡しで親権者を変更するのが適切であろうが、その場合の二男の負担を軽減するという意味でも、二男が父親である申立人や、兄であり申立人が監護している長男等と適切な関係であるのが好ましいのだから、そのための面会交流であり、その面会交流のための調査官調査である。それに申立人が監護する長男には二男のような学校不適応は一切ないのだから、その申立人の監護実績を鑑みても申立人との交流が二男に肯定的に作用すると解するのが合理的というものでしょ? ここ、若林慶浩は無視しないように。父子交流や兄弟交流の利点を不当に無視したり軽視したりして、父子交流や兄弟交流を断絶するための口実を不当に過大評価していたら、まともな判断にならないのは当然でしょ?
また、二男が父である申立人や、兄である長男との交流を求めている場合はどうであろうか。このような二男の意思を蔑ろにすることが子の利益に反するのは明らかである。ちなみに、申立人が監護する長男は二男との交流を求めており、このような長男の意思を蔑ろにすることが子の利益に反するのも明らかである。若林慶浩が長男の心情や長男の兄弟交流で得られる利益についてきちんとまともに考慮できているか、それとも相変わらず都合が悪いことは無視するということで自らの人格や能力についての自己紹介をしてくるかも、本件事件で問われているといえるだろう。
では、二男が申立人や長男との交流を求めていない場合はどうであろうか。その場合、二男は申立人や長男との関係が良好であったのだから、相手方がそれらの関係を断絶させ、二男に一方的かつ不適切な情報を伝えることで、二男に申立人や長男に対するマイナスのイメージを植え付けた相手方が二男の親権者として著しく不適切であるのは明らかであり、この場合も、最善の改善策は二男の親権者を変更することであるが、面会交流によって相手方による二男に対する一方的な独占支配による影響力を弱めることが、二男の利益に適うことになる。
これらを総合考慮すれば、児童の権利に関する条約12条に違反し、敢えて調査官調査を実施しないことが明らかに子の利益に適っているといえる合理的理由はない。
また、相手方は面会交流を禁止する以前の審判が確定して1年ほどしか経っていないとしているが、まず、その審判がまともなものであったかが問題であり、それについては後に詳述しているので、若林慶浩は明確に指摘されてもなお同じ過ちを繰り返すといったくずな態度にならないように。ああ、くずな裁判官だと前回の審判から状況に変化が認められないといったキングオブくずな言い訳をすることも考えられるかな? まあこれだけくずと書いていても敢えてくずになりたがる開き直った判事だと救いようがないが、そもそも前の審判が誤っていればそれを維持することが長男や二男の利益違反することは明らかでしょ? このくらい理解できるよね? それとも子の利益よりも、前の審判に忖度するほうを優先するのかな? その場合、子の利益よりも前の審判への忖度を優先するとの法文上の根拠があるのかを明らかにしようね。それができずに敢えてくずな態度を取るのかも、本件事件でチェックしなければならない点だろう。
ちなみに、「裁判官の誤った判断が確定する」⇒「次の裁判官は思考放棄して当事者が主張した前の審判の誤りを検討しないで、盲目的に前の審判が正しかったことを前提にした判断をする」となった場合、公正な審判ができると思っているのか、
本件事件でどのような判断をするかで示そうね。
それに、1年ほどしか経っていないならば状況に変化がないと言い切れる具体的根拠はないでしょ? むしろそれが半年でも、もっと短く数か月でも状況が絶対に変わっていないと言いきれる根拠はないはずだが? 更に、仮に期間を問題にするとしても、まずはどの程度の期間であれば絶対に状況に変化が生じないといえるのかの合理的説明をしたうえで、その起点とするのは前回の調査官調査が実施された日とするべきである。抗告審とか最高裁とかで、長ければ数年もかかるといったこともありえるのだから、調査官調査から数年が経っていても審判の確定した日を起点として期間を算出するのは、明らかに合理性に欠けており、それでも若林慶浩が合理性があるというのなら、きちんと理由提示義務を果たし、まともに理由を説明できないのなら自らの判断のほうが誤っていると気づくくらいの知性は持とうね?
つまり本件事件は、児童の権利に関する条約12条に対する違法や、調査官調査の必要性、それに期間の算出方法の問題を指摘された若林慶浩が、それでも敢えて二男に「自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与え」ないとの違法に固執するのか、調査官調査のメリットよりもデメリットのほうが明らかに上回っていると言える合理的根拠を説明できるのかが問われている。このことは、若林慶浩個人の資質の問題でもあるが、裁判が法に則った公正性が担保されているのかという問題でもある。
2 児童がその父母の意思に反してその父母から分離されない権利について
児童の権利に関する条約は以下のようにも規定している。
第9条
1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。
2 すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。
3 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。
まず、この2項でも関係当事者が自己の意見を述べる機会を有するとされており、このことからも二男に対する調査官調査による意見を述べる機会の保障が我が国の法律上求められていることになる。
また、3項では児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重するように規定されている。なぜこのように規定されているのでしょうか? 当然、子が親と父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持することが子の利益に適うからですよ。だから本件事件でも法に拘束される裁判官は、上記法に則った判断をする必要がある。
なお、本件事件において父子交流や兄弟交流をすることは二男の最善の利益に適っており、むしろこれらの関係が断絶されていることで二男の利益を害されているのだが、このことは後述していく。
とりあえず、法文上、子の最善の利益は親子の人的な関係及び直接の接触が維持されることなのだから、その関係を維持することでのメリットを不当に軽んじ、その関係を断絶する口実ばかりを不当に重視するといったことがないようにしましょうね。ここも若林慶浩の判事としての資質が表れるところですよ。
2 従前の審判等の問題点
(1) 加害者の主張を検討せずに無視することに法的根拠がないことについて
二男と申立人との面会交流を禁止した福岡高裁は以下のように判示している。
「抗告人は自らの言動や態度が面会交流に関する紛争を招いていることを認識することなく、抗告人の申し立てる面会交流が認められれば、当時者間の紛争がなくなるなどと主張するものであり、抗告の主張を採用する余地はない。」
さて、福岡高裁は申立人が紛争を招いたとして、事実上、申立人を加害者扱いし、その紛争を招いた加害者という属性のみを理由に申立人の主張を検討しないという挙に出ている。あれ? 裁判所って加害者扱いした者の主張は無視するんだっけ? 刑事事件でもそうなの? それとも家事審判では加害者扱いした者の主張を無視して良いという法的根拠でもあるの?
さ、「加害者扱いした者の主張は無視することが正しい裁判だ」ということを本申立でも採用するのか、若林慶浩の判断を明確に示そうね。申立人としては、そのような裁判官らの態度に裁判の公正性は皆無に思われるが。それとも、加害者扱いした者に対しては公正な裁判をする必要がないということかな? そういえば熊本県は冤罪事件として名高い「免田事件」があった地だが、この事件って再審請求によって無罪判決になっているんだよね。あれ? 加害者として一度は確定したのに、なんで加害者の主張を無視していないの? それとも、再審請求は加害者の主張を無視しないが、家事審判は加害者の主張を無視しても良いという法的根拠でもあるのかな? それとも免田事件の再審請求時からは法改正があって、現行法では裁判で加害者の主張は無視して良いというふうにでもなったの?
これは裁判の公正性の根幹にも関わる問題であるのだから、「加害者扱いした者の主張は無視することが正しい裁判だ」と言えるのか、その法的根拠はあるのか、逃げずにきちんと答えましょう。福岡高裁等の判断がまともであるのかはこのこと次第で大きく左右されるのだから。
そして、「加害者扱いした者の主張は無視することが正しい裁判だ」とすることに法的根拠がないのなら、高裁の言い方を真似て言えば、
「福岡高裁は、加害者であるとの属性のみを理由として、抗告人の主張を採用する余地はないなどとしているものであり、福岡高裁の主張を採用する余地はない。」
となるね。
だから、仮に本件事件において福岡高裁の決定に言及するのであれば、当然にその決定が誤りがないものでなければならないのだから、その担保として「加害者扱いした者の主張は無視することが正しい裁判だ」とすることが正当であるのか、その場合の法的根拠はあるのか、きちんと向き合って判示しましょう。
なお、法文上、加害者扱いした者の主張は無視してもかまわないとする規定は存在しない。しかしながら、子の利益を最優先に考慮しなければならないとする規定は存在する(民法766条1項)。そして、後述するように、福岡高裁が申立人を加害者とする属性のみを理由に検討を怠った申立人の主張の中に、子の利益に適った面会交流の実施方法はあった。
そうすると、父子交流や兄弟交流の断絶を優先した福岡高裁等は、申立人の主張が子の利益に適っていたためにこれを合理的理由をもって排斥することができず、そのために申立人を加害者扱いすることで申立人の主張を検討しない口実にしたということなのだろう。
(2) 相手方の父子交流の阻害が二男の利益に反していたことについて
そもそも、子と別居親との面会交流は同居親がまともであれば円滑に実施できるものであり、その実施に必ずしも審判決定を必要とするものではない。つまり、面会交流で紛争が生じるのは、同居親が面会交流を駆け引きに利用しようとしたり、子と別居親との交流を不必要に制限しようとするからである。
ちなみに、別居親が原因で面会交流に関する紛争が生じる場合もあるだろうが、それは別居親の子に対する関わりが明らかに不適切で子に悪影響を及ぼしていたり、別居親が面会交流以外の目的のために面会交流を利用している場合(たとえば、同居親に接触すること目的にしている場合等)等が考えられるが、本件事件にそのような事情はない。
また、仮に相手方が原告が監護する長男と交流したいならば、審判などを持ち出すまでもなく、原告は柔軟に対応するつもりであり、同様の態度を相手方もすることが子らの利益に反するといった特段の事情は認められない。そうすると、仮に相手方が柔軟な父子交流や兄弟交流に配慮をできていたとしたら、二男から相手方に対するの印象は、「お母さんは僕とお父さんのことや、僕とお兄ちゃんのことも大事にしてくれた。だから僕はお父さんやお兄ちゃんともいっぱい良い思い出ができたし、お兄ちゃんみたいにスポーツや勉強も上手になりたいと思えた。」といったものだったろう。しかしながら、相手方の態度は二男に適切な監護をするチャンスを自ら潰したものであった。そして、二男が相手方の行為の実態を知れば、「お父さんやお兄ちゃんが僕のために会いに来てくれても、お母さんはそれを邪魔したし、お父さんやお兄ちゃんが僕のために会いに来てくれたことを逆に利用して、僕からお父さんやお兄ちゃんを引き離した。お兄ちゃんはお父さんと一緒に暮らしていろんな経験をしたり、いろんなことに頑張ったりしていたのに、お母さんのせいで僕はお父さんに可愛がってもらえなくて、僕の人生からお兄ちゃんも消えてしまった」ということになる。このような相手方の態度が二男の利益に反していることは明らかである。なお、相手方は警察を呼ぶといった挙にも及んでいるが、警察が原告を逮捕していないことからも、申立人が法令に抵触する行為をしていなかったことが分かる。
その意味において、そもそも二男の利益に適った父子交流や兄弟交流に配慮する資質に欠けた相手方が二男を監護していること自体が二男の利益に反しており、そのことが紛争の根本的な原因だと言えるし、このような相手方を二男の親権者に指定した裁判所の判断も、紛争の発生に加担したと言える。子と別居親との交流に寛容な親と親権者(監護権者)として優先することを、フレンドリー・ペアレント・ルールと言うが、本件事件はそれに反する裁判所の判断がいかに紛争を生じさせるかと実証したものと言えるだろう。
さて、このことに若林慶浩がガキのように「あーあー聞こえない」といった態度を取るかにも、若林慶浩の判事としての資質が表れることになるだろう。
とりあえず、本件事件は子の引き渡しではなく面会交流であるが、上記の理由から申立人を紛争を生じさせた加害者扱いするのは誤りであるし、父子交流や兄弟交流を断絶されている二男の利益に鑑みても、速やかに父子や兄弟の定期的な人的な関係及び直接の接触が回復されなければならない。
(3) 子と別居親との交流は子の利益の増進になることについて
40もの研究結果を包括的に整理したメタ分析の結果,それぞれの両親と少なくとも35%の時間を過ごす子は,父親や母親とより良い関係を持ち,学問的,社会的,心理的により良く,喫煙,飲酒,薬物使用の可能性が低く,不安,うつ病,ストレス関連の病気の影響を受けにくいことが分かっている(甲1~3)。そうすると、子と別居親との交流を断絶することは統計的に明ら、上記に関するリスクを高め、子の利益に反することになり、このことも当然に申立人は熊本家裁や福岡高裁で主張立証している。ちなみに、両親が高葛藤状態であっても子は両親との交流を維持したほうが子の利益に適うことも明らかになっている。
さて、これらに福岡高裁等の裁判官らはどんな態度だったか。なんと、裁判官らは無視という挙に出ているんですねぇ。「都合が悪いが合理的理由をもって排斥できない当事者の主張は無視する」との裁判官らの態度が、まともなものなのか、そこに裁判官らの理性や良心があるといえるのかが、本件事件でも確認すべきことの1つである。むしろ、「子が学問的,社会的,心理的により悪く,喫煙,飲酒,薬物使用の可能性が高く,不安,うつ病,ストレス関連の病気の影響を受けやすくなっても父子交流や兄弟交流の断絶を優先する」と、裁判官らがそう明記するくらいの潔さがあればあればともかく、単に無視だからねぇ。「裁判官は正しいはずだ」「裁判官は主張や立証を慎重に検討したはずだ」との、裁判官盲信教の信者になることを期待しないでね。裁判官には判断についての理由提示義務(民事訴訟法253条3項)があるのだから、正しい判断というのならそれを検証できる理由提示をちゃんとしようね。そして、親子交流や兄弟交流を断絶することのデメリットを無視している福岡高裁等の決定は、子の利益に適っていたといえる理由提示もしていない単なる無視でしかないのだから、子の利益の観点からも理由提示義務の観点からも不適切なものであった。
ちなみに、なぜこのような統計データが存在するのか、それは当然、両親の別離後もそれぞれの両親と少なくとも35%の時間を過ごしている子が存在するから、データを集めることができているのである。つまりこのような親子交流は実施可能なものであり、アメリカ・アリゾナ州だと6歳以降では平日1日夕方3-4時間+隔週3泊を裁判所自身が例示している(甲3)。そして、申立人が求めていたのもこのような客観的に子の利益に適った親子交流であり、このような客観的な基準を蔑ろにしている相手方や福岡高裁の裁判官等が、子の利益を害し、紛争を生じさせ続けていると言えるだろう。
で、このような客観的に子の利益に適った親子交流を定めていれば、申立人がそれ以上の父子交流や兄弟交流を求める必要性も動機もないのだが、このことも「またか」という感じで福岡高裁等は無視しているのだから、福岡高裁等の判断は誤っているばかりか、裁判官らの恣意的判断に都合が悪いことは無視するという公正性に欠如した態度を世に自己紹介するものであった。
相手方は審判で定めた父子交流や兄弟交流以外は頑なに拒否する態度に固執することで、自らが子の利益に配慮する資質に欠けていることを示しているが、だったら審判の内容を変更して上記したように客観的に子の利益に適った父子交流を相手方が阻害しないようにすれば、それ以上の紛争が生じることはなくなり、父子交流や兄弟交流もでき、そのことは二男が父親や兄や父方祖父母とより良い関係を持ち,学問的,社会的,心理的により良く,喫煙,飲酒,薬物使用の可能性が低く,不安,うつ病,ストレス関連の病気の影響を受けにくくなることなのだから、二男や長男にとっては良いこと尽くめだよね。
だから本件事件で福岡高裁等の決定に言及するなら、上記の申立人が福岡高裁等でも主張した父子交流や兄弟交流の実施方法に、メリット以上のデメリットがあるといえるのかや、それについて福岡高裁等は理由提示義務を果たしているのかや、福岡高裁等が加害者という属性を理由に申立人の主張を審理拒否したことが公正で正しい裁判だったといえるのかが、本件事件でも問われるわけですよ。本件事件で誤った判断(福岡高裁等)を基礎にしたら、結論も誤ったものになるのは当然でしょ。
(4) 相手方に転居の必要性がなかったことについて
申立人は申立人と同居する長男が二男に会いたがっていたこともあり、兄弟関係への配慮から長男を連れて二男の居住地に行った。そうすると相手方を二男を巻き込み転居したわけだが、相手方の言動はつまるところ、「申立人が長男と一緒に兄弟を会わせようと二男の居住地に行ったら、相手方は死にたくなって転居した」というものである。
しかしながら、兄弟の交流が子らの利益に反するとは言えないし、そのときに申立人が二男に会ったとしてもそれが二男の利益に反することでもないし、申立人が兄弟を会わせたいと二男の居住地に行ったことが相手方に対する何らかの法令に反する違法行為に該当していたわけでもない。むしろ、申立人や長男が二男の居住地に行ったことがあるからこそ、申立人が二男の居住地に行ったとしても申立人が相手方に何らかの加害行為に及ぶおそれがないことは立証されている。
さて、相手方に転居の必要性がなかったことは福岡高裁等でも主張しているが、この主張はどのように判断されているかな? なんと、裁判官らは無視という挙に出ているんですねぇ。「都合が悪いが合理的理由をもって排斥できない当事者の主張は無視する」との裁判官らの態度が、まともなものなのか、そこに裁判官らの理性や良心があるといえるのか、理的理由をもって排斥できない当事者の主張があれば排斥しようとしている判断のほうが誤っていると気づくべきではないのか、それに気づいても恣意的判断を強行しているおそれに鑑みて裁判官をより拘束して裁判官の恣意的判断を抑止する法改正が必要ではないのかといったことも、本件事件で問われていることの1つである。
(5) 保護命令について
支援措置の必要性の要件は、保護命令(配偶者暴力防止法第10条)での要件と同様である。そうすると、仮に申立人から相手方に対する支援措置の必要性の要件を満たす加害行為があった場合、保護命令の申立によって接近禁止等が認められる可能性が高く、申立人には仕事があり長男を責任を持って育てているのだから、懲役などのおそれがありながら保護命令に違反する行為に出るおそれがあるといえる具体的根拠はない。そうすると、相手方が支援措置の必要性の要件を満たす被害者であれば、保護命令といった法的手段をとることもできたのだから、この意味においても相手方に転居を余儀なくされる事情があったとはいえない。
要するに、支援措置の必要性の要件を満たしていても保護命令によって被害を防げるのだから、相手方が二男を巻き込み転居する必要性はなかった。また、支援措置の必要性を満たす被害を相手方が受けていなければ、当然、本件支援措置決定は違法であり、相手方が二男を巻き込み転居する必要性はなかった。
そうすると、福岡高裁が相手方が転居を余儀なくされたとしていることに合理的理由は認められない。
どう? これも当然に福岡高裁で説明したけどね。恣意的判断をするのに都合が悪い主張は無視するのが裁判官の裁量権だとでも思っているのかな? 裁判官には、合理的理由をもって排斥できない当事者の主張があれば、排斥しようとしている判断のほうが誤っていると気づくくらいの知性は持っていてほしいものだが。あるいは、気づいていて敢えて故意に偏向判決をしているのなら、知性ではなく良心の問題だが。
ともかく、相手方による支援措置の必要性の要件を満たしていない支援措置申出がなければ、申立人は二男を含む戸籍附票の交付請求をすることで二男の居住地を知ることができるのだから、福岡高裁等が申立人が二男の居住地を知ることができないことを前提とした判断をしていること自体が誤ったものであった。
なお、申立人の上記主張が誤りというのであれば、相手方は申立人のどのような具体的行為が支援措置の必要性の要件に該当するのかを主張立証すれば良いことであり、相手方がその主張立証を怠る以上(そもそも虚偽を主張する以外にそのような主張は不可能であるが)、本件事件においても申立人が二男の居住地を知ることができないことを前提とした判断をすることはできない。
さて、このことは福岡高裁等の根本的な誤りでもあるのだから、この部分に理性的かつ理由提示義務を果たした態度を取れるかに、若林慶浩の知性や倫理観がよく表れることになるだろう。
(6) 父子交流や兄弟交流は子らの利益に適うことについて
既に述べたように、子と別居親との交流は子の利益の増進になるのだから、面会交流を禁止し,相手方の二男に対する独占支配の強化に福岡高裁等が加担したことは子らの利益を害するものであった。
また,相手方が被害を受けるおそれがあるなら保護命令を申し立てればよく、仮に当事者間での面会交流の協議が困難というのであれば,面会交流の日時や頻度,時間の長さ,二男の引渡しの場所や方法等,面会交流の実施方法を細かく定め,受け渡し方法は申立人と相手方が直接関わらないようにして子らが紛争に巻き込まれないようにし,それ以外の父子交流や兄弟交流は禁止したり、相手方が自ら協議したくなければ代理人に依頼するといった方法もあるのだから,父子交流や兄弟交流の断絶が子らの利益に必要だといえる事情は存在しない。
で、このような子の利益に配慮した申立人の主張を、福岡高裁は申立人が加害者であるとの属性のみを理由に検討しない挙に出てるんだよね。だから、属性を理由とした審理拒否が裁判官の態度として適切なのか問題にしているわけですよ。実際、上記のような実施方法であっても子の利益に反するような支障が生じるのか、福岡高裁等は検討した形跡がないでしょ?
ちなみに、相手方の主観的な恐怖心は二男の父子関係や兄弟関係を断絶させる合理的理由にならないし、相手方に転居の必要性がなかったことは既に述べてきたとおりだし、上記の方法であれば申立人と相手方との接触のないのだから、両親の葛藤に子らが巻き込まれることもないし、甲3にあるようにメタ分析の結果、両親間の葛藤が高い場合でも、両親との交流は子に好ましい結果になることが分かっているし、父子関係や兄弟関係が良好だったことからすれば、父子交流や兄弟交流が子らの利益に反することになると言える具体的根拠はない。
(7) 法文上、子の利益が最優先に考慮されなければならないことについて
既に述べたように福岡高裁等は、申立人を加害者扱いしてその加害者との属性を理由に申立人が主張した子の利益に適った父子交流や兄弟交流の方法を検討さえもしない挙に及んでいる。
しかし父子交流や兄弟交流は二男の利益に適うことで、紛争を生じさせずに不履行集や兄弟交流をする具体的方法についても申立人は述べていた。それでも福岡高裁等が一方的に決めつけた申立人の属性を理由に申立人の主張を検討しない挙にお横んだことは、親の不適切な行為を理由に子に不利益を被らせるものであった。
で、現行法では親の罪を子にも償わせるとなっているのかな? 仮に申立人に不適切な行為があったら、二男はその親の罪のために父親や兄との絆を失う罰を受けなければならないと? つまり、福岡高裁等の判断はこういうことを前提にしているものなんだよ? 子の利益を最優先に考慮するならば、そのための主張や提案は誰が言ったかではなくその内容が重視されなければならず、そもそも、法令でも子の利益を最優先に考慮すると規定されているのだから、きちんと学術的な根拠に基づき、子の利益を最優先に考慮しようね。
3 申立人が求める面会交流を決定することで紛争が生じなくなり子らの利益にも適う状況になることについて
さて、相手方は、面会交流を再開すると再び二男を強い対立に巻き込み葛藤を抱かせ、精神的負担を生じさせ、その不安定さを招くことは目にみえているとしているが、さて、この妄想は実現する可能性が高いのだろうか?
そもそも、紛争の原因は相手方が子の利益に適った面会交流を拒否することに固執したことにある。まあ他の見解もあるだろうが、まずは上記を前提に考えてみよう。で、申立人は相手方が申立人と二男との面会を妨害してはならないとする審判を求めている。これを認めた場合にどうなるだろうか? なんと、紛争が生じなくなるんですねぇ。相手方は審判決定を理由に、審判を超える父子交流や兄弟交流を頑なに拒絶していたが、そもそも面会交流の審判は相手方の最低限の義務を定めただけで、それ以上の面会交流を禁止したものではなかった。それなのになぜ、申立人だけでなく長男も二男に会いたがっていたのに、相手方は我が子である長男の思いさえも踏みにじる態度に出ていたのか。ここ大事だから若林慶浩も無視しないようにね。本来、父親が我が子に、兄が弟に会いに来てくれたことは二男にとって好ましい出来事であり、その好ましいはずの出来事を紛争にと変えた相手方の態度こそが、子の利益に反したものであった。だから、子を紛争に巻き込まないために子の親権者はフレンドリー・ペアレント・ルールで決めることが大切なのですよ。
ちなみに、申立人は35%に近づける努力をする等の客観的な科学的知見に基づく子の利益に適った面会交流を求めているのだから、相手方に対して申立人と二男との面会を妨害してはならないとする決定としても、申立人が二男の利益に反するような父子交流や兄弟交流をしていることはありえない。そのことは相手方が二男の学校不適応を生じさせているが、申立人が監護する長男にそのような問題がないことからも明らかである。ここも根拠を大事にした判断を無視しないように。つまり、申立人は子の利益に適った養育ができているから、長男は健全な育成をしているのですよ。相手方がごちゃごちゃ言い訳を述べても、この実際の養育実績以上に説得力があるものはないでしょ? ちなみに長男の状況に疑いがあるのなら、それも調査官調査などで調べたら良いことであり、根拠に基づく判断をすることが大事なことくらい、若林慶浩は理解できているよね? ちなみにこのような意味で、相手方がなんら根拠なく主張している二男の心情についても、それを無条件に鵜呑みすることが合理性や公正性に欠けた態度であるのは当然だよね?
また,申立人が二男の居住地に行ったとしても二男や相手方に具体的な危険が生じる危惧があると言える具体的根拠がないことも既に述べたとおりである。しかしそれでも申立人が二男の居住地に行くことで二男や相手方に具体的な危険が生じる危惧があると言うのなら,申立人が相手方の居住地に行くことを禁止する決定にすれば良いことである。
また、それでも更に若林慶浩が「できるための工夫」ではなく「できない言い訳」にばかり思考を巡らし(児童の権利に関する条約9条を思い出そうね)、たとえば当事者間での面会交流の協議が困難といった口実で父子交流や兄弟交流を断絶しようとするのであれば,面会交流の日時や頻度,時間の長さ,二男の引渡しの場所や方法等,面会交流の実施方法を細かく定め,受け渡し方法は申立人と相手方が直接関わらないようにして、それ以外の父子交流や兄弟交流は禁止し、何らかのやり取りの必要が生じた場合に相手方が直接交渉が嫌なら相手方が親族なり友達なり弁護士なりに代理人を依頼すれば良いことである。そのため、当事者間の葛藤があっても子を葛藤に巻き込まない父子交流や兄弟交流は可能なのだから、当事者間の葛藤は父子交流や兄弟交流を制限・禁止する合理的理由にはならない。
これは根拠に基づく判断には重要なことであり、60件の研究のメタ分析論文により、両親間の葛藤が高いと評価される場合でも、共同養育は単独養育より子どもにとって好ましいとの結果が出ている(甲3)。
メタ分析って分かるかな? たとえば医学の分野では「EBM」の重要性がよく言われている。EBMとは「Evidence-Based Medicine」の略であり、「根拠に基づく医療」と訳されている。これは当然のことであり、医療機関が効果のない治療法で患者の健康を損ねることがあってはならないのだから、医療機関の治療法はきちんとした根拠に基づいた治療法である必要がある。そのためには信頼性が高い研究法で根拠が示されることが望ましいが、このEBMではレベルが低い(根拠として弱い)ものから、大まかに以下のように整理できる。
・データに基づかない専門家の意見
・個別の事例研究
・比較研究(非介入と介入の場合等があるが、ここでは深入りしない)
・データ統合型研究(系統的レビュー)
さて、上記で挙げたメタ分析は、研究法の質でいえばデータ統合型研究(系統的レビュー)に該当する。これも当然であり、たとえば上記した結果は60もの研究論文を集め、それを更に研究することで導き出された知見なのだから、その根拠としての質が高いのは言うまでもない。
いま、裁判官に求められているのは「EBJ」である。「Evidence-Based Judge」ね。「根拠に基づく裁判」とでも訳せば良いだろうか。あるいは、「根拠に基づく裁判をする能力がある裁判官」、「根拠の重要性を理解する能力がある裁判官」でも良いかもれない。これも当然で、裁判官が根拠がなくそのためにまともに説明ができない自らの思い込みを優先して、合理的根拠がある主張を蔑ろにしたら、根拠に基づく判断になるわけないし、子の利益を最優先に考慮した判断にもなるわけないでしょ。
そうそう、データに基づかない専門家の意見も、根拠の質としては高くないが、だからといって全く根拠にならないとまで否定されているわけではない。ただし、では裁判官は? 上記の60件の研究のメタ分析論文で言えば、医学や児童心理学、あるいは社会学なんかも関係する分野に入る余地があるかもしれないが、一般に裁判官はこれらの専門家であるといえる根拠があるだろうか? まあ、ないね。そうすると、上記研究に関しての裁判官のデータに基づかない見解は、そもそも根拠といえるレベルにない、ごみでしかない。なぜごみかといえば、根拠に基づく適切な子の利益を考慮するときに、より質の高い根拠を蔑ろにした根拠のない裁判官の意見は邪魔でしかないからである。ここは、裁判官が「無知の知」を自覚しているかという知性が試され、確認できるところでもある。裁判官が「無知の知」を自覚せず、質の高い根拠に基づいた主張や書証より、自らのデータに基づかないその分野の専門的バックグラウンドもない個人意見や、根拠が不明だが裁判所で運用されている判断を優先させるなら、歪んだ判断になるのは当然でしょ? だからこそ、根拠は大事なんですよ?
裁判官がよく逃げ口上で使う「その他申立人が主張することは,いずれも採用することができない」との、具体的理由の記載がないために検証可能性がなく、事実上、「黙れ、私は何も間違えない。私の言うことは絶対であり、私がその他原告が主張することはいずれも採用することができないと言えば、それが正しいのだ」との裁判官の鬼ごっこ的態度は? 上記は「鬼滅の刃」という作品に出てくる鬼のセリフを改変したものだが、「鬼滅の刃」は「Demon Slayer」と訳されていることから、裁判官の上記の鬼ごっこ的態度はDBJ(Demon-Based Judge「悪魔に基づく裁判」」になるか。これがまともでないことくらい明らかだよね?
4 長男と二男との兄弟関係について
(1) 申立人と二男の関係と同様,長男と二男との関係も良好である。相手方が面会交流を不履行にするより以前,魚釣りを上手くできない二男のために長男が自らの竿を一緒に持たせて釣りを体験させてあげたり,トランポリンで遊んだり,申立人方祖父が用意してくれたすいか割りを長男と二男と近所に住む従兄弟とで楽しんだり,プールに行ったり,スポーツクラブでも上記の子ら3人で笑いながら遊んだり,長男が二男が乗っているブランコを押してあげたり,二男が長男と一緒にブランコに乗りたがったり,川遊びで二男は申立人や長男と一緒に想像力豊かに遊んだりしていた(甲11の1ないし7)。このような兄弟の様子は,兄弟関係の良好さや,それを見守っている申立人と子らの良好な関係を示しており,子らの利益に鑑みれば,これらの関係は今後も継続的に維持されなければならない。
このような子ども時代の兄弟の関わりは,その後の人生における兄弟関係に長期にわたって影響を及ぼすことになるが,相手方は面会交流を一方的に不履行にしてこのような良好な兄弟関係さえも断絶し,兄弟関係に一切配慮せず,事実上,兄弟を生き別れにしようとしているのだから,相手方は子らの利益に配慮する資質や能力が著しく欠如しているというほかない。そうすると,適切な兄弟関係を維持するためには,速やかに二男を申立人に引き渡さなければならない。
なお,長男自身,二男と二男との交流を望んでおり、そのことは相手方にも伝えているが(甲4~5)、それを無視しているのが相手方の我が子に対する態度である。ね? これ1つとっても相手方の我が子に対する態度がまともじゃないことが分かるでしょ? 相手方がどれほど子の利益について良い繕うとも、実際にやっていること(この場合はやっていないこと、つまり我が子に対する無視だが)はこれなのですよ。なら、二男もそのまともじゃない相手方の態度の影響を受けていると解するのが妥当でしょ? そうでないなら二男の不適応がこれほど長期化しているはずないでしょ? だから、若林慶浩が父子交流や兄弟交流を断絶させたいとか、父母間に葛藤があったら子が巻き込まれて良くないので面会交流をすべきでないとかいった思想信条を持っていたとしても、現実を見ようとしてる? 実際に不適応を生じさせているのは父子交流や兄弟交流を断絶された状況にある二男でしょ。現実よりも主義主張を優先するといった愚を侵さないようにね。
あと、長男が二男との交流を望んでいることは現状でも変わりないことは確認しているし、それを疑うなら若林慶浩が何らかの方法で確かめれば良いことである。裁判官としての役職に与えられている権限をきちんと子の利益のために適切に行使しようね。ちなみに長男は以前、二男に会いたいからと、小学校の授業で「さいばんがんばれ」との文字の形に金と銀の折り紙を貼ったものを作り、申立人に渡してきたことがあった(甲6)。どう? 若林慶浩がこのような兄弟交流を求める長男の心情も無視してもかまわないものとの態度なのかも、本件事件で問われる点である。ちなみに甲6の中心にあるのは、天秤をつもりつもりだそうだ。さて、若林慶浩がまともな天秤による判断をしているのは、本件事件できちんと示そうね。ここでくず裁判官を想定すると、福岡高裁等の判断の誤りを本書面で具体的に指摘しているにもかかわらず、それを無視して福岡高裁等に忖度し、その判断に過ちが絶対にないことを前提にした判断をすることか。しかしさ、既に述べたように熊本県は冤罪事件として名高い「免田事件」があった地であり、冤罪があったということは裁判所が判断を誤ったということでしょ? そういう前例があるんだから、きちんと歴史から学べるくらいの知性は持とうね?
で、若林慶浩が福岡高裁等と同様に、事実上、兄弟関係が子の利益にとって無視してもかまわないものだとするなら、その合理的根拠をきちんと示すように。まあ、動画から読み取れる兄弟関係からしても、長男が二男との交流を望むのは当然であるし、このような兄弟関係を断絶することが子らの利益に反することも当然なのだが。だから、このような父子交流や兄弟交流の断絶に都合が悪い証拠を若林慶浩がどのように扱うのか、それとも扱うこと自体をせずに見ざる聞かざる言わざるの猿になるのかに、若林慶浩の資質が問われているのですよ。
そういえばくずな裁判官の手口として、とりあえず当事者の主張は最初のほうで記載するが、それだけで後に記載する判断ではまるっきり無視しているというものもある。そういう姑息な手段も使わないようにね。もうばれてるんだから。
(2) きょうだい関係は,パーソナリティ,社会性と認知的スキル,自己概念,価値観,外の世界から保護されている感覚,といったものに影響を与える。また,きょうだいは,価値観のモデリング,スキルを教えること,傷つきからの保護,そしてしばしばきょうだいの最初の友達として振る舞うことなど,家族の中でさまざまな機能を担っている(甲7)。そうすると,長男と二男との兄弟関係が断絶されている現状が子らの利益を害しているのは明らかである。
さ、紙代も印刷代もDVD代もタダじゃないんだから、わざわざ提出された根拠を故意に無視するといったくずな態度をとらないようにしようね。申立人は父子交流や兄弟交流の必要性の根拠として書証を出しているのであって、若林慶浩が父子交流や兄弟交流を断絶するのに都合が悪い主張立証を故意に無視することを立証したくて書証を出しているのではないのですよ?
5 親子断絶が不登校やPTSDの原因なることについて
中日新聞令和2年11月12日朝刊において,以下の記事が記載された(甲8)。
【小学生時代に母に連れ去れ家を出て,父と別居し,不登校や心的外傷後ストレス障害(PTSD)になった-。面会交流訴訟で弟(16)とともにこの立場で原告に加わった千葉県の男性(20)は十一日,東京地裁への提訴後に記者会見。「面会交流がより多く実施されていれば,ここまで苦しむことはなかったのでは」と,家族と自由に会えなかった過去を振り返り苦渋の表情を浮かべた。(中略)男性は「自由に面会できれば素直に本音がさらけ出せたかもしれない。離れていても,家族に気持ちを伝えたい瞬間はあるはずだ」と訴えた。】
上記記事の男性は親子交流の断絶を人権侵害と訴えており,それが原因で不登校やPTSDになったとしている。親子関係を妨害することは,児童虐待等のよほどの正当な理由がないかぎり子に対する情緒的虐待なのだから,それによって子に悪影響が生じるのは当然である。ね? 現状の二男の状況と類似しているでしょ? 相手方の言動は正に上記の虐待行為に該当しているし,事実,二男は発達や学校適応に問題を生じさせている。上記の当事者の声、そして現実で生じている二男の不適応からしたら、父子交流や兄弟交流を断絶していることが二男の利益に適っているとは到底認められないでしょ。
6 現状が二男の利益に反していることは明らかになっていることについて
(1) ここでは根拠を示しながら、二男が強いられているリスクを見ていこう。若林慶浩はこれらを無視し、「ボクは知りたくないことは見ざる聞かざる言わざるの猿だもん」といった態度を取らないように。
まずはメタ分析の結果で示したように、父子交流が断絶されている現状は、相手方や裁判官らが、二男を学問的,社会的,心理的により悪く,喫煙,飲酒,薬物使用の可能性が高く,不安,うつ病,ストレス関連の病気の影響を受けやすくなる状況を強いていることになる。
次に、相手方には以前から精神疾患があるが,親の精神疾患は子に降りかかる恐れのある危険要因のあらゆる可能性のなかで,もっとも強い精神的な影響を及ぼすもののひとつである(甲9)。事実,二男の発達障害や学校での不適応等も,相手方の精神疾患に二男が強い影響を受けた結果であることは否定できない。というか、精神疾患が身近にいる影響力は馬鹿にできないよ? それが同居人なら毎日影響を受けるんだよ? しかも子どもはその影響力に対する抵抗力が弱いから特に影響を受け易いよ? 二男はそのような精神疾患がある相手方からの影響をずっと受ける環境を強いられてきたんだよ? それで影響を受けないほうがおかしいでしょ? この影響力を無視して子の最善の利益を考慮できるはずがないでしょ? それでも若林慶浩がこの影響を考慮しないというのなら、その合理的理由を示すように。
ちなみに、相手方がせっかく二男に会いに来てくれた申立人や長男の思いを踏みにじったことから、そもそも相手方は父子交流や兄弟交流に否定的であることが分かる。そうじゃなかったら、わざわざ二男の会いに来てくれた申立人や長男を拒絶するわけがないでしょ? で、父子交流や兄弟交流を断絶したい相手方にとって、精神疾患は父子交流や兄弟交流の断絶を維持する口実になるし、相手方の答弁書を見れば、二男の学校不適応さえも相手方は父子交流や兄弟交流の断絶を維持する口実にしている。つまり、相手方にとって精神疾患や二男の不適応は、父子交流や兄弟交流の断絶を維持するのに都合が良いわけですね。こういうのを「疾病利得」とも言うが、つまり本来は好ましくないことでも、それにとって得る利益がある場合、故意か無意識かはともかく、その好ましくない状況を長期化させようとする精神力動が作用することがある。分かりやすい例としては、「学校に行きたくないからお腹が痛くならないかな」といったのも同じ精神力動であり、これが強いと実際に腹痛が生じることも珍しいことではない。このような意味において、相手方が父子交流や兄弟交流の断絶を維持する口実にしていることは、本件事件で重視すべきではない。だって、相手方がこれらを長期化させることで、ずっと父子交流や兄弟交流を断絶する口実にしてくることは目に見えているのだから。実際、相手方はそういう言動をしているでしょ? そういえば代理ミュンヒハウゼン症候群は、子を病気にしてその世話をすることで親自身が周りから評価されるなどの利益を得る、児童虐待の一種であるが、相手方が父子交流や兄弟交流を断絶して二男に不利益を被らせて、更に二男に不適応を生じさせ、更にその二男の不適応を口実に更なる父子交流や兄弟交流の断絶と長期化させ、相手方による二男に対する独占支配を強化するという利益を得ようとすることも、代理ミュンヒハウゼン症候群と類似性があるといえるだろう。
次に、臨床心理士である石垣秀之氏は以下のように述べている(甲10)。
【愛着について十分な知識と観察経験のない調査官は,子どもが母親に強くしがみついているという行動一つを根拠に,子どもが母親に対して良好かつ強固な愛着を有している,と評価することがあり,調査官を心理学の専門家であると認める裁判官はその言を信じます(本当は,信じているのではなくその方が都合がよいだけかもしれませんが)。主たる養育者以外に十分な愛着対象者がいない場合には,子どもは見捨てられ不安に駆られ,主たる養育者との分離に対して強く抵抗を示す場合があります。】
さて,以前の調査官調査時に二男は相手方に対するしがみつき行動が見られる。これは石垣氏の指摘のように,愛着理論からすれば二男の様子は見捨てられ不安の表れと解される。つまり,相手方は二男に十分な安心・安全な環境を用意できていない。
石垣氏は以下のようにも指摘している。
【子どもが自分を求める姿によって承認欲求を満たし,子どもがいつまでも疑いなく自分に従い求めることを期待し,結果的に子どもの心理的自立を妨げ自分の思いで子どもを支配しようという態度や依存が生じることもあります。こういった親の場合,他方親が,自分と子どもとの1対1の親子関係に入ってくることや,子どもが他方親に懐くことを快く思わず,子どもを連れ去って依存・共依存関係を継続させようとすることがあります。】
【連れ去りや引き離しは,実行するまでに大きな不安をもたらしますが,連れ去り後は更に大きな不安をもたらします。連れ去り後の初期における大きな不安は,自分の行った連れ去りは「誘拐」なのではないかという罪悪感から生じる不安です。そのため防衛機制としいての「合理化」が生じることになります。自分の行為は正当な理由に基づく妥当なものであり,何ら責められるべきものではない,と自分自身を納得させることが必要になるのです。】
【防衛機制は本人にそれと意識できるものではないので,連れ去ったことを自我が正当化するため,連れ去りによって当然生じる別居親の怒り感情を,同居時における別居親の普遍的態度であったと自分の記憶を都合よくすり替えたり,実際にトラウマ反応のような症状を呈する場合もあります。遅発性PTSDとの鑑別が必要になりますが,同居時のカルテを開示するように求めても拒絶したり,開示されたカルテを見ると,診断した医師が同居親の主張を鵜呑みにして客観的な根拠を有さずに診断していることが見られますから,遅発性のPTSDではなく,詐病や自己暗示によるPTSDと鑑別することは容易です。】
さて,相手方は正当な理由なく二男を連れ去っての別居を強行し,現在は父子関係や兄弟関係を断絶させるという引き離しも継続しているが,これらは相手方の不安に起因する態度と解するのが妥当である。そうすると,相手方の二男に対する行動原理は不安にあるのだから,そのような不安を基礎とした言動を繰り返している相手方が,二男に安心・安全な環境を用意していくことは困難である。で、ここで相手方が転居する必要が本当にあったのかにもつながるのだが、相手方が転居せずに父子交流や兄弟交流に寛容であったらどうなっていたか? 二男は父親や兄との交流ができ、精神疾患がある相手方から独占支配される影響も緩和されていた。相手方にとっても二男を申立人に預けることで自由な時間ができていた。あれ? 良いこと尽く目じゃない? つまり、本来、父親や兄が会いに来てくれたという好ましいことを、相手方は自らの不安に起因する被害妄想に二男を巻き込み転居することで、より二男に悪影響を及ぼしたということである。
そもそも,二男に落ち着いた安心・安全な環境を用意するためには,二男との関係が良好な申立人や長男との関係を十分に保障する必要があるのだから,それに反した言動を繰り返している相手方が二男の利益を害し続けているのは明らかである。
相手方が父子関係や兄弟関係を断絶していることは,相手方が二男を独占支配しての依存・共依存関係を維持しようとしていることに他ならないし,本来相手方は転居する必要がなかったのだから,それを自己正当化するために相手方は詐病あるいは自己暗示によるPTSDになっていると解される。
つまるところ,精神疾患がある相手方に監護されている環境は,二男が落ち着いた安全・安心感を抱ける環境になっていないし,今後の改善を期待できるとする合理的理由も見当たらない。だって相手方の答弁書を見れば、相手方は父子交流や兄弟交流の断絶を維持する気まんまんで、それを改善しようとする気は皆無のようだからね。
さて、EBJ(Evidence-Based Judge:根拠に基づく裁判)でいきましょう。父子交流の断絶や精神疾患のある者が子の監護者であることのリスクは根拠を示して述べたのだから、若林慶浩が子の利益に配慮するというのなら、これらのリスクを無視しないように。もちろん、自らがクズだと自己紹介したいのなら、若林慶浩は嬉々として偏向判断のためにこれらを無視してくるだろうが。ここに我が国の裁判官の資質や、若林慶浩の人間性が表れることになるだろう。根拠を示しての主張であっても、偏向判断に都合が悪いからと無視するのなら、ホント良心が末期症状になっているし、まともな判断になるわけないよね。ぐだぐだ言い訳をしても、現実は二男の不適応といった結果に表れているでしょ? 判事がそういう現実から目を背けちゃダメでしょ? 二男が現状で強いられているリスクを含めて総合考慮しようね?
(2) 次に、二男の状況を個別具体的に見ていこう。まず二男は発達の疑いが指摘されていたが、発達障害の子で通常学級が困難な場合は、特別支援学級への転級が可能であり、そもそも発達障害があるからといって必ずしも学校不適応を生じさせるわけではない。むしろ現在の小学校は発達障害の理解や受け入れ体制がかなり充実しているのだから、発達障害だからといって学校不適応を生じさせることのほうが少数派である。その意味において、二男の不適応は専ら相手方に帰責される原因によって生じたと言わざるを得ない。
また、相手方は二男の不適応さえも申立人に帰責する主張をしているが、仮に申立人に原因があるとすれば、父子交流が断絶されている現状において、その原因はもはや二男に存在しない状況になっているのだから、その状況においても二男の不適応が長期化していることは矛盾している。
では、二男の不適応はどういうことか。まず父子交流や兄弟交流を断絶することのデメリット、それに精神疾患の親から子が受ける深刻な影響については、既に述べたとおりである。これらは客観的データとして存在するものなのだから、これらを軽視することが不合理で子の利益を蔑ろにする態度であることは言うまでもない。中日新聞令和2年11月12日朝刊での記事(甲9)も、父子交流の断絶が子に与える影響の深刻さを物語っている。
また、本件事件では父子交流や兄弟交流の具体的内容(甲11の1ないし7)も考慮する必要がある。これらの動画で分かるように、二男にとって好ましいものであった。それに対して相手方はどのような態度をとったか。申立人や長男が二男に会いに来てくれたことを口実に、転居をして父子交流や兄弟交流を断絶する挙に及んでいるですね。
さて、「父や兄が会いに来てくれた ⇒ だから会わせた」がまともな親の態度というもので、申立人や長男が二男に会うことが二男の利益に反していたと言える具体手根拠は存在しないし、申立人や長男が二男に会いに行ったことで相手方が申立人から何らかの具体的危害を加えられたとする事実もない。しかし相手方は、「父や兄が会いに来てくれた ⇒ だから転居して父子交流や兄弟交流を断絶した」との態度に出ている。ここで大事なのは二男の心情ですよ。「父や兄が会いに来てくれた ⇒ だから転居して父子交流や兄弟交流を断絶した」に対して、二男が「なるほど」と納得するとても? 「父や兄が会いに来てくれた」を原因、「転居して父子交流や兄弟交流を断絶した」をその結果とすることには、論理の飛躍があるよね。まあ相手方は「父や兄が会いに来てくれた」ことを精神的負担に感じたようだが、ではなぜこれが精神的負担になったのかというと、そもそも相手方が父子交流や兄弟交流を断絶したいとの子らの利益に反した不適切な歪んだ認識を持っていたことに他ならない。ここ、大事だから若林慶浩が別の見解だというのなら、それを具体的に明確にするように。で、相手方が元々が子らの利益に反した不適切な歪んだ認識だから、それに基づく言動も子らの利益に反した不適切な歪んだものとなるのは当然であり、それが父子交流や兄弟交流の断絶や、二男を巻き込んでの一方的な転居だったというわけである。だから、何度も言うようにフレンドリー・ペアレント・ルールが大事なんですよ。
で、子の利益を最優先に二男の心情を考慮すれば、「父や兄が会いに来てくれたから転居して父子交流や兄弟交流を断絶した」という状況に納得できるはずがないでしょ? ここでもう一度、父子交流や兄弟交流の具体的内容(甲11の1ないし7)を振り返ろう。このような好ましい父子交流や兄弟交流を二男がする機会を奪ったのが相手方というわけなんですね。それに二男が反発したり精神的負担を感じるのは当然でしょ? そしてそれが二男の学校での不適応として表出していると解するのが当然でしょ? 二男の主観で言えば「お父さんやお兄ちゃんが僕のために会いに来てくれても、お母さんはそれを邪魔したし、お父さんやお兄ちゃんが僕のために会いに来てくれたことを逆に利用して、僕からお父さんやお兄ちゃんを引き離した。お兄ちゃんはお父さんと一緒に暮らしていろんな経験をしたり、いろんなことに頑張ったりしていたのに、お母さんのせいで僕はお父さんに可愛がってもらえなくて、僕の人生からお兄ちゃんも消えてしまった」となるわけである。相手方や裁判官らがどのように屁理屈を述べようとも、重要なのは父子交流や兄弟交流は好ましいものだったということであり、それを相手方が断絶させたということであり、相手方が二男を巻き込み転居をしたということであり、長期にわたって父子交流や兄弟交流が断絶された現状において二男が不適応を長期にわたって生じさせているという現実である。現実と、「申立人を加害者扱いしたい」との主義主張が矛盾した場合に、主義主張を優先することが愚かであることくらい、若林慶浩は理解できるよね?
あるいは、仮に申立人を加害者扱いするとしても、それと子らの最善の利益を考慮することは別である。申立人に加害行為があったかどうかとは無関係に、二男の利益になるなら父子交流や兄弟交流をしていくべきなのは当然でしょ?
(3) 東京地方裁判所令和3年2月17日は以下のように判示している。
「親である父又は母による子の養育は、子にとってはもちろん、親にとっても、子に対する単なる養育義務の反射的な効果ではなく、独自の意義を有すものということができ、そのような意味で、子が親から養育を受け、又はこれをすることについてそれぞれ人格的な利益を有すということができる。」(甲12)。
で、この二男や申立人の人格的利益を蔑ろにしたのが、相手方や裁判官らということですよ。だから自らの人格的利益が害されたことに起因して二男が不適応を生じさせたり、本件事件のような紛争が生じるのは当然でしょ? 本件事件にしても、相手方が父子交流や兄弟交流に子らの利益に適った配慮ができていたり、裁判所が子らの利益に適った父子交流や兄弟交流を定めていれば、申し立てる必要がないものだったのだから。ということで、紛争を長期化させないことや、裁判官らの杜撰さによる被害者をこれ以上増やさないためにも、本件事件では子らや申立人の人格的利益に配慮した面会交流が定められなければならない。
第2 結語
まず、父子交流や兄弟交流が断絶されることのデメリットや、二男が精神疾患がある相手方に独占支配されていることのデメリットに鑑みれば、速やかに父子交流や兄弟交流が再開されなければならない。
また、申立人が求めているのは発達心理学の研究成果に基づいた子の利益に適った面会交流(甲1~3)の実施であるが,それに対して相手方が審判決定以上の面会交流に応じない態度に固執したことで,紛争が生じている。
そうすると,相手方に対して申立人と二男との交流を妨害してはならないと定めることで、紛争は生じなくなり、二男は父子交流や兄弟交流によるメリットを享受でき、精神疾患がある相手方による独占支配を余儀なくされる状況も軽減され、父親から養育を受けるという人格的利益も回復されることになる。ちなみに、申立人もそれほど暇ではなく、仕事や長男の監護等があるのだから、それほど面会交流に時間を割くわけにもいかず、そもそも申立人が求めているのは発達心理学の研究成果に基づいた子の利益に適った面会交流だとしても長期休暇以外で35%に近づけるのは困難なのだから、申立人が子の利益に反した過度な父子交流や兄弟交流を要求することはありえないし、そのような要求をする動機もないし、そのような要求をするおそれがあるとする具体的根拠もない。それでも上限を決めるべきというのであれば、発達心理学の研究成果に基づいた子の利益に適った面会交流を基準として、それ以上の面会交流を禁止すればよいだけである。
また,当事者間での面会交流の協議が困難というのであれば,相手方が親族なり友達なり弁護士なりに代理人を頼めば良いことであるが、むしろ二男が直接申立人や長男とやりとりすることも良いだろう。ここで「できるための工夫」ではなく「できないための言い訳」に思考の指向性がある場合、「子に葛藤が巻き込まれる」とか言い出すことも想定されるが、子が友達と遊びたくて親に許可を求めることが子の利益に反する状況だとはいえないのと同様、二男にとってその対象が友達ではなく父や兄だった場合に子らの利益に反する状況になるといえる具体的根拠はない。少なくとも、親子や兄弟の生き別れのほうがましなほど強い葛藤状態に陥ると言える具体的根拠はないし、そもそも、以前から父子交流や兄弟交流は良好であった。
それでもまだ文句をつけるのなら、面会交流の日時や頻度,時間の長さ,二男の引渡しの場所や方法等,面会交流の実施方法を発達心理学の研究成果に基づいた子の利益に適った方法で細かく定め、それ以外の父子交流を禁止すればよいだけである。
二男の受け渡しで相手方が申立人に会いたくないなら、相手方以外の者が受け渡しをすればよいことであり、というよりこれは以前から相手方はそうしている。
まあ「できるための工夫」ではなく「できないための言い訳」を相手にしているとキリがないが、そもそも相手方が父子交流や兄弟交流に寛容であれば紛争は生じなかったのだし、相手方が寛容になることができないとしても裁判所が相手方に面会交流を妨げてはならないとしても同じ効果になる。次善の策にはなるが、その他のいちゃもんも面会交流の方法を細かく定めたり、相手方が誰かに代理人を依頼すれば解決できることばかりである。
ああ、申立人が相手方の居住地に行くおそれも相手方は主張しているが、そもそも申立人が二男の居住地に行ったとしても何ら悪いことは生じず、父親が会いに来てくれることは二男にとって好ましいことだという認識の改善が相手方には必要だろう。「申立人が来れば転居しなければならない」といった申立人を危険視した態度こそが、二男にとって悪影響であることに相手方は気づかなければならないし、若林慶浩もこのことに配慮した判断をしなければならない。だって、「お前のお父さんは危ない奴なんだぞ」との態度が子にとって悪影響であるのは当然でしょ? 二男は申立人や長男と楽しく過ごしていたのだから、それに矛盾した、父親はこちらの居場所を知られると転居しなければならないほど危険な奴だとの相手方の態度が、二男の精神的負担になっていないわけがないでしょ? つまるところ、相手方は二男の精神安定よりも、二男に不適応を生じさせようとも二男を独占支配することを優先していると言わざるを得ない。
それに、発達心理学の研究成果に基づいた子の利益に適った面会交流であるが、35%に近づけるのは長期休暇中ででもなければ実現困難なのだから、そもそも普通に父子交流ができていれば、敢えて申立人が二男の居住地に行く動機もない。
ちなみに、「二男が申立人や長男と交流したがることを妨げてはならない」といったことは不適切である。このようなものにした場合、父子交流や兄弟交流に否定的な相手方に影響され、二男が本心を言えなくなることは目に見えている。
申立人は本来、相手方の違法な支援措置の申立がなければ二男の戸籍附票を取得することで二男の居住地を知ることができるのだから、相手方の住所を申立人隠す必要性は面会交流を妨げ理由にならない。これについても案の定、相手方は支援措置の必要性について逃げた主張をしているね。申立人が支援措置の必要性の要件を満たす加害者というのなら、その具体的な加害行為を主張すれば良いことなのだから。こういう相手方の誤魔化しも若林慶浩はきちんと総合考慮するように。なお、仮に申立人が支援措置の要件を満たす加害者だとすれば、それは保護命令(配偶者暴力防止法第10条)の要件を満たしていることになるのだから、接近禁止等が決定されれば仕事があり長男を責任を持って育てている申立人が懲役などのおそれがありながら保護命令に違反して相手方に近づくようなおそれがあるといえる具体的根拠はなく、そうであれば相手方が転居をする必要もなく、関係が良好な父子交流や兄弟交流を断絶したままにしておかなければならない合理的理由はない。まあ、これは仮の話で、申立人に支援措置の要件を満たす加害行為はないし、だから相手方もそれに対する認否自体から逃げたわけだが。
申立人の主張立証に対して、若林慶浩の判断が正しいことを検証可能な理由提示義務を果たしているか、その判断理由の内容に不足なく合理性にも矛盾や見落としなく、世の批評にも恥ずべき点なく示せるものかについて、きちんと確認しようね。
以 上
事件番号 令和4年(家)237号
申立人 *******
相手方 *******
未成年者(二男) *******
主張書面
令和4年8月18日
熊本家庭裁判所 御中
申立人 *******
本件事件では当然、子らの利益が総合考慮されなければならない。そのため、若林慶浩がまともであるのか、それとも若林慶浩が裁判官という立場を悪用して子らの利益を損ねようとしているのかが問われるわけだが。
そのため、総合考慮すべき点について追記する。これらを無視しないように。まあ、子らの利益を故意に損ねたいなら、これらを無視することで若林慶浩の本性を表すのだろうが。
まず、相手方は二男の幼稚園の卒園式のとき、申立人が卒園式に来ることを理由に卒園式を休ませている。さ、これはまともな判断でしょうか? 若林慶浩がまともであるかをここで示そうね。ちなみに、都合が悪いことは無視することがまともな裁判官としての態度だと若林慶浩が考えているのなら、それもここで態度で示しましょう。子の心情を含む子の利益が最優先ということを忘れずに。子の利益を最優先に考慮したとき、父親が幼稚園の卒園式に来ることが子の利益に反しているといえる合理的理由があるのか、若林慶浩の判断を示しましょう。もし合理的理由がないなら、当然、二男を卒園式に参加させなかった相手方の態度が子の利益を蔑ろにしたものであったということだからね。で、こういう子の利益を蔑ろにした行為をしている相手方が二男の利益に配慮した判断をできているわけがないでしょ?
次。相手方やその祖父母は二男の小学校の入学式でも、二男が申立人と関わりたがってもそれを妨害している。具体的には動画(甲13)で確認できるが(職務怠慢せずに確認しろよ?)、相手方らは二男と申立人が話している場面で、敢えて近づき二男を連れ去ろうとして、父子の交流を阻害する行為に及んでいる。更に、相手方の父(二男の祖父)は申立人に対して、右手の平を下にして手首の折り曲げを繰り返しながら「ちっちっちっち」と言うことで,あたかも,犬でも追い払うかのような侮辱的な言動をしている。この相手方の父の言動に対して,すぐ近くにいた二男は二男は,「ちっちて何?」と発言していることから,相手方の父の上記言動は二男も見聞きしていたものであった。また,長男も,相手方の父の上記言動を見ていた。
さ、一生に一度の小学校の入学式というハレの機会に、このように父子交流を阻害したり、父親を二男の前で侮辱する相手方らの行為が、子らの利益に配慮したものと言えるのか、若林慶浩の判断を示しましょう。これが相手方自身の言動ではないにしても、相手方が祖父母を入学式に参加させ、その祖父母の言動を黙認していたのだから、相手方に責任があることに疑いの余地はない。二男にとっても、この入学式の出来事が相手方に帰責される事項であることは実感しているだろうし、仮にすぐには理解できなくても、いずれ容易に理解にたどり着くことになる。学校不適応は本人や学校に問題があるというよりも、親の養育の問題が子の不適応という形で表出していることも珍しくない。そして、相手方はこのように二男に精神的負担を負わせ、父子交流や兄弟交流を断絶することでも二男の人生に不利益を被らせているのだから、このような状況が速やかに改善されなければならないのは明らかである。
ちなみに、大多数の感想としては(甲14)、この相手方らの態度をまともだとは思っていないが、若林慶浩がこのような社会一般的な常識的判断をできているのか、仮に違う判断をするとしてもその合理的理由をきちんと説明できているのか、それともやっぱり都合が悪いことからは逃げるというクズな態度で、そのクズな態度を恥を思える良心も持ち合わせていないのかが明らかになるだろう。ここは、若林慶浩がどのような教育を受けてきたかという親の教育力も表れるところでもあるし、若林慶浩の態度が幼少期から受けてきた教育を根底とするものとの観点からすれば、ここは若林慶浩の家系としての常識力が表れるところでもある。
そうそう、入学式での相手方の父親の言動については、熊本地裁で申立人に対する損害賠償が認められている。そのような不法行為責任が認められるような言動が、二男にとっても不適切であったのは当然でしょ。大多数が感じていることなら、二男も同様に感じていると解するのが自然でしょ? このようにいろいろとやらかしている相手方に独占支配されて父親や兄との楽しかった交流を断絶されたことで、二男が精神的負担を感じていないと現実から目を背けた態度が、二男の利益に適うわけ無いでしょ? 若林慶浩を含め家裁の裁判官らは後見的立場で子の利益を長期的視野で総合考慮しなければならないが、相手方がしていることを二男が理解するようになれば、二男が相手方に否定的感情を持つことは目に見えている。それでも若林慶浩はその立場を利用して父子交流や兄弟交流の断絶を継続させるのかな?
「平家物語」には、父祖の善悪は必ず子孫に及ぶとある。若林慶浩は裁判官としの立場の悪用、子の利益の蔑ろ、親子断絶、兄弟断絶、公平性の欠如、主張の無視等、どのような業を子孫に残していくのであろうか。あるいは、本人や子孫がそのような業を信じないとしても、立場の悪用、子の利益の蔑ろ、親子断絶、公平性の欠如、主張の無視といったことで良心の呵責を感じないという人間性の欠如は、子孫に受け継がれていくのかもしれない。それは子孫自身が判断すれば良い。
次。親に精神疾患がある場合に子が被る悪影響については既に述べたが、更に、ヤングケアラーの問題も本件事件では考慮しなければならない。これは単に子が大人の世話をしなければならないというだけでなく、本来は保護される対象となるべき子が、家族から十分な情緒的共感をされないことを含む。人が精神的安定を得るためには、自らを共感的に受容してくれる存在が重要であり、子にとってその重要性は殊更である。しかしながら、精神疾患がある相手方が二男にそのような情緒的共感を十分にしていることは期待できない。そもそも、相手方が二男に情緒的共感をしようとしていれば、幼稚園の卒園式や小学校の入学式のときような言動をするはずがない。そして、相手方は現時点においても良好であった父子関係や兄弟関係の断絶を継続しようとする主張をしているのだから、この点においても相手方の二男に対する情緒的共感性の欠如が示されている。
そうするとヤングケアラーや二男が相手方から被っている精神的負担の危惧という点においても、若林慶浩が調査官調査等で二男の現状を客観的に確認することなく、本件事件をさっさと適当にとりあえず内容よりも処理件数を増やすことを優先するとの態度で判断することが、民法766条1項の子の利益を最も優先して考慮しなければならないとの規定に反しているのは明らかである。
あと、若林慶浩が「できるようにするための工夫」よりも、父子関係や兄弟関係の断絶のための「父子交流や兄弟交流をできないための言い訳」に全集中したとしたら、どのような屁理屈があるだろうか。相手方が父子交流を妨げることを禁止すれば、紛争が起こり得ないことは既に述べた。精神疾患があり、父子交流や兄弟交流を断絶することを望んでいる相手方に二男が独占支配されている現状が、二男にとって不適切な環境であることも述べた。学校不適応は発達障害等が直接の原因にはならないし、相手方が父子交流兄弟交流を断絶しても二男は改善していないのだから、相手方による監護状況が二男に悪影響を及ぼしていると解するのが妥当であることも述べた。ああ、若林慶浩が偏向判決する場合、二男の不適応から目を背けるか、相手方の不適切な対応から目を背けて、父子関係や兄弟関係が断絶されていることでのデメリットを無視したり軽視することもありえるだろうが、そのような自らのクズっぷりの自己紹介はしないように。あと、どうしても申立人と相手方を接触させたくないのなら、面会交流の内容を協議の必要がないほど細かく、しかし子の利益に適った内容で定めれば良い。が、そもそも相手方はこれまでも弁護士に代理人を依頼しているのだから、相手方が直接協議をする必要はないし、むしろ相手方に二男の意思が捻じ曲げられないようにするため、申立人と二男とで交流方法を検討するのもよいだろう。心配なら父子交流や兄弟交流の月々の上限を決めるといこともありえるかもしれないが、それをするにしても合理的な根拠のある子の利益に適った交流頻度(甲1~3)をきちんと考慮するように。それにこれも書いたが、申立人も暇ではないのだから、父子交流の時間を35%に近づけるのは長期休暇中くらいでないと困難だし、申立人が二男の利益に反した交流を求めるおそれがあるといった裏付けもない。
また、くずな裁判官はうじゃうじゃいるようなので、その詭弁の手口はいずれまとめて整理して公表するつもりだが、その申立人の態度と、子の対する態度は当然に区別しているから心配なく。実際、申立人は相手方と異なり仕事をずっと継続しており、相手方と異なり長男を特段の問題なく健全に監護しているのだから、区別できていることは実績からも明らかでしょ。それでも疑うなら、長男に対して等の調査官調査でもすれば良いことで、自らの権限で確認可能なことを調べもせず、妄想を根拠とした判断が自らのクズっぷりを自己紹介するものであることくらい理解できるでしょ?
くず裁判官いちの呼吸、「父子交流や兄弟交流をさせないためのこじつけ」に全集中なんて場合、申立人と相手方の葛藤も言い出しそうだが、相手方が高葛藤のために冷静に二男の利益を最優先に考慮することができてないことは、二男にとって悪影響なのだから、尚更その二男への悪影響を軽減するためにも父子交流や兄弟交流が必要になってくるのは理解できるよね? では申立人の葛藤は? そもそも相手方が0歳の二男を連れ去り別居をしたことで紛争が生じており、その後も相手方の不適切な言動やくず裁判官のために複数の訴訟や審判などがあっているが、その間も父子交流や兄弟交流は良好であった。つまり、ここでも申立人は相手方との紛争と二男との関わりはきちんと区別できていたんですね。論より証拠でしょ? 申立人には父子交流において二男の関係が良好であった実績があり、それが現状でできなくなっていることを裏付ける根拠はない。それに甲3で示したように、仮に両親間の葛藤が高い場合でも、別居親との交流は子どもにとって好ましいとの研究結果もある。つまり、仮に両親間の葛藤のために子に何らかの負担が生じたとしても、それ以上に両親との交流を断絶することのデメリットのほうが大きいというわけなんですね。だから、根拠に基づく裁判が重要なんですよ。若林慶浩が「そんな根拠や実績よりもボクが考えついた父子や兄弟を断絶する理由のほうが正しいもん」というのなら、それが根拠があるものなのか、あるいは、自らがまともな教育を受けてきていないことを証明するものでしかないのか、きちんと考慮しましょうね。そして、合理的理由を持って排斥できない当事者の主張立証があれば、それを排斥しようとした判断のほうが誤っていると気づく知性くらい持とうね? そもそも、裁判所が根拠に基づく適切な父子交流や兄弟交流が可能な決定をしていれば、紛争は生じず本件事件も申し立てる必要はなく、二男も父親や兄や申立人方祖父母らと良好な交流ができ、それによって二男の精神的負担を軽減することができ(心理療法にプレイセラピーがあるように、子にとって共感的に関わってくれる大人がいる環境で伸び伸びと過ごすことは、不適応状態を改善する治療効果が期待できる)、二男が心理的不適応に専門的知見や経験を持つ申立人と適切な関わりを持てていれば二男の学校での不適応も改善できていた可能性を否定できない。つまり、相手方や裁判所は、客観的には異常というほかない態度を取り続け、事実、二男の不適応は長期化しているんですよね。目を背けて現実逃避するなよ。
最後に、法的にも人道的にも、もっとも大切なのは子らの利益ですよ。
以 上
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
