
楽器のように歌う21世紀のジャズ・ヴォーカリストたちと Introducing マイケル・マヨ with PLAYLIST
マイケル・マヨ(※Michael Mayo 発音的にはマイケル・メイヨかもしれない)というヴォーカリストの声を初めて聴いたのはおそらくネイト・スミスの『Kinfolk : Postcard from Everywhere』だっただろうか。ちょうど、その頃、黒田卓也とどこかで雑談していた時に「最近NYだとマイケル・マヨってヴォーカリストがすごくて話題になっている」って話をしてくれたのを薄っすら覚えている。
ネイトのアルバムでは同アルバムにグレッチェン・パーラトもゲスト・ヴォーカリストとして起用されていて、その後、起用されたニーボディの『Chapter』『By Fire』ではグレッチェン・パーラト、ベッカ・スティーブンスとともに名を連ねていた。
2010年代以降、グレッチェン・パーラト、ベッカ・スティーブンスを筆頭にカミラ・メサやサラ・エリザベス・チャールス、カヴィタ・シャー、もう少しオーセンティックなベクトルだとセシル・マクロリン・サルヴァントやジャズメイア・ホーンなど、圧倒的な歌唱力を持った女性シンガーの台頭があり、彼女らの声がシーンの発展に大きく貢献していた。
”歌”だけでなく、器楽的な”声”の威力と、その声を重ねること=コーラス(実際に複数人の声を重ねたり、多重録音で重ねたり、ハーモナイザーで疑似的に重ねたり、方法は様々なだが)により生まれる響きが複雑なハーモニーを駆使する彼女らの存在は現代のジャズにとって大きな力になった。その声の存在が付与した可能性が作曲家たちのクリエイティビティを刺激し、新たな音楽へと導きシーンを変えた、といっても過言ではないだろう。
だからこそ上記のヴォーカリストたちや彼女たちとコラボレーションしていたジャズミュージシャンのシーンには、普段はジャズのシーンで活動しているわけではないビラルやレイラ・ハサウェイ、ジェイコブ・コリアーやネイ・パーム(ハイエイタス・カイヨーテ)、ミシェル・ウィリス、更にはデヴィッド・クロスビーのようなヴォーカリストたちまでもが度々出入りし、相互にコラボレーションを繰り返している。ヴォーカル表現は21世紀以降のジャズにおける重要な要素になっている。
とはいえ、そういったヴォーカリストたちの登場は決して突然変異的なものではない。様々な形でバンドのサウンドに貢献している彼女たちの歌唱は先人たちの延長にあり、ジャズヴォーカリストたちの進化の蓄積がもたらしたものでもある。
喉を使って発することができるあらゆる音を音楽にしようとした奇才ボビー・マクファーリンや正統派ジャズ・ヴォーカリスト/ソウルやR&B系譜のヴォーカリストの両面で表現を拡張してきたダイアン・リーヴス、7オクターブを超える音域を駆使するラッシェル・ファレル、コーラスワークの可能性を追求してきたマンハッタン・トランスファーやニューヨーク・ヴォイセスといったヴォーカル・グループなど、80年代以降の様々なヴォーカリストたちのチャレンジが礎になっているのは他でもない彼女たち自身が言及している。そういった歴史的な連続性としてヴォーカリストたちの進化を見てみても面白い。(※文學界 2020年11月号 JAZZ×文学 掲載の論考”ジャズに言葉は不要なのか?”も参照いただけると嬉しい)
そのあたりのグレッチェン・パーラトやベッカ・スティーブンスらに代表される21世紀以降のテクニカルなヴォーカリストについては以下のプレイリストにまとめてみたので聴いてみてほしい。
21世紀以降のアメリカのジャズシーンに大きな貢献をしているセロニアス・モンク・コンペティション(※現在はハービー・ハンコック・コンペティションに名前が変わっている)のヴォーカル部門で2015年にジャズメイア・ホーン、2010年にセシル・マクロリン・サルヴァント、2004年にグレッチェン・パーラトが優勝している。賞金やメジャーデビューの権利が与えられるだけでなく、若手の登竜門として、その後のキャリアのステップアップにも繋がるこのコンペティションで、若手たちがその技術や音楽性を競い、切磋琢磨してきたこともシーンのレベルの向上に一役買ってきたように思える。
特に器楽的な歌唱法とポップなセンスを兼ね添えたグレッチェン・パーラトの登場は21世紀のジャズ史にとって大きな転換点だったと僕は考えている。ジャズがハイブリッドになっていき、新たな表現を見つけないと自身の音楽を形にできなくなってきていた多くのジャズ・ミュージシャンたちがグレッチェンの声を求めた。そして、2010年代以降、グレッチェンが切り開いた場所にベッカ・スティーブンスやエスペランサ・スポルディングと次々と魅力的な声が現れた。特にベッカ・スティーブンスはグレッチェンとは異なる方向性のテクニックと声量豊かでエモーショナル且つパワフルな歌唱、そして、ジャズ・ヴォーカルというよりはUSフォークやUKトラッド、インディーロックなどに親しんできたセンスがもたらすハイブリッドなサウンドのへの対応力により、グレッチェン並み/もしくはグレッチェン以上に多くのアーティストの作品に起用され、ジャズミュージシャンたちが思い描いた声を使った表現を具現化させ、シーンを前進させた、と言えるだろう。このプレイリストはそんな「グレッチェンやベッカが開拓してきた流れと、その後」といったコンセプトで作ったプレイリストだと思って聴いてもらえると嬉しい。
で、そんなジャズ・ヴォーカルのシーンに2010年代末に突如現れた新星がマイケル・マヨだ。
男性でもテクニックを持ち合わせた個性的なヴォーカリストはいるにはいたが、人数は少なかった。ベテランだと前述のボビー・マクファーリンやヴォーカリーズの名手カート・エリング、もう少し下だと声楽寄りのセオ・ブレックマンなどがいて、コンテンポラリージャズな領域だとピーター・エルドリッジ、アフリカ音楽経由の個性派リオネル・ルエケなどがいた。
ただ、意外といなかったのが器楽的な歌唱とR&Bなどの領域を横断する男性ヴォーカリストだった。もちろんグレゴリー・ポーターやホセ・ジェイムス、クリス・ターナーらは今のジャズシーンを代表する男性ヴォーカリストで、彼らはR&Bやヒップホップにも造詣が深い。とはいえ、グレッチェン・パーラトやベッカ・スティーブンスのような器楽的な歌唱でバンドのアンサンブルに加わるとなると少し適性が違う。その意味では器楽的な歌唱が異常に上手く、R&Bなどのポップな領域にも親和性があるマイケル・マヨは今までにいなかったタイプの男性ヴォーカリストだと言えるだろう。
そして、”器楽的”の次元ではなく、楽器と全く同じ立場でバンドのアンサンブルに加わり、もうひとりの管楽器としての”楽器そのもの”の役割と担うことができる驚異的なテクニックは歌唱力の水準が高まっている現在のシーンの中でも頭ひとつ抜けている。ベン・ウェンデル『High Hearts』やクリスチャン・ユーマン『ALLEMONG』でのパフォーマンスを聴けば一目瞭然だ。
そして、もう一つ付け加えるならばコーリー・スマイス『Accelerate Every Voice』。コーリー・スマイスはアンソニー・ブラクストンやタイショーン・ソーリーらとも共演するピアニストで、このアルバムは声をテーマにした現代音楽とも親和性が高そうな作品で、ここではジャズというよりは声楽的なヴォイス・パフォーマンスを聴くことができる。声だからこそ表現できる様々な音色や響きやテクスチャーを喉から発生させている。
その圧倒的なレベルの高さと、対応できる音楽(ジャンル)の幅の広さなどを考えるだけでも、マイケル・マヨはアメリカのジャズシーンを刺激する存在になりそうな予感がある。そして、ハードルが引き上げられれば、また次の世代はそれを乗り越えてくる。またその活動を逐一追いたくなる楽しみなアーティストが増えて、僕はワクワクしている。
⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩
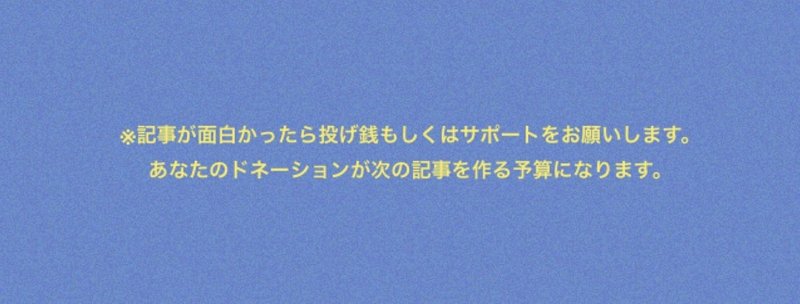
ここから先は
¥ 100
面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。
