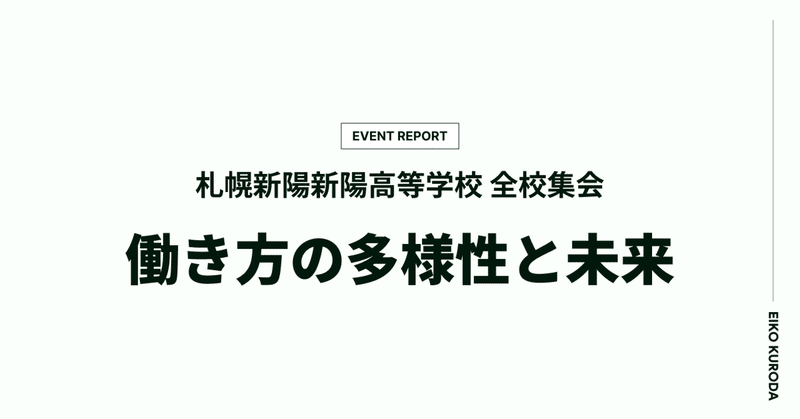
【イベントレポート】働き方の多様性と未来@札幌新陽高等学校 全校集会
こんにちは!
複業人材と企業・自治体をWEB上で繋ぐマッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営している株式会社Another worksの社長秘書、えいちゃんです!
新型コロナウイルスの影響や、従来のオフラインが基本の社会からオンラインという手段が生まれたことにより、複業やキャリア、新しい働き方への関心が高まっています。そんな中、株式会社Another worksでは、代表の大林さんが多くの登壇機会をいただいております!中でも今回は、2022年12月にお話させていただいた札幌新陽高等学校でのイベントレポートをお届けします!!
札幌新陽高校の全校集会にて、高校生650名に向け、校長の赤司さんと対談をさせていただきました!
将来の働き方やキャリアに悩むすべての人に是非読んでいただきたいです!
2023年も複業が当たり前になる世の中に向け、啓蒙活動を続けております!登壇機会をご検討いただける皆様、下記よりご連絡お待ちしております🌸
札幌新陽高等学校 全校集会 多様性対談
札幌新陽高等学校 赤司 展子校長 × 株式会社Another works 大林 尚朝 代表
参加者:札幌新陽高等学校 生徒650名および教職員の皆様
テーマ:働き方の多様性

赤司校長:
大林さんの仕事について教えてください!
株式会社Another worksという会社で、代表取締役を務めている大林です。
複業したい人、現在は50,000名以上がプラットフォームに登録し、複業人材を探している企業とマッチングするというビジネスをしております。札幌新陽高等学校様とは、このビジネスの一環で、学校現場での複業人材登用を共に推進するために連携協定を締結しています。
複業という文化を作っている私から見て、まず言えることは、皆さんが社会人になるときは、1人が1社で働くという時代は、とうに終わっているということです。
今、人口が減り続けていく中で、1人が何社もかけ持たないと労働力が不足していく時代です。国が打ち出す施策にも、「副業・兼業」というキーワードが多数出てきており、企業の副業解禁を促進するようなメッセージも含まれています。
今、働き方や雇用のあり方にも「多様性」が必要とされているのです。
そこで、この複業という新しい働き方を、いかに日本全国、企業、自治体、学校など垣根を超えて、人材を移動できるのか、いわゆる流動化できるのかを考え、複業のサービスを運営しています。
赤司校長:
26歳で起業されたとのことですが、なぜ起業されたのですか?
私は、実は、26歳で起業したいと思っていました。
元々歴史が好きで、日本史も世界史もどちらも好きなのですが、経営やビジネスをしていると過去の偉人から学ぶことが多くあります。
学生の皆さんは受験勉強など日々辛いことや不安なことがあると思います。
ビジネスにおいても同様です。
では、なぜ不安なのか、それは経験したことがないからだと考えています。
ではどのように不安を解消すればよいのか。そこで、過去経験したことがある人、その中でも大きな事象を扱い影響を及ぼしてきた昔の偉人が参考になると思い、学んできました。これが昨今叫ばれている、文学、リベラルアーツというものだと認識しています。
そんな中、私は吉田松陰という人物が好きです。彼は、明治維新の最中、外国の文化を次々に取り入れていなくてはならない時代に、黒船が来航し、他の人々が恐れおののく中、26歳で黒船にのろうとした人物です。
彼は、自らが外国に行き、海外の文化を日本に取り入れなければ、日本を変えることができない、日本を多様性のある国へと成長させる維新を起こすには外国のことを学ばなければならないと思い、行動しました。
吉田松陰が、日本を変えるために行動した26歳というタイミングで、私も日本の雇用という働き方に維新を起こそうと思い起業しました。
赤司校長:
26歳で起業すると決める、というのも新しいキャリアプランの在り方だと感じました。一方で、労働市場を変えようと決意することは、やはり珍しいのかなと思います。
私も、自分の働き方だけではなく、社会における働き方への柔軟性、あるいは窮屈さに課題を感じることは多くありますが、それは働いた経験から分かったことです。
大林さんはなぜ社会に出る前から「働き方」をテーマに起業をする決意を固めたのでしょうか。
私は、自分の中で原体験と未来を見据えて考えています。
私の原体験は、大分の田舎で生まれ育ち、父親が会社経営をしていたという点があります。皆さんと同じ高校生の頃は、どこか漠然と、自分はいつか起業し、父親のような人生を歩むだろうと考えていました。
父親を見ていると、周りにいつも従業員がいて、彼らの労使の関係、労働者と使用者の関係はどうなってるんだろうと疑問に思い、父親が通っていた早稲田大学の法学部に進学しました。
法学部では、法律、特に労働法を勉強を勉強し、突き詰めていった結果、正社員にこだわり続けるような時代ではなくなっていくだろうという考察に至ったのです。複業で関わったり、プロボノというボランティアで関わったり、1カ月や半年という期間だけ関わってもらったり、という多様な働き方になっていくと考えたのも、父親の背中を見て、そして大学での学びが根底にあります。
一方で、私も高校生の頃は学生でした。漠然とした将来への不安を抱え、高校3年間を過ごし、早稲田大学へ進学したい一心で受験勉強をしていました。
皆さんのなかにも、未来に対して漠然とした不安を持つ人は多い思います。
大学を目指す生徒さんも多いとは思いますが、高校を出た後の世界はとても楽しいです。好きな人と好きなだけ時間を過ごし、学びたいことを学び、会いたい人に会い、ビジネスを学ぶこともできます。近年は学生起業も増えてきています。
皆さんが向かう未来には、明るい通過点もあります。不安を持ってる方は、できれば明るい未来を想像しながら、日々生きてほしいです。
そして、大学を経て、働くことになる未来は想像できるでしょうか。
高校3年生の人にとっては5年後、高校1年生の人にとっては7年後。
その未来は、結論、全く分からないというのが答えです。
現代のビジネスの世界で起こっていることは、過去例を見ないスピードでの進化です。東京で従業員のいない店舗があったり、自動運転を実証実験する街が出てきたりしています。
では、なぜそこまで進化が早いのか、間違いなくインターネットの普及があります。2008年に発売されたiPhoneをきっかけにスマートフォンが普及し、日常生活が圧倒的に変わり、便利になりました。
そして、世界的パンデミックとなった新型コロナウイルスは、誰も予想することができなかったでしょう。もしかしたら、5年後、7年後、予測できない事態が起こる可能性もあります。将来何が起きるかは、全く分かりません。
そんな中で、高校時代の自分に言いたいことは、未来に不安を思い、未来を憂う必要は全くないということです。
ただ、変わらないものはあります。
労働力人口の減少や少子高齢化をし続ける日本の未来は、何がどうあっても絶対に変わらない普遍の事実だと思います。人口4,000万人以上の国の中で、日本が圧倒的に1番の高齢化国です。2番がイタリアですが、圧倒的に1番です。
つまり、この変わらないものに目をつけて、「複業」という領域で起業したというのが起業の背景です。近年、ようやく政府が「副業・兼業」を推進し始めましたが、なかなか政府の歩みは遅いのが実情です。そこで、起業家として私が日本の雇用を変えていく、そう決意しました。
赤司校長:
私自身も校長として複業をし、”複”業という言葉を使っていますが、”副業”と聞くと、本業というメインの仕事があり、隙間時間で何かをしたり、お手伝いをするというイメージがまだまだ多いと思います。
度々出てきている複業という言葉において、複数の”複”という字を使っているのはなぜでしょうか?
”複”業は、副収入を得るためだけの仕事ではなく、仕事にメインやサブを分けず、複数の仕事、複数の居場所、そして複数の仕事への目的を持ってほしい、という意味で定義しています。
「複業クラウド」というサービスは、複業したい方が、クラウドというITの力を使って複業ができる、複業の社会的インフラになることを目指し、名付けました。
「複業クラウド」は、月額でお金を支払い、サービスを利用するSpotifyやNetflixの複業採用版だとイメージしてください。
複業したい方50,000名が登録し、複業を探すためにインターネットサービスに登録し、複業を採用したい企業は月額数万円の月額費用をお支払いいただくだけで何名でも採用できるというサービスを日本初で作りました。
赤司校長:
複業したい人と採用したい企業の仕事の出会いの場なのですね。
どんな方が、複業を探しているのですか。
企業にお勤めの方も、フリーランスの方もいらっしゃいます。
以前は終身雇用が一般的でしたが、1人が1社で勤め上げる時代は既に変わってきています。当時の時代には合っていたものの、現代に立脚すると合っていないためです。
働き方の多様化というキーワードがあるように、複業はお金稼ぎのためだけではないと思います。そもそも、お金稼ぎだけが働く目的ではありません。
働く先に何があるのかというと、ウェルビーリングというような幸せだと考えています。1回きりの人生で、その人生の期間の中でいかに幸せに生きるかです。
お金のために働き続け、50代、60代になってお金を持っていても、20代、30代、40代が楽しめなかったというという後悔があれば、その時間はいくらお金を払っても取り返すことができません。
では、いかに幸せな人生を掴むのか。1社に所属して働くことはもちろん、その会社だけではできないことをしたいと思った時に、もう1社複業で居場所を増やしてみるという選択肢があります。また、自分の趣味で複業先を選ぶことで金銭報酬ではない感情報酬を得ることができます。例えば、サッカーが好きで、何かサッカーチームに関わりたいというときにスポーツチームで複業をすることができます。札幌新陽高等学校様でも、何か教育に何か携わりたい、無償でもいいから時間を使いたいという人が、複業で参加しています。
本当にやりたいこと、挑戦したことを、転職したりせず、実現できるのが複業です。
赤司校長:
札幌新陽高校で募集したところ80名を超えるエントリーがあり、本当に驚きました。
先ほどの感情報酬という言葉は、まさにウェルビーイングが満たされるということでしょうか?
まさにおっしゃる通りです。私も大分県で生まれ育ち、将来大分のために、何かしたいと思い続けている人間です。
例えば、皆さんのなかにも、北海道を出て東京で働きながら、ただ北海道に何か関わりたいとか、何か恩返しをしたいみたいな人は出てくると思います。
そういう時にお金ではなく、自分の感情を得るために複業で関わることができます。
赤司校長:
複業という働き方があることで、同じチームのメンバーが正社員だけでなく、複業や外国人にながら関わる人など、多様な文化や地域の人たちが集まるようになると思います。
一方で、価値観や考えが違うことで共に仕事をする難しさもあると思いますが、だからこそ多様性が深まると思います。
生徒がディスカッションをする中で、意見が合わず、どう乗り越えるかが難しいのですが、仕事の中ではどう解決しているのでしょうか。
これはビジネスでも難しいことだと思います。株式会社Another worksの場合は、「挑戦するすべての人の機会を最大化する」ために集まり、存在しているという共通の目標があります。その目標に向かうための仲間を集めているのです。
また、コミュニケーションで一番重要なのは、会話の場を強制的に設けることだと思います。その場で、ただ会話をするだけではなく、なぜこの会社に入ったのかとか、何を楽しみに生きているのか、何が弱みなのか、逆に何が強みなのかなど、お互いを理解するやり取りをします。また、それはチャットではなく、対面で肉声で話し合うことです。
顔を見て話すからこそ伝わり、テキストだけでは伝わらないことも多くあります。テキストコミュニケーションでは、ビックリマーク、ある、なしで伝わり方が変わったり、なるべく簡潔に伝えないと思うと、無機質な文章になってしまったりということがありますよね。
だからこそ、対面で、相互理解を深めるコミュニケーションが欠かせないと考えています。
赤司校長:
最後に生徒に向けたメッセージをお願いします。
一番伝えたいことは、未来を憂うことなく、今を楽しむことです。
これから、受験や北海道を離れ挑戦する人もいるでしょう。将来への言語化できない不安や、環境が変わることへの不安もあると思います。
しかし、誰も未来は予測できず、過去を憂いても何も変わりません。全力で今を楽しむことに尽きると思います。
また、もう一つのキーワードとして、「挑戦」があると思います。
挑戦とは、理想や夢を掲げ、現実との差分を理解し、その差分を埋めるために覚悟を決めて、努力し続けることだと思っています。
例えば、将来起業したいという夢があれば、今の自分に足りていないところを理解をした上で、覚悟を決めて努力をすること。この大学に行きたいという理想夢があれば、その大学に行くために何ができるのか、今が何が足りていないのかを知り、差分を埋めるために、覚悟を決めて努力すること。
挑戦は、非常にシンプルです。
以上、多様性対談のイベントレポートでした!
最後までお読みいただき、ありがとうございます!
札幌新陽高等学校 赤司校長の目線でのnoteはこちら!
Another worksの記事10選もnoteにまとめています!
EIKO KURODA
▶EIKO KURODA プロフィール
▷Another worksサステナビリティ
▶取材や登壇のご依頼はこちら
▷Another worksや私とお話してくださる方、お気軽にご連絡ください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
