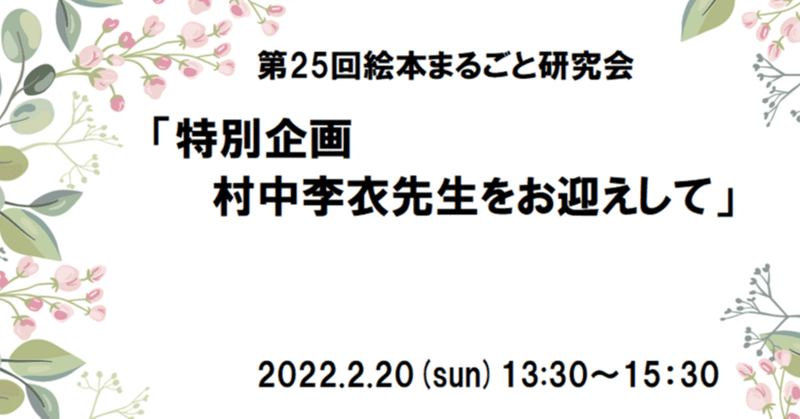
第25回絵本まるごと研究会
2022年2月20日に開催した「第25回絵本まるごと研究会」は、特別企画として絵本専門士養成講座でお世話になった村中李衣先生をお迎えしました。
村中先生とのディスカッション
1.最近気になっている話題について、村中先生よりコメントをいただきました。
話題その1:日本の絵本と世界の絵本を比較して、日本の絵本が世界に通用するのか。日本の絵本の現状について。
海外の絵本が翻訳紹介される場合、評価の定まったかなりレベルの高い絵本であるという前提があるので、そのまま日本で手に入る翻訳絵本と日本オリジナルの絵本を比較することは難しいです。
ただ、先日翻訳者の方々のフォーラムで以下のようなことが報告されたのですが、私は??と首をかしげました。それは、「海外では社会的弱者の問題を描いた作品でも、弱者を理解するという第三者的な視点でなく直接当事者自身がその痛みを生きる姿が描かれている」という発言です。いかにも日本はそういう意味で遅れているという指摘でしたが、果たしてそうかな?日本でもそうした問題意識で描かれている作品は多くはなくてもちゃんとあるのにな、もっというと、そういう日本の作品にもきちんと目を向けてもらって海外にも積極的に紹介してもらわないといけないんじゃないかと思いました。そのためには、編集者やそれぞれの出版社の営業スタッフも含め、手渡し手の努力が求められると思います。
また、翻訳紹介する際に日本のオノマトペや、日本の文化的習慣を伝える難しさもありますから、立場の異なるもの同士のさらなる視点開拓のための勉強会をするのもよいかもしれません。
2.明石市で数年前から実施されている保育絵本士の養成講座があります。ここでは、絵本を手掛かりにして保育を豊かにする取り組みが行われています。そこで、受講生である保育士さんたちの主な興味関心は、「年齢に合わせた絵本の選び方」や「表現の読み分け方」といった実際のノウハウを求めるものでした。本当に大切なことはこうしたノウハウだけを習得することではないのはもうみなさんはお分かりだと思いますが、絵本専門士さんたちが、こうした「読み分け」をどのようにするかというような質問を受けたらどのように答えられますか?という村中さんからの投げかけで改めて一緒に考えてみました。
たとえば、『三びきのヤギのがらがらどん』を大中小のヤギとトロルの読み分けを質問されたときにどう答えますか。
(会員の答え)
・テンポや重みを変えながら、だんだん重くしていく。
・自分が感じたように、それを伝えるように読んでくださいという。
しかし、大きいヤギのがらがらどんのしわがれ声とトロルの声が表現分けしにくい。
→村中先生は、息の集め方を工夫することで、声の高さを無理に作り分けなくても、違いが伝わると教えてくれました。そしてその息の集め方を実際にやってみました。 小さいヤギは、人差し指に息を吹きかける感じで。中くらいのヤギは、手のひらに息を当てる感じで。大きいヤギはシャベルで掘るような感じで。トロルは首を回して沼の中にぬらぬらいる感じで。心の中でどう息を集めるか、自分の息をどう整えるかで、自然と読みが変わってくることを実感できました。
(おまけのはなし)
『バナナです』は、対象が誰なのかで、読み方が自然に変わります。
・中学生に読む。斜めに構えて生きにくい感じで。
・赤ちゃんに読む。ほっこり手のひらに言葉を載せる感じで。
つまり、どんな絵本でも、作品の主人公との響きあい、聴いてくれる人との響きあい、自分の内なる意識との響きあいなど、さまざまな世界との相互交流の意識が大事です。相手と息がどのように合うのか、まさしく「息が合う」状態を作ることが大切です。
(学生への読み方アドバイスの例)
読みを指導するときに、自分にもできるんだと気づいてもらえる導きをしたいと思っています。たとえば、味もそっけもない読み方をする学生には「あなたの今の読み方は店員さんがきれいな手袋をはめてショーケースの中の品物を見せている感じだね。できれば、ショーケースの中からひとつずつを出して手に乗せて見せてあげるように読んでみようか」と言いながら、実物を掌の上に乗せるような読みを体験してもらいます。こうした一見まどろっこしいような比喩的に思える説明が、却って、「新しく生きる場を与えられたような気持ち」を起こさせるのか自信がなくて不安な消え入りそうな学生もみるみる読み方が変わっていきます。自分の今の読みは〇か×か、とだけ気にしていた心が解放されるからでしょうか。
村中先生の読み方へのアドバイスは、的確で、愛情にあふれていて、我々も学ばねばならないことが多くあることを感じました。(大学専門研究員・嘱託講師 森さん)
参加者による発表

『あららのはたけ』(偕成社 2019年)
作:村中李衣 作:石川えりこ
Web 連載として始まった物語のタイトルの最初の案は「うふふののはら」。その後寛容なイメージの「あらら」に変更。連載の読者だった不登校の女の子へのメッセージとして本にされたそうです。
エリのお母さんのモデルが先生ご自身であったり、風の通り道が実話であること、クモの巣の話はある絵本作家さんの言葉であった事など大変興味深いお話でした。特におじいちゃんのモデルであるお義父様のお孫さんへの愛情あふれる畑のエピソードは子どもにかかわる者として大いに学ばせていただきました。子どもの今しか出来ないこと、大切にします。(幼稚園教諭 福羅さん)

『体育がある』(文研出版 2021年)
作:村中李衣 絵:長野ヒデ子)
あこは、4年生。運動が苦手です。こなくていい体育の時間は、すぐにやってきます。跳び箱飛べません、逆上がりできません。そんなあこが心配で、ママは鬼コーチに変身。ママと体育の練習をします。でも、成績はC。やはり、体育は好きになれません。二学期に入ってすぐ、大好きなおばあちゃんが遊びに来たその夜、事件がおこて…。
体育が苦手な子どもたちへ、村中先生からのエールが届きます。そして、子が親を、親が子を思う気持ちが優しく伝わります。ぜひ、親子で読んで欲しい1冊です。(学校司書 増田さん)

『はんぶんぺぺちゃん』(佼成出版 2008年)
作:村中李衣 絵:ささめやゆき
私は、今回どうわのとびらシリーズから「はんぶんぺぺちゃん」という本を選びました。
村中李依先生の文章描写が、その瞬間瞬間をとらえていて、はっきりとその情景が浮かんできました。特に甘露堂の陳列ケースに並んだお菓子の様子が手に取るように伝わってきて、和菓子の色合いや風味まで感じて口の中がほんのり甘くなりました。また、昔のガラスのショーケースは木の枠でできていて、力を入れて磨くとチャリッときしむ音も表現されていて五感に響きました。村中先生の描写があまりにも鮮明なのでどんなことに心を配っていらっしゃるのかお尋ねしました。
村中先生は、「物を見た瞬間にシーンの描写がそのまま心の中に残るの。」とおしゃいましたが、実は、それだけではなく誰でも安心するような言葉を使ったり、その言葉で書いた気にならないように、思いを深めて深めて、言葉を選んでいると教えてくださいました。現在の作文教育では、こじゃれた言葉や大人に褒められるような言葉を子ども達が使っているように思える。文章が上達するより世渡り上手になる・・・。どういう言葉に人が興味を持つか?ではなく、内側の内側の自分の言葉を探して書くことが大切だと思いますと、お話してくださいました。今の子どもたちは大変多忙で今を生きるに必死。「未来は近づくと夢は遠ざかる。将来の夢は同じ速度でやってこない。」という村中先生の言葉が印象的でした。また、村中先生の恩師でもある村田喜代子さんの傑作短編集「八つの小鍋」をご紹介してくださいましたので、ぜひ読んでみたいと思います。(カルチャースクール講師 森さん)

『哀しみを得る 看取りの生き方レッスン』(かもがわ出版 2017年)
村中李衣/著
クモ膜下出血により治療介護状態になった筆者の母と家族。愛も葛藤もある母への想いや個性的な父、夫、息子、娘と織りなす看病、介護、看取りの日々。看取りという人生の大きな節目の出来事を「生きることのレッスン」ととらえ、そのレッスンをひとつずつ超えていく過程が描かれています。それぞれに真剣で、大変そうでありながら、やわらかなユーモアに包まれています。
「歩かざるを得なかったその道は、いのち咲く道でした。」
現在、義母と同居して介護している私は、この本のはじめにでてくるこの言葉に、いつも励まされています。
「哀しみを得る」事でしか見えないものがあるのでしょう。この現状の中で前を向いて、“哀しみの向こうへ”進んでいきたい思います。(図書館司書 野村さん)

『こころのほつれ、なおし屋さん。』(クレヨンハウス 2004年)
村中李衣著
これは絵本でも児童文学でもなく、村中先生が大学の授業でおこなったワークショップの記録です。若い学生たちが先生の出す課題に対して、たぶんたいして真剣でもなく始めて、でも取り組むうちにだんだん自分や他者の心の奥底にあるものと向き合い、今まで気づこうともしなかったことに気づき得ていく様子が赤裸々に綴られています。
数多くの著書の中、「村中李衣」という人そのものをもっと知りたい、近づきたいと思って読んだ1冊でした。読みながら、個人ではなく相手あってこそたどり着く場所があるのだと感じました。これは絵本の読みあいにおいても同じです。人はひとりではない、時に面倒で苦しくても、感じ合い、伝え合うことで生まれる確かであたたかなもの。村中先生の著書にいつも感じられるものは、読みあいの場にも共通する大事なことなのだ、と自分の中でパズルのピースがはまったかのように得心しました。
先生は、ワークショップには決まった答えも結末もなく、ただどうなろうと学生たちを受け止める「覚悟」を持ってやっていた、とおっしゃいました。どんなときにも受け止めてもらえるという安心感が、学生たちにとっては自分の気持ちを受け止めるに至るまでの灯台の光だったのだろうと思います。灯台には程遠いかもしれないけれど、私も周囲の子どもたちの心にろうそくの灯りくらいは灯せる人間でありたいと強く願いました。(子育て支援室スタッフ 石坂さん)

『くつしたのはら』(日本標準 2009年)
文:村中李枝 絵:こやまこいこ
山口県の梅光学院幼稚園による「くつしたのはら」の実践記録を絵本にしたものです。
たいよう組は,ごきげんはらっぱまで出かけます。今日は長靴をはいて,その上から古い大人の靴下をはいて…なんかへーんなの!と子どもたち。たくさん歩いて,野原でいっぱい遊んだあとは、脱いだ靴下を大事に幼稚園に持って帰って,植木鉢に植えました。
それから毎日,みんなで植木鉢のお世話をすると…おやおや、靴下から小さな芽が出てきましたよ。同じ野原を歩いても,出てくる芽はいろいろな形,違う芽。不思議。
でも,ひとつだけ何にも出ていない植木鉢があります。まさとくんの植木鉢です。まさとくんは,どうしてもお母さんの靴下から芽が出てくるのが嫌で,土をぎゅうぎゅうに押し固めていました。でも,土を掘るとそこには小さな芽が!あれほど嫌がっていたのに,今度はそっと土をかけたまさとくんでした。
友達の数だけ広がる“くしたのはら”。
ご家庭でも実践してみてください。どんな芽が出るかお楽しみ!(出版社営業 清水さん)

『たなばたのねがいごと』(世界文化社 2108)
作:村中李衣 絵:えがしらみちこ
七夕にねがうことは、一般的に、「○○になりたい」とか、「○○ができるように」とかの願いがよく見られる。しかし、あおいちゃんは、先生にいわれた「こわれたりなくなったりしないもの。じかんがたてもだいじなもの」ってなんだろうと一生懸命考える。とうとう家族への思いの大事さに気づいたあおいちゃん。画面いっぱいの笑顔に癒された。実際のモデルはあったのかとの疑問に、「じいちゃんが長生きしますように」との短冊のエピソードを紹介していただいて、また、さらにほっこりした。(大学専門研究員・嘱託講師 森さん)

『「こどもの本」の創作講座』(金子書房 2021年)
著:村中李衣
本書は、絵本作家を目指す方だけでなく、お仕事でプレゼンテーションする方や、誰かに何かを伝える機会の多い方にお薦めしたい一冊です。自分の「癖」や、相手に分かりやすく伝わる「筋」に気付くことができます。絵本がお好きな方も、ワークショップに取り組んでみてください。これまでに気づかなかった絵本の魅力に出会うことでしょう。
私は、絵本の擬人化に興味を覚えました。本書を読んで、村中先生の著書には、キャラクターが擬人化された作品が少ないことに気づいたからです。この質問に村中先生は、『日本語ーことばは時をこえる!』(玉川学園出版部 2014年)で擬人化に取り組んだ制作秘話をご紹介くださいました。擬人化の効果や、どのような作品が擬人化に適しているのかなど、さらに考えてみたくなりました。(財団職員 矢阪)

『こくん』(童心社 2019)
作:村中李衣 絵:石川えりこ
主人公の歩行器を使う少女ちさとが、「こくん」とうなずいて自分を試すようにチャレンジしていく姿、私たちを勇気づけてくれます。絵本は読み手を想像の世界に引き込みます。読み手は今の自分と重ねて読んでいくのではないでしょうか。大学生が卒業するあなたに贈りたい絵本に選びました。(大学教員 德永さん)

『うんこ日記』(BL出版 2004年)
作:村中李衣 絵:川端誠
あとがきに、村中先生と川端先生が「絵にまつわるエピソードを聞いて」絵本にしたとある。どのようなエピソードによりこの絵本を制作することになったかお聞きしたいとの質問に対し、村中先生から次のようなお話があった。
施設にいる子どもがたった1日お母さんと過ごした日に、たぶんお母さんの手作りではないファミレスなどで一緒に食べた、ハンバーグやニンジンなどの入った大きなバーバパパのようなうんちの絵を描いた。それは、お母さんと一緒に過ごした子どもにとっては誇らしい記憶である。その絵を基に、一般の子どもを主人公にした、お父さんも登場する絵本にした。
お正月とお盆の時しか一時帰宅できなくても2人の家族での文化がある。それぞれの家庭の文化を描いて絵に込める。意味のある作品を創りたいと川端先生はおっしゃっている。(学校司書 横田さん)

『うんこ日記』(BL出版 2004年)
作:村中李依 絵:川端誠
食育絵本だと思っていた「うんこ日記」が生まれた経緯を、「絵本の読みあいから見えてくるもの」(村中李依 ぶどう社 2005年)で知りました。母親の愛情を渇望していたしょうへいの「消化したんだから全部自分のものだ!」という強烈な独占欲に気づき、驚きました。
先生のお話を聴いて、この作品に愛情に溢れた家族を描かれた理由がわかった気がします。「最終的には子どもは自分の力で変わっていく」という子どもへの信頼と希望、「家庭」という一番小さな単位にそれぞれの文化がちゃんとある幸せ…そう考えると、生きた証である7段うんこが神々しく思えます。(中高図書室司書 坂本さん)

『あららのはたけ』(偕成社 2019年)
作:村中李衣 絵:石井えりこ
この作品を読み、私は、登場人物一人一人の生きていく力、生きていこうする力を感じました。エミの、考えて行動する力。えりの、気づき考える力。けんちゃんもカズキも、弱さや悲しさもあるけれど、それでも変わっていこうとする柔らかで強い力。おじいちゃんの、おばあちゃんの「生きる」も自然と共に生きていくという「生きる」も受けとめる豊かな力等々…それらの力が互いに関わり合うことで、より強く深くなっていくのではないだろうか…そんなことを感じさせて貰いました。
村中先生のお人柄が伝わる、温かで前を向くことのできる素敵な作品だと思いました。(小学校教員 村田さん)

『みんがらばー!はしれはまかぜ』(新日本出版社 2016)
文:村中李衣 絵:しろぺこり
「絵本を読む」とは、自分との対話なのだと感じました。「自分の枠」の中で終わらせることもできるし、その枠を超え先が見えない大冒険に旅立つこともできる。どちらの道を選ぶかは、自分。とはいえ電卓を弾いて導き出す答えとは異なり、答えが見えない選択をし続けるしかない。苦しいこともあれば、楽しいこともある。どれも自分であり、その自分の先に何かがある。良い悪いで分けず、その瞬間の自分と丁寧に向き合うことが読みあいへと繋がっていくのではないか。村中先生のお話から、そう感じました。(認定保育園 園長 藤得さん)

『絵本の読みあいからみえてくるもの』(ぶどう社2005)
著:村中李衣
私が絵本に携わるうえで、バイブルとなる本です。絵本を「読みあう」こと、思いを共有することによって、その人がその人らしく生きていけるように寄り添うこと。
図書館利用者の方の悩みは「読み聞かせがうまく出来ない」「聞いてくれない」という、読むこと聞くことに重点を置いている内容が多いです。そんな時、この本で紹介されている『がたんごとんがたんごとん』の読み方のバリエーションをお伝えすることで、絵本を一緒に読むことの楽しさ、コミュニケーションの大切さに目を向けて頂くことが出来ています。
『うんこ日記』は主人公にとって「うんこ」の絵が「自分の命を生きていくことの頼もしい宣言」に思えるという先生の言葉に、これは、絵本で伝えていける大事なメッセージだと感じ、この思いをたくさんの人と共有したい!「うんこ日記大会」を開催したいと思いました。(図書館勤務 舘向さん)

『そっちへ行ったらあぶないにほんご』(草土文化 2002年)
著:村中李衣 イラスト:つだかつみ
『ちいさいなかま』という主に保育者と保護者を読者に想定した雑誌に4年間連載されたエッセイの中から、村中先生が選択して1冊の本にまとめた書籍です。「やっぱりヘン」「こどもへのまなざし」「であえたしあわせ」「たいせつななにか」の4部に分けて編集され、ご自身のお子様2人や旦那様等のご家族のエピソードも沢山出てきます。
私が1番心惹かれたのは(すなおないい子)2番目は(はるよこい)3番目はこの2つ以降全て…。日本語が本来持っている力、日本語で人と人との関係を作っていくことのむずかしさやおもしろさを、改めて鋭い文と愉快なイラストで気付かされました。(保育者養成校教員 相沢さん)

絵本専門士による絵本まるごと研究会は、絵本・応援プロジェクトに参加しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
