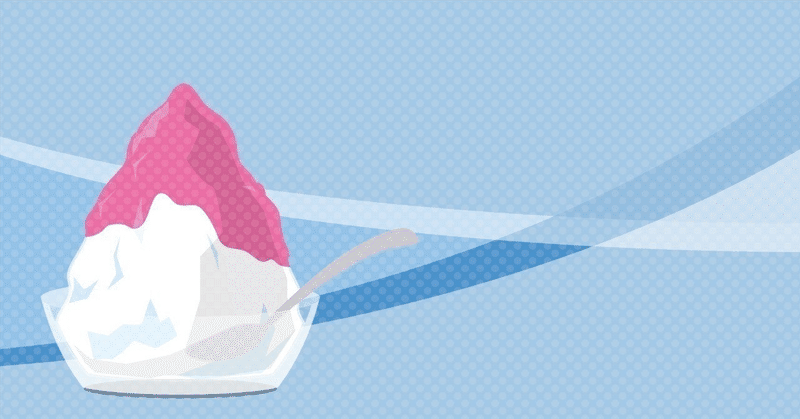
【一般TCG理論】”なぜ回復は弱いのか” MTGの歴史
世界初のTCG、MTG(マジック・ザ・ギャザリング)が発売されたばかりの初期。カードゲームのセオリーがまだ蓄積されていなかったため、色々とバランスの壊れたカードが印刷されたことは有名だ。
Ancestral Recall (青)
インスタント
プレイヤー1人を対象とする。そのプレイヤーはカードを3枚引く。
同じような有名な話に「マジックの黎明期には、ライフ回復が過大評価されていた」というものがある。
MTG初期のライフ回復カードたちは、軒並み異常に重い(コストパフォーマンスが悪い)ことから、TCG初心者が陥りがちなように、開発部には「回復が強い」と認識されていた、という俗説である(しかし、本当にそうだろうか?)
Healing Salve / 治癒の軟膏 (白)
インスタント
以下から1つを選ぶ。
・プレイヤー1人を対象とする。そのプレイヤーは、3点のライフを得る。
・クリーチャー1体かプレインズウォーカー1体かプレイヤー1人を対象とする。このターン、それに与えられる次のダメージを3点軽減する。
Lightning Bolt / 稲妻 (赤)
インスタント
クリーチャーやプレインズウォーカーやプレイヤーのうち1つを対象とする。稲妻はそれに3点のダメージを与える。
これは白の「治癒の軟膏」と対になる赤の火力カード「稲妻」を見ればあきらかである。回復と火力で額面3点だけは同じであるものの、自分から能動的に撃てる、クリーチャーに撃つことでより大きなダメージやアドバンテージに繋げられる火力(赤の稲妻)のほうが圧倒的にバリューが高く、強い。にもかかわらずサイクルカードとして同列に追加されている。するとやはり白の回復は適正コストではないのか?
しかしそう単純ではない。問おう。そもそもカードの適正コストとはなんだろうか?

火力は回復よりもシステム上強いのだから、3点火力のサイクルカードで刷るべきカードは8点回復くらいじゃないか?という考え方は妥当だろうか。
ボードゲーム設計のセオリーとして「ゲームには終わりに向かう性質を持たせるべきである」というものがある。
Maroもそう書いている
#5) 勢い
ゲームには、終局に向かう性質が必要である。ゲームが終わるような要素を入れなければならない
別の出典
■収束性
・ゲームは長すぎないか?
・ゲーム中、必ず進行する要素はあるか?
・その要素はゲームの終了と関係しているか?
・ゲームの終了を近づけない得点アクションはないか?
回復のほうが強いとゲームはまったく終わらないので、それを避けるためのある種の不公平性というものは措置する必要がある。
これは将棋を例に出すとわかりやすい。将棋は攻めている方が有利ということが一般的に言われている。受け棋風の棋士は、攻めが有利の環境ではあまり活躍できないので可哀相だ。ここで将棋のルールをより公平にしようと「攻め将棋」と「受け将棋」の強さをバランスすることは誤りである。なぜならそうなった場合、「受け将棋」が得意であるプレイヤー同士で対戦するとゲームは高確率で引き分け(持将棋)に終わってしまうからだ。
現代の将棋は攻め有利であり、トッププロやコンピュータ同士の対局に顕著な先行有利はその副次的な産物であるが、「受け将棋」の棋風同士で対戦しても勝負がつくくらいには攻め有利の環境だからこそ、将棋は歴史上ゲームとして稀にみるほど成功したとも言える。
ゲーム初期の回復カードが異常に重かったのも、ゲームの進行を巻き戻すようなアクションに対してはより慎重になるべきというボードゲーム的に至極まっとうな設計思想が反映されたのかもしれない。とくに初期はカードプールにライフでの特殊勝利や回復によるバフなど回復を直接ゲームエンドへつなげるギミックが存在しなかったので、ライフ回復は本当にただライフを回復するだけだった。
ここまでの論を見ると開発部が合理的に見えてくるかもしれないが、MTGにおけるカウンターポスト(超遅延デッキ)の歴史などを紐解くと、開発部は1ゲームのプレイ時間などに途中まであまり頓着しなかったのではないか?とすら思えてくる。しかしデザイン上何となく回復カードのコストを軽くすることに抵抗があったとしても理解できる。

そこでタイトルの”なぜ回復は弱いのか?”という問いに対しては、「ゲーム設計者にゲームの収束性を弱める行動を強くするインセンティブがないから」という回答を与えたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
