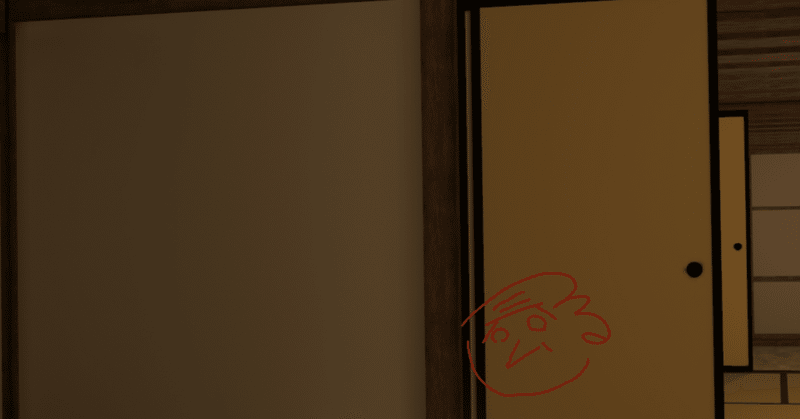
もーちのVR日記その21 表現の自由戦士なんて言うけど
その意見がいかに真理であろうとも、もしそれが充分に、また頻繁に、かつ大胆不敵に論議されないならば、それは生きている真理としてではなく、死せる独断として抱懐されるであろう
表現の自由はどこまで大切なのだろうか?
表現の自由を擁護する立場は表現の自由戦士と呼ばれる。たしかに表現規制に対して毅然と反発し「いかなる不当な欲望によっても表現の自由は制限されてはならないのだ」という当たり前の真理のために戦っていくことは大切だ(どうせ閉経したババアの気に入らないものを貶めたいというだけのわがままをまちがっても社会に通してはならない)。けれどひとつだけ見失ってはいけないことがある。表現の自由がいかに大切であっても、イスラム教にだけは喧嘩を売ってはならないということだ。
表現の自由の大切さを謳うあらゆるアーティスト、表現者がいわゆる「表現の不自由展」といった逆張りめいた活動をしようとも、イスラムにだけは手を出さない理由はここにある。相手が本気だからだ。
「表現の自由は大切だ。だから何者にも屈してはいけない」と、イデオロギーに影響をうけるものたちは観念論に囚われてしまいがちだが、冷静に考えて、イスラム教には屈しろ。イスラム教は表現に対するテロリズムを実行力として保有する組織である。どんなことも言える・できるのはその理念が社会で尊重される限りにおいてで、本気で殺しにくる異文化相手に表現の自由を主張することは無意味だ。むこうが本気で殺しにくるなら表現の自由は道を譲るだけだ。表現の自由戦士は表現の自由聖戦士ではない。大人になりきれない日本の美術家やアーティストだってじつはそれはちゃんとわかっている。
つまりテロリズムには本当に効果があるのだ。その代わりイスラム側は相応の代償を払っている。聖戦は命を捧げるし、イスラム教のイメージは近づきがたいものになる。地球全域でこのコストを維持するのは相当大変だ。宣伝費は高くつく。しかし彼らには譲れないものがあるというメッセージを発信することにいまは成功している。築き上げられたイメージ、むこうは譲らないのだ――じゃあこちらが譲ろう。彼らは得がたいものを得た。バカにされない権利だ。ちなみにリベラルはこのバカにされない権利を希求しつつ敬遠される義務のコストを支払わないどころか逆に愛されようとする病理を負っている。
しかし表現の自由を信じる者たちだってかつては政府の弾圧で命を落としてきたんじゃないですか? 「蟹工船」「党生活者」の小林多喜二だって命を捧げた。なぜ表現の自由戦士がいまや殉教してはならないんだろう? それはわれわれの棲む現代社会が生命の権利を表現の自由よりも上に置いているからだ。いや、理屈っぽく言われなくても分かるはずだ、命あっての自由だと。しかし、それでも表現の自由のために命を捧げるのだと言うなら構わない。かなり怪しいが。
、
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
