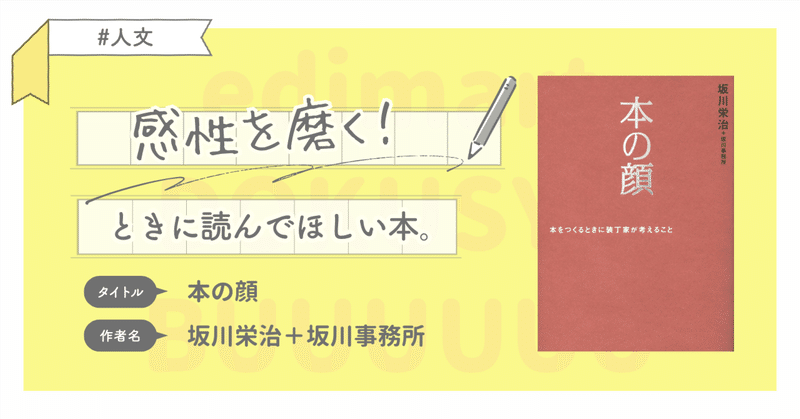
書評『本の顔』/知られざる”装丁”の世界へ
こんにちは。エディマートの堀田です。
『エディマート読書部』のブックレビューをお届けします。
今回ご紹介する本は『本の顔 本をつくるときに装丁家が考えること』。
新生活がはじまり、「今年は本をたくさん読もう!」と本屋さんへ足を運ぶ方も多いのではないでしょうか?ずらっと並ぶ本棚を眺め、なんとなく表紙に惹かれて手を伸ばしてみる…。そんな出合いを演出する本の顔、いわゆる”装丁”について書かれているのが今回ご紹介するこの本です。
本書では日本を代表する本の装丁家、坂川栄治さんが手掛ける数千冊の中から約180冊を厳選。「1冊の装丁ができるまで」を図解した内容になっています。
ふだんは知る機会の少ない装丁の世界。本好きの方、デザイン好きの方はもちろん、広く「コミュニケーション」を仕事にしている方におすすめしたい一冊です。

書籍情報
『本の顔 本をつくるときに装丁家が考えること』
著者:坂川栄治+坂川事務所
出版社:芸術新聞社
発行:2013年10月
この本を手に取ったきっかけ
『本の顔』は2013年10月に刊行されました。私が手にしたのはそれよりもずっと後のことで、古本屋さんで目にしたのがきっかけです。
古本とは思えないほどきれいで、品良く本棚に置かれていました。まさに「装丁に惚れて」この本を手にとり、中身をチラッとだけ見てすぐに購入。編集を仕事にしているので勉強になればと思ったと言えばそうですが、それよりも「これを本棚に並べたい!」と感じた気持ちの方が強かったです。
どんな本?
「人と人とのコミュニケーションが装丁をつくる」それを30年間、第一線で実践してきた坂川栄治と坂川事務所による、装丁の教科書。
『本の顔』の説明にはこう書かれており、各ページには誰もが本屋さんで見かけたことのある装丁がずらっと並べられています。
たとえば、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』や『わたしを離さないで』といった小説をはじめ、絵本ですと『だるまさんが』『にじいろのさかな』、ビジネス書では『スティーブ・ジョブズ 驚異のプレゼン』など。
どうでしょう?きっと読んだことはなくても、本屋さんや図書館、学校などで見かけたことがある本ばかりだと思います。表紙がわかるリンクを貼っておきましたので、よろしければ「これもそうなんだ!」と驚きを分かち合ってもらえたらうれしいです。
おもしろいのが、これら有名な表紙のバリエーション案が一部で紹介されているところ。採用されて世に出たものとガラッと変わっていたり、本当に細かく色や配置が調整されていたりと、どこに、どんなこだわりがあったのか解説文付きで知ることができます。
バリエーション案と採用案を見比べていると、「たしかに採用案の方が良い!」と腑に落ちるから不思議ですね。
わたしの感想
本書の「はじめに」では、こんな一文から書き出されています。
私はどうしてもなりたくて装丁家になったわけではありませんでした。
そこから坂川さんの生い立ち、境遇、経験が語られ、一つひとつのエピソードから仕事に対する信念が伝わってきます。そして何よりも心に響くのが、文章から伝わってくる坂川さんの表現の豊かさ。
坂川さんが「人と人とのコミュニケーションが装丁をつくる」にたどりついた経緯はぜひ本書を手にとって読んでほしいですし、本における装丁の影響力をあらためて感じさせられます。
また本書の帯文を執筆された又吉直樹さんは、こんな風におすすめされていました。
今までに坂川さんの装丁と知らず
本の佇まいに惹かれて買った本が何冊もあった。
豊かで鮮やか。何かを創りたいと思う人、必見です。
───又吉直樹(ピース)
本書で「デザインは強い、デザインすることは楽しい、を伝えたいのです」と書かれているように、日本を代表する装丁家としての30年の積み重ねが丁寧に、分かりやすくまとめられた一冊。
この本も?この本も?となりながら、気づけば読みたい本が一気に増えてしまいますよ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
