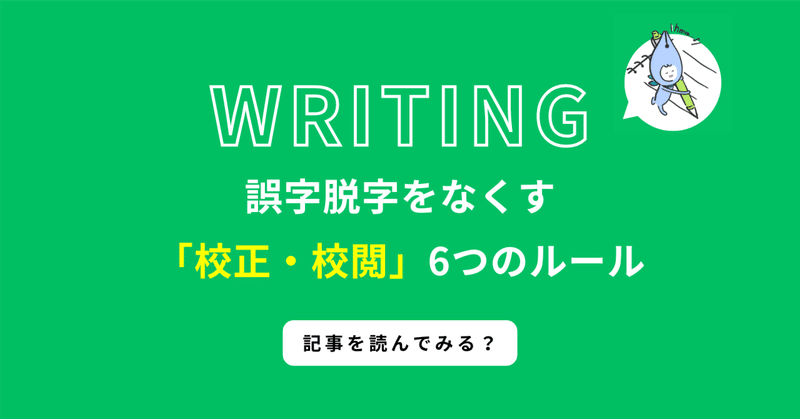
誤字脱字をなくす「校正・校閲」6つのルール
こんにちは。エディマートの須崎です。
新聞・雑誌などの印刷媒体やWeb記事の制作にとって、欠かせない作業があります。それが校正・校閲です。
校正も校閲も、大きな意味では間違いを見つけるための作業。もし間違いに気づかず印刷・製本してしまった場合、簡単には修正できなくなってしまうため、なんとしてでも未然に防ぎたいものです。
もちろん印刷媒体に限ったことではなく、すぐに修正可能なWeb記事であっても、信頼性を高めるためには、校正・校閲は大切な作業だと言えます。
編集者やライターにとって校正・校閲は身近な作業ですが、例えば自社の情報を外に発信する広報の方、オウンドメディアを立ち上げて執筆も自社でやっている企業の方などにとっても無関係な話ではありません。
公に向けて文章を書く人なら誰でも、校正・校閲について知っておいたほうがよいでしょう。
専門でやっているプロの方もいるほど、校正・校閲は奥が深い仕事です。
今回は15年以上にわたり、間違いのない記事づくりをめざしてきた当社がノウハウとして蓄積した、編集者・ライター視点での、校正・校閲のコツや精度の上げ方についてご紹介します。
1.校正と校閲の、共通点と相違点
校正と校閲の違いは?
校正と校閲は間違いを見つけるという点では同じですが、その作業内容は異なります。
校正とは?
誤字や脱字を正す作業。印刷物での校正では、元の原稿と最新の原稿を照らし合わせ、間違いを見つけ出します。
校閲とは?
文章の内容や表現に誤りがないか、事実関係に間違いがないか確認する作業。データなどの確認を行う「ファクトチェック」も校閲に含まれます。
校正・校閲はなぜ必要なのか?
編集者やライターなら誰しもが、大小あれど間違った情報を掲載してしまった苦い経験があるのではないでしょうか。
当社の周りからも、「電話番号を間違えたまま掲載され、その電話番号を買い取ることになった」「イベントの日程を間違えたまま出版されたため、現地で来場者にお詫びをした」「名前を間違ったため、印刷後にシールを貼った」など、ミスによってユーザーに多大な迷惑をかけ、自身も大変な経験をしたエピソードが聞こえてきます。
校正・校閲の作業を怠ると、誤字脱字や内容の矛盾に気づかず、それどころか間違った情報を世の中に発信してしまうかもしれません。それはいわゆる「誤植」と呼ばれ、編集者やライターにとって何が何でも避けたい事態です。
友人同士のメールや個人のSNSなどであれば、あまり気にしなくてよいかもしれませんが、たくさんの人が読む文章ならどうでしょう。
もしあなたが誤字脱字だらけの記事を目にしたら、「ここに書かれてあることって確かなの?」と内容まで疑いたくなりませんか?
実際、情報自体に間違いがあれば、読者にも迷惑がかかってしまいます。
Web記事の場合、紙媒体と違ってすぐに訂正できる特性があり、スピード性がメリットでもあるので、校正・校閲にあまり時間をかけられないのが現状。しかし、信頼性を上げるためには、Web記事にとっても校正・校閲は大切です。
校正・校閲は誰がするのか?
ところで、校正作業は誰がするものなのでしょうか。
大手の新聞社や出版社には校正(校閲という名前の場合も)の部署があり、専任で作業にあたることが多いようです。また、校正・校閲の専門会社に頼るケースや、制作会社などは編集者がその業務を担うことも。
エディマートでは、制作物の規模や予算によって、専門のプロの校正者に依頼をする場合もあれば、社内の編集者が校正・校閲作業にあたることもあります。
校正・校閲では何をチェックするのか?
間違いを見つけると言っても、具体的に何をチェックすればよいのでしょうか。
前述のように、厳密に言えば校正と校閲では作業は異なります。しかし、編集者やライターは、校正と校閲を同時に行うことが少なくありません。
この記事を読んでいる方も、自身が校正と校閲を兼務することが多いと想定し、両作業のポイントをまとめて紹介します。
・「て・に・を・は」の助詞の使い方は正しいか
・誤字・脱字はないか
・ら抜き・い抜き言葉を使っていないか
※例/× 食べれる → ○ 食べられる、× 読んでる → ○ 読んでいる
(ただし、話し言葉として許容される場合もあります)
・矛盾が生じていないか
・間違った日本語を使っていないか
・事実関係が間違っていないか
・表記はそろっているか
※例/「嬉しい」と「うれしい」、「一人」と「1人」など、漢字・ひらがな・数字などの表記が混在していないか。媒体の中で表記をそろえたほうが、見栄えがよくなります
2.校正時に見落としたくないポイント
どんなにしっかりチェックを重ねても、やはり人間なのでミスは起きてしまうのが現実です。しかし、誤植の中でも致命的なものがいくつかあります。これはクレームにもつながってしまう危険があるので、注意深く校正・校閲にあたらなければなりません。
クレームにもつながる危険な間違い
・値段や個数、日程などの数字
・店舗名や人名、社名、地名、商品名などの固有名詞
・住所や電話番号などのデータ
・差別表現や不快表現
先ほども一部を例に出しましたが、「商品の値段が実際は50,000円なのに一桁間違えて5,000円になっていた」「イベントの開催日が1日ずれていた」といった数字に関する誤植や、「問い合わせ先の電話番号が間違っていた」というデータの誤植は、読者にもクライアントにも大きな迷惑をかけてしまいます。正しい情報かどうか、入念なチェックをしておきたい部分です。
そのほかにも注意したいのが、差別表現や不快表現。人種や職業、病気、ジェンダーなどに関して無意識に使った言葉が、人を傷つけてしまう可能性もあります。
自分では差別の意味を含んでいなかったとしても、人によって受け止め方は異なるため、少しでも可能性があれば避けたほうがよいでしょう。
例えば、以前は当然のように使われていた看護婦や保母さんという言葉は、同じ職業を男女で区別するのは良くないとされ、現在は「看護師」「保育士」と言い換えられるようになりました。
世論が何を問題視するかは時代によって変わるので、常に意識するようにしたいですね。
3.精度を上げるために心がけたい6つのルール
2003年に創業した当社も、少なからず誤植を経験してきました。その都度、ベストな校正・校閲の方法を検討し、改善を行っています。
15年以上にわたり、正確な情報発信に努めてきた当社が、現在、校正・校閲の精度を上げるために心がけていることをご紹介します。
●紙に出力する
PCのモニターでは文字を追いづらく、紙に出力したほうが間違いに気付きやすいと言われており、当社でも出力紙で校正することを推奨しています。
(ただし、最近はデジタルシフトの波を受け、iPadなどを活用することも。アナログに近い感覚で使えて、小さい文字も自由自在に拡大してチェックできるなどメリットもあります)
●他の人に見てもらう
自分で執筆した場合、一人よがりにならないよう、自分以外の視点を入れると、思わぬ気づきがあります。間違いを見つけるのが得意な人もいますが、自分の原稿だとどうしても見落としがちです。それだけ自分の文章を客観的に見るのは難しいもの。
●時間を置いてみる
自分で執筆した文章を自分で校正する場合、執筆してから時間を空けたほうが、客観的な目で見ることができます。
●作業者に的確に伝える
修正指示は基本的に赤ペンで書きます。なぐり書きなど読みづらい指示を入れると、デザイナーやDTPなどの作業者が解読するのに時間がかかるだけでなく、時には間違った認識のまま修正してしまうことも。
誰もがわかりやすいような明確な指示を、きれいな引出線とともに余白に入れるようにしましょう。文中などに埋もれた修正の指示は、見落としにもつながります。
●時には妥協も必要
例えば、表記の統一。「うれしい」と「嬉しい」が同じ記事内で混在していたとします。もちろんそろっているのが好ましいですが、違っていたからと言ってクレームにつながるという可能性は極めて少ないでしょう。
時間が限られている場合、校正ポイントをしぼり、統一表記のチェックは最低限に抑え、クレームにつながりかねない数字や固有名詞などを優先的にチェックするという臨機応変な対応も必要です。
●プロの校正者を併用する
「他の人に見てもらう」でもふれましたが、自分の文章を客観的に見るのは難しいもの。もっと言えば、制作会社の全員が「間違った知識」や「共通の先入観」を持っていたとしたら、社内の別の目を通しても、間違いは防げません。
また、医療や介護、美容、金融など、誤った情報が時に大きな損害を与えたり、死にもつながりかねないデリケートな情報は、専門機関にファクトチェックを出すべきです。
当社でも、取り扱う情報の内容、ボリューム、納期から総合的に判断し、プロの校正者を併用することが少なくありません。もちろん、その分の制作費はかさみますが、軽視すべき点ではないと考えますし、クライアントにも丁寧に説明をして理解を得るようにしています。
4.最後に
何度も校正作業を重ねても、誤植は起きるときは起きてしまいます。新聞や雑誌などしっかりとプロの目を通した出版物でさえ。だからこそ校正を疎かにしてはいけません。
「複数人でチェックしてあるからたぶん大丈夫」という姿勢で臨むのはもってのほか。校正は誤植を防ぐ重要な作業なので、読者に正しい情報を届けるためにも、クライアントに喜んでいただくためにも、気を引き締めて臨みたいものですね。
また、校正・校閲をしっかりと行った、高品質なアウトプットを求めるときに、当社を頼っていただくのも一案です。
困ったときはお気軽にご相談ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
