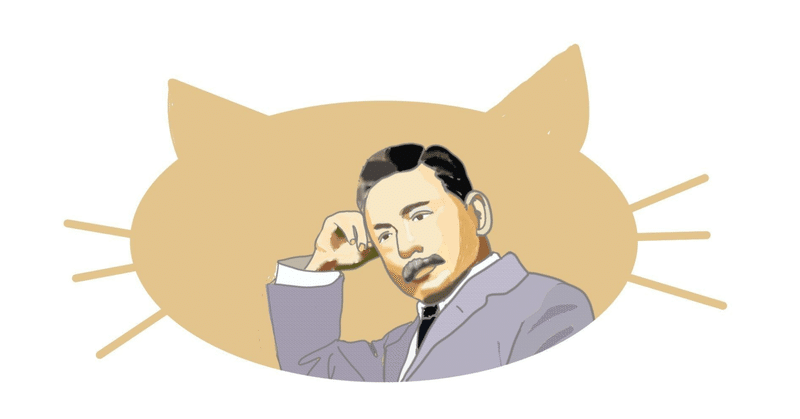
【文学】夏目漱石の「自己本位」
noterがわからなくなった
枝瀬です。
昨日の記事、
少なからずショックでした。
実は、
内容の出来について
ささやかだけど、
自分なりの手ごたえがあったんです!
うまく書けたかな、
特に末尾が決まったな、なんて。
で、
本筋に比べたら、記事の枕は
結構どうでもよくて
ネタがないから、
末っ子の娘(小学校3年生)の
漢字テキストの解答を
えいや!と出したら、

コメント欄が
「ケツイ よかった!」の
オンパレード(笑)
noterのみなさんが、
こんなに ケツ 臀部が好きだったのか・・、と
わからなくなってしまいました・・。
仲川光さん「日本文学入門」読んでます
仲川光さんの
定期購読マガジンを読んでいます。
日本文学のなかから、主に近代文学をご紹介します。 作者、書き出し、あらすじ、時代背景を紹介するとともに、解説では、仲川光ならではの視点で、物語の心理描写や人間模様から学べるポイントをご紹介!
学校では教えてくれない、ここだけの文学評論です!
これは惹かれました!
一般的な解釈は、
教師として生徒に教えていましたから、
おおむね知っているつもりです。
でも、
文学は
「その人の解釈」が
おもしろいんですよね。
たとえば、
夏目漱石「吾輩は猫である」を
読んでみたとして、
Aさんの解釈はなんなのか?
Bさんの解釈はどのようなものなのか?
その違いが楽しい。
僕は
「仲川光さん」(ヌル禁女王)という
クリエイターの解釈に興味があって
購入しました。
これがnoteの僕流の楽しみのひとつです。
僕、かつては
高尚な文学少年だったもので・・。(みなさんはケツが好きなんでしょ)
夏目漱石ロンドンで悩む
光さんの定期購読マガジンの
1回・2回は夏目漱石「こころ」が
ピックアップされていました。
この光さんの記事を読んでたら、
漱石とnoteを結び付けて
語りたくなったので
簡単に紹介しますね。
漱石は東京帝国大学(今の東大)の卒業生。
得意教科は「英語」でした。
帝国大学2年生のとき、
その「英語力」を買われて
教授の依頼により
古典『方丈記』の英訳をしたこともあるほど
語学力に優れていたそうです。
大学卒業後は英語教師として、
松山・熊本で教鞭を奮います。
そんな漱石、
明治33年に文部省から
ロンドン留学の命を受けます。
これ、
「超」がつくエリートコースです。
「給費」留学生ですから。
国のお金で
「お国のために学んで来い!」ってなわけで、
研究テーマは「英文学」でした。
でね、
ここからがおもしろいんですけど、
漱石、
「英文学のおもしろみ」が
今ひとつ理解できないで悩むんです。
もっといえば
大学在学中も
「英語を好きになれない」
悩みを抱えていたのです。
私の個人主義
大正3年11月25日、
漱石(当時47歳)は、
「私の個人主義」という題目で
学習院の学生に講演をしています。
大学時代、学んできた英語になじめず、
ロンドンで英文学を研究している最中も
葛藤が続いていたことを
漱石は
(学習院の)学生に語りかけます。
以下、引用しますね。
少し長くなりますが、
ぜひ漱石節を楽しんでください。
私は大学で英文学という専門をやりました。
その英文学というものはどんなものかと
お尋ねになるかもしれませんが、
それを3年専攻した私にも何が何だか
まあ夢中だったのです。
(大学の)試験にはウォーヅウォースは
何年に生まれて何年に死んだとか、
シェークスピアのフォリオは幾通りあるかとか、
あるいはスコットの書いた作物を
年代順に並べてみろという問題ばかり出たのです。
(中略)
英文学はしばらくおいて
第一 文学とはどういうものだか、
これでは到底わかるはずがありません
私はこの世に生まれた以上
何かしなければならん、
といって何をしていいか
少しも検討が付かない。
私はちょうど霧の中に閉じ込められた
孤独の人間のように
立ちすくんでしまったのです。
(中略)
私はこうした不安を抱いて大学を卒業し、
同じ不安を連れて松山から熊本へ引っ越し、
また同様の不安を胸の底にたたんで
遂に外国まで渡ったのであります。
それで私はできるだけ骨を折って
何かしようと努力しました。
しかしどんな本を読んでも
以前として自分は袋の中から
出るわけに参りません。
この袋を突き破る錐(きり)は
ロンドン中探して歩いても
見つかりそうになかったのです。
私は下宿の一間の中で考えました。
つまらないと思いました。
いくら書物を読んでも
腹の足しにはならないのだと諦めました。
同時に何のために書物を読むのか
自分でもその意味がわからなくなってきました。
漱石は真面目な人です。
給費留学生として、
「税金」で「国のため」に「仕事」をする以上、
その責務を全うしようと
英文学の本を読み漁ります。
・・が、
つまらない・・。
どうしても、
なじめない・・。
責任感ゆえに
仕事を遂行できない自分を許せず、
ロンドンでノイローゼにかかってしまいます。
漱石、目覚める
引き続き、引用します。
この時私は始めて文学とはどんなものであるか、
その概念を根本的に自力で作り上げるよりほかに、私を救う途はないのだと悟ったのです。
今までは全く他人本位で、
根のない浮き草のように、
そこいらをでたらめに漂っていたから、
駄目であったという事に
ようやく気がついたのです。
たとえば
西洋人がこれは立派な詩だとか、
口調が大変好いとか云っても、
それはその西洋人の見るところで、
私の参考にならん事はないにしても、
私にそう思えなければ、
とうてい受け売りをすべきはずのものではないのです。
この箇所は大切で、
当時の日本とロンドンの関係は
発展途上国ー先進国の関係ですから、
漱石にしてみたら、
先進国の人の意見や感受性を
「鵜呑みにしないぞ」と
決心しているのです。
私はこの自己本位という言葉を
自分の手に握ってから大変強くなりました。
彼ら(西欧人)何者ぞやと気慨が出ました。
今まで茫然と自失していた私に、
ここに立って、
この道からこう行かなければならないと
指図をしてくれたものは
実にこの自我本位の四字なのであります。
要するに
ロンドンの人が、
英文学を読んで
面白いと言っているからといって、
漱石がおもしろいと感じるとは限らない。
漱石は
自分がおもしろいと思うものを
追及すればいいという
「自己本位」の態度によって
自分の進む道が見えた
という講演内容なんですね。
この文章、昔からすごく好きで。
僕はいずれ学校教育に
「自己探究」て科目ができたらおもしろいな、
と思ってます。
◻️◻️◻️◻️◻️◻️◻️◻️◻️◻️◻️◻️◻️
自分は何者なのか?
なにが得意で、なにが苦手か?
何をすれば他人も自分も喜んで
お金を稼ぐことができるか?
◻️◻️◻️◻️◻️◻️◻️◻️◻️◻️◻️◻️◻️
これを学び実践することは
因数分解より、
古典文法より大切だと思ってます。
それが、
できる場が
noteですよね。
ロンドンいかなくてもいい。
便利な世の中です。
光さんの記事を読んで、
そんなことを考えた
ってお話でしたー。
引用多めでごめんなさい💦
文学もnoteも
自分が何者であるかに気づくプロセスなのだ。
#66日ライラン 参加16日目。
【追記1】「だい@初担任のサポーター」と同一人物です。
原則、平日(月・水・金)3回で教育系の発信をしています。
【追記2】
共同運営マガジンはじめました。
ぜひご参加ください!
【追記3】
ついでにkindle本出版してます!
こちらも是非、お読みいただけたら嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
