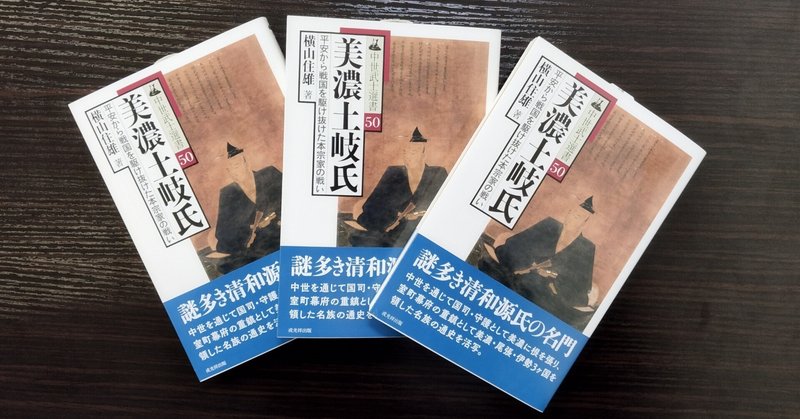
横山住雄著『美濃土岐氏』を刊行します
3月の新刊、横山住雄著『美濃土岐氏』(中世武士選書第50巻)が刷り上がってきました。
下記サイトより【試し読みページ】が確認いただけますので、ぜひご覧くださいませ。
本書の目次は下記の通りです。
【目次】
第Ⅰ部 源氏の名門・土岐氏の興亡
第一章 平安・鎌倉時代の土岐氏と美濃
第二章 守護土岐氏の発展
第三章 土岐西池田家の時代
第四章 戦国時代、動揺する土岐氏権力
第五章 斎藤道三との抗争と中世土岐氏の終焉
第Ⅱ部 土岐氏の歴史を掘り下げる
Ⅰ 土岐長山頼元の新出史料について
Ⅱ 中世前期の久々利東禅寺について
Ⅲ 「可児郡寺院明細帳」に見える久々利円明寺の由緒
Ⅳ 土岐久々利氏の史料追加
Ⅴ 土岐市妻木町崇禅寺調査行記録
Ⅵ 土岐明智氏と妻木氏の系譜補正(上)
Ⅶ 土岐明智氏と妻木氏の系譜補正(下)
Ⅷ 土岐氏の守護館の移動――特に革手・鵜沼府城について
中世を通じて美濃国(現在の岐阜県南部)を中心に繁延した土岐氏は、清和天皇の皇子貞純親王を祖とするいわゆる清和源氏を出自とします。貞純親王の子・源経基が美濃の国司である美濃守となって以降、この一族と美濃との関係が生じますが、具体的に現地美濃にどのように権益を獲得していったのか、土岐氏を名乗り始めたのかはいつかなど、実は諸説ある、謎多き一族です。
鎌倉時代は有力御家人ではありましたが、中央の政治史にその名が見え始めるのは鎌倉末期で、後醍醐天皇が鎌倉幕府の倒幕を計画したとされるいわゆる「正中の変」では、土岐頼兼・多治見国長など多数の土岐一族が関係していたことはよく知られています。
飛躍のきっかけとなったのは、後醍醐の誘いを受けた足利尊氏が六波羅探題を攻めた際に土岐頼貞が尊氏軍に加わり、以後、各地の合戦で軍功を上げたことで、美濃国守護にも補任されています。
頼貞の子が、足利軍と北畠顕家軍とが激突した青野原の戦いで活躍した土岐頼遠で、週刊少年ジャンプで連載中の『逃げ上手の若君』でも頼遠の(超人的な)奮戦が描かれ、話題になりました。その後、頼遠は光厳院が乗る牛車を射るという狼藉で処刑されますが、土岐一族自体は難を逃れ、頼遠の甥・土岐頼康の時代には美濃・尾張・伊勢3ヶ国の守護に任じられたほか、侍所頭人をつとめるなど、幕府の枢要となっていきます。
しかし、頼康の跡を継いだ康行の時代、力を付けすぎた土岐氏を警戒した室町幕府第3代将軍足利義満による政治介入がなされ、美濃守護職のみは確保したものの、大幅に勢力を削減されました(のちに伊勢守護は一族の土岐世保家が獲得)。
以後、土岐氏歴代は室町幕府のもとでしばらく安定した時期を送りますが、応仁・文明の乱を契機に土岐氏にも戦国時代の波が押し寄せます。徐々に勢力を落としていく中で、斎藤道三が台頭してきたことはよく知られています。
最後は道三により美濃を追放されたとはいえ、土岐氏は戦国時代まで美濃守護として各地の勢力とわたりあった名族と評価できるでしょう。室町幕府の守護の実態を解明する上でも重要な事例と言えます。
以上、本書ではこのような沿革をもつ土岐本宗家の歴史を、濃尾地方の中世地方史研究者として名高い横山住雄にまとめていただきました。本当は土岐本宗家以外の土岐一族の歴史をまとめた上で一冊にする予定だったのですが、土岐本宗家の通史についての原稿をお送りいただいた後、令和3年(2021)に横山先生がご逝去されました。
お送りいただいた原稿だけでは一冊の分量にならなかったため、どうすべきか悩みましたが、これまでの学恩に感謝し、貴重なご研究を埋もれさせるのは忍びないということで、ご遺族とご相談の上、それ以前に横山先生からお預かりしていた土岐氏周辺に関する論文も掲載して一冊にすることにいたしました。
そのため通常の「中世武士選書」シリーズとは少々異なった点がございますが、以上のような事情に鑑み、ご容赦いただければ幸いです。
横山住雄先生の遺稿となった本書、ぜひ多くの方に手に取っていただきたいと心より願っております。
文責:丸山
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
