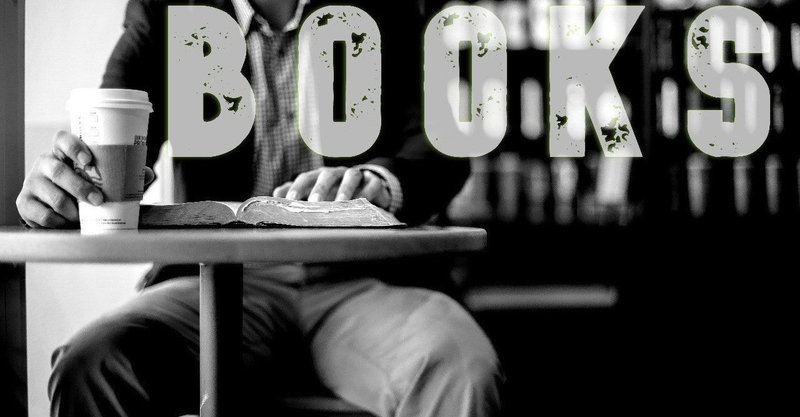
今週の2冊その1 ドラッガーのマネジメント
今週の2冊、その1はこちら。
人こそ、最大の資産である
経営学書として異例の100万部を突破した『マネジメント[エッセンシャル版]』。事業とマネジメントにおける目的の本質を捉え、人と人とが働くことの真髄を訴えかけるドラッカーの「基本と原則」は、多くの人の感動を呼び続ける。ドラッカー経営学の集大成から、いま私たちに求められる資質を学ぶ。NHK放送で大好評を博したテキスト2011年度シリーズを単行本化!本文、詳細な注釈に加え、番組4回で放送されたゲストとの対論、読書案内などを新たに収載した完全保存版。(Amzzonより抜粋)
図書館にあったので、手に取ってみました。
NHKの100分で名著って面白いですよね。あの番組が好きなのでこれも面白そうだと思ったことと、
マネジメント=上司がやること=自分にはない知識と思って
上司が見てるものがわかるのかな~と思って読みました。
ドラッガーの波乱万丈な人生
この本はドラッガーの入門編といっていいと思います。
それくらいわかりやすい。
まずドラッガーがなぜこのような本を書くに至ったかのか
その背景となるドラッガーの人生が描かれています。
これがまあ興味深いったらありゃしない。
彼が幼いときWW1が始まり、栄華を誇ったハプスブルク家は崩壊、
生まれたオーストラリア=ハンガリー帝国も解体され
「文明の終わり」を身をもって経験したドラッガーは
後ずっと「文明とは何か」を考えるようになったそう。
資本主義・社会主義が結局はお金を誰がどこで搾取するかがかわっただけで
結局人間を幸せにはしてないのでは…と思った彼は
「経済人の終わり」「産業人の未来」という本を出します。
この産業人の未来から、「組織」というものに関心を持ち
GMやら色んな企業をじっとみて「マネジメント」という本を書いた。
人を幸せにする社会=文明=マネジメントである、という結論をもとに。
超ざっくりですがこんな感じ。
そしてナチスにスカウト?みたいなことされてたんだな…とか
GMにめちゃくちゃキレられたエピソードとか
職をかなり転々としてたんだとか、大学ろくに行ってなかったとか…
人としてのエピソードが面白くて、
こんな人があの本を書いたのかと親近感がわく。
所謂偉大な本を読むときって、どうしてこの本が生まれたのか
その背景を知ることって結構面白いと思うんです。
その時の社会はどうだったのか、だからこういう本が生まれたのか
書いた人の人生はどうだったのか。
これを知るだけでもかなりこう、豊かになった気がします。
マネジメントとは演出?
「人こそ最大の資産である」と書いているドラッガーは
人の弱点ではなく強みを引き出すべしと言っています。
これは樺澤紫苑さんの「ストレスフリー大全」にも書かれていて
まず、個人としても強みを伸ばす方が弱みを消すよりも真価が発揮されること、
弱みを克服するより強み強化の方が成果が早いこと、
なによりストレスフリーだということを書かれていました。
https://www.amazon.co.jp/dp/B089VZVC1J/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
で、これは組織においても一緒。
一人が全部できるわけはない、だからそれぞれの強みを活かしたチーム作りが必要ということ。
私は5,6年前から「コモンビート」という市民ミュージカル活動に関わっているのですが
その演出も「個人個人の個性を最大限活かす」というものだったと思います。
コモンビートの理念が「個性が響きあう社会」なので、その演出もその人らしさや持ち味を活かすということ。
自分が職場としてどういう強みがあるかというと
コミュニケーション力と実行力はかなーりあるんです。
でも、緻密なことは本当にできない。
事務作業ほど苦手なものはない。
短距離選手のイメージです。
でも私とは逆の人もいるわけです。
目立った企画はしていないけど、地道に丁寧にコツコツ進めていく。
マラソンランナーのように。
あ、だから組織はなりたつのか…と。
みんながみんな同じ強みだと、組織としての弱点になる。
お互いの凸でお互いの凹を補い合うことこそが大事なんだな…と。
日本の教育って凹を減らしていく感じじゃない…とか思ったけど
その話は長くなりそうだしまた今度(笑)
自分に取り入れてみよう
この本を読んで自分に取り入れてみようと思ったことは
・他の歴史上の偉人と言われる人の人生とその社会を知りたいので知る
・多様性=人の凹ではなく凸を見て学ぶ
・自分が組織にどう貢献しているかを意識するようにする
この3つを心がけていきたいなと思います。
もうすぐ退職ですが、少しでも今のチームに貢献できますように。
そしてその経験は必ず次の役に立つ!
それでは!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
