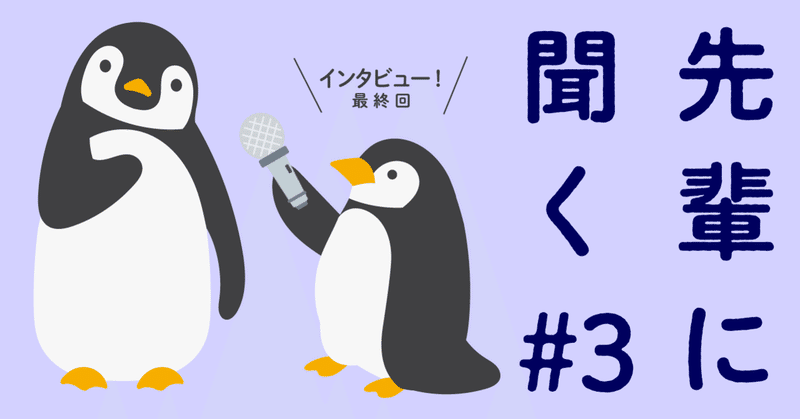
先輩に聞く|第3回 営業部Yさん
「先輩に聞く」第3回では、営業部のYさんにお話を伺います。書店営業を担当するYさんには、本の売り方についてお聞きしました!
=================
●イースト・プレスの書店営業について
――イースト・プレスで書店営業を始めるまでの経緯を教えてください。
私はもともと、書店で8年ほど勤務していました。8年くらい働いたあと、他業種の営業を経験して、「書店経験+営業経験」という足し算で出版社の営業になった感じです。
――シンプル!
――そもそも、書店営業ってどんなことをされているんですか?
いろいろありますが、新刊営業についてお話しますね。
書店さんへの販売促進は、発売日の約2ヶ月前から開始します。書籍の魅力がわかりやすく伝わるようにチラシをつくり、そのチラシを持ってお店に直接訪問します。その際、制作中の裏話をしたり、「この本の隣に置くと一緒に買ってもらえそうですね」などと展開場所の相談をしつつ、注文内容のご提案をしています。
――やはり、たくさん受注できると「ヨッシャ!」って感じなんでしょうか。
そうですね、正直嬉しいです!
ただ、そのお店の客層とマッチしない商品をご提案しても、お店に迷惑が掛かってしまいます。「どんな人に読まれる本か?」という本の読者層、「どんな人がどれだけ訪れるお店か?」といった書店の客層や規模を踏まえ、提案冊数を決めています。
そのぶん、きめ細かい営業が必要になりますから、「このお店では5冊中4冊売れたから、また入れてもらおう」というふうに、店舗単位、数冊単位で様子を見ます。
――「受注して終わり」というわけではないんですね。
新刊発売後には、売り場づくりも行っています。書店に訪れた人の興味を惹けるように、「POP」と呼ばれる拡材を使用します。
――書籍の紹介POP、店頭でもよく見かけます。
また、書店営業は書店員さんと会話をしたり、店頭で他社本をチェックしたりして、今の売れ筋をリサーチします。わかったことは編集部にも伝えて、次の企画の参考にしてもらっています。
――市場調査も行っているんですね。
●どんな書店にどう置くと売れる?
――これまでにイースト・プレスでヒットした本について、「こう営業したのが良かった」みたいな話を聞かせてください!
『しょぼい起業で生きていく』はビジネス書だったので、まずはビジネスパーソンの行き来が多い駅ナカの書店で仕掛け販売をしていただきました。
ただ、一口に「ビジネスパーソン」と言っても、経営者か、マーケティング担当者か、営業マンかによってターゲットは変わります。
この本の場合、「キャリアで失敗しても大丈夫」というゆるいメッセージが魅力的なので、管理職でバリバリに働いている40代以上よりは、20~30代の若手の人がターゲットになると推測しました。若い人が多い地域のお店で仕掛けていただいたところ、うまく売り上げを伸ばすことができました。
『不動産2.0』は、「不動産の価値がどう変化するか」という本なので、不動産業者が読むと考えました。だから、大手不動産屋や不動産デベロッパーが多い地域、街ぐるみで開発している地域に重点的に仕掛けました。品川やみなとみらい、名古屋あたりですね。そうしたら、こちらも売り上げを伸ばすことができました。
――地域もけっこう見るんですね。
そうですね。主要都市の大規模なお店であればいろんな人が訪れますが、日本にある書店のうち、ほとんどは郊外のお店です。その地域にどんな人が住んでいて、どんな本を求めているかを考えなくてはいけません。
――なるほど!
探り探り営業をして成功したパターンもあります。
『まんがでわかる自律神経の整え方』は累計20万部を超えていますが、当初、「どう売ろう?」と悩みました。イースト・プレスでは健康実用書を扱うことがあまりなかったからです。
しかもこの本は、内容は健康実用だけど、つくりはコミックエッセイ。当初は健康実用書の棚に置いていただく予定が、コミックエッセイの棚に置かれてしまうことがよくありました。
しかし幸いなことに、健康実用書とコミックエッセイは、両方とも30~40代女性がメインの読者層です。どちらの棚に置かれても問題はありませんでした。女性客の多い店舗でよく売れていることに気付き、うまく仕掛けられるようになった感じです。
――棚が合っているかどうかも、ヒットの要因なんですね。
――書店員時代に、「こう置いたらよく売れた」みたいな話はありますか?
雑学文庫の担当になったとき、棚への置き方で売り上げがガラッと変わったことがあります。
はじめは什器で2列、雑学の棚を置いていたんですが、売り上げはほぼゼロ。歴史ものとか科学ものとか、幅広い雑学本を集めていたので、お客さんも何を買えばいいかわからなかったんだと思います。
結局このときは、棚で扱うのをビジネス系の3社の本にしぼりました。駅ナカの書店だったので、通勤客を狙って、ビジネスパーソン向けの雑学本だけを集めたんです。
テーマを絞ると、「こういう棚なんだ」とわかってもらえるので、ビジネスの勉強をしたい人が見に来てくれます。結果、月間600冊くらいは売れるようになりました。
――すごい変化…! ジャンルをしぼるのが効果的なんですね。
●本のジャンルについて
――ジャンルが雑多だと大変……という書店員経験からのお話がありましたが、イースト・プレスの新書レーベル「イースト新書Q」も歴史ものから科学ものまでジャンルが幅広いですよね。
――こうなると、売るのが大変ではないですか?
「イースト新書Q」の場合、ジャンルは幅広いんですが、「ほどよい学術感」がどれもあります。そのため、「単行本を買うほどじゃないけど、軽く知的好奇心を満たしたい」と新書棚に来るお客さんに向けて売ることができています。
たとえば、『身近な鳥のすごい事典』。これは、高価な図鑑を買うほどじゃないけど知りたい…という人に手に取られました。2018年の本ですが、今も売れ続けてロングセラー商品となっています。
――安価でざっくり学べる感じが良いんですね。
昔の新書は、「岩波新書」や「中公新書」のような、ほぼ学術書のようなものしかありませんでした。そんな中、新潮社がカジュアルな新書レーベルをつくって新書ブームが起き、いろんな出版社が新書を出すようになったと言われます。
その当時、新書のコンセプトになったのは「専門書の入り口」。詳細に学ぶには専門書が必要だけれど、入り口程度には学ぶことができるよ、というものだったんです。「イースト新書Q」も、専門書の入り口としてのニーズにぴったり合っているのだと思います。
――なるほど!
「入り口」なので、読んで終わりになる本ではなく、読んだ先に何かを学びに行けることも大事です。
最近ヒットした『よくわかる思考実験』も、哲学や思考術を学ぶ取っ掛かりになる感じがウケているように思います。
新書に限らず、単なる雑学よりは、教養になりそうな本や、実用的な本のほうが長く売れます。「この本を読めば何かできるようになるかも」という期待感が購買意欲につながるんじゃないでしょうか。
――企画づくりで意識してみます!
=================
本連載では、さまざまな角度から、出版業界やイースト・プレスのことを聞いてまいりました!
今回は書店営業についてお話を伺いましたが、第1回では電子書籍事業について、第2回では官能小説やコミックエッセイの編集についてインタビューをしています。
ぜひ、ほかの回ともあわせてご覧ください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
