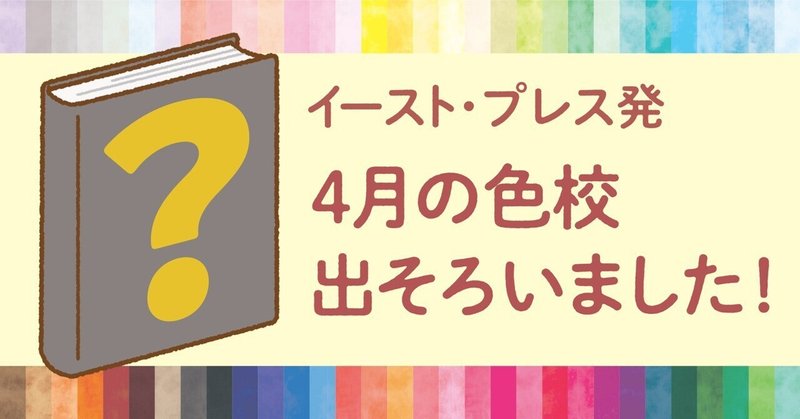
4月の色校が出そろいました!
「そもそも色校って何?」
色校とは、正式には「色校正」といいまして、著者やデザイナーさん、編集者などが、思った通りの色で印刷できているかを、実際の印刷を始める前に確認するための試し刷りのことです。カバーや表紙など、カラーで印刷するものは必ず色校をとります。絵本や写真集などのオールカラーの書籍では、本文ページも色校をとることがあります。
■4/11発売 『カラー版 パブリックアート入門 タダで観られるけど、タダならぬアートの世界』
街角にあるアート=パブリックアートのみどころを写真満載で紹介。

駅前にあるブロンズ彫刻や、広場におかれた立体オブジェ……みなさん、ふだんなにげなく目にしている街角のアレ、気になったりしたことありませんか?
この本は、街中にある「タダで観られるけど、タダならぬアート」を紹介しています。
なかには不思議なアート作品の写真が満載。その数、104点!
表紙カバーではそのアートたちをチラ見せということで、写真をタイル状にレイアウトしてもらいました!
デザインしていただいたのは、装丁新井さん。
膨大な写真データを送ったのですが、さらっとばっちりな配置をしてくれました。
ぜひ、お手にとってください!
■4/20発売 『尼人』
現代美術を詐欺だというおかんを藝大大学院出のアーティストは説得できるのか!?

ダウンタウンをはじめ優れたお笑い芸人を次々と輩出する尼崎市。作者は、そんな尼崎のワケあり風俗街である「かんなみ新地」近くで生まれ育った。3人兄弟の長男。家は当然のようにドのつく貧乏。少年時代には2度鑑別所に入り、更生プログラムで行った美術館でピカソに出会い感動。トラックの運転手をやりながら、東京藝術大学に入り大学院まで出て、作品も高い評価を得るようになった。しかし、母親はいまだ息子のことを正真正銘、詐欺師だと思っている。本書は、そんな母親に向けて、また分断と貧富の差が広がる世界に向けて書いた貧民蜂起のためのスラム芸術論です。
カバーデザインは、鈴木成一デザイン室。著者の写真をコラージュして、「尼人」とかたどっています。どこかビートルズ「ホワイトアルバム」に入っていたリチャード・ハミルトンによるコラージュ作品を想起させます。阪阪神・淡路大震災のおかげで、松田さんの昔の写真はほとんどないわけですが、おかんが大事にしていた子供時代の写真が使われています。それは七五三のお祝いで、おかんが自ら三越の包装紙を工夫して作ったパーマンのヘルメットを松田さんが被っているというものです。写真はこちら。

批評家の黒嵜想さんが僕の仕事を「スラムからの福祉」と評してくれたことがある。貧困層の流儀や価値観、生き方を見て、それよりも上の社会階層の人たちが「元気になったり」するならば、それは正に「スラムからの福祉」だと。福祉は上から下へとに行われるだけではない、と。そしておかんは「スナック太平洋」で、毎日それを行っていた。そんな地獄と天国を結ぶような所業にはダイナミズムがあり、それはめちゃくちゃ「芸術」だ。この本はそんな芸術の、血筋や人種などといった縛りを超えた、僕ら尼人という文化的アイデンティティーを示す本でもある。そして、それを作品として残そうとするのが「芸術家」の仕事なのだ。(最終章「何も深刻じゃない」より)

今月は以上2作品をご紹介しました。
是非、書店でお手に取ってご覧ください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
