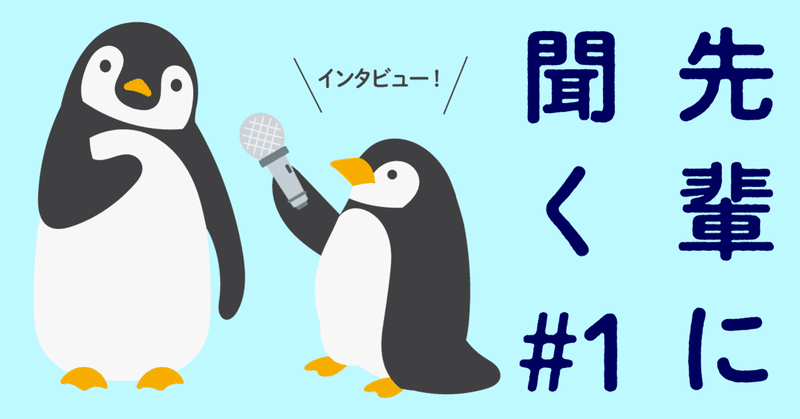
先輩に聞く|第1回 デジタルコンテンツ部Iさん
今年の春に入社した書籍1部のKです。出版のことも社内のこともまだよくわからず、日々あたふたしております。
そんな様子を見かねてか、ある日「先輩社員にインタビューせよ」とミッションが下りました。
今回の連載「先輩に聞く」では、駆け出し編集である私が、社内のさまざまな部署の方に話を伺い、出版業界とイースト・プレスについて学ぶ様をお届けしたいと思います。
第1回の先輩は、編集・ライターから電子書籍のマーケティングまで、出版業界における様々な仕事を経験してきたデジタルコンテンツ部のIさんです。
===
●編集・ライターから電子書籍のプロになるまで
<Iさん略歴>
1996年~ 出版社などで編集・ライター業務に従事
2006年~ 出版社で電子書籍事業に携わる
2012年~ 電子取次会社で営業職に従事
2021年 イースト・プレス入社
――キャリアの初期は編集をされていたんですね。
そうですね。大学時代から出版社でアルバイトをしていて、そのまま入社して雑誌編集になった感じです。
――アルバイトから社員に……という経路、出版社あるあるな感じがします。
当時はネット環境も整っておらず、またバイク便全盛になる以前だったので、記事に掲載する写真や原稿を、新聞社や作家の元に受け取りに行く見習いからのスタートでした。
また、週刊誌の編集者として採用されたので、最初は占いやプレゼントコーナーといった小さな記事から編集作業を覚えていきました。
そこを辞めた後はフリーでライターをやったり、編集プロダクションで月刊誌の編集長になったり、しばらく転々としています。
――そこから、どういった経緯で電子書籍に携わるようになったのでしょうか。
ある出版社の電子書籍担当に転職したことがきっかけです。それまでとは業務内容がかなり変わりますが、興味があって入社しました。
入社した2006年は、日本ではまだ電子書籍の黎明期です。その出版社でもこれから電子書籍担当をつくるというところで、オープニングスタッフのような形で採用されました。
当時はAmazon Kindleも楽天Koboもありません。電子書籍という未知の媒体に対し著者の懸念も強かったため、契約書の結び方やウェブでのプロモーション方法について、関係者と一緒に考えて進め、形にしていきました。
――今は当たり前になっている電子書籍の、本当に最初の時期に関わっていたんですね。
その会社の電子書籍事業は海外展開も視野に入れていて、当時からするとかなり先を見据えていたと思います。電子書籍を海外で配信する際のページの見せ方のほか、どう権利を受け渡すか、というライセンスの扱いについても、事業開始時から検討していました。
――すごく働きがいがありそうに感じますが、その後、電子書籍の取次会社に移ったのはなぜですか?
「世界を見るのもいいけど、まずは日本に電子書籍を広めるべきなんじゃないか」と思うようになったからです。
日本にある未開拓の市場を放っておくのはもったいない、と感じたんです。そこで、電子書籍の取次会社に移り、いろんな出版社に電子書籍を導入してもらう営業職に就きました。
――なるほど!
取次の仕事は10年ほど続けました。その間にテクノロジーも進んで、日本でも電子書籍は身近なものになりました。
以前は通勤電車で読むものといえば新聞か雑誌だったのに、今は車内を見回すと、10人に2、3人は電子書籍を読んでいます。網棚に週刊誌が置かれている光景ももう見かけません。
●イースト・プレスの電子書籍事業について
――イースト・プレスに移ったのはなぜですか?
各作品のマーケティングに携わりたくなったからです。
電子書籍は、いったん世に出せば在庫切れになることがありません。その特性を生かせば、作品のファンを最大化することができると感じました。そこでコンテンツホルダーへの転職を考えていたとき、イースト・プレスの募集が目に留まり、入社したという経緯です。
――紙の本だと書店にずっと置いてもらうのが難しいので、「在庫切れにならない」という電子書籍を活用するのは重要ですね。
イースト・プレスでは、電子書籍事業をどのような方針で進めているんでしょうか。
会社として電子書籍の売り上げを伸ばそうというとき、まずは電子化する作品数を増やすのが基本的な戦略になります。新刊だけでなく、既刊も電子化するということです。昔の作品では著者から電子化の許諾を取っていないこともあるので、その場合は契約を見直す必要があります。
イースト・プレスの場合、私が入社した時点で過去の契約の整理もほとんど終わっていて、堅実に電子書籍の売り上げをあげている状態でした。ですから今後は、積極的にプロモーションを行って売り伸ばしを図るフェーズに入っていきます。
――電子書籍のプロモーションはどういった形で行うものなのでしょうか。
効果的なプロモーションの一つは、電子書店が行っているキャンペーンに作品を参加させることです。電子書店ごとに「BLが得意」「ビジネスが得意」といった特色がありますから、その書店に合わせた内容で、こちらから電子書店に提案することもあります。
電子書店では、様々な切り口の特集が組まれます。例えば、年末の「占い本特集」のような季節感をもとにした特集。ほかにも「メディア化作品」と話題性のある作品を括ったり、「ハイスペ彼氏(が出てくる)」など作品のテイストで組まれたりすることも多いですね。
――「ラブコメ特集」とか「新社会人必読本特集」とか、いろんなものがありますよね。
イースト・プレスは実用書から文芸・マンガまで刊行作品のジャンルが幅広いので、さまざまなキャンペーンに参加することができます。ビジネス書などにジャンルを特化させブランディングを行う出版社もありますが、ジャンルが多彩なイースト・プレスはこういう点では有利なんです。
――「ジャンルが多い=大変」というイメージでしたが、電子書店では良いほうにも働くのですね。
最後に、メッセージがあればお願いします。
自費出版サービスも充実してきた中、著者が出版社に原稿を預ける大きな理由の一つは、作品を広く売ってくれるからです。認知を広げやすい電子書籍を活用すれば、読者はもっと増えるはず。1つの作品から生み出せる利益を最大化できるように、頑張って事業を進めていくつもりです。
===
これまでの電子書籍業界のこともわかり、大変勉強になるインタビューでした。
次回は、書籍3部Jさんにお話を伺う予定です。お楽しみに!
*「先輩に聞く」第2回、第3回は下記のリンクからご覧ください*
ぜひ、ほかの回ともあわせてご覧ください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
