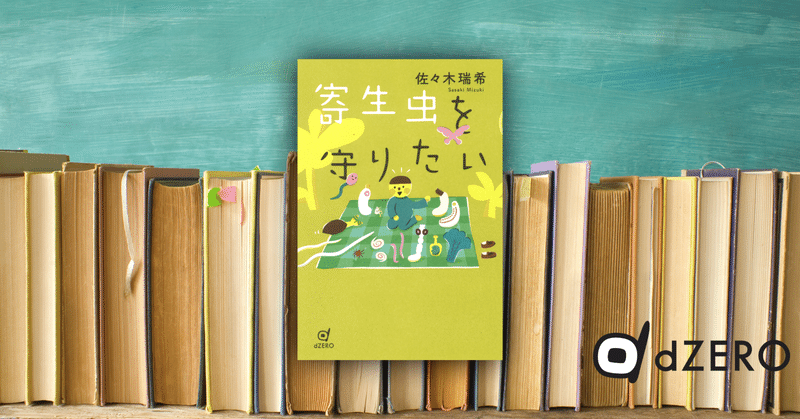
寄生虫を守りたい
はじめに
こんにちは、dZEROのHKです。今回は、寄生虫学者で獣医師の佐々木瑞希さんの『寄生虫を守りたい』を紹介させていただきます。
気鋭の研究者がユーモアたっぷりに描く「寄生虫学」の引力!
概要
寄生虫になったつもりで考えれば、未知の生態系が見えてきます。著者の佐々木さんは子どもの頃、虫が嫌いでしたが、ひっそりと生きる「小さなものたち」の世界へ引き込まれました。世界中に存在する寄生虫は、研究者でさえ混乱するほどの多様性があります。その一方で滅びゆくものも多く、目にする機会の少ない貴重なものもいます。緻密かつ巧みに設計された体内構造、機能美、そしてライフサイクル。ほとんど知られていない寄生虫の生態とその研究方法を写真とともに紹介し、その独特な魅力を語りつくします。
著者紹介
寄生虫学者、獣医師、博士(獣医学)の佐々木瑞希さん。佐々木さんは、1979年、宮城県生まれ。北里大学獣医畜産学研究科博士課程修了後、旭川医科大学助教を経て2023年に独立、寄生虫研究所の開設を目指しています。専門分野は寄生虫学、獣医学で、主に鳥類を終宿主とする鉤頭虫類の生活史や、ロイコクロリディウム属吸虫、エキノコックスなどの条虫について研究しています。寄生虫学を普及させるためにSNSなどを通じて寄生虫の様々な生態を発信するとともに、一般からも広く寄生虫情報を募っています。
この作品のポイントと名言
「寄生虫」という言葉を恐れ、気持ち悪がっている方に寄生虫のおもしろさを知っていただくことは、私の楽しみであり仕事の一つだと思っている。(まえがき、p1)
寄生虫研究者にとっては、寄生虫だけではなくて哺乳類や鳥類、魚類などの脊椎動物、昆虫や軟体動物などの無脊椎動物、さらには植物までとにかくあらゆる生物が研究対象となる。(まえがき、p4)
宿主特異性が高い場合、頼りにしていた宿主が絶滅してしまえば、寄生虫も運命をともにする。このはかなさも寄生虫の生きざまの美しさだと思う。(序章、p17)
大きな声では言えないが、私も子供の頃は「虫」が嫌いで、特にイモムシなんかは写真ですら直視できないほどであった。(序章、p22)
「寄生」とは生物が他の生物に依存して一方的に利益を得ながら生活することである。寄生は共生の一種なのであるが、「一方的に依存」するため、片利共生、すなわち寄生される側の生物である宿主にはメリットがないのが普通である。(第一章、p26)
フタゴムシ科の単生類は二個体がクロスした状態で合体し成虫になるため、全て「フタゴ」状であり、私はコイにいるものもウグイにいるものも「フタゴムシ」と呼んでしまうのだが、それは誤りである。(第一章、p35)
その他の動物に食べられてしまったり、念入りに加熱調理されてしまうとそこで寄生虫の命は尽きる。それを前提として、無性生殖により大量のセルカリアが産生され、放たれているのだろう。無事に成虫になれるのは奇跡的な確率に違いない。(第一章、p38)
知床半島ではヒグマがサケを食べて感染し、肛門から長い紐(日本海裂頭条虫成虫)をぶら下げて歩いている様子が目撃されることがある。(第一章、p46)
鉤頭虫はヒトに害を与えるものがほぼないので寄生虫学の教科書にはほとんど載っていないが、私のおすすめの蠕虫なので一般向けイベントなどで積極的にアピールすることにしている。(第一章、p54)
そもそも寄生生活を送るメリットはどこにあるのだろう。寄生虫になったつもりで考えてみる。(第一章、p68)
芽殖孤虫はもう成虫になることはなく、永久に分裂増殖で増えるだけの動物になってしまったのかもしれない。(第二章、p90)
地面をほじくればダンゴムシやムカデ、ミミズの仲間もいる。それらの中にも寄生虫は存在する。休日に家を出て少し散歩してみれば、そこは寄生虫の楽園である。(第三章、p95)
感染オカモノアラガイが植物の上のほうにいることが多いという報告があるため、「ゾンビ」と化して寄生虫に操られていると思われているのかもしれないが、ロイコクロリディウム幼虫が宿主を操作している証拠は見つかっていない。(第三章、p110)
トガリネズミにはトガリネズミ、ネズミにはネズミの条虫と決まっている。何度も言うがこれが宿主特異性である。適合しない宿主の体内に取り込まれた場合、そのまま消化されて死んでしまうのであろう。(第三章、p134)
水中で発育し(モノアラガイ)、空に飛び立ち(昆虫)、そこに飛んできた終宿主に食べられて成虫になる(コウモリ)なんて、こんなに凝った生き方ってあるだろうか。(第四章、p154)
魚の腹に詰まっているあのウドンはやがて鳥に食べられて、空を飛ぶ。食べられなければそのまま魚とともに幼虫のまま一生を終える。哺乳類など他の動物に食べられればそのまま死に、消化されて排泄される。寄生虫研究者に見つかれば標本にされる。運任せのウドンである。(第四章、p165)
砂などに付着したメタセルカリアが偶然口に入って感染するのだろうか。感染しても重篤な害はなく、ゴロゴロするとか結膜炎になる程度と言われているが、変な虫が眼に寄生していたら普通は嫌だろう。私は少し憧れる(寄生されてみたい)。(第五章、p180)
内視鏡を用いて虫体を摘出しなければ痛みから解放されることはない。ある経験者は「三日くらい我慢していたがやはり耐えられず病院に行った」と言っていた。患者も頑張ったが寄生虫も相当頑張ったのだと思う。(第五章、p188)
病気を引き起こすため嫌われがちなアニサキス幼虫だが、寄生虫観察には最高の教材となる。ご家庭での寄生虫学入門として、生魚を捌いて生きたアニサキス幼虫を観察し、その後調理しておいしく食べるというのをおすすめしている。(第五章、p192)
私の感覚では、ヒトに寄生する寄生虫の中には「まあ、寄生されちゃってもいいかな、むしろ一度くらいは経験として寄生されたい」という寄生虫と、「絶対寄生されたくない」寄生虫がいる。(第五章、p211)
包虫の実体は、拡張し続けるクローン大量製造マシンのようなものであり、SFっぽさがあって心惹かれるのだが、それが自分の体内に建設されるのは誰でも絶対にイヤなはずだ。感染から数か月経過したネズミは肝臓も肺もリンパ節も包虫に侵され悲惨な状態となる。(第六章、p222)
メタゴニムス属吸虫を絶滅から救うために(救いたいと思う方は少ないと思うが)、私一人が頑張ってアユやコイを生食して川で排泄しても、力になれないと思う。寄生虫を守るためには、宿主となる動物の保護、ひいては現存する自然環境の保全が必要だ。(第六章、p243)
寄生虫に関する研究をしていると、「その研究は何の役に立つのですか」と聞かれることがある。これはまた失礼な質問だなあと思いつつも、確かに役には立ちませんねと納得している自分がいる。(終章、p246)
あらゆる生き物を同じように評価しなければ、生態系全体の状況をつかむことはできない。寄生虫だってその一員なのだから、研究してもらう権利はある。寄生虫視点から考えれば、これまで知られていなかった生態系における生物同士のつながりが見えてくるかもしれない。(第章、p248)
寄生虫は「このステージをこの宿主のこの場所で過ごさなければならない」というように宿主への依存度が高い。寄生虫種によっては世界でたった一種の宿主にだけ頼っているものもいる。まさに「あなたがいないと生きていけないの」という面倒なやつだ。(終章、p250)
「寄生虫を守る」というのは、別に虫卵をばらまいて寄生虫感染を広げようというものではなく、生態系の一員としてそのまま維持されることを望むだけだ。今ひっそり生きている小さいものたちに、また出会えるように。(終章、p251)
dZEROHKのひとこと
寄生虫といえば怖いものと思われがちですが、この作品を読めばそんなことはないとわかります。アニサキスなど、病気を引き起こす寄生虫はいますが、それは人間が宿主ではないから。正しい宿主に寄生すれば病気を引き起こしたりしません。正しい経路で正しい宿主に寄生しなければ寄生虫は死んでしまいます。アニサキスを飲み込んで腹痛でのたうち回っているとき、アニサキスも人間の胃に寄生できずにのたうち回って苦しんでいます。思っているよりも寄生虫も生きていくのが大変なようです。
かつては人間を宿主とする寄生虫もいましたが、公衆衛生がよくなってそれらの寄生虫も減ってしまいました。寄生虫は化石にならないので、これまでどのような寄生虫がどれだけいたのかは誰にもわからないのが少しだけ寂しいです。
おまけ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
