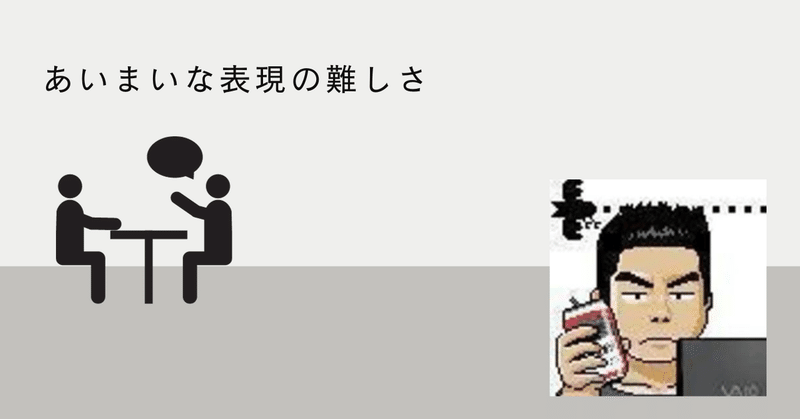
あいまいな表現の難しさ
あんたは言葉の使い方ってのを気にするようなことに日々出くわしているかい?
なんとなくねっとをいつも通りぶらついていたらこんな記事を見つけたんだよね。
まあ、いつの時代でも言葉ってのは生き物だからドンドコ変化していくもんだ。
そのコミュニケーションに使われる言葉ってのがかみ合わないなんてのは今に始まったことじゃないと思うんだけれど、どうも最近はこのギャップが生まれる頻度が上がってきているんじゃなかろうかって感じの記事だったんだよ。
曰くスマホだとかで短文でコミュニケーションを日常的にすることが多くなってきているから、端的に事実だけを伝えるようになっていっているって感じ。
そう読んでみてから「うん?そうか?」って思ったんだよね。
確かに短文でのコミュニケーションは増えているとは思うけれど、若者に限らず仲間内でしか通じない隠語みたいなものを使うってのは昔から変わらなくないか?
と思いつつも、「あいまいな表現」ってのがいろんな不都合をこさえているってのも現実問題として増えているような気もする。
今回は日常におけるあいまいな表現について考えてみる回だ。
ちっと俺たちが無意識で使っている表現について考えてみようぜ。
指示語のあいまいさ
まず、俺たちの日常会話で使わない日はないと思えるくらいに使っているのが指示語だと思う。
あれ、とか、これ、とかのいわゆる「こそあど言葉」ってやつだ。
俺がワカゾーの頃の仕事での会話でこんなのがあったんだよ。
「アレの件ですけど良い感じにナニしといたんで」
「おう、ナニ出来たんならアレはもうOKだね」
もう、見事なまでに何も伝わらないはずの会話で何かが伝わっていたんだよね。
そこにあったのは圧倒的と言っていいほどの信頼関係だったと思う。
今ほど、仕事に対する品質(と言う名の行動の数値化)が求められていなかったってのもあるかもしれないけれど、それを置いておいてもあの信頼関係ほど安心感を持てたものもないってのも事実なんだよな。
そう考えるとあいまいであることは絶対悪ってわけじゃないとも思えてくるわけだ。
外来語のあいまいさ
ところが、俺としてはワリカシ気に食わないあいまいさってのもある。
それが外来語の多用によるあいまいさだ。
「企業としてのコンプライアンスを順守するだけでなく、組織としてのパーパスと個人のパーパスをどうコミットしていくかが重要」
ほら、何言ってっか分らんくね?
「企業としては法律守っているだけじゃだめで、企業の存在意義をどう示していくのかが大切。そのためには個人の存在意義と組織の存在意義をどうやって結び付けて、その結果をきちんと示し続けるという意志を持つことが重要」
みたいな意味なんだけれど、そうやって言葉を変えて腑に落ちているヒトってレアなんじゃないかな?
俺の印象に過ぎないんだけれど、こういう外来語を安易に使っちまうと「こうだと思ってた」って感じのすれ違いは増えていくと思うんだよな。
でも外来語抜きで話すのってやろうとすると相当なムリゲーなんだよな。
って言ってるそばからゲームとか言う外来語使っちまっているし。
なんだ?電子遊戯とでも言えば良いのか?
余計分らんっつーの。
難しいのぉ。
数字のあいまいさ
難しいといえば数字だ。
数字ってのは本来あいまいさを究極にまで削り落としているはずなんだけれど、この数字ですらあいまいさってのは忍び寄ってくる。
例えば最初の記事でも書かれていたけれど「500円弱」という表現がある。
これを500円を切るくらいの値段って認識しないヒトが一定数いるらしい。
500円と弱だから500円とちょっとって意味でとらえるそうだ。
なんか分からなくもない。
宅配便に「19時前に来てくれる?」って言って、18時に来られたら、「オマイ何してくれとんじゃ」ってなるようなこともあるかも知らん。
数字にしておけばあいまいさを回避出来るって思っちまうことが多いとは思うけれど、そんな風に数字にこそあいまいさの罠が仕掛けられているってわけだ。
なあ、あんたはどう思う?
俺たちはこのあいまいさとどう付き合っていけば良いんだろうな?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

