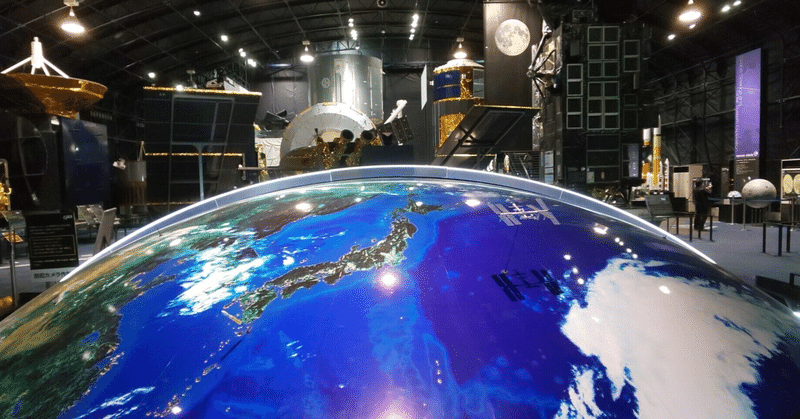
つくば市の高齢化状況について[2]
こんにちは。つくばに住む研究者です。
今回は前回に引き続き、つくば市の年齢別の人口の増減を分析します。
Cohort分析を通して人口増加の偏りや高齢化の様子をみていきます。
使用するデータは前回と同様です。前回は国勢調査3回分のデータを使って人口ピラミッドを描写しました。

先細りになる全国・茨城の人口の様子とつくば市ではだいぶ人口の変化の様子が異なるようです。しかし、2013年の時点で一番のボリュームゾーンの年齢帯は35~39歳でしたが、2023年では45~49歳に移っており、着実に高齢化は進んでいます。高齢化率(65歳以上の人口比率)は2013年の17%から、2023年には19.1%まで増加しました。
人口の将来推計をする際、最もよく用いられる統計分析手法がコーホートを用いた分析です。コーホート(cohort)とは、共通した因子を持ち、観察対象となる集団を指します。今回の共通因子は「同期間に出生した集団」となります。これを用いて将来の人口推計をする手法がコーホート法です。
コーホートを用いて、将来の人口予測を計算する方法をコーホート法と言う。コーホートを分析し、時系列の変化を軸に人口の変化を捉え、そこから得られる性別・年齢別生存率、性別・年齢別移動率、母親の年齢階級別出生率、出生者の男女比などを用いる。多くは、国勢調査のデータを用いることから、コーホートセンサス変化率法とも言う。
とあります。まずはつくば市について、2023年と2018年のデータから、各年代の人口変化率を見てみましょう。それぞれの世代の人数を列に、縦に年度の異なるデータを並べたデータフレームを作成します。今回もこれまでのコードの使い回しですので、Pythonのコードは割愛します。
こんな感じのデータになります。

さて、2018年の「0~4歳」の人口は、5年後の2023年には「5~9歳」の人口としてカウントされているはずです。増減は転出や転入、死亡などの要因が考えられます。0~4歳は自然出生の割合が多いと考えられるため、コーホート分析では「子供女性比」を用いて算出します。まずは、5歳以上の人口について増減率を計算します。
増減率を計算すると次のようになりました。単位は[%]です。

つくば市について、2018年の時点の0~4歳の人口は、転出や死亡を差し引いて、5年後には12.68%ほど増えているようです。20歳〜24歳の人口増加はさらに多く、34%が流入人口です。この世代別の変化率についてグラフを作り、全国や茨城県の様子と比較してみましょう。

なかなか興味深いグラフになりました。
つくば市は人口変動が特に大きいようです。つくば市では55歳以上の人口が減少傾向ですが、それ以下の世代の全てで増加しており、特に15歳〜19歳の人口の増加が顕著です。おそらく筑波大学の学生の影響もあると思われます。その後の20〜24歳の学校を卒業してファーストキャリアを始めるくらいの年齢では流出が多いためか増加率は少なくなりますが、30〜34歳の人口でも増加幅が大きいようです。
5歳〜9歳の人口も大きく増えています。この年齢の子供の大部分は親を伴って移動しているはずです。2018年の時点でつくば市外に住んでいた、主に25歳〜29歳の夫婦が0~4歳の子供と共に移住してきた割合が多いと言えそうです。
次回以降、得られた変動(移動率)を用いて5歳以上の人口の推移を予測し、子供女性比を用いた出生数の推定を合わせて、つくば市の将来の人口推移を計算します。
ところで、つくば市の人口分析については「社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会」から詳細な報告書が出ていますので、気になる方はぜひ。
また、RESAS:地域経済分析システム:人口の社会増減より、3階級での人口の移動数も調べられます。2021年〜2022年にかけて生産年齢人口の増加数は鈍りましたが、14歳以下の人口増加数は急伸しました。
また、つくば市が平成27年に報告した将来人口の推計では、つくば市の人口のピークは2035年で235,000人程度で、生産年齢人口は2030年から減少するということでしたが、実際には2022年時点で人口は25万人を超えており、状況は大きく変わったと言えるでしょう。つくば市のように変化の激しい都市では、他の自治体より多くの統計チームを準備し、細かな分析が必要となるでしょう。

それでは。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
