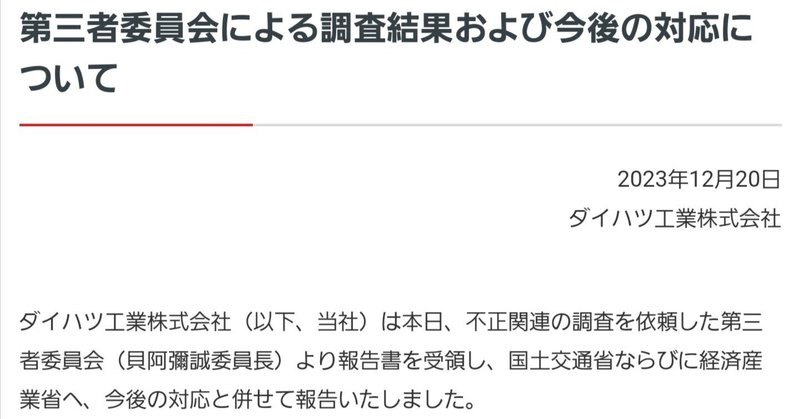
メーカーとしての信頼とは?
こんにちは。
自動車ライター/インストラクター/ジャーナリスト/ドラマーの齊藤優太です。
今回は、日本車の信頼性について考察します。
というのも、ここ最近、日本の車業界の不正やトラブルが多く、私自身「日本車って大丈夫?」と疑いたくなるほど酷いからです。
というわけで、今回は、2023年12月20日に報道された「ダイハツの不正問題」、「ホンダとデンソーが謝罪したパーツ不具合問題」を中心に、日本車の信頼性について考えていきます。
2023年12月20日に報道された2つの自動車業界ニュース
まず、2023年12月20日に報道された自動車業界の大きなニュースを紹介します。
ダイハツの不正問題
2023年12月20日、ダイハツは第三者委員会による不正関連の調査を報告書を受領し、国土交通省ならびに経済産業省へ、今後の対応と併せて報告しました。
この報告書により、過去から現在にかけて多くの不正があったことが明らかとなり、車の安全性や信頼性を疑う事態になっています。
詳しくは150ページ以上ある報告書を見ていただければわかります。ただ、全て読むのは時間がかかるため、ここでは一部を抜粋し掲載します。



注目してほしいのは不正行為の件数です。
国内生産・生産中は不正行為が80個、国内生産・生産終了は不正行為が58個、海外生産の不正行為が36個もあります。
これらの不正の背景は次の通りです。


開発スケジュールがタイトでプレッシャーもあったことが調査報告書からわかります。
ダイハツのプレスリリース(報告書公開のお知らせ)
ダイハツのプレスリリース(今後の対応)
デンソーのリコールとホンダ車の事故
デンソーの燃料ポンプの不具合も安全性や信頼性に関わる重大な事案です。
2023年12月20日には、デンソーとホンダが遺族に謝罪しました。
デンソーは、2023年12月13日に燃料ポンプに関する対応について、次のように発表しました。
2020年3月より、各カーメーカー様から届け出されております当社製燃料ポンプに関するリコールにつきまして、カーユーザーの皆様、ならびにカーメーカー様にご心配・ご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。
事故で亡くなられた被害者の方およびご遺族に深い哀悼の意を表します。また、負傷された被害者の方およびご家族に心よりお見舞い申し上げます。
リコールの対象となっております燃料ポンプの不具合は、燃料ポンプを構成する部品の1つであるインペラにおいて、樹脂密度の低いものが燃料によって変形し、作動不良に繋がることが判明しています。そして、日本国内において約 380 万台のリコール届出が出されており、不具合に対する対策をカーメーカー様と共に実施してまいりました。
リコールが拡大した経緯としまして、不具合原因の継続調査を進めていく中で、燃料ポンプの実際の作動不良の発生には条件が複雑に絡んでいることが判明してまいりました。燃料ポンプの製造から車両に組付けするまでの期間やその環境の影響、市場不具合の状況などの調査結果も確認しながら、カーメーカー様と連携して対応を進めております。
今後も引き続き、カーメーカー様のリコールに迅速に対応するため、最善の努力を続けてまいります。
改めまして、多くの皆様にご心配とご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。お客様の安心・安全を第一に考え、今後も引き続き、各カーメーカー様と連携しながら、真摯に誠実に対応してまいります。
複数の条件が重なって不具合が起きると発表されていますが、この発表に私は「?」となりました。
なぜなら、燃料ポンプはあらゆる条件に対応できる部品でなければならないと私は考えているからです。車は、さまざまな環境で使われます。また、刻一刻と変化する環境や条件の中で使われる乗り物です。
信頼というのは、どんな環境や状況でも不具合やトラブルが発生することなく走行できるからこそ生まれるのではないでしょうか。
特定の条件や環境でなければ正しく作動しない部品を搭載している車に命を預けられますか?
おそらく、多くの方は「そんな車になんか乗れたもんじゃない」となるでしょう。
信頼性に関わる重大な問題が増える理由
かつて販売されていた車と現在販売されている車では、安全に関する性能や検査基準が異なります。
乗員保護性能だけでなく、衝突時の保護性能、対歩行者保護性能、運転支援システムなど、安全な構造かつ複数の機能を搭載していなければ、安全基準を満たしていないと判断され販売することができません。
つまり、開発する項目が増え、時間やコストがかかるということです。
開発コストや開発にかけられる時間を昔のままにして、現在の基準に適合する車を作れるのでしょうか?
日産 GT-Rを開発したカリスマエンジニアの水野和敏さんは、かつての講演会で次のように述べています。
要約すると「80年代や90年代の自動車開発の資源が1.0必要だとした場合、今の車の開発資源は1.7に増えてます。開発にかかる資源は増えているのに、自動車メーカーの数は増えず、車種のバリエーションが増えてます。つまり、1台ずつの中身が薄くなってきてるということ。」(トークショーの内容を抜粋し編集しました)となります。
まさに、水野さんが言っている通りだと思います。
2015年の動画公開当時でも開発資源は昔より増えているということは、2023年末時点で開発に必要な資源はもっと増えているでしょう。
このように、開発しなければならないことは増えているのに、人という資源や時間という資源を増やさずに車を開発したらどうなるのか。。。
まるで、勉強せずにテストに挑んでいい点数をとろうとする人のようです。
勉強せずにテストで100点取ろうとしたら、カンニングなど不正をする人もいるでしょう。
このような不正が自動車メーカーで行われていると言っても過言ではありません。
不正をしてテストで満点を取った車に命を預けられますか?
私は「NO」と答えます。
満点とれるのは当たり前!基準以上の構造や機能で勝負しなければ勝てない
国が定めた基準を満たし、100点満点取れるのは当たり前です。
なぜなら、テスト問題が公表されているからです。
メーカーとしてモノづくりをするなら、基準で定められている範囲以上の領域でモノを作らなければ他社との差別化はできないでしょう。
共同開発や技術提携をしてもいい。ただ、それぞれのメーカーの個性を主張するためには、見てくれや装備だけを差別化するのではなく、文化や独自の思想を大切にし、人という資源を時間をかけて育てる必要があるのではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
