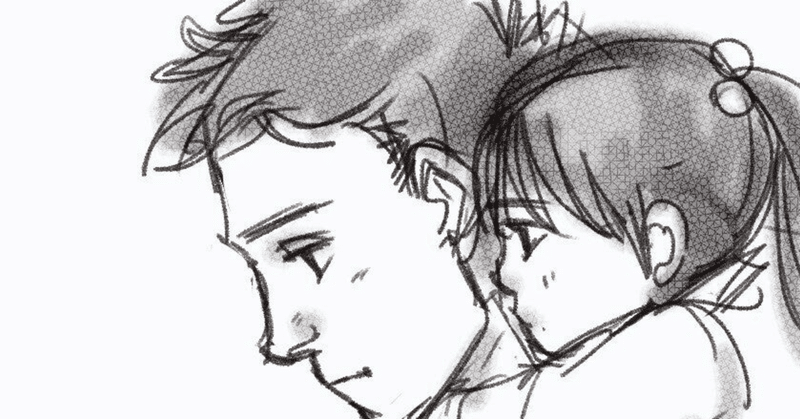
隠し子の叫び-父との再会物語#8 未来へ
一つの家族だった私たちだが、ばらばらになっていく過程で、父も姉も母も私も苦しい過去を抱えながら、過去と決別しながら、過去から学びながら、それぞれの方法で前へ進んでいったのではないかと思う。人はどうやって過去と向きあったら良いのか。この問いを思い巡らす時、私の心にいつも浮かんでくるのは次の言葉だ。「死んだ過去の上に未来を築いてはならない。どんなに苦しくても過去を否定してこそ新しい未来が開けるのだ。そこに希望を置いて出発しよう」これは私の古いクリスチャンの知り合いの家に「復活」と題して詩のように綴られ、綺麗に清書され、壁に貼ってあったものである。彼女はある神父の著書の中からこの文書を見つけ、きっとこれは「復活」を意味するものだと思うと言ってそう題し、大切にしている言葉だと言った。聖書を含め人々にインスピレーションを与える様々な書物に過去と未来に纏わる心を打つ詩や言葉はきっと他にも多く見つけることができるのであろうが、なぜか私は過去について思い巡らす時、心の引き出しに仕舞ってあるこの言葉をいつも思い出してしまう。過去を「否定」という言葉のニュアンスが受け入れ難い部分もあるが、「否定」以外にどうしても良い言葉が見つからいのも不思議なのだ。母と姉の口癖に「あの時ああしてれば。こうしてれば」というのがある。戻らない、やり直せない過去のことをいつもそんなふうに言う彼女たちの言葉や考えが私はいつもやるせ無いと思ってきた。しかし私より父の良い思い出も苦しい思い出も鮮明に記憶に残っている彼女たちにとっては、こんな言葉が口癖になってしまったのも仕方ないのかと今では思える。
今回父と私たち家族についての真相がわかった時、私も何度も過去に戻れたらと思った。なぜ もっと早く父の手紙が見つからなかったのか。なぜあの時父のことを探し始めなかったのか等々の悔しさでいっぱいなのだ。神様が一度だけタイムトリップさせて下さるなら、どうしても戻りたい過去がある。それは当時高校生だった私に母が語った日だ。「あなたを父親のない子供にしたのは私だからこの罪だけはどんなに償っても償いきれない」この言葉を発した母のイメージは暗闇に包まれている。いつも頑固で強いイメージの母が弱々しく申し訳なさそうに暗闇の中で自分の罪を静かに語るのである。私はこの時母は私に謝りながら、天上にいる神に自分の罪の告白をしていたのではないかと思っている。そして彼女はこの日からシングルマザーの高きプライドと共に、娘に犯した罪の償いの人生を歩むこととなった。許されることなら、今の私のままこの日に帰り、彼女に伝えたい。「お父さんが帰ってきてくれて私はとても嬉しいよ。よかった。お母さんだってもうこんなに苦労してお店で夜働いて酔っ払いの相手しなくてもいいんだよ。これからやっとお父さんがお母さんと婚約した時約束した全てが戻ってくるんだよ。老後もシングルマザーのまま生きるのはきっと寂しいよ。それでも、もしお母さんがお父さんとの再婚を望まないなら、お父さんに一年に一回でいいから会わせてくれる?」
こんなことができたらどんなに良いだろう。あの時の彼女に共同養育の大切さを説得できるだけの知識と勇気と、そして子供である私への家族以外から得られる国や地域や学校の支援があれば、私の人生は一転していたのであると思うと無念である。しかし無念のまま立ち止まっていたら「復活」にはならない。「死んだ過去の上に未来を築く」ことになってしまう。そのようにならないために私はここで自分自身に誓う。神が私に与えられた使命「日本の共同親権・養育社会実現への貢献と親の離婚後の子供たちの心理支援と介入」を常に思い起こし涙を拭いて力強く生きて行かなければならないと。父との半世紀後の繋がりは非常に嬉しく、そして苦しいものであったが、この私の実体験が、社会に生かされるならば、これほどの励みと喜びはない。
家庭裁判所調査官小澤真嗣氏(2020)は、「片親疎外」の子供たちの心理について下記のように述べている。「一方の親が面会交流の重要性を理解せず、利己的な判断により、面会交流を妨害、実施しない場合、子の精神状態は、以下のような重大な影響を被る。①拒絶のプロセスに巻き込まれた子どもは、別居親との関係が失われる結果、同居親の価値観のみを取り入れ、偏った見方をするようになる、②同居親が子どものロールモデルとなる結果、子どもは自分の要求を満たすために、他人を操作することを学習してしまい、他人と親密な関係を築くことに困難が生じる、③子どもは完全な善人(同居親)である自分と完全な悪人(別居親)の子どもである自分という二つのアイデンティティを持つことになるが、このような極端なアイデンティティを統合することは容易なことでななく、結局、自己イメージの混乱や低下につながってしまうことが多い、④成長するにつれて物事がわかってくると、自分と別居親との関係を妨害してきた同居親に対し怒りの気持ちを抱いたり、別居親を拒絶していたことに対して罪悪感や自責の念が生じたりすることがあり、その結果、抑うつ、退行、アイデンティティの混乱、理想化された幻の親を作りだすといった悪影響が生じる」(小田切紀子著「序章子ども中心の面会交流に向けて 小田切紀子・町田隆司(編)『離婚と面会交流−子どもに寄りそう制度と支援』 金剛出版, pp.v-xvi. 2020年出版)。
私のこれまでの半生の人格形成の歩みと心理的兆候を自己分析する際、この4つの心理的特徴が全くもって私自身のものと一致するため驚愕している。
「①拒絶のプロセスに巻き込まれた子どもは、別居親との関係が失われる結果、同居親の価値観のみを取り入れ、偏った見方をするようになる」→姉は同居親すなわち母の価値観を取り入れ、母と友達のような関係を作っていった。私は、幼い頃母とは週に一度しか会えず、会った時も母は私より随分年上の姉との時間を大切にしている様子で、母からは心理的虐待を受けた思い出の方が多く、育ての親である祖父と祖母の価値観を信じ頼るしかなく、彼らの価値観が新宗教であったため、結局新宗教に没頭する人となってしまった。そしてその新宗教の布教師であった祖母からの「父が悪い人」という呪文のような言葉は私の中で絶対的信条となってしまった。
「②同居親が子どものロールモデルとなる結果、子どもは自分の要求を満たすために、他人を操作することを学習してしまい、他人と親密な関係を築くことに困難が生じる」→私は直接的な育ての親である祖父母に大変甘やかされたため、自分の要求を満たすために他人を操作する癖が幼少の頃から身につき、これまで様々な場面で良好な人間関係を築いてこれなかったという大きな反省がある。又、母との関係においては、週に一回帰ってくる母から冷たくされ、自分が間違っていなくても謝ったり、彼女に認められたい一心で懸命に子供なりに心を尽くしてきた。その母への接し方が身についてしまい、大人になってからも、母のような強い性格の人を前にすると恐ろしく、わざわざ下手に出てしまうことがある。その結果、その人にもっと威力を与えてしまうという点において私は人を「操作」しているように感じる。
「③子どもは完全な善人(同居親)である自分と完全な悪人(別居親)の子どもである自分という二つのアイデンティティを持つことになるが、このような極端なアイデンティティを統合することは容易なことでななく、結局、自己イメージの混乱や低下につながってしまうことが多い」→②に付随する重要な人格形成の問題である。失われた父性を奪還するために50年間苦心し求め続けてきたアイデンティティの問題とは私の人生テーマそのものだ。父親に棄てられた娘というアイデンティティを抱えながら、父性とは?母性とは?人間性とは?と問い続ける過程の中で、フェミニズム、ユング心理学、宗教学、キリスト教神学等々の学問と精神性を追求する世界で彷徨い続けてきた。そのことによって結果的に私の学問知識は向上し、心の栄養をたくさん戴くことができたと思いそれなりに満足はしていた。しかし、この父性を昇華するための人格形成と学問を求める道は決して容易いものではなく、自死や対人関係の苦しみと常に隣り合わせのでこぼこ道であったのである。今回の父との劇的な繋がりの後、思いがけず、共同親権という新しいテーマに出会い、これまでの私の心の鍛錬や学問の追求の成果や回答が更に一層明確化されたと思うような体験をすることとなったことは大きな収穫と言える。
「④成長するにつれて物事がわかってくると、自分と別居親との関係を妨害してきた同居親に対し怒りの気持ちを抱いたり、別居親を拒絶していたことに対して罪悪感や自責の念が生じたりすることがあり、その結果、抑うつ、退行、アイデンティティの混乱、理想化された幻の親を作りだすといった悪影響が生じる。」→なぜもっと父を早く探さなかったのか。なぜ同居家族のいうことを鵜呑みにして50年も過ごしてしまったのかという後悔と騙されてしまったという情けなさと怒りで私の心はいっぱいである。父の真相がわかった直後は抑うつとなりカウンセリングを随分受けたし、父が恋しく、子供のように父に会いたいと一人になると泣き続けた。理想化された幻の親を作り出している部分は多かれ少なかれあると自己分析している。実際に私は父の幻を見てしまった。ユング派専門家も様々だがあるユング派分析家に私の父はアニムスだと思うと言った時、それは違うと言われ、長いレクチャーを受けさせられそうになり、静かに距離を置いた。私の父親像がその人に崩されてしまっては怖いと思ったのだ。逆に私の思いをそのまま受け止め、父の幻を見た体験も疑わず、それはビジョンだねと理解し励まして下さったユング派専門家もいた。象徴的に現象を理解するユング心理学の場合、幻の親という概念が決して否定的ニュアンスのみを持っている訳でもない点は興味深い議論であるが、実際に父と面会交流が定期的にできていれば、父をソウルメイトやアニムスや内在する父性というような捉え方をせず、一人の父という人間として見ることができたことは確かであろう。
このような心理士としての自己分析が現在の私の臨床体験に非常に役立っている。それ以前も、ユング派志向心理士として教育分析を積極的に受けてきたり、親の離婚で傷ついた多くの子供たちの心理介入を行なってきたが、単独親権社会という先進国で稀に見る日本の社会問題や自分自身の「片親疎外」問題には専門家であっても疎かったのである。このような状況下で、一人の心理専門家として歩んできてしまったということが、情けないと同時に、洗脳の恐ろしさにただ驚嘆するばかりなのである。
「片親疎外」という心の傷の痛みを体感できたことは正に私にとって「産みの苦しみ」の恵として捉え感謝すべきことであると思っている。今回の苦しみの体験の中で得られたことは多くあるが、私にとって一番大きな出来事は、父に再会できたということももちろんだが、それよりも増して重要なことは「棄てられていなかったことがわかった」ということなのだ。母は私を父親のない子にしたということに己の重大な罪を感じている。しかし、私にとって一番辛かったことは、父親がいなかったことではなく、「父親に棄てられた」ということだった。それを母は案外気づいていないのかもしれない。棄てられていたということと棄てられていなかったということの事実の違いは私にとって大きすぎる。半世紀も「棄てられた娘」というアイデンティティと共に生きてきたのだ。これまでの私は一体何者だったのだろうかと自分の存在意義や生き方そのものを考え直さなければならないほど深刻な事態と受け止めている。しかし、人生100年時代という今を生きる自分であるからこそ、今後、100歳まで生きて、これからの半世紀を「棄てられていなかった娘」として生き直す覚悟を持つことができると思い、心を新たにしている。
いつも心の真ん中にポッカリと穴が空いているような気持ちでおり、その心の傷は、父親に棄てられためにできたものだと思ってきた。しかし、そうではなかったのだ。棄てられたというのは母の大きな虚偽であったのだ。それがはっきりわかった今、私はやっと心の傷の処置ができる。その傷の処置とはユング派志向心理士として教育分析を長年受けてきたことのやり直しも含まれている。今回の父との繋がりが、私にとって、そんな大きな事態を招いているとは姉も母も、ましてや父さえも知る余地もないであろう。
母と私の確執の根本的問題が明確にされたことも産みの苦しみの恵みの一つだ。高校生の頃から、なぜか母が好きになれず、そのことで悩み始め、眠くて眠くて仕方がなく、やる気はあっても学校にも行けず眠るしかない日々を過ごしていたが、その頃がちょうど母が父からの復縁を私にはっきり説明せずに断った時期であったと判明した今、当時の私の心理状態と母との関係について大いに納得できる部分がある。私の知らないところで父と母の私に関する秘密のやり取りがあったのを私の内的世界が察知して、母との関係がギクシャクする結果を招いたいのだと思う。
今、残念ながら同居親であった母に対しては、50年間も父のことを隠され裏切られてしまったという感情が一番にあり、以前から感じていたが、尚一層、母は「影(無意識の中に潜在する抑圧された誇れない自分の部分)」の象徴となってしまった。実の母親を100%愛せないというのは悲しいことであるが、この気づきによって私に良い心の変化が現れた。それは、影の正体を知ることができ、その対応もわかり始めてきたということなのだ。失敗をした時など幼少の頃の母との苦しい思い出が心に浮かび、一層落ち込み始めることがあるのだが、父と繋がる前は、そのような時は「私さえ死ねばいいのに」という希死念慮が浮かぶのが常であった。しかし父と母についての真相が分かってからは母にきつくされたことを思い出しても「この女のために私が死んでたまるか」という強い生きる意思の声が心の中に響き渡るようになったのだ。これは私にとって大きな心の収穫だ。「影」という存在が今までうっすらとぼやけていたのがはっきりと浮き彫りにされ、影との付き合い方がやっと分かり始めた証拠であると思っている。
これまで私が金銭的に困っていた時、私はなんとか自分でやりくりできると言っているのに、母は自分に余裕があるから大丈夫助けるからと言い支援してくれた。しかし途中で、「なんでここまであなたの世話をいつまでもしなければいけないのか」、「どこまで私を地獄へ落とせばあなたの気が済むのか」などと言い怒ってくる。それなら最初から支援するからと言わなければ良いのに思うことが度々あった。その彼女の異常といえるまでの献身的姿勢は私への愛のためもあるかもしれないが、それよりもまず、自分の罪の償いのために無理をしてでも私に尽くさなければという思いがあったためなのだとやっとわかった。今まで彼女が私にしてくれたことが愛であれば重すぎて受け止めることができないが、償いであれば、納得し受け取れることができる。この発見により私の心は非常に救われた。
私が彼女を影と考える時、影である彼女から否定されたことを彼女と闘いつつ私は懸命に守ってきて良かったと思える。彼女から否定されたこと・・・それは考えることと「女であっても」勉強を続けることである。親戚のおじさんが最近、私の父はとても頭がいい人で、いつも何かを考えてたと教えてくれた。母は、私が姉や母とは違って小さい頃からいつも考えなくても良いのに何か考えていた。何も考えずに楽しく生きれば良いのに。眉間に皺を寄せて考える癖を辞めないとお嫁にいけない・・・などとよく言っていたが、私がそのように考えているところが父に似ていて嫌だったのかもしれないと思うと彼女の言動が納得できる。しかし、私は考え続け、その結果、博士になることができて良かった。母に否定されても辞めずに続けていたことが実り、その結果、父に巡り会った時、博士になってカウンセラーとして奮闘している自分を褒めてもらえたのだ。だから、私はこれからも父のように考え続け、彼のように目標を見失わず、上へ上へと登り続けるような人生を生きていきたい。
具体的な夢が最近一つできた。それはいつか父の苗字に戻りたいということだ。私は父の苗字が意味する動物が勇敢で優雅で純粋なイメージがあり大変好きである。これから失われた50年間を取り戻すアイデンティティ再構築の過程で、私はどうしてもその父の苗字を名乗りたいのだ。民法第791条【子の氏の変更】によれば、私の申し立ては可能であろうとある弁護士に相談した際アドバイスを受けた。しかし、それがうまく行かなかった場合、私は社会変革の一環として、法的アプローチを取りたいと思っている。実の娘である私が実父の復縁の気持ちをはっきり聞かされず母が一人で断ったこと(恐らく私も同意しているというような説明を私に代弁して父に勝手に伝えたと考えられるが)は、私の当時の子供としての人権を悉く侵害する行為であり、その結果私の人格形成や心理状態に大きな影響がもたらされ、シングルマザーとなった母親の心理も一層追い詰められ、母娘の関係も悪化してしまった。これらの問題は、私と母の単なる家族関係の問題として捉えるべき事ではないと思っている。私と母の確執の問題は単独親権イデオロギーに強く影響を受けており、この問題を単に親孝行という日本文化や人を赦すべきという宗教的価値観の範疇に収めてはならない。これは単独親権国家である日本の「国家」としての問題である。私は、現在東南アジアに在住しているが、日本をモデル国家として非常に尊敬する人々によく出逢う。しかし、彼らに、日本のこの単独親権問題を伝えると非常に驚かれるのだ。「アジア諸国の中であなたの国ほど素晴らしい先進国はないのに、なぜそんなことが日本で起こっているのですか」と不思議がられる。そこで私は日本人であることが恥ずかしくなってしまう。私は、海外に在住する母国日本を愛する一人の日本人として、日本国家が共同親権を導入し、日本の民主主義を真に誇ることができる日が来ることを待望している。実親が実子の親として認められるということは人としての権利と義務が尊重される基本的人権の問題なのだから!
父と繋がってから幾つかの印象的な夢を見てきたが、一番心に残っている夢が一つある。母のスナックが壁のないオープンスペースになっており、宇宙船のように見える。厨房の中の真ん中に母がおり、私は母の左横にいる。大学生の時のように私はカラオケの設定の係をしている。母は店主として客を迎える位置にある。父が入ってくる。父が半世紀後私たちを訪れた。父は私と母を知っている。私も父を知っている。しかし、母は父を知らない。いや覚えていない。父がカウンターの真ん中の席に座り、父と母が向き合った途端、母が急にパタンと倒れて死んだ。その後母の葬式があったが、母はみすぼらしい赤い籠の中に入れられていた。この籠は遺体とともに火葬炉に入るのではなく、火葬炉まで運ぶだけの役割をする。この夢について、ユング派ドリームワークのセラピストとプロセスワークをした。そのセラピーの中で父のイメージは私に語った。「私は家に帰ってきた。あなたに会うために帰ってきた。私が帰れば彼女は死ぬと分かっていた。しかし私は帰ってきた。彼女が死んだ。だから私は今、あなたと話をすることができる。強く雄々しくありなさい。これまで私はずっとあなたと一緒だった。これからもずっと一緒だ。あなたはとても大切な人だ。あなたの時がやっと来たのだ。自分を誇りに思いなさい。強く雄々しく生きなさい」私はこれを「アニムス」の言葉と象徴的に受け止めている。私はこれから「アニムス」と共にスナックが変容した宇宙船に乗って心の旅を続けるのだ。母の遺体が納められた赤いみすぼらしい籠は、プロセスワークで私自身であることが分かった。多くの人間の「影」を受け入れ、癒す、自らも傷ついた「container (容器)」である私は、まるで見窄らしい籠なのである。これを象徴するような「傷ついた癒し人」(H .J.M.ナウエン著、西垣二一・岸本和世訳、『傷ついた癒し人』、日本キリスト教団出版局、2016出版)というコンセプトは私の心の支え、モットーとなっている。
こちらに来てから父から二つのプレゼントが届いた。一つは彼が長年愛用していたペン、もう一つは籠のバッグである。神様は私に父を通して新しい使命を与えて下さっているように思える。ペンは勉強を続け書き続けることを意味している。籠のバッグは傷ついた「container (容器)」としてのカウンセラーの私を意味するだろう。この二つのミッションを大切に「世界一のカウンセラー」を目指してこれからも生きていきたい。日本出発前に父の手紙が何十年も眠っていた母のスナックの二階を夫に改装してもらいカウンセリングルームにした。教育機関契約終了後から出発までの間僅かのケースであったが、そこでカウンセリングを行なった。何故か5年前向こうでの仕事も決まっていないのにこちらの仕事を辞めて夫を一人残して日本に帰るかどうするか迷っていた時にあのスナックの二階の空間を思い出していた。そこをカウンセリングルームにすれば良いと思い立ち、出発を決意した。日本へ移動後すぐに仕事が見つかり暫くそこは空き部屋のままだった。しかし父の手紙がそこで見つかってから私はいつかその空間をカウンセリングルームにしたいと一層強く思ったのだった。その場所は父と私が出逢った場所、宇宙船なのである。私は心の中にあるこの宇宙船という名のカウンセリングルームでこれからも父と旅をするのだ。未来へ向かって。
父は50年の月日を経て私たちの所へ戻って来てくれた。それは父が想像していたような高級車で子供達にたくさんのお土産をもって35年ほど前に帰るはずだったイメージとは随分違っているのだろう。けれど父は私に沢山の心のお土産を持って帰ってきてくれたと思う。悔しいけれどこれでよかったというか、やはり神の計画であったなあと思う。箱庭療法の教育分析の最後に描いた箱庭イメージは家族のシーンであった。私が新生児を抱いて暖炉の前で座っている。その背後には家に帰ってきたばかりの夫がいる。冬のはずなのに外には椰子の木がありここは不思議な場所だと私はセラピストに言った。その夫のフィギュアは他界した前夫のような他の人のような気もするとセラピストに伝えたのを覚えている。あの帰宅したばかりの夫のような人は実はもうすぐ戻ってくる父を予兆した人物だったのかもしれないと今思える。母親の両腕の中にいる赤ちゃんは私で、その箱庭の中で再生したのだと思う。そして、奇しくも、本物の新しい命、待望のベイビーが私と夫の前に今や訪れた。
50年の時を経て再び繋がった私たち家族。父母は高齢者だが未だにそれぞれ現役で働いている。父は会社経営の傍ら無料で経営コンサルタントを行ない、私たち家族を傷つけてしまったことを深く反省しながら、新しい家族を大切にしつつ社会貢献に勤しんでいる。母はシングルマザーで生き通したプライドを棄てずに生きがいであるスナック経営を続けている。父も母も形は別でも人の悩みを聞く相談役をしている。その娘である私もカウンセラーをしているのは共時性の技にも思える。母のことが大好きな姉は母の店の手伝いをしながら、母に寄り添いつつ、それなりに楽しく生活をしている様子だ。姉はきっと父も母も好きなのだろうと思う。父と50年ぶりに繋がったことを静かに喜びつつ母との生活も引き続き大切にしている。皆それぞれに第二の人生を懸命に生きている。ばらばらになった私たち家族。半世紀後巡り会い、少しずつ修復しつつも、昔と全く同じには戻れない私たち。父、母、祖父、祖母、兄弟姉妹、そういう名前がついているだけで、究極的には、父でも母でも姉でもない。いくら血縁の関係があってもそれぞれに一人の人間であるし、大切な何かを伝えるために私の前に家族の名を持って現れた人々に過ぎないと私は思っている。家族という人間関係のしがらみに苦しむ時、その関係を本質的ではなく、象徴的に捉えることで、心が楽になり励まされることを皮肉にも私の家族から教わった。
母は私の「影」。しかしその「影」が私にしてくれた三つのことに私は感謝している。良い教育を与えてくれたこと、反面教師となってくれたこと、父の手紙を捨てないでいてくれたことだ。そんな「影」という名の実母によって奪われた父性を奪還するための半世紀の旅が終焉を迎えた。私は今、ここで高齢の母と母親代わりであった天国にいる祖母に伝えたい。「私を愛してくださり、育てて下さって、ありがとうございました。でも私は、あなたの愛に応えた生き方ができずにすみません。ただ、あなたからいただいたものを感謝して頂戴し、それらの贈り物を今後の人生に活かし、私なりの社会貢献への道を歩んでいきたいと思っています。」そして、私は、今日というこの日も、「世界一のカウンセラー」という父からもらった最高の勲章の言葉を胸に刻みつつ、父がくれたペンを握り、学び、書いていきたい。カウンセラー、執筆者、妻、母としての新しい半世紀の旅は今始まったばかりだから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
