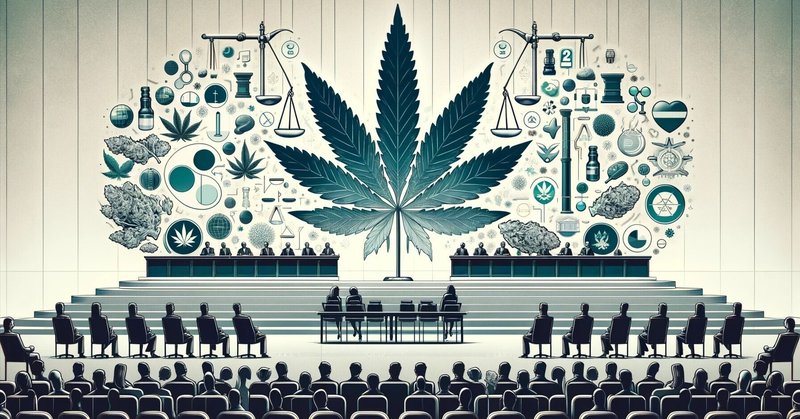
大麻取締法改正とその問題点の解説
大麻取締法改正
2023年10月24日、第212回国会(令和5年臨時会)で大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案が提出されました。
この法案の改正理由は以下のようなものです。
・大麻やそこから製造される製品の医薬利用を可能とするため
・大麻草の栽培の規制の見直し
・大麻の施用罪の適用等に係る規定の整備
改正の概要
厚労省のリンクから概要を転載いたします。

大麻の定義の変更
まず改正案で重要な点は大麻の定義の変更です。
以前の定義は、「大麻草及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」としていました。つまり大麻草から作られる製品は繊維や種を除いて大麻と定義されていました。
今回の変更では「大麻とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)をいう。」としています。
これによれば大麻草や乾燥大麻は「大麻」ですが、その抽出物や樹脂などは大麻に含まれないこととなります。しかし大麻の成分としてはTHCは「麻薬」として規制されています。またCBDは規制されていません。
以上から、
・大麻から抽出されたTHC→大麻ではないが麻薬
・大麻抽出物、大麻樹脂→大麻ではないがTHCを含めば麻薬
・CBD製剤→大麻でもなく麻薬でもない
ということでしょう。
大麻の取り締まりが麻薬及び向精神薬取締法に吸収
ここが大幅な改正で驚きましたが、大麻の所持や医薬利用を規制する大麻取締法第1章第4条が丸々削除されることとなりました。
[参考]
第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
四 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。
そして、麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)で、「麻薬とは別表1に掲げる物及び大麻をいう。」と定義しました。つまり大麻を法的に麻薬と定めました。
これにより、大麻は麻向法による管理を受けることとなります。また、大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に変更されます。
このことで、「医療用大麻」は医療用麻薬のように管理されることとなり、医療用大麻の施用が可能となります。
また同時に、嗜好目的での大麻の所持、使用、輸入、輸出、製造、譲渡は麻薬と同様の罰則となります。これは以前より厳罰化することを意味します。
以前は大麻は所持については罰則があるものの使用については罰則がありませんでしたが、麻薬となると使用罪が発生します。また、大麻の単純所持は5年以下の懲役とされていましたが、麻薬となれば7年以下の懲役となります。
この改正案の問題点
この改正案は、大麻の医薬利用を今までの医療用麻薬のシステムを流用して行えることと、今まで大麻取締法の取締上の穴であった「使用罪」の不在にパッチを当てられるという点で、一石二鳥を狙ったものと考えます。
しかし、この改正案には大きな欠点があると考えます。
大麻も他の麻薬も一緒くたに規制して良いのか
この改正案では大麻を麻薬に含め、一緒くたに規制することとなります。
麻向法ではジアセチルモルヒネすなわちヘロインのみ単純所持で10年以下と強い罰則になっています。これは別格として、その他のドラッグは害によらず一律同じ罰則です。そこに問題点があると考えます。
そもそも麻薬とは何かですが、医学的な厳密な定義ではケシから派生した化合物すなわちオピオイド製剤のことを指します。
オピオイドにはモルヒネ、オキシコドン、フェンタニル、メサドン、コデインなど様々なものがあります。また医療用にはほぼ用いられずもっぱらドラッグとして流通するヘロインも含まれます。
オピオイドは強い鎮痛効果を持ち、疼痛治療に大変有用です。一方で使用により多幸感を伴う陶酔感があり耽溺性と依存性が強く、ドラッグとして不適切に使用した場合には害が強いものとして知られています。また、過量投薬で呼吸抑制作用があり時に死に至ることもあります。
欧米ではオピオイドの不適切使用はしばしば社会問題となっており、ヘロインはもちろん、処方薬のオキシコドンやフェンタニルなどもドラッグとして流通し健康被害を起こしています。
更に日本の麻向法での「麻薬」はオピオイド以外にもコカイン、LSD、MDMA、メスカリンなどのドラッグも含まれています。ここに今回は大麻も加わることとなりました。これは要は覚醒剤以外のドラッグは全部麻薬扱いにしたということになります。(ちなみに覚醒剤、特にメタンフェタミンはドラッグの中でも害が強いものになりますが、日本で開発された化合物であり、第二次世界大戦中に軍事的に利用され、戦後に民間に流出し乱用が問題となりました。そのため覚醒剤取締法が制定されたため別の枠組みで取り締まられています。)
ドラッグの害の程度に基づく取り締まり 欧州の論調
2000年代になり欧州でドラッグの害の程度による取り締まりを行うべきであるという考えが提唱されました。これはドラッグを根絶することではなくドラッグの害を軽減することを目指す「ハームリダクション」論やリベラル派による人権意識の高まりとリンクしたものと考えます。
ハームリダクションではヘロイン、コカイン、メタンフェタミンなど害の強いハードドラッグに関しては、依存症など問題のある使用者に対して罰則ではなく治療を優先します。また、大麻のような害があまり強くない「ソフトドラッグ」では、単純使用者に強い罰則を与えるとキャリアを失うなどで社会的な損失が大きく、それが薬物の害を上回ると考え、非犯罪化や軽犯罪化を行います。もちろん大麻がハードドラッグと比較して害や依存性が少ないとはいえ、若年者や精神疾患のリスクのあるものに関しては害が強く出る可能性があり、リスクのある集団に対してはしっかりとした対策を行う必要はあります。
そのような背景があり、イギリスのNutt博士らが、薬物の専門家を集め、客観的な評価に基づくドラッグのランク付けを行いました。その論文はランセット誌に掲載され大変な注目を集めました。
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673610614626?via%3Dihub

使用者への害と他者への害をスコア化してドラッグの害のランク付けを行っています。アルコールが72点と高くなっていますが、これは非常に広範に蔓延し、使用者、使用量が多いことも反映しているかもしれません。
非合法ドラッグにおいてはヘロイン55点でトップ、続いてクラック・コカイン54点、メタンフェタミン33点、コカイン27点です。大麻は20点となっています。
これを受けて、フランス、ドイツ、オランダ、オーストラリアなどでも同様の検討が行われ、またEUでも行われています。その国の社会状況により害のランクは微妙に異なるものの概ね一貫性があり、ヘロイン、メタンフェタミン、クラックコカインはやはり害が強いし、またアルコールも害が強く、一方で大麻は中間ぐらいの害と評価されています。

このような流れから大麻は害が比較的強くないとの認識が共有され、ほとんどのEU諸国で非犯罪化、軽犯罪化しました。
またアメリカのいくつかの州やカナダなど北米においても大麻を合法化するところが出てきています。(ただし北米での合法化は経済的なメリットを考慮した別の背景もあると思われます。)
https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis
日本の法改正に足りないところ
今回の日本の法改正に足りないところは、ドラッグをすべて麻薬にまとめてしまい、ほぼ一律に取り締まることにした点です。
ドラッグの効果や害は化合物によって異なります。まずそれをクラス分けするべきです。そして客観的に検証された害の程度に基づいた罰則や対策を行うべきです。
自傷他害のない使用者に罰則を与えるのは大きな権力の介入です。大麻の害の程度を鑑みると逮捕監禁するほど公共の福祉を害するか議論の余地があり、日本国は大きな人権侵害を行っている可能性があります。取り締まりのためには害の根拠を明らかとするべきですし、その害の程度に見合った取り締まりを行うべきです。
次回の法案改正ではただ物質を羅列するのではなく、ドラッグの分類とその害の程度の評価を行いその表を追加すること、また害の程度により法定刑の重さの妥当性を検討することを要望します。
国が決めた法律に反するのだからドラッグユーザーには一律厳罰で良いという非寛容なパターナリズムではなく、ハームリダクションと人権の考えを取り入れ、人権に配慮した優しいより良い社会をつくっていただきたいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
