
感謝【母の願い 我々なき後に我が子を護ってくださるすべての皆様へ】1000スキ❤️ありがとうございます🍀🌈
私のTOP固定記事が昨日1000スキ❤️をいただきました。
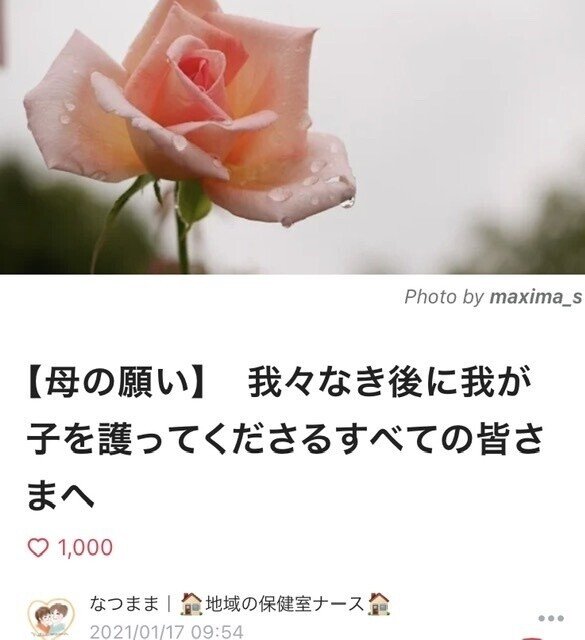
こんなにたくさんの方の目に止まり、それだけでなく【スキ❤️】をポチッとしてくださった方が1000人を超えるなんて…、感謝でいっぱいです。
娘は笑顔がキュートな22歳。アンジェルマン症候群という重度の身体知的障害者です。
てんかんなどの症状や身体障害を併せ持つ最重度の知的障害者の娘が、5年前に特別支援学校の高等部を卒業し、ますますたくさんの福祉関係の方々に支えられて生活するようになりました。
通所施設は【生活介護】。自宅では【重度訪問介護のヘルパーさん】。
一瞬たりとも目を離すことのできない娘は、ほかにも【ショートステイ】や【日中一時支援】など、ありとあらゆるサービスを利用しながら自立生活を目指しています。
娘のような重度の障害者は、これまでの社会観・価値観では、親や家族が生きて元気でいる限り家族が世話をして、親兄弟がいなくなったら当然のように施設入所。そんな選択肢が主流でした。
もちろん施設入所がいけないわけじゃありません。ありがたい社会福祉システムであり選択肢の一つです。
でも、自宅でゆったりくつろぐのが好きな我が子は、日中活動が終わったら気兼ねなく自宅で過ごしたいと思うのではないだろうか、そんな選択肢もあってもいいのでは?と思い、私たちは娘が親なきあとも住み慣れた地域・自宅で暮らせるという自立の道を模索することにしました。
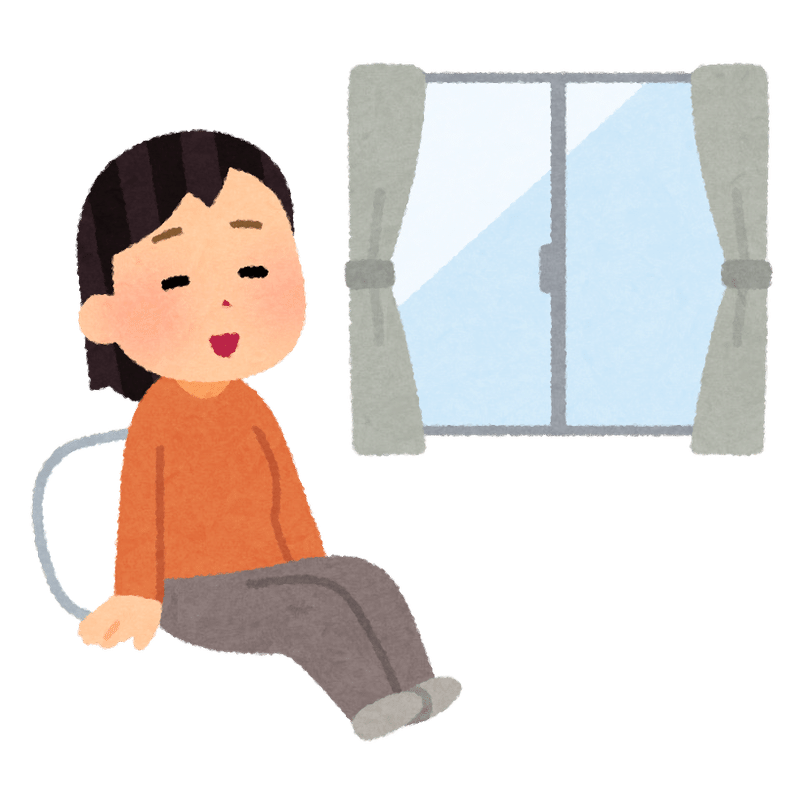
親なきあとのことは【親あるうちに】
親なきあとのことは、当然ながら【親あるうちに】準備が必要です。やってみながら失敗したり、人と人の関係性で合う合わないは必ずあるのでそれを見極めたり。
お伝えしにくい細々したことを娘の代弁者になって関係者さんにお伝えすることも親あるうちの大切な仕事ですし、どうしても合わなければお断りもしなきゃいけません。
それは施設入所だってグループホームだって実は同じなんです。誰だって入所してみて合わなかったら住み変える選択肢が欲しいでしょう?
だから、本当はとても早くから自立の道は始まっています。

【親あるうちは親がみる】という社会観・価値観
ところが、社会の多くの方(当事者もその中に含まれます)の社会観・価値観が【障害者は親あるうちは親(家族)がみる】であるために、なかなかこの準備が進みませんでした。
福祉サービスの手に託そうとすると『あれ、お母さん調子悪いの?』『お兄ちゃんとお留守番できない?』『お母さん、どうしても働かないといけないの?』と、尋ねられ、これらの問いに対しお答えすることさえ嫌になってしまう日々。
怪訝な顔をされながらも私たち家族の人生の選択をお伝えし続け、【親が楽をするためではなくて娘の自立支援をお願いしたいんです】と言えばなんとか理解していただけるようになってきたのはごくごく最近です。(今でもまだ首をかしげられることがありますが💧)
【親なきあとの準備】というのは、そんなごく最近世に現れてきた社会現象なので、重度障害者の生き方に関することや、障害ゆえに起こるトラブルの対処法、なぜこうしたいか、どう関わっていただきたいか、などをお伝えするときに誤解が生じがちでした。
親なりに一生懸命、気分を害されないようにお伝えしようとするのですが、いかんせん、社会に浸透していない考え方だから共通言語がないのです。
親が楽をしたがっている。
そんなに細かいことを言うのなら親がやりなさい。
まずは家族、できなくなったら税金や社会資源を使うことを考えなさい。
そう言って意見が食い違ってしまう方々に悪意はないのだと思います。時代がそういう時代で、それが常識だったのでしょう。
こんな言葉を投げかけられるたびに、昔の方は限界まで抱え込んで頑張ってこられたんだなぁ、と思うと同時に、障害者さん本人は何の準備もなく、きっと突然親の急病など家族の環境変化に翻弄されたのだろうなぁ、と切なくなります。
私たちに何があっても慌てない準備を
もちろん、私たちは、親がやってきたこと全てを他人様に担ってほしいなんて決して思っていませんし、娘は人が大好きですから私たちが思っている以上に支援者さんと良い関係を築いたりします。それぞれの方と娘との関わりの中で新たな支援方法が生まれるでしょう。
私が合わない人と娘が合わない人は明らかに違います。当たり前ですよね。
そんな素敵な関係や支援方法までもぎ取るなんて親のエゴなんです。
だから、親の思い込みかもしれないエゴと紙一重の愛情を、支援者さんにどう伝えれば嫌な気持ちを抱かれることなく娘を安心して託せるだろうか…と考えて考えて考え抜いて書いた文章がこちらです。
それが今、大きな誤解を生むこともなく、こんなにもたくさんの方に読んでいただけたことを心から嬉しく思っています。
この記事がますます多くの方の目にとまり、我が子を愛するあまり、そして遺していくことを憂うあまり、こんな文章を必死で紡いだバカがつく愚かな親心を、ますます多くの方に知っていただくことができればうれしいです。
そして、障害者もその家族もいろんな選択肢を持ちながら、自分らしく自立していく道を、当たり前に目指すことができる社会になればこんなに嬉しいことはありません。

🌈💕🌈💕🌈💕🌈💕🌈💕🌈💕
最後までお読みいただきありがとうございました。
地域の保健室をしつつフリーランスとしてお仕事している笑顔大好きなつままが、重度障害であるアンジェルマン症候群のキュートな娘との豊かな生活と、医療や福祉について思うこと、日々の小さな気づき・感動などを綴っております。
スキ❤️、コメント欄への感想などをお寄せいただければとっても嬉しく励みになります😊🌈サポートなんていただけると至上の喜びです💕
ぜひこれからも、読みにいらしてくださると嬉しいです😊
📖なつままのマガジン
笑顔が増えるための活動をしています。 いただいたサポートは、稀少疾患であるアンジェルマン症候群の啓蒙活動、赤ちゃんから高齢者まで住み慣れた地域で1人でも多くの方が笑顔になるための地域活動の資金として大切に使わせていただきます(^^)
