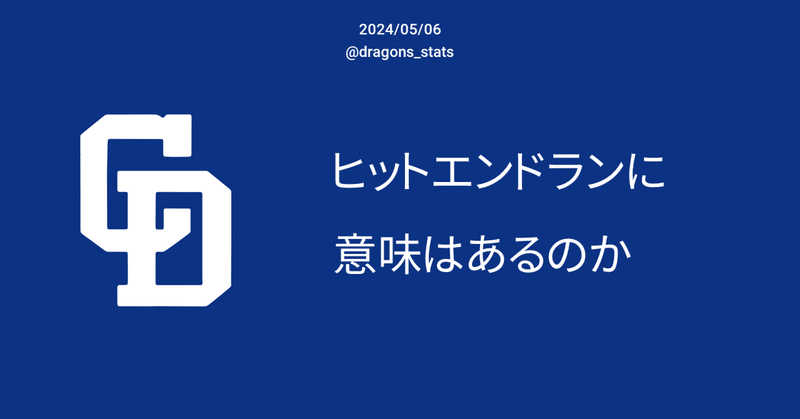
ヒットエンドランに意味はあるのか
今日(5/6 対巨人@バンテリンドーム)も中日ドラゴンズは果敢にエンドランを仕掛け、失敗していました。以前から疑問だったのですが、果たしてエンドランに意味はあるのでしょうか。閑話休題的に自分の考えをまとめます。
今日は初回の2番・村松の場面(走者: 福永)と、6回の8番・尾田の場面(走者: 山本)でエンドランを試みてどちらも失敗しています。
自分がエンドランに懐疑的な理由は3つ。①打者は普段打たないようなボール球でも無理やりスイングしなければならない。②走者は単独スチールと異なり投手のモーションを盗めない状況でも走らなければならない。③リスクが高いわりに1塁走者が3塁まで進める場面は限られる。
①について、打者はカウントを有利にできる状況やフォアボールを選べる状況でも、サインが出ている以上スイングすることを強制されます。今日の初回の村松がまさにその状況でした。サインさえ出ていなければフォアボールを選べていました。
②について、単独スチールの場合、走者は投手のモーションを盗めると判断した(セーフになると自信を持てる)状況でのみスタートを仕掛けます。ですが、エンドランのサインではそんなことはお構いなしにスタートを強制されます。たいていの場合良いスタートは切れません。足の速い選手でもエンドラン失敗三振ゲッツーになりやすいのはこういった理由だと推察しています。今日で言うと6回の山本のスチールは、尾田が空振りをした瞬間にダブルプレーがほぼ確定していました。あまりにもハイリスクな賭けです。
③について、ライト前ヒットであればエンドランを仕掛けようが仕掛けまいが、1塁ランナーは3塁まで到達できることが多いです。一方センター前やレフト前では、エンドランを仕掛けていても必ず3塁まで到達できるわけではありません。要するに、「リスクに対してリターンが小さいのではないか」というのが3つ目の理由です。
一方エンドランのメリットとしては、1塁ランナーが盗塁するので、右打者の場合はセカンドが、左打者の場合はショートが2塁のベースカバーに動きます。そこで大きく空いた一二塁間(または三遊間)に打球を転がせばヒットになりやすい、というものです。当然ですが、打者に高い技術力が求められます。また、チームとして相手の配球を読む必要もあるでしょう。リスクを取るので、作戦を実行するにはそれなりの根拠が必要になります。阪神が上手いイメージですね~。(あくまでイメージです。)
また、ダブルプレーを回避できる可能性が高いのもメリットと捉えられるでしょうか。ただし、ライナーの場合は逆にランナー飛び出しのダブルプレーになってしまう場合もあるので、評価が難しい所です。打球数としてはライナーよりもゴロの方が多いので、ここでは一応メリットに分類することにします。
そして裏のメリットとして、送りバントと同様「首脳陣が采配してる感が出る」ことが大きいんじゃないかなと自分は思っています。空振り三振ゲッツーはバットに当てられない選手のせいにできますからね。フォアボールを逃した可能性や変なボールに手を出して凡打になってしまった可能性については正当に評価されることはありません。
ここまで書いてきて自分の考えを思い直すところも少しあったのですが、やっぱり自分としてはエンドランはリターンに比べてリスクの方が高い作戦だよな~という結論です。
エンドランの効果みたいなのを数値で見積もることはできないんですかねえ。作戦の成功率とか、試行後の得点期待値の平均変化量などで数値化できないでしょうか。Deltaさんあたりにぜひトライしてもらいたいところです。(自分の手元のデータではバント同様「失敗」の記録が入っていない…泣)
というわけで、この話題はこの辺にしたいと思います。皆さんはエンドランという作戦についてどう思いますか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
