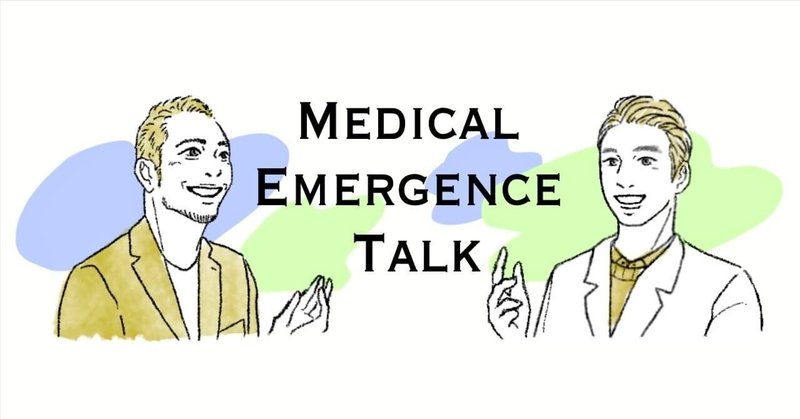
【Medical Emergence Talk】#11〜痛み治療、本当に正しいのはどっち!? 整形外科VSマクロなアプローチ(後編)〜
痛みの治療で実際に現場ではどんな事が行われているのか?
前編では、典型的な『整形外科的なアプローチ』をシミュレーションしました。今回は、『マクロな視点からのアプローチ』。対比を楽しんで読み進んでください!
前編を読んでない方は、まずはこちらから!
膝の痛みの治療
〜マクロなアプローチの場合〜
川尻:僕の場合は、最初に機能チェックをします。ただ、その中で、靭帯が切れていないか?骨折がないか?などの基本的な整形外科的なテストもします。リハビリをする上で、患者さんの状況や気をつけるべきことを知るために、整形外科的なチェックはやっぱり大事。その上で、エクササイズなどを行って、機能改善をしていきます。
朱田:機能と構造の両方を考えるなら、結局、整形外科的なアプローチと一緒ってことですか?
川尻:そこは、変わらないですよね。なぜ、私たちの治療が機能から入るかというと、結局構造的問題が痛みに直結してないからです。例えば、レントゲンで半月板がピヨって飛び出てている事がわかったとしても、それは半年前もあったものかもしれない。でも、半年前は痛みはなかったというケースがよくあるんですよ。
朱田:それはもう、その通りですね。
川尻:手術で半月板の飛び出た部分を取ったとしても、その後はリハビリで機能改善をしていきます。これって結局、手術をしない場合と一緒のプロセスを辿っていますよね。だったら、今の状況から機能改善をして、より良い状況を作っていこうよって思うんですよね。
「手術をするという事は、とても大きな怪我をする事と同じ」です。靭帯や、半月板は修復されるかもしれませんが、その過程で非常に大きな身体へのダメージがある。しかも、その構造と痛みの症状との間には、明確な因果関係があるわけではない。ならば、大きなリスクをとってまで手術をする必要は、必ずしもないんじゃないかと思います。
朱田:すごくわかります。
川尻:手術をしたからと言って、基本的なリハビリ内容が変わることはない。それどころか、手術をしたからこそやるべき事が増えてしまう。ならば、まず手術の前に機能改善をやろうよ。そしたら、ほぼ良くなると思っています。
朱田:例えば「医者に半月板損傷で、手術を勧められたんだけど悩んでるんですよね」という人にはどうしますか?
川尻:まず、僕のところに来る時点で、手術をしたくないはずなんですよ。悩んでるわけですよね。その場合は、前回お話したような「痛みとは?」の話をします。
朱田:それは、どのくらい時間をかけるんですか?
川尻:30分〜1時間ぐらいですかね。痛みの本質について理解をしてもらわないと、頑張ってエクササイズをしても、「でも俺の半月板って、こうやし・・・」という呪縛が取れないので。
痛みの話を「誰がするのか」問題
朱田:だからやっぱり、前回の対談でも話した「痛みの話を誰がするのか」っていうのが大きいと思うんですよね。
川尻:そう!めちゃくちゃでかい!今の整形外科の仕組みって、基本的には診察とリハビリの2軸しかないと思うのですが、そこに3本目の柱として「痛み教育」みたいなものが組み込まれる必要があるかなと。
朱田:本当にそうですね。僕は日々、外来で痛みの本質的な話もするんですけど、反応は様々です。すごい反応してくれる人もいるし、全然反応が得られない人もいます。
僕が手術をする基準としては、痛みの話に理解を示してくれるかどうか。理解してくれる方には、リハビリを勧める事が多いです。うちの理学療法士は、痛みの話をしっかりしてくれるのでほぼ全員が良くなる。手術なんか必要なくなる。
一方、「痛みの原因は構造だ」と信じている人の場合は、手術をすることが多いです。そうしないと、前に進めないんですよね。
川尻:とてもよくわかります。我々の本質的な意味でのゴールは、「患者さんの痛みがなくなって、健康に幸せに人生を過ごすこと」。だから、患者さんの信じてるものにちゃんと寄り添ってプランを立てていくってのは、めちゃくちゃ重要な要素ですよね。
朱田:そうですね。たまに「先生!とにかく早く、手術してください!」みたいな、前のめりな人がいて驚きますけどね(笑)
痛みの改善の先にあるゴールを明確にする効果
川尻:我々が本質的にすべきなのは、ゴールを明確にすること。中間のゴールとして、痛みがなくなるっていうことはあるかもしれないけど、実はもっと先に、「好きなテニスをしたい」「友達と旅行に行きたい」など、もっと具体的な理想があるはずです。そこをちゃんと思い出してもらうということが大事だと思っています。
朱田:わかります!
川尻:結局のところ、脳の中での安心・安全の量を増やしていく行動が、痛みを改善するわけだから、「あなたの中にできることが、実はいっぱいありますよ」ということを思い出させてあげるのがすごく大事だと思うんです。例えば、それは睡眠改善や、食事改善かもしれないし、人間関係かもしれない。自分にもできることがあるんだっていう自己効力感を持ってもらうってことが、実はすごく大事。
朱田:そう考えると、川尻さんの方が、患者さんに期待をしてるんだと思うんですよ。多分、医者はあまり人に期待してないんですよ。例えば食生活による内臓や腸環境を、この人に言ってもどうせ変わんないだろうって思っている。
川尻:はいはい。
朱田:だったら、構造を変えちゃった方が早いよ。っていうアプローチなのかなと思いました。
川尻:それは確かに、あると思いますね。クライアントさんの意識が変わる理由は、二つあると思っています。一つは、正直なところ、患者さん本人のお財布がどれぐらい痛むか?
朱田:なるほど。
川尻:それなりの金額を払うとなると、やっぱり決意がいりますよね。
前向きな状況でセッションが始まることが殆どです。一方で、保険診療だと自分のお財布は傷まないから、前向きに耳を傾けない可能性はあると思います。朱田:そうでしょうね。
川尻:もう一つは、患者さんが「いい気分になること」なんですね。未来に対して、前向きな何かを感じることがすごく大事なこと。今の患者さんの現状を否定してしまうのではなく、一旦受け入れて、そこからの道を提示するっていうこともすごく大事だと思っています。
朱田:川尻さんのアプローチは、疾患や、痛みの場所によって軸は大きく変わらないっていうことですか?
川尻:そうですね。そこは変わらないですね。
朱田:具体的なエクササイズの内容は変わるかもしれないけど、進んでいく流れは同じ統一理論があるっていう感じですね。
川尻:基本的にそうですね。
朱田:前にこの考え方の話をしたときに、ある整形外科医の方から、「全部一つの理論で解決できちゃったら、おかしくないですか?」みたいに言われたんですよ。整形外科的には、もっとミクロな違いによって治療方法は違ってしかるべきじゃないか?ってことだと思うんです。
川尻:なるほど。表層に見えてる現象だけを見ると様々だけど、深掘りしていくと、結局本質は一つのところにまとまると思うんですね。
イメージは、進化の樹形図みたいな感じです。枝の一番先端の部分には、様々な種があって全然同じものには見えないんです。でも、元を辿っていくと、実は1つにまとまっていくみたいな感じ。見た目はバラバラだけど、人間だからっていうところで最後一つにまとまっていくはずなので、だからここは最終療法は必要だと思うんすよね。
朱田:そういったマクロな痛みのアプローチを広めるには、患者さん教育が先か、医療者や治療者の教育が先か?どちらからアプローチするのがいいんでしょうね。
川尻:うーん。難しいな。ミクロなアプローチは、短期的な結果が出るから分かりやすいけれど、本質的なマクロなアプローチって、ようわからんと言われちゃう。
朱田:難しいですよね。
川尻:先日読んだ「RANGE(レンジ)〜知識の「幅」が最強の武器になる〜」という本の中に、非常に面白い例がありました。
アメリカの大学で、微分積分の単元を二人の先生が担当しました。一方の先生は、解法をしっかり教えてくれて生徒たちのテストの点数はすごくよかった。もう一方の先生は、解法ではなく本質的なところを教えたので、微分積分のテストの成績はあまり良くなかった。でも、最終的に高等な問題をやらせると、本質を教わった生徒たちの方が成績が良かった。「超専門化」した人よりも、多くの分野に精通し知識と経験の「幅(レンジ)」のある人のほうが成功しやすいといった内容が書かれていたんです。
朱田:なるほど。面白い!例えば、膝の半月板の治療方法の話をするときに、「半月板の構造ってこうだよ」みたいなのだけで終わらせてまわず、そこからの繋がりをどれだけ想像させるか大事ということと同じですね。
川尻:結局は、本質的で深くて、そのときには「何かようわからんなあ〜」って人が悩み苦しむプロセスがあるほど、結果的にその先が良くなっていく。それは、医療者、治療者にも当てはまるというのを読んだときに、すごく納得したんですよね。
朱田:確かに今まで僕が受けてきた教育を考えても、ぶつ切りではありますよね。肩なら肩、膝なら膝のそれぞれの治療法で、それぞれのネットワークみたいな話は聞いたことがないし、繋げて考えるという発想はないですよね。
川尻 :そうなんすよ。
朱田:昔、同級生の脳外科の友人と話をしたときに、「整形外科医は、首で終わっている。首から下と首から上は繋がってると思ってないでしょ」って言われたんでよ。本当にその通りだなと思うんですよね。
川尻:そうですよね。
朱田:まとめて考えると、痛みへのアプローチに個別の対策というのはなくて、本来は一つのルートみたいなのがあって、膝なら膝、肩なら肩の中で、多少そこに構造的な評価が加わっていくっていうのが、川尻さんのマクロな視点からのアプローチ。整形外科界のアプローチはその逆で、肩とか膝のパーツを個別にミクロに対策していく。
今後は、それをどう全体に広げていくか・・・
なかなかハードル高いですね(苦笑)
川尻:ですね(笑)じゃあ、どうしたらいいんだよ?という話を、次回考えていきましょう!!
*この連載は、オンラインサロンMEG※(Medical Emergence Group)で配信されていた対談の一部を編集してお届けします。
朱田 尚徳 (所沢あかだ整形外科 院長)
富山医科薬科大学医学部医学科卒業。国内外の整形外科病院勤務ほか、Jリーグのチームドクターなどを歴任。2020年、埼玉県所沢市に「所沢あかだ整形外科」開院。理学療法士や鍼灸師とともに、チーム医療の推進を行っている。日本整形外科学会認定整形外科専門医、日本体育協会公認スポーツドクター、義肢装具等適合判定医。
川尻 隆 (SASS Centrum, Inc. 代表 アスレチックトレーナー 組織改革デザイナー)
サンディエゴ州立大学を卒業。2007年よりアメリカカリフォルニア州サンディエゴにてIntegrated Holistic Medicine Clinic/パーソナルトレーニングジム“Body Craft”を経営。2017年に株式会社SASS Centrum,を設立し代表取締役に就任。新しい医学・医療の形を「動作学」を基礎に研究を続けている。
