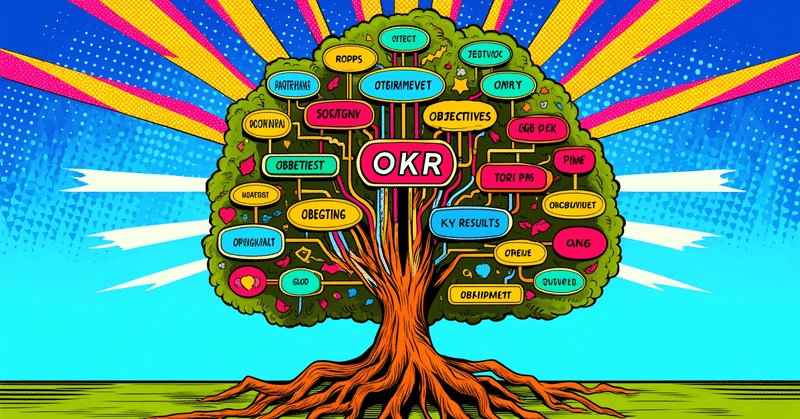
OKRをツリーにする前に言っておきたいことがある
「OKRはツリーではない」から約1年半
以前、「OKRはツリーではない」というタイトルで登壇したことがあります。OKRを採用している多くの現場で、組織レベルのOKRから個人レベルのOKRまでをツリーでつなげる「OKRツリー」で運用しているけれど、OKRはツリーじゃなくてもいいんだよということを伝えたい発表でした。
「ツリーじゃなきゃいけないと思っていたけど、ツリーじゃなくてもいいんですね!」など、様々な反響をいただきました。
それから1年半。「OKR」というキーワードを入れてGoogleで画像検索すると、OKRをツリーで捉えた画像がたくさんでてきます。この状況は1年半前とあまり変わっていません。それだけ、目標を組織全体で連携させていくことは重要だということの表れです。
ツリーで扱うときに気をつけておきたいこと
OKRをツリーで扱うことは、組織ーチームー個人の目標をアラインメントさせるという点において有効です。ですから、ツリーで扱う事自体を否定はしません。自分もツリーで扱うことがあります。
ただ、ツリーで扱う際に、気をつけておきたいポイントが一つだけあります。それは「階層ごとのすりあわせ」です。中でも「ツールを使った自動化」には注意を払っておきたいです。
OKRを管理するツールには高機能なものがあり、下位レイヤーのOKR進捗をそのまま上位レイヤーの進捗に反映させてくれるものがあります。下位レイヤーのO1が達成度0.8になったので、上位レイヤーのK1の達成度も0.8になる…といった具合です。
OKRは、なりたい姿、達成したい状態をOで描きます。そうなったことを示す成果指標をKRで設定します。そうなると、ツリーで上位と下位をつなぐときには定量的に示されたKR(上位)を下位にとってのなりたい姿として解釈する作業が発生します。

この特徴があるからこそ、チームは自分たちのOKRを主体的に捉え、前に進むことができます。(そんなことをせず直接KRをブレイクダウンしていけばいいではないか、という意見もあると思います。それはそれで有効な手段ですが、であればOKRではなくKPIを使ったマネジメントが適切です。)
そういった特性があるので、OKRをツリーで扱う場合はレイヤーをまたぐポイントで「対話」を行い、そのO(下位)がどのくらいKR(上位)に寄与しているのか確認する作業が必要になります。それにもかかわらずOKRツリーで数値の自動連動をしてしまうと、以下のような弊害が発生します。
上位OKRと下位OKRのズレに気づかない
OKRが適切に設定されてないことに気づかない
下位のOKRを達成しても上位のOKRの達成に寄与しない場合でも、下位のOの数値が向上すれば自動的に上位のKRが向上するので、ズレていることに気づきません。見かけ上は進捗してしまう。
本当の課題は自動化ではなく、自動で連動できてしまうOKRの質
そもそもこういった連動ができてしまう状態に課題があります。定量的に示す成果指標と、なりたい姿を描くOは直接的にはつながらず、翻訳が必要なはずです。それにもかかわらず自動的に更新できる状態というのは、下記いずれかの状態になっていると考えられます。
KR(上位)が定量的になっていない
O(下位)が定量的になっている
後者の場合、ものによってはOが定量的になることもありえます。この場合はツールで機械的に連動していても問題はないでしょう。
前者の状態は、O(上位)が達成したことを示す成果指標があいまいになっていることを意味します。「◯◯の準備ができている」「◯◯の合意がとれている」といった表現になっている場合はこれに陥っている可能性があります。
では、なぜ「◯◯の準備ができている」など曖昧な表現なのに、KRとして定量的に計測できてしまうのか。それは、「a1ができたら10%、b1ができたら20%…」など、状態に対して進捗の数値を当てはめるかりそめの定量化が行われるからです。そして、a1, b1などが下位のOとして設定されると、「下位のOの進捗を足し合わせたもの」が「上位のKRの進捗」になるため、構造上「自動的に更新」できるようになってしまいます。
向かいたい方向に向かっているか、対話で確かめよう
なりたい姿をOで描き、それを達成している状況を成果指標として定量的にKRで設定する。これは難しい作業です。ちゃんと定量化できていない成果指標を設定してしまうことは、ざらにあります。
実際、最初から定量的に設定するのは難しい場合もあります。(自分たちの知識・情報不足、対象の不明瞭さなどによる)
そういった場合には少しづつ目標に向かいながら適切な成果指標を探っていけばよいでしょう。このときにツールで自動化し、その妥当性を確認する作業をスキップしてしまうと、微妙なOKRであることに気づくチャンスを見失ってしまいます。
ツールは便利なものです。自動的に上位と下位を連動してくれるのもよい機能でしょう。ただ、そのときにツールに任せきりになるのではなく、定性的な目線で上位と下位が意図通り適切に接続できているかを確認するようにしましょう。一人ではなく、チームで対話しながら確認していきましょう。また、そもそもツリーにするべきか?も合わせて考えたいところです。自動で数値を連動させるツールがあると、OKRとはツリーであるべきだなんて思ってしまいますが、そんなことはありませんから。
今日はここまで。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
