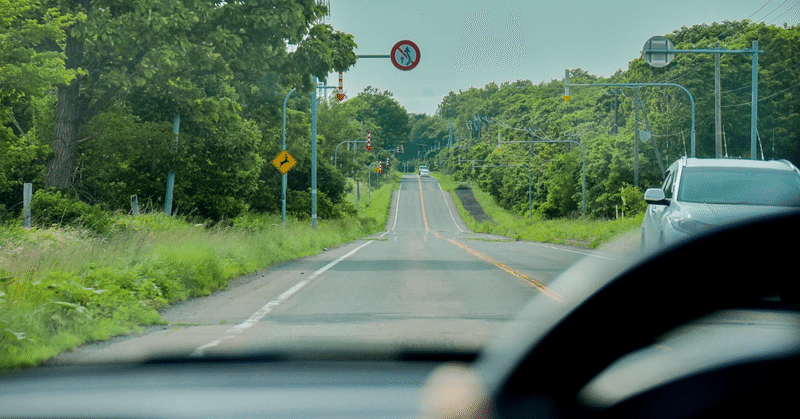
被災地に行くな、に対するささやかな違和感
年が明けてすぐ、能登で大きな地震がありました。
たしか災害ボランティアなどの考え方が広まったのって、1995年の阪神淡路大震災のときくらいからだったでしょうか。
2011年の東日本大震災のときもそうでしたが、ここ10年〜20年で災害(震災)に対するアクションやレベルが向上しているのでしょうね。
今回の地震に関しても、自己満足でネガティブな影響を与えるかもしれない行動に対する懸念が、SNSや各種配信(私の聴いているVoicyなど)で聞かれました。
災害時の行動に対するみんなの意識が上がっていること自体は素晴らしいですし、叫ばれていることもある程度合理性のあることかなと感じます。
ただし、条件反射的・アレルギー反応的に「被災地に行くこと」そのものを全否定しかねないような言説に対しては、私はいささかの違和感を覚えています。
以下のような理由からです。
行政の手だけですべてが回るはずがない
発災直後に、計画も経験もないまま詰めかけるのは当然良くはありません。交通網の復旧・安定運用や物資・人・情報の管理を、最大限円滑に行うことも重要です。
一方で、「災害なんだから自衛隊やプロにすべて任せておけばいい」というのも、それはそれで思考停止であり都合のいい慢心であるような気もするのです。
被災地では、各自治体職員や自衛隊・警察・消防など、そして元気で動ける地元民・近隣自治体住民の方々が必死に活動されていると思います。
とはいえ、人的・物的・心的問題が同時多発的に噴出している状況下において、地元住民と行政のパワーだけですべてをカバーするのは不可能です。彼ら彼女らは必要不可欠で重要で中心的な部分に注力せざるを得ず、それ以外のすべてを受け止めることはできません。必ずこぼれ落ちる部分が出てきます。
そういう部分を民間の協力によって拾い上げる動きというのは必ず必要とされるし、大きなダメージを負った被災地にとって重要な役割を果たすことになると考えます。「自助・共助・公助」という言葉がありますが、民間の力で災害時に何ができるのかを考え続ける姿勢は、ずっと必要ではないでしょうか。
もちろん現地自治体やボランティアセンターと連絡を取ったり、自分たちの分の食料や燃料等を用意したり、刻一刻と変わる現地の情報やニーズを汲み取り続けることは言わずもがな必要ですが、ノウハウやちゃんと力のある民間団体・ネットワーク(NPOなど?)の意義ある活動にまで萎縮効果が及ぶことがないよう祈ります。
災害にはフェーズがある
私も特筆して災害に詳しかったり経験豊富なわけではないので偉そうには言えないのですが、地震に限らず災害発生後の展開には必ずフェーズがあります。一次避難・二次避難などの言葉もあったように記憶しているのですが、
発災直後はまず命を守ること、72時間ラインが有名ですが巻き込まれた命をいち早く救うこと
その次に避難生活を最大限ケアすること、身の安全を確保しながらできる限り皆が心身を落ち着けられるよう、物資供給や避難所環境整備や情報共有を行うこと
その後に生活の再建や街の本格的な再建、未来に向けて日常を取り戻していくこと
ざっくりと分けるのであれば、こんな感じですかね。
フェーズによって重要なことや必要とされる物・人、民間で力になれる部分が変わってきますし、さらに言うとこれらは同時並行的・重層的に展開されることになります。
そのため、「現地に行く」という行動に関しても、どのフェーズで何を目的として誰が行くのか?によって、だいぶ話が変わってくるはずです。
ジャーナリズム(報道)は大事
報道に関して語る上での参考事例として、先に地震とは直接関係のない話をします。
ウクライナにロシアが侵攻した際、(政府方針なのか業界や社会の姿勢なのかはちょっと分かりませんが)国内メディア(ジャーナリスト)が現地で本格的な取材をすることに関して、消極的な雰囲気があったと記憶しています。
↓48分半あたりの質問。https://t.co/vo7Wr9JHul
— うにぽん☮️ (@c0h66ant1er) March 4, 2022
現地での取材、独立性のある報道が重要だという意見に激しく同意する。
命を粗末にしろということではなく、緊急事態のときこそ、報道の果たす役割は大きい。
遠く離れた私たちが現地状況を知れるのは、果敢に取材を続ける記者たちがいるからこそ。 https://t.co/NjjJ6gPdTB
ついでに、この志葉さんの記事も素晴らしいので読んでほしいです。
それは、結局のところ、報道というものを、いかに重視しているか否かの違いなのだ。例えば、警察官や消防士は危険も伴う仕事であるが、誰もこれらの仕事をすべきではないとは言わない。それが必要な仕事だからだ。だが、日本の記者達には「紛争地取材を行うべきか」という、海外メディアからすれば奇異な問いが常に突きつけられ、実際に手足を縛られる。
この、報道の持つ重要性が社会全体で共有されていないのって、私はけっこう危険だと思っていて、真剣に考えていかないと今後も様々な局面で自分たちの首を絞めることになりかねないと思います。
戦争・紛争と自然災害は少し違うかもしれません。ただ、刻一刻と状況が変化し、支援や解決のために情報の量と質が必要で、政府機関や行政だけでは力不足だったり間違えたりこぼれ落ちたり遅れたりすることがある、という点は共通しています。
また、日本は世界的に見ても行政や政府への期待や信頼度が高い国だと聞きます。それがある意味社会の秩序に繋がっている面もありますが、一方で「行政に任せておけばまあ安心よね」みたいな一本槍思考に陥りやすい傾向にあるとも言えます。
そうではなくて、民間のノウハウ、社会コミュニティの力など、多面的に災害後の現地をケアする気運は高めておきたいですね。
そのためにも、ジャーナリスト(テレビ局や新聞社含む)の現地取材は重要だし情報の量と質の向上に繋がるし、現地の行政やボランティア活動と連携すれば、それこそ重要な情報リソースにもなります。
フリーのジャーナリストが大量に押し寄せたらどうなるんだと言われればたしかにそうなのですが(ただ定量的な話をしている人はあまりいないような… 私もできませんが)、「行くな!→ ←いや行く!」みたいな話をするよりも「私たちがどういう役割を果たせるのか」や「いつどうやって行くと効果的か」という話をした方が良いんじゃないかなと感じました。
'24/01/06 最終更新
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
