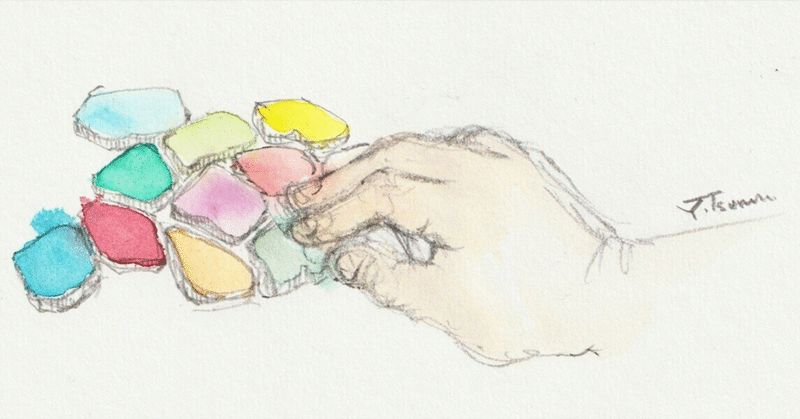
隙間を埋めるスキーマーミニ読書感想『学びとは何か』(今井むつみさん)
言語心理学者・今井むつみさんの『学びとは何か』(岩波新書、2016年3月18日初版発行)が学びになりました。話題になった『言語の本質』より前に出版されたものですが、物事の習得・熟達はどのように進むのか、「生きた知識」とはどういうものを指すのかといったテーマはこちらの方が深められる気がします。今井言説のキーとなる「スキーマ」の概念も、本書の解説が分かりやすかったです。
ダジャレのようなタイトルにしてしまいましたが、スキーマとは何か?と聞かれればこう答えればいいんだと(自分なりに)腑に落ちたのが、これです。隙間を埋めるスキーマ。スキーマとは、言語世界の隙間を埋める知識体系(システム)のことです。
著者は「映画でお葬式と言われずとも、お葬式の場面と分かる」というメタファーで説明する。
例えば、映画で考えてみよう。黒い服を着た人たちが集まり、何人かが泣いていて、みな暗い顔をしている場面からいきなり始まったとしよう。それがお葬式の場面だとは誰もひと言も言わないし、ナレーションでも語られない。でも、私たちはいちいち説明されなくても話についていける。それは私たちが、「お葬式」というものがどういうものなのかを知っていて、映画のその場面が「お葬式」の場面なのだということがわかるからだ。
なぜ、黒い服の人たちが泣いているとお葬式だと分かるのか。説明されなくても分かるのか。それは過去の体験、あるいは学習から、お葬式がそうした様式を持つことを知識として知っているからです。
逆に、このような知識がなければ、黒い服も涙もアイコンとしての意味をなさない。お葬式のスキーマが、お葬式の認識を可能にしているのです(日本のお葬式を知らない外国人の中には、お葬式だと思わない方もいるように)。コミュニケーションの隙間を埋めるのがスキーマである、と。
スキーマについて押さえておきたいのは「誤ったスキーマは往々にしてある」ということ。そして、誤ったスキーマも悪くはないということです。
特に、これは子育てにおいて意識したい。例えば子どもの母国語の習得は、スキーマの構築です。ゼロから母国語を理解していくには、スキーマが不可欠。そして子どもは、誤ったスキーマ=思い込みを使い、試行錯誤しながら言語を学ぶといいます。
これまで何度も述べてきたように、これらの「思い込み」のスキーマはいつも正しいわけではない。間違う可能性もあるけれど、よい解決をもたらす確率が高い、というような性質のものだ。人間は乳児の時からこのような「思い込み」をどんどん自分でつくっていく。そして、その「思い込み」を使って次に起こることを予測したり、新しい要素の学習をしている。
例えば、日本のお葬式の光景を「結婚式だ」と解釈するスキーマだとしても、それによって誤解することで「そうか、これはお葬式なんだな」と気付くことが可能になる。過ちを恐れず、果敢にスキーマを駆使することが、学習には不可欠です。
だから、子育てには「正解」を求めすぎない方がいい。過ちでもなんでもスキーマをバンバン使っていく方がよくて、萎縮してスキーマが使えないよりも遥かに学びになるからです。
親が自分の子どもを見ずに世間を見て、よい子育ての方法はひとつ、望ましい子育ての結果もただひとつと考えるエピステモロジーを持っている場合と、子どもを注意深く観察し、寄り添いながらいっしょに何が(ベストではなく)ベターかを考えていこうとするエピステモロジーを持っている場合とでは、子育てのしかたは自ずから違ってくる。
ベストよりベターを。それは、目の前の子にとってのベターであるように。肝に銘じたいと思います。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
