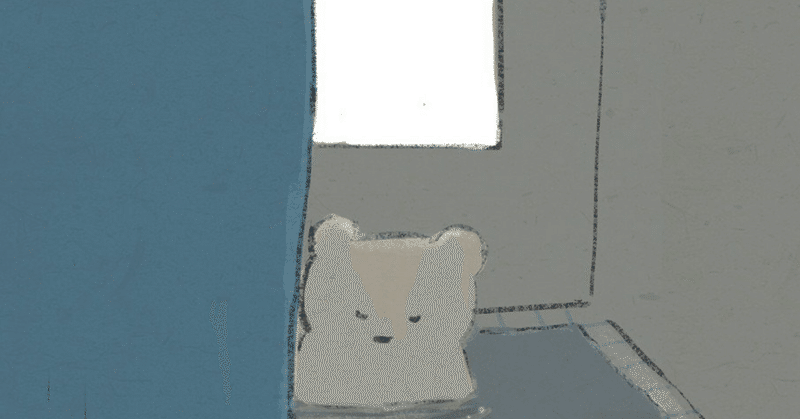
密室を開く「ノイズ」ーミニ読書感想『娘が母を殺すには?』(三宅香帆さん)
書評家・三宅香帆さんの『娘が母を殺すには?』(PLANETS、2024年5月15日初版発行)が面白かったです。文学作品などでたびたび描かれる「父殺し」ならぬ、娘の「母殺し」。ジェンダー上女性の方が身に迫るテーマかと思いますが、男性・息子・父親の読者にとっても「密室的な関係・コミュニティから抜け出す方法」として読めます。
また、最近話題沸騰の、同じく三宅さんの著書『なぜ働いているのと本が読めなくなるのか』とつなげて読むのも面白い。なぜなら本書は、読書を困難にする「全身社会」の裏面をあぶり出した批評でもあるからです。
当然ですが、物理的な殺害を意味しません。「母殺し」とは、想像上・観念上で、娘を縛る母親という存在をどう相対化していけるか、という話です。それはなぜ難しいのか。それは「母は愛情で子を支配する」からです。
簡単に言い換えれば、「父」は強さで子を支配するが、「母」は愛情で子を支配するということである。父はタテのヒエラルキーで規範をつくるが、母はヨコのゾーンで規範をつくる。そのため、強くなれば倒すことができる「父」の規範と、愛情を拒否することでしかそこから逃れられない「母」の規範とでは、大きく性質が異なる。
著者は別の箇所で「弱さによる支配」という言い方もしていて、興味深いと感じました。つまり、愛情による支配は、物理的ではない。「それを失うことは悲しい」というデメリットをもって、ある種、子の側から「積極的に支配されにいく」状態を作り出してしまう。だからやっかいなのです。
「強さによる支配」は暴力的で、だからこそ父=敵に仕立て上げ、単に父より強くなれば「父殺し」は達成される。しかし、仮に母を同じように倒しても、母は最初から暴力を用いていない。だから「母殺し」は肩すかしになってしまう。この難しさを言語化した点が、本書の素晴らしい試みです。
なぜなら「弱さによる支配」は、「娘と母」以外にも、日本社会にありふれているように思うからです。例えば私は発達障害のある子を育てていますが、「普通」や「場の空気」もそうではないか。誰かが、空気を読むことを強制しているわけではない。だけど、そこには強い規範性があって、空気を読めないことは「愛されない」ことに直結してしまう。「私は空気を読まないよ!」と叫んだところで、その空気は倒せやしない。
では、こんな困難な「母殺し」はどう達成できるのか?それが本書の探究であり、読みどころです。
そういう意味ではここから先は、ネタバレになっている面もあるので、ここまでで本書に興味を持たれた方は閉じて、書店に走って頂きたいです。
***
本書後半で提示される「母殺し」。それは逆説的に「母を殺さない」という方法でした。つまり「母と対峙するよりも、母を相対化できる他者を見つける」という方法。
ここでいう他者は、ヒト・モノ・コト全てを含む。具体例としては、映画『私ときどきレッサーパンダ』の主人公が、母がけげんな表情をする「推し」のコンサートに、それでも行くことが挙げられている。
いうなれば、「母殺し」とは、母と娘の密室から出て、外の世界に出会う旅、なのだ。
「母に愛されなくても、これを愛せているなら、私の人生はこれでいい」と思えるようなもの。「母はああ言っていたけれど、それはひとつの価値観でしかないから、気にしなくていいや」と気づかせてくれるもの。そんな「他者(モノでもヒトでもコトでもいい)」と出会うことが、重要なのである。
「母殺し」を「密室から出る旅」に置き換える。これが本書の提示した、素敵な風穴だと私は思います。
そもそも「○○殺し」を、「相手を超克する」「二項対立化して相手より勝る」という発想が、「父殺し」的だとも言えます。マッチョな発想。そうではなくて、その場から立ち去る。広い空の下へ、旅に出る。それが著者の提唱する、さわやかな「母殺し」の方法です。
そして注目したいのは、ここで述べられている「母に愛されなくても、これを愛せているなら、私の人生はこれでいいと思えるようなもの」という部分です。これは、前半で紹介した著者の話題作『なぜ働いているのと本が読めなくなるのか』で提唱される、「ノイズ」に通じます。
『なぜ~』では、「読書はノイズである」とうたわれている。
本のなかには、私たちが欲望していることを知らない知が存在している。知は常に未知であり、私たちは「何を知りたいのか」を知らない。何を読みたいのか、私たちは分かっていない。何を欲望しているのか、私たちは分かっていないのだ。
この読書は、狭義の読書に限らない。『なぜ~』においては、「自分が愛すること」、つまり音楽が好きな人にとっての音楽だし、アイドルが好きな人にとってのアイドルが、人生を豊かにするノイズだとされる。それは、私が欲望していると知らなかった欲望だし、未知の世界である。
本書と『なぜ~』をつなげて読めば、つまり「母と娘」「規範と個人」の密室を解く鍵は「ノイズ」にあると言えます。どこまでも広く深い世界にいざなうノイズこそ、「母殺し」の旅のスタートになりうる。
『なぜ~』においては、このノイズを、「仕事に全力を尽くすべきだ」という「全身社会」が抑圧してる構図が描き出される。つまり、全身社会が、「母と娘」の密室を生んでいる、とも言えます。
本書では「母殺し」の困難さの背景には、女性=専業主婦として、家族のケアを一身に担わせる戦後社会の固定的ジェンダーロールがあると看破されている。つまり、父・息子が家事を免除されること、「父(息子)の不在」が、母娘問題を難しくしている。
著者はおそらく、全身社会が読書を困難にしたことの裏面として、本書を書いたのではないか。「男による」全身社会が女性にケアを押し付け、「密室」を作り出したことをあぶり出し、それをこじ開けようとしたのではないか。本書と『なぜ~』は、双子のような本だと感じます。
だからこそ、どちらも面白いし、つなげて読むともっと面白いと思います。
◎『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の感想はこちらの記事になります。よろしければご覧ください。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
