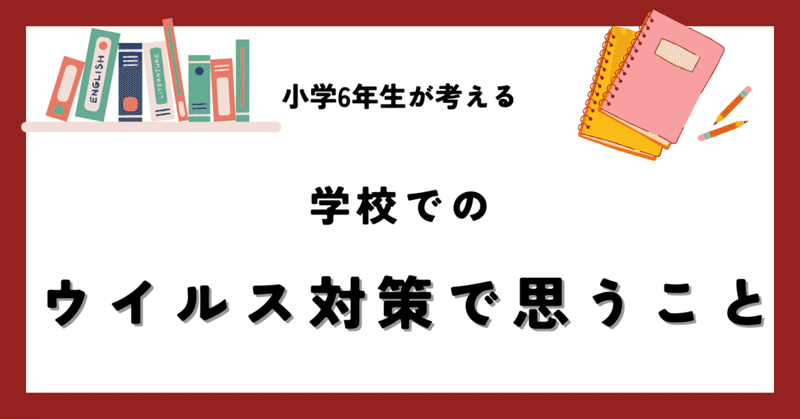
学校によるウイルス対策の現状と考察
最近、インフルエンザ、コロナウイルス、溶連菌等のウイルスがまた広がってきています。そんな中で集団生活そのものと言える学校ではどの様な対策をしているのか、また、生徒が思う改善して欲しい点について考えます。
感染対策
まず、学校ではどんな対策をしているか紹介します。
⒈体育館の割り当て変更
基本的に、学校の人数が少ないので、中・昼休みでは三学年で共有していましたが、対策時は1学年を順番に使う方式に切り替えました。これだと広々と使うことができるのでいいですが、多学年交流ができないのは学年間に壁を作るのではないかと心配になります。
2.一部教科の中断
感染防止のために、音楽の歌・リコーダー、家庭科の調理実習はカットされました。家庭科は技術的な方面を学べばいいですが、音楽はやることがなくて担任の教師も困っていました。ちなみに、音楽の時間は他の授業に代えたり鑑賞をしたりしました。
3.学級閉鎖・学校閉鎖
これは最終手段です。どうしても感染拡大を抑えられなかった場合は、学級閉鎖や学校閉鎖を行いました。1回目はオンライン授業があったらしい(インフルエンザで寝ていました)のでまだいいものの、2回目は軽いワークしかありませんでした。そのため、教師によると授業カリキュラムがギリギリだと話していました。
⒋給食の対策
学校教育活動においては、マスクの着用を求めないことが基本となること、また、学校給食の場面においては、「黙食」は必要ないこと
新型コロナウイルス感染症対策について(通知)」より一部引用
これは、文部科学省が2023年5月に公開したコロナ対策マニュアル変更の通知です。ここにはっきりと「黙食は必要ない」と明言しています。ですが、教師の指示によってまだ黙食をず〜っと続けています。これは一体どうなのか。正直、黙食しても焼け石に水のように思います。
学校は「恐れている」
学校はウイルスに「恐れすぎている」。僕はそう思います。その理由を簡単に説明すると、次の通りです。
学校は、恐れすぎている。周りがどんどんと緩和していているのに、2020年(コロナが流行り始めた頃)から少し緩和とまた強化を繰り返している。結果、何も変わらない。
こうなります。その具体的な現状と理由について、説明します。
1.コロナ対策による大幅規制
まず、コロナによる対策が始まったのは2020年初頭あたりからです。
マスクの着用、黙食、リコーダー等の規制などの今のベースになる規制が始まりました。
⒉膠着状態に、そして緩和
2023年半ばぐらいまではあまり対策は変わりませんでした。2023年以降は5類指定もあり順次解除されていきました。マスクを外す人が多くなり、できることも広がりました。ですが、またコロナの波はどんどん大きくなり…
⒊結局学級閉鎖
ついに2023年、学級閉鎖がされました。当時やることがとても多く、かなり忙しくなりました。あとあと聞いた話によると、オンライン授業は「できることがとても少ない」らしいです。
⒋規制、緩和、また規制
そうして、波が大きくなるたびに感染対策を行い、小さくなればまた緩和していくという体制になっています。そのせいで安定的な授業が受けれなくなっています。僕たち現6年生は復習系が多めなのでまだいいですが、低学年にはちょっと疲れてしまうのではないかと思ってしまいます。
まとめ
今回は学校による感染対策の現状と思ったことを書いてみました。
もちろん全く気にしないことは危険ですが、「正しく恐れる」ことが改めて大切だと思いました。
今年学びたいこと——まずは、安定して勉強したいです。また、ICTによるスマートな勉強を進めてもらいたいです。コロナで言えば「with コロナ」というようにこれからはコロナウイルスと付き合っていくことになります。適切な知識、適切な対策。これこそが1番効果を発揮する対策方法ではないでしょうか。
今までビジュアルのScratchやソフトウェアの使い方を学んできたので、個人的に今年学びたいことは、Python(プログラミング言語)と思っています。学校で学びたいことは、中学校での技術家庭科ぐらいかなぁ〜って思っています(笑)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
