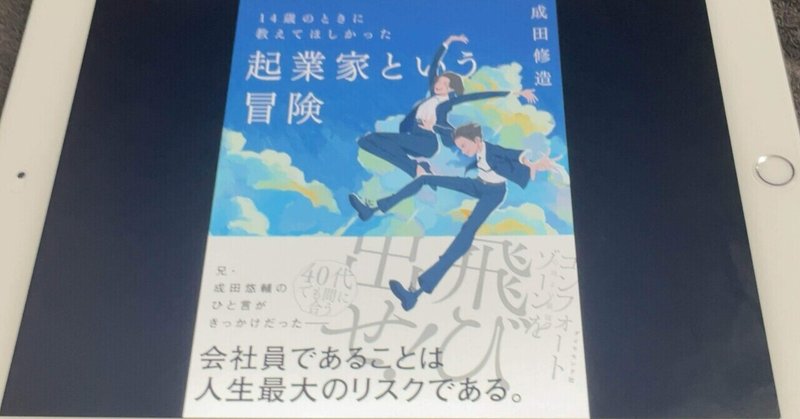
【#読書】起業家という冒険 #成田修造
14歳の時に教えてほしかった 起業家という冒険
著者 成田修造
【読む前にスキ❤️付けてくださいね👍】
いやー、良書でした。
今回はネタバレ少なめにお勧めしていきます。
成田悠輔さんの弟で、クラウドワークスの創業者の1人である成田修造さんの著作です。
40歳でも間に合うと書かれています。
『スタートアップ』ゴリ推しかつ、これが日本に残された唯一の手段だ、みたいな事が書いてあります。
本書は僕みたいなサラリーマンだけをやってきた人や、転職に迷う人、『転職なんて』と思ってる人に推したい。
僕らが絶滅危惧種認定されてること、
僕らが日本経済を壊した者たちの系譜にいることを感じ取れると思います。
すでにスタートアップを始めてる人考えてる人は、本書を読めば進むべき道の安心材料になると思います。頑張っていいのだと思えるはず。
「会社や組織に依存せず、自立して目標を持ち、リスクをとって行動していく」という観点で考えれば、
副業や独立、転職なども十分起業家精神をともなう行動だと思うのです
この一文からもわかると思います、どれもやってない人は【堕ちます】断言します。
なんなら堕ちてます(煽り)
まだ間に合います。
(いろんな)本を手に取り情報を仕入れて行動を一緒に変えていきましょ。
日本政府も着々とスタートアップ支援を進めています。
どの県、どの自治体にもスタートアップを応援する制度や仕組み、組織があります。
お金も用意されています(正しく使われているかは疑問だけど)
お上もスタートアップして欲しいのです。
何故かを考えましょう。
本書後半には、より具体的な考え方や副業の選び方『割合』など詳しく書かれています。
何からとかどのくらいとか、メリットがわかると思います。
社内起業の話もあります。
インサイトでアントレプレナーシップを持つ者
『イントレプレナー』という造語が出てきます。
会社員はここにワクワクすべきです。
【感想】
昭和の
『いい大学に入って、大きな会社に入って、安定した生活を定年まで👍』
という人口ボーナス時期(人口増)に出来上がった高度経済成長期を支えた戦略は平成に入って腐り始め都市伝説となりました。
明確に人口オーナス時期(人口減)に入ってなお、その幻想を語り続ける人らはたくさんいます。
人口オーナス時代での戦略はこれまでと違い、生き残りをかけたやり方になります。
高回転で自由度高く、『みんなで』やる方がいいと感じています。
男が『無理して』働き方、それを女性が家庭で支えるという人海戦略が効かなくなってきているのは明らか。
今後は、男女関係なく、
むしろ女性にも経済活動に参加してもらって誰も取りこぼさない社会になっていく(べき)と思います。
そのためには旧来の概念である『定時』とかコアタイムみたいなものをぶっ壊して、女性が女性らしく、自由度の高い働き方とそれに見合うインセンティブが与えられる方がいいなぁと思うのです。
同じように働かなければならないとか、
無茶な公平や平等の考え方捨てないとそもそも経済回らない。
女性によるスタートアップさんは旧来のサラリーマンより働いているし、かつ自由度高い勤務で頑張ってる。お子さんがいる場合は会社連れてきてたり、リモートで好きな時間や隙間時間に頑張ったりして『稼いでいる』
会社員という働き方が合わないは人も『見え』はじめていて彼らも『そう簡単には格差から堕ちない』ということを選択して頑張ってます。
彼らこそスタートアップの原石なんだろうなと感じます。
僕らサラリーマンの多くが『給料日までの暇つぶし』になっていて頑張っても頑張らなくても給料変わらないって生活してるから、そりゃ頑張らない人が増えますよね。
会社にとってコストでしかない。
だとすれば【法律が変わる事】を予見しなければならない。
日本では給与増額を政府が企業に求めています。
ってことは、企業が求めるのは経営者意思による的確な人員増減だと思います。
会社員は『移ろいゆく者たち』になるはずです。
逃げ切り世代の背中を追いかけてたら船に乗り遅れますよ。
会社の看板を下ろしたときの自分を想像してください。
『怖くて眠れない』が正しい反応です。
なんとかなるやろとタカを括るのもあり。
しかし、なんとかするのは自分です。
僕たちはどこへ行っても
『通りすがりのサラリーマンさっ』
を目指そう。(要検索:ARMS 高槻巌)
【よかったらフォローと、スキ❤️を、そしてX(Twitter)でシェアと感想を頂けると幸いです】
あとがき
さぁみなさん、大海原で会おう。
お読みいただきありがとうございました。もし参考になったり面白かったと思っていただけましたらサポートよろしくお願いします。次の執筆のモチベになります。
