
ヒトからイヌへ「うつるあくび」について考えた。
いやはや、このパンデミックは、いったいいつまで続くんでしょうね。
テレワークをする機会が増え、外出が減り、中には巣ごもり状態が続いているという人もいらっしゃることでしょう。
こんなルーティンを続けていると、ついあくびをする回数が増えてもおかしくありません。
実はかく言う筆者も時々思いっきりあくびをします(笑)
そもそも、この「あくび」という現象はなぜ起こるんでしょうか。
確かに疲れているときにあくびをすることがあります。睡魔に襲われると無意識にあくびが出たりもします。
しかし、あくびをするのは、そうした生理状態のときだけではありません。
たとえば、アスリートが競技の始まる直前に「あくび」を連発する様子がテレビの画面に映し出されることがありますが、あれは何なのでしょうか。
あくびとカーミングシグナル
イヌは不安なときや緊張した際にあくびをすることがあります 。このあくびは「カーミングシグナル」と呼ばれ、自分を落ち着かせるための行動だといわれています。
以前から気になっていたこともあり、この機会にいろいろと調べてみました。
まず、着目したのが、ストレスとあくびの関係。

参考画像:猫のあくび
爬虫類・鳥類・哺乳類・魚類はすべて、けんかなどのストレスをもたらす行動の前やその最中にあくびをするということです。
この場合の「あくび」は、自分を落ち着かせる効果はあるかもしれません。
「脳の最適温度」仮説
しかし、あくびによってストレスが軽減されるとして、そのメカニズムはどういうものなのでしょうか?
そこで、行き着いたのが、脳を約37度の最適温度に保つのに役立っているという仮説です。
これまでの研究で、ストレスや不安が脳の温度を上げることがわかっています。脳が熱くなりすぎると物事に対する反応が鈍くなったり、記憶力が低下したりします。パソコンを使い続けると熱くなって、動作が重くなる。あのイメージと似たような現象です。
人間の脳は、ちょうどコンピューターのように温度にすこぶる敏感だといいます。脳がうまく機能するには低い温度を保たなければなりません。そこで、あくびをして脳のオーバーヒートを防いでいるというのです。
あくびをすると、上顎洞(副鼻腔の1つ)の仕切り壁が動いて、送風機のように脳に空気を送り込んで温度を下げることができるそうです。
と、ここまで「あくび」の話を聞かされた皆さん、あくびが出そうになってませんか?
あくびを専門的に研究している心理学者の中には、あくびについて考えたり、あくびに関する文章を読んだりするだけで、あくびが誘発されるという指摘もあります。
うつるあくびは共感の表れ?
ところで皆さんは、「伝染性のあくび」は他者への共感の表れであるという説をご存知ですか?
この“共感説”について 少し深掘りしてみましょう。
イタリアのピサ大学の研究で、あくびの伝染は、より親しい者同士のあいだで起こりやすいことが明らかになっています。研究者は「あくびの伝染には、共感が主導的役割を果たしている」と結論付けています。
その「共感」が、たとえ退屈あるいは倦怠感に関連したものであるにせよ、動物行動学的にも無視出来ない状況になっているようです。
進化の産物か
ごく最近の研究で、南アフリカに暮らす野生のライオンには、仲間のあくびに「感染」した後、しぐさを同調させる傾向が見られたといいます。
ライオンのあくびの確率は、群れの別のメンバーがあくびをしているのを見た場合、見なかった場合に比べて、139倍も高いことがわかったということです。
とりわけ注目すべきは、次の点です。
🦁ライオンが他のライオンのあくびをまねた後、そのライオンと同じ行動を取った。2頭のライオンが互いに横たわっていたとき、1頭のライオンがあくびをすると、もう1頭もあくびをした。その後、先にあくびしたライオンが立ち上がると他方のライオンも立ち上がった。
狩りや子育て、侵入者からの防御を群れで行なう点で、ライオンはオオカミなどのイヌ族と共通しています。このような社会的動物にとって、伝染性のあくびには、特別な意味があるという指摘があります。
複数の報道記事(英文)が伝えた以下のコメントを紹介しておきます。
米ニューヨーク州立工科大学適応行動認知研究所の所長アンドリュー・ギャラップ氏「今回の研究は、オオカミやチンパンジーといった集団生活を送る動物が群れの警戒を高めるために伝染性のあくびを進化させたという説を裏付けるものだ」「伝染性のあくびは集団意識や脅威の検知に役立つ可能性がある」
高い確率で、イヌ族のあくびを誘い出す方法
伝染性のあくびが起こる可能性があるのは、同じ種のメンバー間だけではありません。

ドイツのある研究施設の囲い地で放し飼いにされているディンゴの群れ。この写真は、私があくびをしてみせた直後の様子
イヌの前でわざとあんぐり口を開ける。あくびをして見せ、そのイヌがまねるかどうか試す。
私は、こんなことをときどきやって楽しんでいます。
やり方をくふうすれば――たとえば、まずふつうにあくびをしてから、次に、手の甲を自分の口の横にあて、あくびをするのと同時に手のひらを大きく開く。
こうしてイヌの口吻に似た形をつくり出して相手に見せる――かなり高い確率で、イヌのあくびを誘い出すことができます。
これは、『犬は「しつけ」でバカになる』(2011年、光文社新書)をお読みになっている皆さんには聞き覚えのある語りだと思いますが、2本足の犬(私のことです)が同書で書いた一節です。
上の写真のあくびはしぐさの「伝播」というべきものでしょう。
あくびをしながら写真を撮るのも楽じゃないです(笑)
この場面は、ディンゴが筆者と共に遊んだ(暴れた)後です。
ディンゴのこのあくびは共感のなせる業ではないか、と筆者は直感しました。
相手と心理的に距離が近いほど体の共振が起こりやすいのです。

やにわに筆者に対して遊びに誘うポーズをとる

「こいつは気になるなあ」と言わんばかりに筆者の靴の匂いを嗅ぐ
たとえば、恋愛初期に意中の相手といっしょに食事をしたとき、そのしぐさをついまねしてしまう。
そんな経験のひとつや二つ、皆さんにもあるのではないでしょうか。
ディンゴのこと
それにしてもこのディンゴたち。
(上のあくびの写真)顔はそっくりですが、やはりそれぞれに個性があるのがよ~くわかりますね。私があくびを誘いだそうとして成功したのは8頭の群れのうち2頭でした。
後のディンゴたちはといえば、
このヒト、何やってんの?
というところでしょうか(我関せず、と寝てるディンゴもいますが)。
しかし家庭犬ではないディンゴからあくびを引き出せた。
このことで、筆者はちょっぴり誇らしげな気分になれました。
🐾 ディンゴは犬ではない?
最近、オーストラリアの複数の大学の研究者が、ディンゴは犬ではなく独自の種だと主張しています。その根拠は、ディンゴにはイエイヌとは異なる多くの特徴があり、1000年以上にわたってオーストラリアという地理的に隔絶された土地に生息し、家畜化された痕跡がないというものですが、これには異論もあります。仮に犬が野生化してディンゴになったという従来の説が覆されたとしても、“イヌ族”であることには変わりありません。
「共感」説には、科学的な裏付けも
もしもこうした伝染性のあくびが、イヌの内側に存在する「共感力」と関連したしぐさだとしたら......ただの生理的な反応ではないということです。
この「共感力」は、人間にとって大きな意味があるのでは?
イヌは人間のマナーに従って生活しています(少なくとも飼い主にそう期待されて生きている)
犬が人のマナーに従うということは、人間の持つ感性と知性に共感できるということではないでしょうか?
ヒトからイヌへのあくびの伝染に、「共感」が役割を果たしているという考えについては、科学的な裏付けが取れているようです。
2013年に東京大学と京都大学の共同研究チームが注目すべき実験を行なっています。
一般家庭で暮らす25匹の犬に飼い主と知らない人のあくびを見せ、その反応を観察した。また、それらの人々に別の表情をしてもらい、イヌがその違いを認識できるかどうか調べた。さらに、イヌの「ストレス度」を測る心拍計測器をつけた。
その結果、犬にあくびが伝染する頻度は、あくび動作を見せた時の方が、その他の口の動きを見せた時よりも非常に高かった。飼い主のあくびに応じた割合は、見知らぬ人の時より3倍以上高かった。イヌの心拍数については、飼い主の場合と見知らぬ人の場合にほとんど変動がなく、どちらの場合もストレスを感じていないことがわかった。
この研究報告によれば、イヌたちの「伝染性のあくび」は、人間への共感を示す行動だと示唆しているというわけです。
さて、あくびの話も、いよいよ終局です。
皆さん、この話を読みながらあくびをしましたか?
もしあくびをしたのなら、あなたの隣のわんちゃんはそれに続きましたか?
最後まで読んでくれて、ありがとう!!
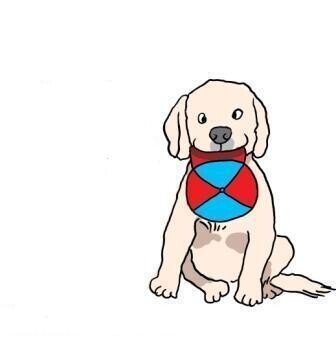
もしこのコラムを「いいね」と思ったら、「❤️」ボタンを押したり
Twitterでシェアしたりしてね👍🏻
最後まで読んでくださりありがとうございます。 皆様からのサポートは、より良い作品をつくるためのインプットやイラストレーターさんへのちょっとした心づくしに使わせていただきます。
