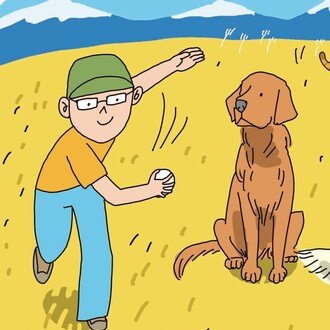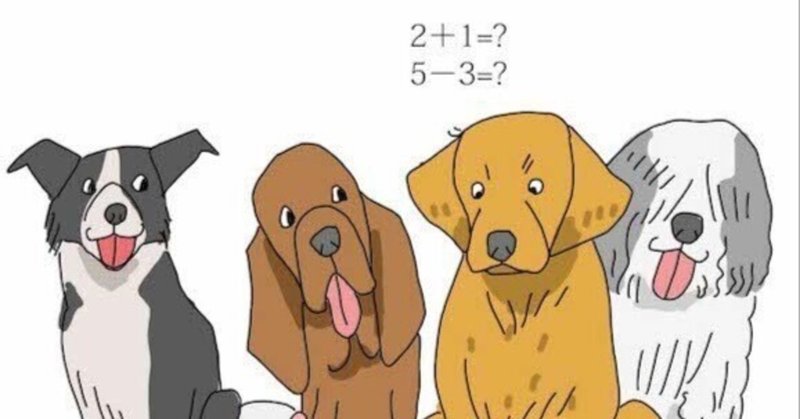
ここまでわかった犬たちの内なる世界 S2#06犬の数的センス
算数ができる天才犬の謎
足し算・引き算は朝メシ前、かけ算・わり算もどーんと来い!
算数に挑み、正答率は、ほぼ100%。テレビにこんな”天才犬”が登場することがあります。
筆者はテレビの画面を通してではなく、「生」で数回その様子を見たことがあります。 筆者がフィールドにしていた八ヶ岳山麓の牧草地にも “計算のできる犬“がいたのです。 その答え方は、次のようなもの。
「2足す2は?」と、質問されれば、「ワン、ワン、ワン、ワン!」と4回吠え、「5引く4は?」と問われれば、「ワン!」と1回吠えます。
正解の度に、ごほうびのトリーツをもらえます。
このゴールデンレトリバーは、テレビにも登場して、お茶の間をあっと言わせました。 パーフェクト! 正答率は100%です。

ところが、本当は、暗算をして いるわけではないのです。
常識で考えてみてください。上の写真のような平方根の計算がイヌにできるわけがないじゃないですかと言っている筆者ですが、実は紙に計算式を書くにあたって「どうせやるなら、 ありきたりの四則計算はやめて、ルートを使いましょう」と持ちかけたのも筆者です(笑)
計算をしていないのに、 どうして正解を出し続けることができるのでしょうか?
これに答えるには、「クレバーハンス効果」の話を始めなければなりません。
動物行動学や心理学の本でよく取り上げられてきた有名な話なので、ご存知の方も少なくないと思いますが、 ここでは、ざっくりと紹介しておきましょう。
20世紀初頭、「とても頭がよくて計算のできるハンスという馬がいる」と喧伝されました。紙に書きだして計算問題を出すと、ハンスは地面をひづめでたたいて答えを示します。1~100までの自然数なら難なく答えます。加減乗除はもちろん、分数を少数に変換することさえできるのです。
「こりぁすごい!」たくさんの科学者が、動物の思考力のすばらしさを実演するものだと褒めたたえました。当時は動物行動学が産声を上げたばかりということもあり、動物の思考力を過大評価する風潮があったようです。
後に、ハンスは暗算などしていないということが明らかにされました。ハンスは、問題が書かれた紙など見ていなかったのです。固唾を呑んで自分を見つめる観客のようすに細かい注意をはらいつつ、ちょっとした動きや合図に反応して、自分のたたき終わるタイミングを計っていた、というのが真相だったのです。

イヌが正解を出すことができた理由はもうおわかりですね?
「計算」の原理は、ハンスと同じで、質問者のちょっとした動きや合図に反応して、吠え終えるタイミングを計っていたのです。
質問者(飼い主)から送られているサインは、よほど注意していないとそれと気づかないようなものです。ふだんから飼い主のしぐさをよく観察していたこのゴールデンレトリバーは、そのサインを決して見逃さなかったのです。
このようなことが、 もちろんすべてのイヌにできるわけではありません。イヌの個体差には大きな開きがあります。
そもそも、合図を出す人とそれを読み取るイヌとの親和性がなければ「クレバーハンス効果」が生じることもないでしょう。
イヌの計算力の実態は?
前提条件は量的多少がわかること
実際のところはどうなのでしょう。イヌに算数はできない / イヌも算数ができる
あなたはどちらだと思いますか?
計算能力の前提となるのは、ものの大小だけでなく、ある量が別の量よりも多いか少ないかを識別できるかどうかです。
最後まで読んでくださりありがとうございます。 皆様からのサポートは、より良い作品をつくるためのインプットやイラストレーターさんへのちょっとした心づくしに使わせていただきます。