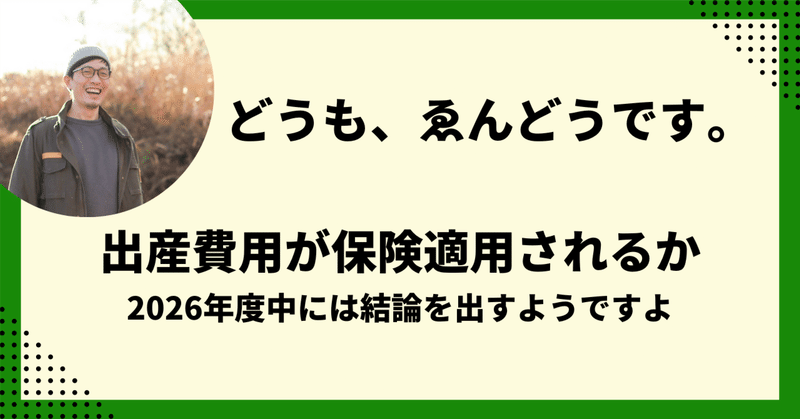
いよいよ出産費用に保険適用されるか
どうも、ゑんどう(@ryosuke_endo)です。
少子化対策の一環として、厚生労働省とこども家庭庁が出産費用の保険適用を検討しているそうです。
2026年(令和8年)度を目標に、出産にかかる費用を保険でカバーすることを目指し、その検討会が開かれました。
そもそも論として、なぜ出産が保険適用されてないんだろうってことをご存知ない方もいらっしゃるでしょうし、もしかしたら「保険が適用されて40万円」みたいな金額感なのだと思っている方もいらっしゃるでしょうから、その辺を改めて見ていくことにします。
出産費用の現状
まず、現在の日本における出産費用について。
厚生労働省が2021年に公表した出産費用の推移を見てみると、2012年以後で出産費用は右肩上がりであることがわかります。ドンドン高騰化しているってわけですね。

全国平均と中央値を見てみると、45万円台なのですが、地域や医療施設によってその金額は大きく異なります。
たとえば、東京都の公的病院での出産費用は平均して約56万5000円、一方、鳥取県では約35万7000円と、かなりの差があります。

なんでこのように差が生まれるのかといえば、地域の所得や物価、妊婦年齢等といった多くの要因が絡み合っていて、最も影響を与える要因は所得だったそうです。

じゃーなんで所得が多い地域は高くなるのかっていうと、私立医院が多いからって話なんですよね。私立ってことは、それぞれにサービスを競うことになりますよね。付加価値としておいしい食事を提供したり、産後ケアを手厚くしたり。
それぞれに事業者として差別化を図ろうとした結果、、高騰化し続けているってことなんでしょう。おまけに少子化で産む子どもの人数が少なくなっているわけで、一人単価が高くなってもおかしくありませんよね。
じゃー、かといって高額化する出産費用に対して何にも手当というか補助がないのかっていうと、そんなことはありません。日本ではいくつかの公的支援制度が存在しますして、代表的なところを挙げていくと…
出産育児一時金: 2023年4月から、出産育児一時金が42万円から50万円に引き上げられました。この一時金は、妊娠4か月以上で出産した場合に支給されます。
妊婦検診費の助成: 各自治体が提供する公費助成により、通常14回の妊婦健診が無料となります。これは、妊娠届を提出すると交付される「妊婦健康診査受診票」に基づきます。
高額療養費制度: 健康保険が適用される帝王切開などの場合、1か月の医療費が一定額を超えた場合、その超過分が支給されます。
保険適用の背景と議論
で、今回の主題となっている保険適用の議論は、少子化対策としての意義が大きな背景となっていることは大いに関係しているわけで、出産にかかる経済的負担が軽減されることで、出生率の向上が期待したいわけです。
もちろん、保険適用には財政的な課題も伴います。
出産を保険適用することで公的負担が増加しますから保険料や税金の負担が増えることが予想されますし、既存の支援制度との兼ね合いを見ながら、どのように財政負担を軽減するかを議論し結論づけていくってことなんでしょう。
そもそも、なんでこれまで保険適用が見送られてきたのかも見ていく必要があります。
まず、前提として出産は自然な生理現象と見なされ、病気や怪我と異なり、基本的には医療行為としての保険適用の対象外とされてきました。これにより、医療保険制度の枠外で取り扱われてきたと。これが根本。
次に、出産費用の保険適用には多額の公的資金が必要となります。少子化や高齢化による医療費の増加といった背景から、財政負担が増えることを避けるために保険適用が見送られてきたことも考えられます。
かといって無策だったわけでもなく、出産育児一時金や妊婦検診費の公費助成など、既存の支援制度だって一定の役割を果たしていて、それらが出産費用を補助する形で機能してきました。そのため、追加的に保険適用を行う必要性が低いと判断されてきたってこともあるでしょう。
でも、保険適用されるってことは医療費が一定の基準に制約されるってことにもなりますから、医療機関が提供するサービスの質に影響が出る可能性があります。特に高品質なケアを提供するために、自由な価格設定を維持することが求められてきたからこそ、地域での出産費用の格差が生まれたことになります。
保険適用のメリットとデメリット
では、保険適用することによりメリットやデメリットはどんなことがあるんでしょうね。
まず、何よりも経済的負担の軽減されます。
保険適用により、出産にかかる自己負担額が大幅に減少しますから、これは特に年齢が低い世代の経済的に厳しい家庭にとって大きなメリットとなるでしょう。
次に、保険適用されれば最低限の質を担保することになりますから、一定以上の品質を持つ医療サービスを受けやすくなります。妊婦健診や産後ケアなどの支援が充実し、母子の健康がより確保されることにつながるかもしれません。
そして、何よりも少子化対策になることが期待されますよね。
出産にかかる経済的負担が減ることで、子供を持つことへの心理的・経済的ハードルが下がり、出生率の向上を期待したいところです。
逆にデメリットとなることは何か。
単純に、これまでにかかってこなかった医療費負担が大きくなりますね。
保険適用により、医療費の総額が増加する可能性がありますから、これに伴って保険料や税金の負担が増えるかもしれません。
保険適用されることによって、医療機関の収益構造が変わる可能性が考えられます。特に小規模な私立産科では、高待遇なサービスを売りにしていたのに保険適用しなければならなくなったおかげで収入の減少や経営の圧迫なんてもことも考えられるのではないでしょうか。
そうなれば、全体的にサービスの低下を招く可能性もあります。
保険適用するってことはサービスの標準化が進むことになりますから、個々のニーズに対応した高品質なケアが提供されにくくなるかもしれません。さらに、過度な負担が医療従事者にかかり、医療従事者への負担が増加した結果、離職する人たちが増えてしまいサービスの質が低下するリスクもあります。
おわりに
と、こんなところかな。ここまで30分ですね。
今日はこの辺で失礼しまーす。
ではでは。
ゑんどう(@ryosuke_endo)
#えんどうnote 、マガジンをフォローすると通知が届きます!
X(Twitter)もやってますのでフォローしてください!
最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。 お読みいただき、それについてコメントつきで各SNSへ投稿していただけたら即座に反応の上でお礼を申し上げます!
