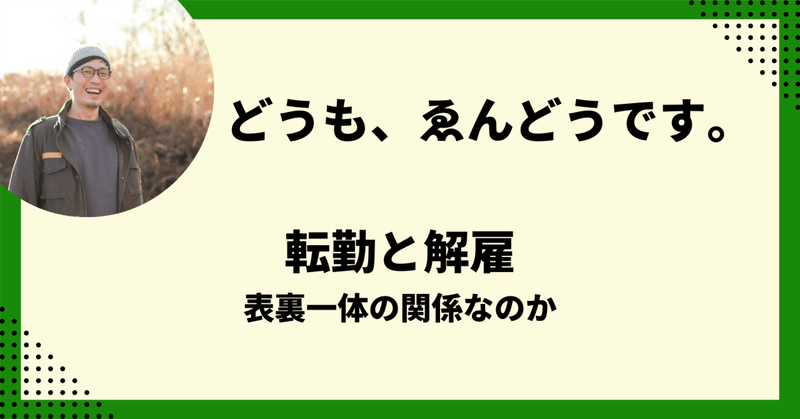
「転勤」と「解雇」の関係
どうも、ゑんどう(@ryosuke_endo)です。
日経新聞にデカデカとダチョウ倶楽部のギャグが掲載されているので驚きました。
内容は、厚生労働省が新たに定めた労働条件明示の制度に関するもので、大々的に「転勤」を扱ったもの。「聞いてないよ」と記載があるのは、『会社員にとって転勤はありふれた光景だ。』といった書き出しからも分かる通り、突然の辞令によって転勤を指示された従業員の心情を表現してのものでしょう。
でも、転勤があるだなんてのは全国規模や各都道府県の中に支店や支所を持つ、それなりの規模を有する会社でなければ有り得ない話で、それほど多くの人に関係する話とは思えませんが、ネット上を中心に悲喜交々が投稿されるってことは、それに苦しんでいるというか、悩んでいる人は一定数いることが伺えます。
今回は、この新制度の中身に少し触れつつ、転勤と解雇の関係性について考えていくことにします。
「雇用条件の明示」に関する新制度について
詳細は厚生労働省のページにあるので「これ、みといてー」で終わりなのですが、それだとわざわざ取り扱うのに不親切なため、一応の解説を入れてみます。
新たな制度において提示されているのは主に以下の3つ。
1. 就業場所・業務の変更の範囲の明示
まず、全ての労働契約の締結時および有期労働契約の更新時には、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加えて、これらの「変更の範囲」についても明示が必要となります。将来的な配置転換、つまりは転勤の可能性を明確に提示する必要が出てきたわけです。
2. 更新上限の明示
次に、有期労働契約の締結時および更新時には、契約の更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無とその内容を明示することが求められるようになっただけでなく、最初の労働契約締結後に更新上限を新設・短縮する場合には、雇用主はその理由を労働者に事前に説明しなければいけません。
3. 無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示
最後に、雇用契約における有期から無期への転換ルールに基づき、無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、雇用主側は無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)と、無期転換後の労働条件を明示する必要があります。特に、無期転換後の労働条件を決定する際には、正社員等とのバランスを考慮した事項について説明するよう努めることが求められます。

この制度改正の目的は何かというと、労働者の雇用安定と雇用に関する透明性の向上でしょうね。特に有期労働契約において、労働者が将来的な雇用条件を明確に把握できるようにすることで、無期転換の機会を含む労働条件の変更が不意に行われることを防止することができますから、労働者の権利保護を図っていることが伺えます。
企業にとっては、労働者への説明責任が強化されるため、労働条件の変更や無期転換の機会に関する情報提供の徹底が求められ、実務面においては少し工数が増えることになりますが、労働者にとっては雇用条件がより明確になることで、キャリアプランの見通しが立てやすくなるでしょう。
「転勤」と「解雇」の関係性
上記の制度が変わることによって労働者にとっては見通しがよくなったように思えますが、直近の就業場所だけでなく未来に転勤する可能性のある場所まで明示されることになった点については、正直なところ実質的に意味をなさないでしょう。
会社へ応募する段階において転勤する可能性や事業所の住所などが記載されていますし、それらを事前に把握した上で労働者側は応募しているわけですから、労働条件通知書に記載されたとて「知ってます」ぐらいなものです。
労働者が結婚や出産、育児に介護などライフステージによって転勤を渋る理由が出てくることは想定できますが、入社時点でそれを予測していたとしても転勤に関して拒否をしたくなるかどうかまでは読めないものでしょう。
転勤を拒否することは出世の道が断たれることといった理解は多くの人がしていることでしょうが、それは「会社の指示に従えない人」だからと言って解雇されないことを免除されることとのトレードオフです。
日本の雇用慣行において労働者側が転勤を受け入れることと、会社都合での解雇が難しいことは密接に関連しており、従来の雇用慣習において日本は終身雇用制度によって従業員を簡単に解雇できない代わりに業務上の必要に応じて転勤を命ずることができましたが、これは安定して雇用してもらうことの裏返しといえます。
このコインの裏表といえる仕組みは、高度成長期には企業の成長と従業員の生活の安定に貢献してきたことから企業は長期的な視野に立って人材の育成を行うことができたものの、現在のようなグローバル化が進み、あらゆる産業構造も変化してきた状態では維持が難しいのは自明でしょう。
企業側からすれば、転勤は解雇を回避するための一つの手段です。仮に、特定の部署の業務を縮小する必要がある場合、解雇ではなく他の部署への転勤を命じることで、従業員を継続的に雇用することができますから、企業は法的リスクを回避しつつ、経営資源を最適化できます。
しかし、従業員にとって転勤命令は生活に大きな影響を与える可能性がありますが、解雇されないという保証があるため、一定の安定性も得られるる点は利点かもしれません。
つまり、解雇されないのであれば転勤もやむなしでしょうってのが現状の制度なのです。
なぜ日本では簡単に解雇できないのか
よく、アメリカのドラマなんかをみていると「Fire you!」といってクビを宣告される人を見かけます。有名な都市伝説で、スティーブ・ジョブズはエレベーターで一緒になった従業員が「自分のやっている仕事」について説明できなかった際に「Fire you!」といってクビを切るだなんてものが出回っていたぐらい、アメリカでは「仕事をしないのであればクビ」は経営者が持つ当然の権利行使なのです。
日本ではそうなっていないことはご存知の方も多いかと思いますが、これは労働者の解雇が「解雇権濫用法理」に基づいて厳しく規制されているからで、解雇が社会通念上相当と認められない場合、無効となるというものです。
なぜ、そこまで厳しくなっているのかというと、労働基準法第20条や解雇権濫用法理(労働契約法第16条)により、正当な理由がなければ解雇は無効とされるからであり、その要件として以下の4つが示されています。
解雇(業務上)の必要性
解雇回避の努力
解雇対象者の選定基準
労働組合や労働者への説明・協議の適正さ
いま、解雇規制についても緩和の動きがとられているそうなので、今後は変わっていくのかもしれません。
ですが、もし、仮に転勤が嫌なのであれば違う会社に移るなりして、自分の人生を自分で決定できるわけですからね。自由にすればいいんじゃないでしょうか。
おわりに
ま、最終的には雑な締め方をしてしまいましたが自由にできるんだから自由にすればいいって話ですね。それに、転勤が嫌なのであれば、相応の実力と実績を伴って交渉する他にありません。それもなしに駄々を捏ねることは大人がすべきことではないでしょう。
ではでは。
ゑんどう(@ryosuke_endo)
#えんどうnote 、マガジンをフォローすると通知が届きます!
X(Twitter)もやってますのでフォローしてください!
最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。 お読みいただき、それについてコメントつきで各SNSへ投稿していただけたら即座に反応の上でお礼を申し上げます!
