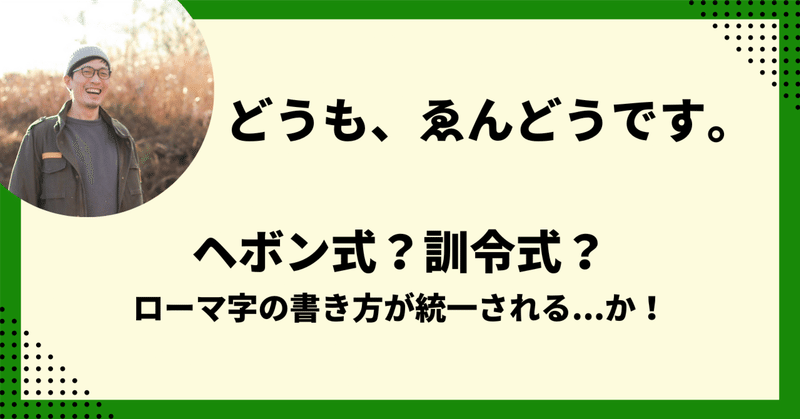
ローマ字の書き方が変わるかもしれない
どうも、ゑんどう(@ryosuke_endo)です。
もうね、これは由々しき問題というか、看過できませんよ。
多くの日本語話者のみなさんは、英語よりもローマ字の方が馴染み深いことでしょう。ぼくのようなドメスティック日本人からすると、ローマ字の方が英語っていうか、英語よりもローマ字の方が大切っていうか、そもそもローマ字が存在しなければ、こうやってタイピングをして文字を羅列させることもできませんからね。
そんな、我々の生活に身近なローマ字ですが、記入の仕方が二通りあるってことをご存知ですか。その名もヘボン式と訓令式と言いますが、この記入の仕方が、将来、統一されるかもしれないといった報道がNHKから出されていました。
報道の内容は、文部科学省がローマ字の書き方について、現在の時代に合うようにわかりやすくするよう専門家に依頼したとするもの。現在、訓令式とヘボン式の2つの書き方があり、どちらを使うかで意見が分かれています。特にパスポートや案内看板などはヘボン式が使われているのですが、文部科学省はこれを受け、より詳細な調査を行う予定としています。
ヘボン式とか訓令式といっても「?」と具体的に想起することができない人も多いでしょうから、簡単に説明していきましょう。
たとえば、「し」を書くときに「shi」か「si」か迷う人もいれば、迷わずに「si」とタイプしてしまう人もいるでしょう。
ヘボン式とは、19世紀にアメリカの宣教師ジェームス・カーティス・ヘボンによって考案されたローマ字表記法とさてています。ヘボンさんは日本語を英語圏の人々に教えるために、日本語の発音を英語のアルファベットで表記する方法を確立した偉大な人物です。
どういうものかというと、具体的には、「し」を「shi」、「つ」を「tsu」、「ち」を「chi」と表記します。これは、日本語の発音をなるべく英語の音に近づけるための工夫をしたことの裏付けといえます。
ヘボン式の特徴は、日本語の音を外国人にとって発音しやすく、理解しやすい形で表記することです。そのため、英語圏の人々にとっては学びやすく、観光案内やパスポートなどの公的な場面でも広く採用されています。たとえば、日本の都市名や駅名もヘボン式で表記されることが多く、外国人観光客にとっては非常に便利なものとしていまだに多くの場面で活用されています。
また、ヘボン式はローマ字入力においても一般的に使用されます。たとえば、「し」を「shi」と入力することで「し」と表示されるように、日本語入力システムでもヘボン式が標準として広まっていますから、我々、日本人にも自然とヘボン式に親しむことが可能となりました。
ヘボン式はその明快さから、日本語学習者にとっても有用だそう。英語の音に近い表記法を採用することで、発音のガイドとして役立ちます。そのため、日本語教育の場でも広く用いられています。
が。
ヘボン式には一部の日本語の音を完全には表現できないという欠点もあり、たとえば、「ふ」を「fu」と表記することで、実際の発音とは微妙に異なる音になることがあります。また、日本人にとっては英語のアルファベットを使うため、直感的でない場合もあるのが困りどころ、だそうです。
一方、訓令式は、1937年に日本政府が制定したローマ字表記法みたい。
日本語の発音をより正確に表記するために、日本人自身が使うことを前提に設計されているので、「し」を「si」、「つ」を「tu」、「ち」を「ti」と表記します。ヘボン式が英語話者になれ親しめるように考案したのに対し、日本語の音をそのままアルファベットで表現することを目指したものです。
訓令式の特徴は、何よりも日本語の音を忠実に再現すること目指したこと。
これにより、日本語の発音をそのままローマ字に移すことができ、日本人にとっては直感的で理解しやすい表記法となっています。例えば、「し」を「si」と表記することで、日本語の「し」の音をそのまま表現できますからね。
また、訓令式は、主に教育の場で使用されており、小学校や中学校で学ぶローマ字表記法の基本となっています。これにより、子供たちは日本語の音をそのままローマ字で表記する方法を学び、将来的に外国語を学ぶ際にも役立つスキルを身につけることができます。
しかし、訓令式は国際的にはあまり広まっておらず、外国人にとっては理解しにくい表記法となることがあります。たとえば、「si」と表記されても、英語圏の人々には「し」の音として認識されにくいことがあるそう。
また、パスポートや国際的な標識などではヘボン式が主流であるため、訓令式を使う場面が限られています。
訓令式のもう一つの欠点は、日本語の一部の音を完全には表現できないことにあるそうで、結局はヘボン式と同様に課題があるってことです。
たとえば、「じ」と「ぢ」を区別する表記が難しいため、誤解が生じることがあります。また、日本語特有の発音を完全にローマ字に置き換えることが難しいため、精度に限界があるとされています。
まぁ、なんていうか、こういう話があるんだってだけなのですが、暇つぶしにはなったでしょ!
ではでは。
ゑんどう(@ryosuke_endo)
#えんどうnote 、マガジンをフォローすると通知が届きます!
X(Twitter)もやってますのでフォローしてください!
最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。 お読みいただき、それについてコメントつきで各SNSへ投稿していただけたら即座に反応の上でお礼を申し上げます!
