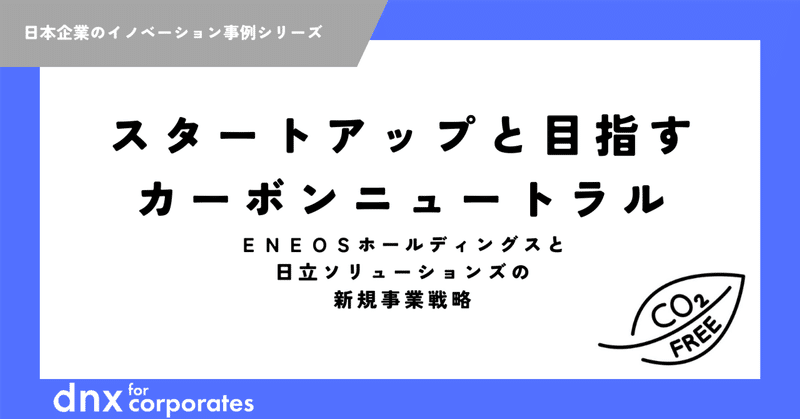
スタートアップと目指すカーボンニュートラル|ENEOSホールディングスと日立ソリューションズの新規事業戦略
世界的な重要課題であるカーボンニュートラル実現に向け、Climate Techに取り組むスタートアップへの注目が高まっています。こうした市況の中、同課題への対応に迫られる大手企業は、スタートアップとどのように連携し、どんな取り組みを進めているのでしょうか。ENEOS CVCを通じて国内外のスタートアップへの投資と事業開発を行うENEOSホールディングス。そして、ドイツのスタートアップと連携し、サプライチェーン脱炭素支援ソリューションを展開する日立ソリューションズ。両社の取り組みや立場の違いについて、対談形式で紐解きます。

はじめに ー 迫る期限とClimate Techへの注目
前田:パリ協定では世界的な平均気温上昇を1.5度に抑える努力を続けることが目標として掲げられていますが、2023年時点で同数値は1.48度に達しており、温室効果ガスの排出は依然として止められていません。日本に限らず、世界中で天災による甚大な被害が出ていることも、皆さんが実感していることでしょう。

こうした課題感を受け、投資家のClimate Techに対する視線は熱くなりつつあります。パリ協定以降、米国に限らずグローバルでClimate Tech領域のベンチャー投資額は急速に伸びました。

Climate Techを細分化して見ると、新しいエネルギーの供給、生産系、農業系、交通系、環境管理など、さまざまな領域においてスタートアップが活躍しています。すでにユニコーンとなった企業もあり、今後の成長が期待できるところです。また、自主的カーボンクレジット市場(VCM: Voluntary Carbon Market)は2030年まで爆発的に伸びるだろうと予測されており、VCの立場から見て、Climate Techは非常に注目度の高い領域であると考えています。
ENEOSホールディングスと日立ソリューションズのカーボンニュートラルに向けた取り組み
前田:では、ここからはENEOSホールディングスと日立ソリューションズの取り組みについて聞いていきます。まずENEOSホールディングスの取り組みについて、大間知さんにお話いただきましょう。
大間知:私たちENEOSグループはガソリンスタンドでおなじみの石油事業のほかに、電気・都市ガス事業、再生可能エネルギー事業や素材事業、金属事業などを手掛けています。ENEOSホールディングスにENEOS CVCが新設されたのは、約5年前のことです。投資判断をENEOS CVC内で完結させ、スピーディな投資を行うことを強みとする私たちは、すでに150億円規模の出資実績を積み重ねてきました。

ENEOSホールディングスは「エネルギー・素材の安定供給と、カーボンニュートラル社会の実現の両立」を目標として掲げています。その目標達成のために、水素、再エネ、脱炭素といったエネルギー領域、そしてEVやカーシェアリングといったモビリティ領域を中心に、私たちは投資探索や事業開発を推進しています。

特に注力しているのは、「まちづくり」、「モビリティ」、「脱炭素社会」、「循環型社会」、「データサイエンス・先端技術」の5つのテーマです。国内に約1万2000件あるサービスステーションのネットワークを活かしつつ、脱炭素・循環型社会の実現を先端技術によって実現していきたいと考えています。現在はテーマごとに国内外のスタートアップ約42社への投資を行い、事業開発を進めています。
前田:次に小沢さん、よろしくお願いいたします。
小沢:日立ソリューションズはサステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)を旗印とし、自社改革とお客様に対するサービス提供、双方におけるサステナビリティを追求しています。その中で、私はサプライチェーンマネジメントとカーボンニュートラルに関わる取り組みを担っています。

取り組みの具体例として挙げられるのは、サプライチェーン脱炭素支援ソリューションの展開です。サプライチェーンで発生するCO2排出量を可視化・予測し、SX/DXといった各企業の削減の取り組みへと結びつけていくためのソリューションを私たちは提供しています。本ソリューションの一部である、製品あたりのCO2排出量の計算・可視化とサプライヤーCO2排出量の測定・管理・削減には、昨年から日立グループのCVCを通じて連携しているドイツのスタートアップのLCA脱炭素プラットフォームが活かされているのも特徴のひとつです。
ENEOSホールディングスと日立ソリューションズのアプローチの違い
前田:二社の立ち位置の違いをもとに、もうすこし詳しく取り組みについて聞いていきましょう。日立ソリューションズは、直接スタートアップに投資する機能を持たない中で、さまざまな企業のCO2削減に対して何ができるのか、どのようなツールやプラットフォームを導入すれば実現できるのかという視点でカーボンニュートラル実現に向けて取り組んでいますね。その取り組みを進めるうえで、VCをどのように活用されていますか。
小沢:私たち日立ソリューションズとしては直接的な投資機能を持っていませんが、日立グループ内には日立ベンチャーキャピタルというドイツを拠点とするCVCがあります。同社でドイツのスタートアップ企業に投資をする中で、今回連携しているMakersiteとも出合えました。また、DNX Venturesとは北米カリフォルニアを拠点に連携しており、グローバルで将来性のあるスタートアップを探索することができています。この連携を通じて、すでに数十製品を日本に持ち込むことができました。
前田:「スタートアップ=シリコンバレー」という印象が根強くありますが、今回のテーマであるClimate Techに関しては、世界中で同時多発的にイノベーションが発生しています。その目まぐるしい動きをフィルターしていく目的でのVC活用、というヒントを得られました。
一方、ENEOSホールディングスは石油事業を担うENEOSを中心に、CO2排出量が国内CO2排出量の約20%近くを占めるという特徴があります。自社で研究所も有しており、時にはスタートアップと連携して技術開発をしていることもあると聞きました。先ほど説明していただいたENEOS CVCは、こうした前提の中でどのような役割を担っているのでしょうか。
大間知:まず前提として、一般的にCVCには研究開発部門の下に置かれるものもあれば、会社全体の方針を決める経営企画の下に置かれるものもあります。ENEOS CVCはどちらでもなく、完全に独立した形になっているのが体制面での特徴です。それを踏まえて、ENEOS CVCの一番の目的は事業を創ることです。そのため、一技術の開発を目的とせず、長期的な視点で事業開発を追求していく点が研究開発部門とは異なる点と言えるでしょう。また、スタートアップへの投資機能を持っているのは、ENEOS CVCのみです。
ENEOS CVCにおける財務リターンと戦略リターンの捉え方
前田:なるほど。CVCでは財務リターンと戦略リターンをどのように求めていくかという議論がよくありますが、その点についてもお聞かせください。
大間知:戦略リターンのひとつは、まさに目的である「事業を創る」ことです。ENEOSグループはCO2排出量が多いので、グリーン(ブルー)カーボンクレジット創出は事業開発の一環と定義できます。そうした観点から見れば、私たちはそうした戦略リターンに重きを置いているCVCと言えるかもしれません。一方で、財務リターンをまったく気にしていないかと言われれば、決してそうではありません。会社が運営している以上、資本コストはしっかりカバーしていくという最低限の目標を持っています。
前田:財務リターンを一定以上は求めるものの、それ以上に新規事業開発という大きな目的を掲げ、グリーンカーボンクレジット創出に向けたパートナーシップを探しているということですね。ところで、石油産業の大元の事業についてはシュリンクしていかなければならないプレッシャーが強いのではないでしょうか。だからこそ新規事業開発の重要性が高まっているとも言えそうでしょうか。
大間知:そうですね。ガソリン車の燃費は年々良くなっていますし、これからはEV車が一般に普及していくでしょう。こうした市況感を受けて、当然石油の需要は減っていきます。そこに代わる事業を展開するために、現在は企業買収などを通じて再生可能エネルギービジネスのすそ野を新たに広げている最中です。研究開発部門では、水素とCO2から合成した「合成燃料」を作る研究が進んでいます。こうした研究開発成果と、オープンイノベーションを通じてスタートアップから得られるピースを組み合わせながら、新規事業へと結びつけていくことが重要だと考えています。
日立ソリューションズが見るカーボンニュートラルへの取り組みの現地点
前田:一方、日立ソリューションズはCO2削減に向けたツールやプラットフォームを、多種多様な企業に対して導入する立場です。その観点から、カーボンニュートラルへの取り組みは今、日本企業においてどの程度進んでいるのか、率直な感想をお聞かせください。
小沢:カーボンニュートラルの取り組みがビジネスとして成功している事例は、残念ながら国内にはそう多くないのが現状だと思います。国内のCO2排出量の約3分の1を占める製造業界では、自動車や化学、鉄鋼などの各業界の企業が手探りをしながら選択肢を検討しています。その中でも、年商1,000億円クラスの大手企業は、会社として取り組まなければならないというプレッシャーを強く感じていることでしょう。
自社で取り組んでみたものの、時間もコストもかかりすぎるという課題を抱えて日立ソリューションズに相談してくださる企業も珍しくありません。カーボンニュートラル実現まではまだまだ時間がかかりそうではありますが、これからパイオニアが道を切り拓き、日本産業の改革を牽引していくことになるでしょう。私たちもその一助となれるよう、支援を続けていきたいです。
前田:なるほど。CO2排出量が多い産業から取り組みが進んでいる、という単純な話でもないようですね。取り組みへの速度感や熱量は産業領域ごと、あるいは企業ごとに異なってきそうですが、彼らを動かすプレッシャーの根源は社会的な要請なのか、メディアなのか、あるいは株主なのかというと、どれが近いでしょうか。
小沢:実際の現場の声からすると、バイヤーからの要請が一番近いかもしれません。サプライヤー全体におけるTier1、Tier2のサプライヤーが情報開示の要請、つまりバイヤーからの「どうなっていますか」という問いに対して答えなければならないということが、動機づけとして非常に大きいです。
成功事例|ENEOS CVCによる「マルチモビリティステーション」立ち上げ
前田:こうした難しさを各企業が抱えている背景を踏まえたうえで、ENEOS CVCの取り組みの中での成功事例をお聞かせください。
大間知:東京都内の「マルチモビリティステーション」立ち上げについて紹介します。「マルチモビリティステーション」とは、自転車やキックボード、e-bikeといった複数の電動モビリティと、電動二輪向けのバッテリーのシェアリングサービスを提供する拠点です。本拠点を事業化させるために、私たちは複数のスタートアップに対する出資を行い、連携しながら単月黒字化に至るまでの道のりを歩みました。そして昨年度の12月、本事業をENEOSグループ内の既存事業部門に提案し、本格的な移管へとこぎつけました。

ちなみに、同拠点に用いられている樹木は久万高原町のものなのですが、ENEOS CVCは同町と連携し、森林を活用した脱炭素社会の実現、林業の担い手不足などの社会課題の解決といった価値創造を目指しています。今回の「マルチモビリティステーション」における樹木活用については、ENEOSグループ全体を見るカーボンニュートラル戦略部につなぎ、今回の活用事例をベースとして価値創出の事例を増やしてほしいと伝えました。
前田:素晴らしいですね。CVCがスタートアップと共に事業開発を行い、それを社内の事業部門に移管していくことが実現できていることに驚きました。いずれ何かしら本社の事業につなぐという話は出るものの、結局は動かないことのほうが多いのです。こうしたモデルがしっかりあることはスタートアップからしても非常にありがたいでしょうし、CVCとして適切なシナジー作りに成功している印象を持ちました。
スタートアップとの連携がカーボンニュートラル実現への足がかりに
前田:最後に、お二人が感じているスタートアップと連携していく難しさと、期待していることについてお聞かせください。
大間知:ENEOS CVCの活動について社内のマネジメント層に説明していると、彼らとスタートアップとの意識には大きなギャップがあると痛感します。そのギャップを埋めるために、マネジメント層が現場に足を運ぶ機会をつくったり、スタートアップとコミュニケーションを取る場にマネジメント層を加えたりと日々工夫していますが、こうした意識のすり合わせはとても難しいところです。ENEOSグループは長年石油事業を続けてきた会社ですから、「安定供給」という意識が根強いです。今後は、それとともに、目まぐるしい変化を受け入れる意識の醸成も必要と強く感じています。
小沢:日立ソリューションズも同じく、これまでのビジネスで培われてきた考え方や常識があるからこそ、自由にできるところと、そうでないところがあるというのが正直なところです。例えば新製品を作るとき、「その製品は日本のお客様に何個売れるか」という発想で確度を図る意識が前提にあると、投資家の方々から大規模な投資を受けて果敢に挑戦する事業というものを、なかなか想像できないと思います。私自身、そういった違いをもどかしく思うこともあります。一方で、私たちの立ち位置だからこそ生み出せる価値というものもあると感じていますし、スタートアップが生み出す価値をその立場から活用していきたいという想いを持っていますので、今後もスタートアップとの連携を強固にしていきたいです。
大間知:社内の研究開発部門だけでは新しい価値を生み出すのが厳しい時代の中で、スタートアップとの連携がより重要になりつつあると考えています。私たちは国内外のスタートアップと共に事業を育み、社会に実装することで、その価値が循環していく世界を共に創りたいです。特にカーボンニュートラル、CO2排出量の削減、グリーンカーボンクレジットの創出といったテーマは重要だと考えています。ここについては、一層スタートアップの皆さんと共に追求していきたいと思います。
(DNX for Corporates 編集部 執筆・宿木雪樹、編集・野村佳美)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
