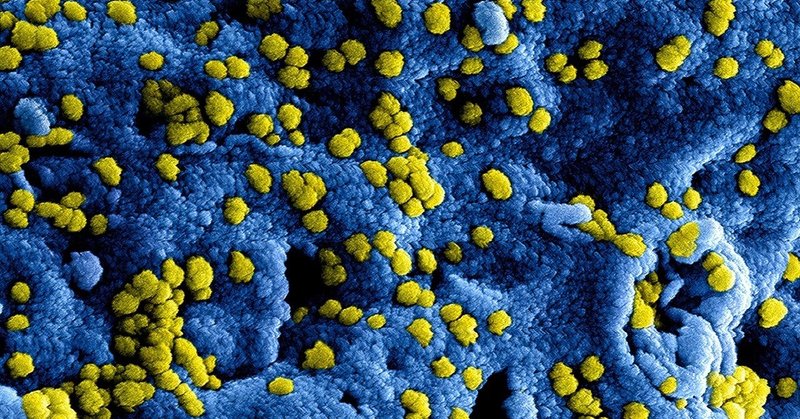
リアルタイムPCRについて
ちょと解説してみます。基本的なPCRについては以下に書いています。
簡単に説明すると、PCRはある特定のDNA遺伝子を部分的に増やす方法です。方法として、2本鎖の1本づつをプライマーという短い塩基配列(特定のDNA遺伝子の一部の塩基配列と相補的なもの)を使うことで1本鎖を2本鎖にします。ということで1回の反応で2本が4本に、2回複製すると4本がそれぞれ2本複製するので8本になります。2のn乗となるということです。
PCR の復習でした。
リアルタイムPCRも基本的には同じことをします。リアルタイムPCRの原理としては大きく2つ方法がありますが、よく使われ特異性が高い方法を紹介します。
TaqMan法と呼ばれるものから。2本のプライマープともう一本プローブと呼ばれす塩基配列に蛍光色素がついたものを用意します。
原理の詳細は上記を参考に。特異性として、プライマー2本に挟まれて増幅された上で、プローブが反応して蛍光を発することで通常のPCRよりも特異性(間違いが少なくなる)が上がります。あと通常のPCR(コンベンショナルPCR)では電機泳動による基本目視でバンドを確認することになりますが、リアルタイムPCRでは蛍光を機械的に検出することで検出感度も上がります。
もう一つのインターカレーション法については少し癖のある検査法ですので現在ではTaqMan法が主に使われています。
TaqMan法では、原理的には、プライマーとプローブの設計がしっかりしていればほぼ間違いなく検出することができます。
しかし、実際に検査する場合には多種多様な検体があるためそのウイルスRNAなどを分離、単離することが非常に大事になってきます。ここで失敗するとどんな感度、特異性がある検査だとしても正確な結果は出せません。
例えば架空のプライマーとプローブを作ってみます。
プローブの蛍光色素であるFAMを発光しないようにBHQで止めている状態です。増幅するときにBHQが外れて蛍光を放ちます。
2本のプライマー
① Fowerd AAAACCCCTTTTGGGGGG
② Riverse CCCCTTTAAAGGGCCCCC
1本のプローブ(FAM:蛍光色素、BHQ:クエンチャー)
③ Plobe FAM-AAACCCCCGGGGTTT-BHQ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
