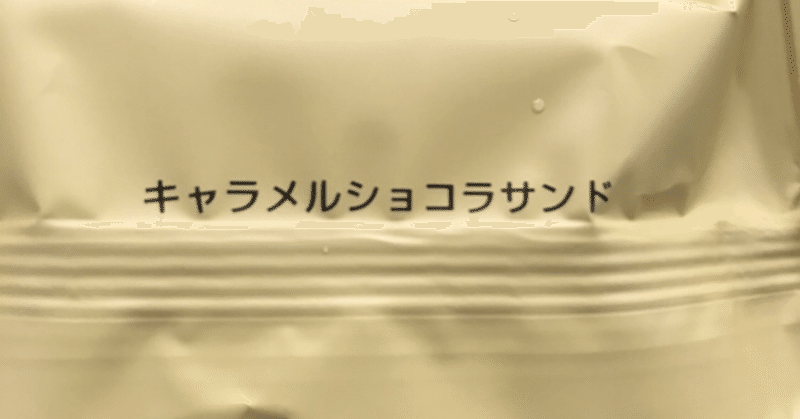
みずあめ
青く濁った目を細くしながら、その人はわたしに「男に襲われたら金玉を噛みちぎれ」と言った。推定、齢、4歳頃のはなし。
どたばた走りながらそのひとの家から帰る支度をしていたら、ふと、台所に、スプーンが突っ込まれている小瓶を見つけた。きらきらひかる小瓶。
「ねえ、なにこれー!」
「水飴。」
母が、「着いたから早く出ておいで」と電話をかけてきて、祖母が「忘れ物はない?」と私を急かしても、動けなかった。
水飴。
祖母が荷物を纏めながらなにか言っているけれど、よく聞こえない。
わたしは突っ立って、その人といつも一緒に見ている日本昔ばなしのビデオのことを考えていた。和尚さんと水飴と、亀と、どく。水飴。あのみずあめだ。すごい。ここに水飴がある。
(あれが、水飴…)
すると、祖母が背を向けたその一瞬、その人がわたしの口にスプーンを突っ込んだ。驚いて見上げると、何事も無かったかのように気だるそうな目をして、「荷物もったか」と私に聞いた。
はじめて食べた水飴は甘くて、甘くて、甘くて、
------------------
夏、祖母と母に黙ってわたしを川に連れて行き、どこからか水着やミッフィーの浮き輪も出てきて、アイスを食べながらずぶ濡れになって帰り、後になって大人たちに怒られていたこと。その人が持ち上げた火が付いた蚊取り線香がわたしの足首に小さな火傷をつくったこと。わたしの手を引いて家に送る途中、「お父さん、みかん、いかがですか」と言われた時の「仕事中」と答えた横顔のうつくしさ。冬になると灯油を換える姿を見るのが好きだった。屋根から伸びる氷柱の味。その人の家に忘れたままだった、青いたまごっちが無いとピアノ教室に行きたくない行かない、と家の下で泣き叫んでいたわたしの自宅に、車でたまごっちを届けに来てくれたこと。小学校1年生、バレエの帰り道、友達と帰ってみたくて、迎えに来てくれたその人を置いてふたりで帰ってしまったこと。そうして、けして怒られなかったこと。病院のにおい。行くたびにどんどん細く小さくなって言葉の出なくなったその人を見に行く意味がわからなくて、見たくもなくて、いつも、病室を出て待合室の漫画ばかり読んでいたこと。海辺で「⚫⚫、」と手を振ると、よわよわしく手を振り返してくれたこと。帰り道、お寿司屋さんの駐車場で、頭が痛いと呟いて、お寿司屋さんに行けなかったこと。そうして、それから、どこにも行けなかったこと。焦げ臭い火葬場で、「見たくない こわい」と逃げ惑ったのに、大人に無理やり箸を握らされたこと。
優しくできなかったのに、その人はいつでも優しかったこと。
求めても求めても手には入らないのに、良さを痛いほど知っているということ、あたたかさを知っているということは、ひどく切ない、と思う。
わたしがその人、祖父と会えなくなってから、何度目の梅雨入りだろうか。
わたしは祖父のことが好きだった。
祖父はわたしのことが好きだったろうか。
いつの間にかわたしは、大人になってしまった。そうして、社会に出てはじめての春を、どうにか終えたらしい。私の隣の席には、個包装の飴が沢山置いてあり、わたしに指導をしてくださる年配の先輩が座っている。
よろしくお願いします、と、はじめて挨拶をした日、「あ、似てる」と思った。生きていれば恐らく同年代だろうという年齢、背格好や話し方、青くにごった目、ぶっきらぼうだが突然飴を放り投げて寄越してくれるような優しさが、祖父に、よく似ている。
常に忘れかけているけれど、絶対に忘れない人。思い出のすべてが、大きくなったわたしを何度も励まし、笑わせ、奮い立たせ、今日を生かしている。行ってきます。今日はあれ聞いて、これも教わりたい。眠い目を擦り、じめじめとした早朝の満員電車に身を捩じ込みながら、今日はわたしがコンビニエンスストアで飴を買って行こう、と思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
