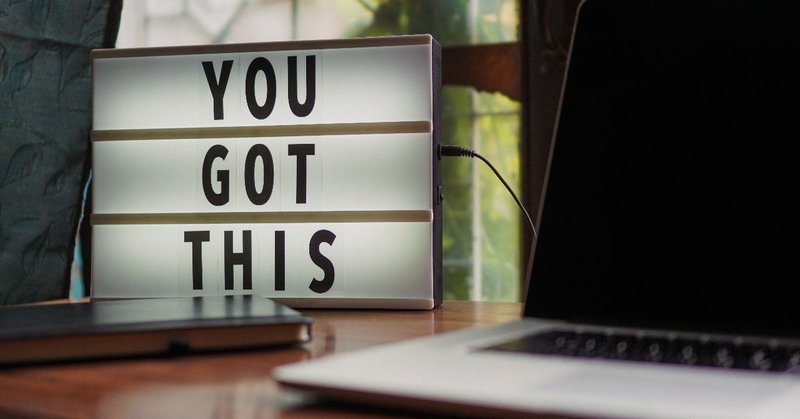
リサーチャー自身の「理解」がリサーチの質を上げる 【デザインシンキング・コンサル⑪】
こんにちは。DONGURIでデザインシンキング・コンサルをやっています、矢口泰介(@yatomiccafe)です。
私は、組織開発や事業開発のプロジェクトにおいて、その初期に定性リサーチを行いますが、組織リサーチや、UXリサーチは「客観的に正しい答え」がもともと得られにくいものです。
これらのリサーチは「仮説を客観的に検証する」ためのものではなく、「得られた結果をもとに、とりあえずの行動に落とす」という発想的性格を持っていますが、その性格からすると「デザインリサーチ/リサーチャー」の質を上げるのは「まずリサーチャー自身が考え、理解する」ことではないかと思うのです。
リサーチの目的とは「わかる」こと
大前提すぎて書くのもはばかられますが、デザインリサーチ/UXリサーチなどにおいて、リサーチをする目的の一つは、「何かがわかった」という結論を出すためです。
「何かがわかる」というのは、非常に奥が深いことです。「わかる」ためには、
1. 「何をわかりたいか」という目的を立て
2. 今のところの仮説を立て
3. 適切なリサーチ手法を選択し
4. リサーチの結果として、仮説を検証し
5. 「ここまではわかった」という理解を示す
というざっくりとした一連の運動を踏む必要があります。
そのステップ一つ一つが非常に奥が深いのですが、リサーチの質=「わかる」の質を上げるためには、上のステップ一つ一つに、リサーチャーの「主観」が必要なのではないでしょうか。
リサーチャーの主観による理解とは
「主観による理解」とは、「リサーチャー自身が何を問題ととらえ、どう理解していくか」という認知の活動を指します。
というのも、リサーチによって「わかる」必要があるのが、事象の裏側にある「背景の構造」だからです。
・なぜKPIを達成できないのか?
・なぜユーザーはそういう行動をするのか?
・なぜインタビュイーはそのような発言をするのか?
・組織がイキイキしていないのはなぜか?
などの事象に対し、「事象を生み出している背景の構造」を捉えるためには、リサーチャー自身の「洞察」と「理解」が重要になってきます。
先に述べたように、デザイン・リサーチは、「客観的に正しい答えを出す」という性格のものではなく、「とりえあずここまではわかった。次に何をしようか」という、いわば行動のトリガーを生み出すために行う性格があります。
客観的に正しい・正しくないではなく、とりあえずこれでやってみる、という行動のトリガーになるためには、「ここまではわかった」という、リサーチャー自身の「腹落ち」の感覚が、ものを言うのだと思います。
その「腹落ち」の感覚が深く、行動のトリガーになりやすいほど、デザインリサーチとしての質が高い、と言えそうです。
リサーチの質を上げるためには?
では、リサーチの質をどのように高めるのか、というと、リサーチャー自身の「洞察の質」がものを言うでしょう。優れた洞察は、優れた仮説を生みます。
そして、その優れた洞察を得るためには、リサーチャー自身が「自分は物事をどのように[わかる]のか?」という理解のプロセスを、自分で把握しておく必要があるのではないでしょうか。
論理的に理解するのか、直感的に理解するのか、フレームワークを使うのか、過去の事例から引っ張り出すのか・・・etc、人それぞれの「理解プロセス&腹落ちポイント」があるのではないかと思うのです。
この意見はかなり感覚的&主観的(すみません)ですが、デザインリサーチャーは、自分自身が物事をどう理解したか?を把握し、その理解のプロセスを伝えることで、リサーチの役割を大きく果たすことにつながるのではないかと思います。
少し前に関連した内容のnoteを書いてましたので、合わせてご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
