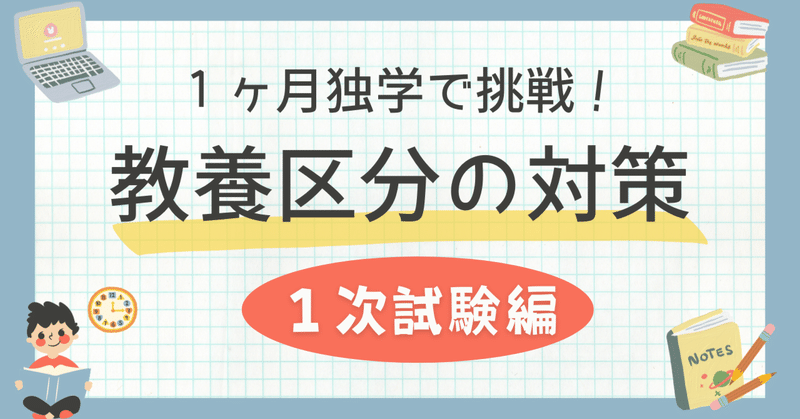
【独学・1ヶ月】教養区分(国家総合職)の具体的な対策方法:1次試験編
はじめに
こんにちは、地方国公立の平凡大学生です。この記事は2024年度以降に教養区分(国家総合職)の試験を受ける人、情報を集めたい人に向けて試験対策の方法と当日の様子を紹介します。
私は2023年の秋(試験日は10月1日でした)に教養区分の試験を受けました。その際、試験に関する情報量が少なく、noteに非常にお世話になったので自身の受験体験を公表して受験者の皆さんのお役に立てればと思います。
教養区分の合格者は、大抵有名大(東大、京大、etc…)が多く、地方国公立の学生が挑むのは強張ってしまうと思います…。ですが、私と近しい立場の人に向けて親切になるように執筆したので、どうぞご覧ください。

本題に入る前に私の試験結果等について、ここで自己紹介をしておきます。自己採点によると Ⅰ部:16点 Ⅱ部:18点 でした。
(追記:2次試験も突破し最終合格しました!!!)
例年と比較して受験者が通常より1000人も増加し(受験可能年齢が引き下げられたため)通常なら受かっているはずの点数でも、今年は合格ラインが大きく引き上げられるのではないかとヒヤヒヤしながら合格発表を待っていました。何度もTwitter(現X)を巡回し、他の人はどんな点数なんだろう…と調べるぐらいには情けなかったです。そしてそんな不安を裏切るかのように合格者受験番号に私の番号はありました。毎回思いますが、このヒヤヒヤした状態で合格者の受験番号を探す瞬間が私は嫌いです笑
そんな私ではありますが、今回の記事の目玉にしたいのは、独学であり、対策期間に1ヶ月程度しか要していない点です。しかも1日あたりの勉強量は平均して1時間程度でした。人によっては1年も前から対策を始める例も見られますが、適切な対策法(と言ってもあくまで私が考えたものに過ぎないですが…)をもとに学習すれば最低でも3週間〜2ヶ月程の期間で1次試験は突破できるのではないかと思っています。それでは本題に参りましょう。
試験内容の詳細は前提にしているので、不安がある方は「国家公務員試験採用情報navi」と検索して「試験情報」をクリック、「受験案内」を参照し、大まかな日程や試験種目などの詳細を確認してください。
◯試験全体の概要
私は理系の学生ですが、この教養区分は文系はもちろん、特に理系の学生に受験を強く推奨します!さらに2023年度から大学2年生も受験可能になったため、できるだけ早い段階で受験しておくと尚良いでしょう。その理由は、
①秋試験(教養区分)に落ちても春試験で挽回できる可能性が残される
②受験経験があることで、これ以降の公務員試験に慣れることができる
③試験内容に専門性がないため、かなり取り組みやすい
④民間に就活する際にも心の余裕ができる
メリットしかありませんね…笑
キャリア官僚に興味があり他の公務員試験を受ける予定があるなら、受験することをお勧めします。
◯1次試験の概要
1次試験は「総合論文試験」と「基礎能力試験(多岐選択式)」の2つがあります。論文は午前に、基礎能力は午後に行われるのですが特筆すべきは「総合論文試験」は1次試験の合否に影響しない点です。教養区分の試験はおよそ倍率が20倍で、1次試験は10倍、2次試験は2倍と言われています。したがって、まず対策に重点を置くべきは「基礎能力試験」です。ですが、試験全体のウェイトを見てみると「総合論文試験」の方が圧倒的に高いことが分かると思います。なので次点と言えど「総合論文試験」を軽視しすぎないことを念頭に置いておきましょう。

試験対策といえば『過去問』の利用が必須ですが、この記事の対策法も例に漏れず『過去問』が大活躍します。これについて1つアドバイスをしておきます。本屋に行っても過去問は手に入りません!!! 正確には類似のものを入手することは可能ですが、本当の過去問を手に入れるには人事院に開示請求する必要があります。これについては参考にできるサイトがいくつかありますので、「人事院 過去問 開示請求」などでググると良いと思います。なお、開示請求には時間を要しますので、遅くとも2ヶ月程前から動き出しましょう。
以下に述べる対策法では少なくとも5年分は過去問を要しますが、開示請求をすると意外と良い値段になります。なので、もし受験仲間がいるようであればデータ形式で過去問を入手し、折半してしまうのが裏技だと思います笑
◯1次試験の対策方法
1次試験に必要な対策時間:1時間/日 × 1ヶ月
(不安であれば2ヶ月、自信があれば数週間)
具体的な流れとしては
基礎能力試験Ⅰ部を最初の方(1〜3週間目)に重点的に取り組み、
基礎能力試験Ⅱ部、総合論文試験を最後の方(3〜4週間目)に重点的に取り組むイメージを持っておいてください。
この理由を簡単に説明しますと、基礎能力試験Ⅰ部は早期に取り組み、問題に対して慣れておくことが肝要です。内容は文章読解、数的処理、判断推理、資料解釈になりますが、特に数的処理、判断推理に慣れるには時間を要します。試験対策を始める前の段階で、試しに2〜3問ほど問題を解いてみてください。(人事院のHPに数問だけ類似問題があります。)
手も足も出ないレベルの人は1日の勉強量を更に30分以上、増やす必要が出てきます。かろうじて考察は進むが肝心の答えまでは至らないレベルの人はこのままで大丈夫です。数的処理、判断推理はパターンに当てはめて攻略することで解答していくものですが、ベースとなる考察力はパターンを暗記する程度では磨かれないと個人的には思います。そしてこの考察力は今までの受験経験や学習によって人それぞれです。多くの問題に触れて考える機会を増やすことが大事です。具体的な手段は後ほど紹介します。
基礎能力試験Ⅱ部は共通テスト(旧センター試験)とほぼ同等のものですが、重要なのは数学を除くほとんどが知識分野に偏っている点です。最近の出題傾向としては、物理や化学でさえも具体的な計算というよりは知識を問うものが多くなっています。つまり、直前の大量暗記が功を奏します笑
私は残念ながら暗記が非常に苦手なタイプの人間です。早めに覚えても試験当日にはするりと知識が抜け落ちていることでしょう。なので直前2週間ほどで暗記しまくるという力技の対策を紹介させていただきます。
さて、改めて確認しますが、基礎能力試験Ⅱ部より基礎能力試験Ⅰ部の方が比重は高いです。大まかにⅠ部の1問がⅡ部の2問に相当すると考えてよいでしょう。Ⅱ部もそこそこの点数を確保しつつ、Ⅰ部の点数をより伸ばす方に力を入れてください。
(ここから先は、必要な参考書等と具体的な対策法、意識すべき重要事項や当日の様子などを記載しております。)
ここから先は
¥ 350
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
